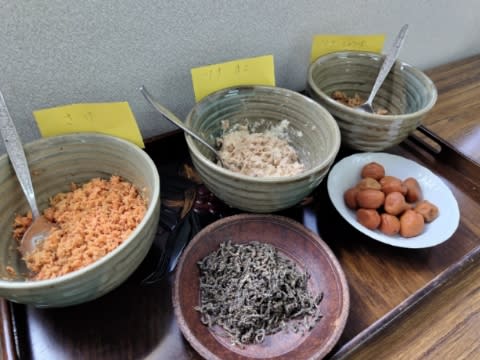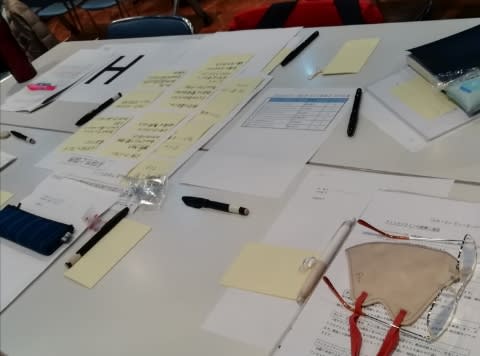辻由起子さんのFacebookをシェアします。
↓
『妊娠。不安しかない。誰にも話せない』
20代女性からの相談が相次いでいるので、「相談あるある」を共有します。
✔️ 周りからの期待がすごいもんね。
そうなんです!!
最初に、「おめでとう」と言われるから、幸せにならないといけない…というプレッシャーがすごくて、不安な気持ちを誰にも話せなくなりました。
✔️ パートナーは生理の苦しみを体験していないから、悪気なく「惜しい!」言動をしてくるしね。
そうなんです!!
そもそも生理でホルモンに影響されて、年の4分の1は心も体もしんどい…っていうのを理解してもらいにくい。
生理痛のない女性にも理解してもらえない。
だから妊娠のしんどさは、もっと理解してもらえない。
つらい時に「感情的」って思われるのもしんどい。
✔️ 令和になっても「母性神話」で努力根性論を求められるしね。
そうなんです!!
「妊娠は病気じゃない」「母親ならアタリマエ」って周りから言われました。
意識がなくなりかけて救急車を呼ぶかどうか迷った時も、甘えてるって言われました。
✔️ 国の感覚もおかしいから、つわりで休みたくても傷病手当の申請がいるしね。
そうなんです!!
妊婦さんに対する国の扱いがひどすぎる!!
つわりで動けないのに、傷病手当の書類のために診察に行って、後日書類を取りに行って、それから申請…。
✔️ だからといって仕事を辞めたら、赤ちゃん連れで次の仕事が見つかる保障はないしね。
そうなんです!!
子育てや教育にお金がかかるのは、ちょっと調べたらわかること。
私も働かないと育てられない。
今でこれだけしんどいのに、妊娠と仕事の両立に耐えられる自信がないです。
✔️ 奨学金の返済もあるしねぇ…。
(大学生の2人に1人が奨学金を利用しているので、20代の相談で水を向けると、たいていヒットする)
そうなんです!!
ひと月2万円の返済があるのに、これからどうやって生きていけばいいのか…。
✔️ 世代間ギャップがひどすぎて、上の世代には現代的な苦しさを理解してもらえないしねぇ…。
そうなんです!!
「私の時はこうだった」という話をされても、今は違うから!!と言いたいです!!
✔️ そして同年代は、キラキラなSNSしかアップしないから、スマホを手にするのもしんどい。
そうなんです!!
だから、誰にも相談できなくて、苦しかったです。
子どもを産みたいと思うことは、贅沢でしょうか?
つらすぎて、話してるだけで泣けてきました。
なんで女性だけこんな仕打ちを受けないといけないんですか?
-----
子を産み育ててくださる人を社会一丸となって支えないと、幸せな未来は実現しません✨
そもそも2つの心臓を、1人の体で動かしているって、偉業!!!!!
↑
このメッセージがよく理解できない人はいても、反論できる人はいないと思います。
本当に、妊娠・出産は人の人生の一大事なのです。
世の中が「女は子どもを産むもの」が当たり前だった時代には封印されていた「産まない」選択肢、
「産む時期を考える」ことができる今の時代には、
「突然の妊娠」は、大きな選択を迫られます。
そして、妊娠・出産はそこで終わりではなく、そこからが山あり谷あり地獄あり、の何年間か(しあわせだなあと思う日があっても)が必然です。
なぜ「妊娠・出産・子育て」がこんなにもたいへんなのか。
それは、助けてくれる「人」がそばにいないつらさです。
子どもがいることの豊かさを実感できる人(身近な先輩)が見えない不安です。
これはお金では買えません。
私は、子どもが6人いるのですが、
子育てを助けてくれる人や、いつも「子どもがまちにたくさんいることをすばらしいこと」と言って、
自分の子どもだけでなく「町中の子どもたち」のために動いていた先輩お母さんたちと出会ったことの結果だと思っています。
私が初めての子育てに必死だったころは、
まだ「子育て支援」なんていう言葉はありませんでしたが、
でも「子育て」をしている人が肩身の狭い思いをせずに、子育てできていた時代でした。
もちろんそれは、仕事をしている母が少なく、
専業主婦同士が助け合えたからできたことで、今の時代では難しいことです。
では、今ならどんなことができるか?
ー相談したり、話し合ったする場所が、まず必要なのです。
「妊娠したらどうすればいいんだろう」と悩む人の「気持ち」を聴き、
いっしょに悩み、その人が選んだ「気持ち」を、「それでいいよ」とか「もう少し考えてみる?」とか言ってくれる身近な人が必要なのです。
そのためにがんばっている「子育て支援センター」が、阪南市にもあります。
そんな場所が、もっと地域にたくさんあることが親支援であり、
いっしょに子育てしていることに気づき、
子育てをすることで見える社会がひろがっていることに気づくことで「もう一人産みたい」気持ちにつながるかもしれないことに期待したいです。