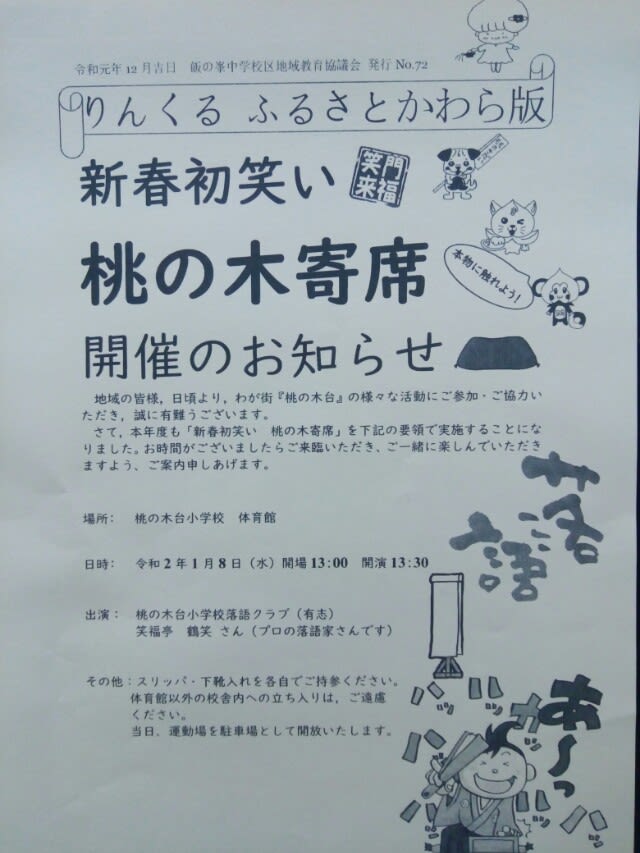待ちに待った、阪南市での「泉州アートサミット」。
サラダホールの外では、
20店以上の出店があるマルシェも開催されていますが、
私は、今日は「平田オリザ」さん漬けの1日です。
午前中は、
小学校5年~中学生を対象にした、
「コミュニケーションワークショップ」による「劇作り」担当でした。
午後は、
そのワークショップの成果発表、
基調講演、
パネルディスカッション、
という、主食も副食も「平田オリザ」さん、という贅沢な1日を過ごしました。
そのワークショップの報告。
●まずは、導入
自己紹介とかはなく、「今日の仲間を知る」ゲーム
・きょうだいの数で分かれる
→分かれたあと、自分は何番目か、などの質問があって、次に進む
・誕生月で分かれる
どちらのゲームも、自分から「きょうだいの数」や「誕生月」を言わないと始まらない、ということがポイントで、自己紹介とかいう「やらされ感」なく、自然に「参加」できる手法です。
さらに、
・手拍子の間は自由に歩き、手拍子がやんでオリザさんが「○人!」と言ったらその人数で集まる、というゲーム
これも、キャンプのプログラムなどではよく使う「仲間作り」ゲームですが、
ここから、2つのグループにするところが、圧巻でした。
まず、
「男女が混在する○人のグループになる」をクリアしたあと、
参加人数の半分の「7人ずつ」、
「男女が混在」
「小5と小6が混在」
のグループになる、
という指示で、
この日初めて会った14人の子どもたちが、
人数や男女や学年の偏りがなく、
しかも「自分たちが作ったグループ」で自然に2つになったことが、
すごいなあと感じました。
●いよいよ劇作り
はじめは既製の台本があり、
それで7人の「役」と「設定」をつかんだあと、
「設定」や「セリフ」を自由に変えていい、という流れでの劇作りが始まります。
ここからの、子どもたちは、
本当にリラックスして、
グループの中の誰もが「参加」して、
劇を作っていました。
●オリザさんからの学び
・「劇」では、どんな「ウソ」(本当でないこと)をやってもいい。でも、1つの「ウソ」は、そのあともずっと「ウソ」に合わせていかなければならなくなる
・自分のセリフは、自分で決めていい。ただこれも、「次の人やその次の人のセリフ」も考えてあげないと、話が続かない。話が続くように考えること。
・「ウケる」ことばかり考えると、スベったときに収拾がつかなくなる。奇抜なセリフにしてもいいが、リスクがある。
・「人を傷つけるセリフ」になっていないか、よく考える(想像する)
台本づくりの過程で、
こんな「人権の学び」があることを目の当たりにして、
平田オリザさんのすごさを改めて感じました。
「人に優しく」とか、
「相手のことを考えて」とか、
みんながわかっていることをどう伝えるか、について、
「コミュニケーション」の中での学びの大切さを、
もっと生活の中で生かしていくべきだと感じました。
さらに、オリザさんからは、
「劇を作るなかで、意見が対立したとき」
●「じゃんけんで決める」「多数決で決める」という方法だけではなく、「大切だと思うことについては、『とことん話し合う』」という方法がある。
「この問題解決をどの方法で解決すればいいのかがわかるのがおとなだ」
というメッセージをいただきました。
劇作りはおまけで、
作る過程での一つ一つのメッセージが宝物だったワークショップでした。
子どもたちが
午後からの成果発表も含め、
何を感じたかを知ることはできませんが、
きっとどこか胸の奥に残る体験になったことと思います。
1日中サラダホールの館内にいたので、
外のようすはお昼の何分かだけの雰囲気しかわかりませんでしたが、
こんな風景でした。

平田オリザさんを軸にした「泉州アートサミット」は、
ぜひ続けていきたいと思いました。
コミュニケーションワークショップの間は写真は撮れなかったので、
午後からの成果発表の出番を待つ子どもたちの雰囲気だけの紹介です。