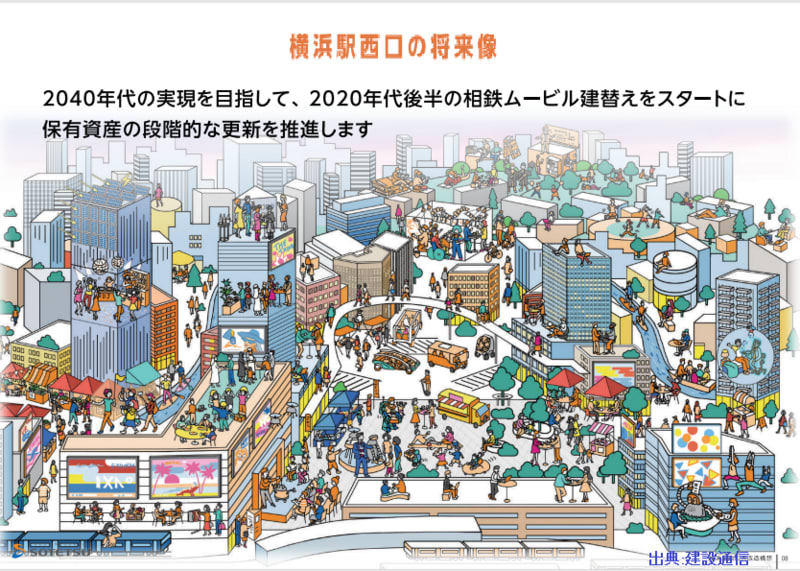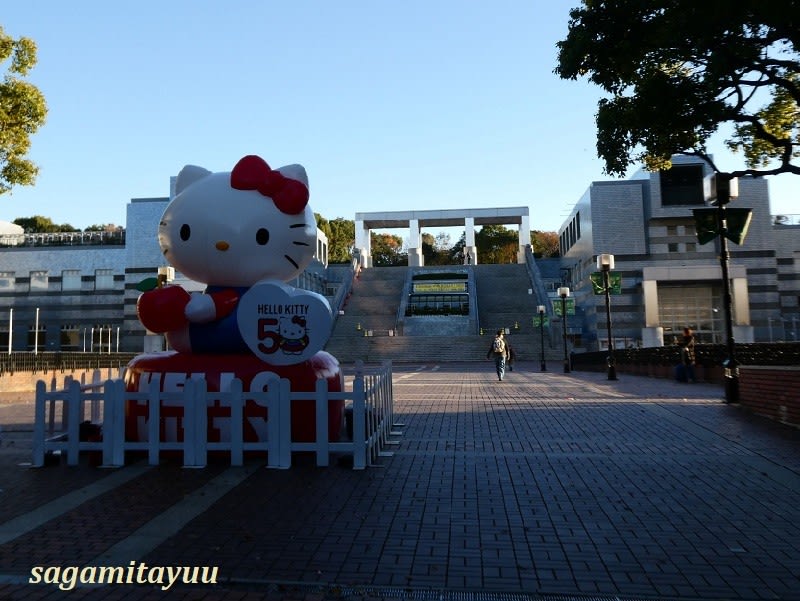福島県田村郡三春町大字平沢字担橋に三春町のメイン駅は東日本旅客鉄道磐越東線の「郡山駅」から二つ目「三春駅」である。1914年(大正3年)開業。1日の乗車人数は650人。「三春」という地名は春の代表花の桜、桃、梅の三つの春の花が咲くことから名付けられた。三春町の面積は72.7㎡、人口は18,3千人(平成27年国勢調査)。現在の三春町は昭和30年に三春・御木沢・沢石・要田・中郷・中妻・岩江の7町村が合併し誕生した。戦国武将田村氏が三春町に城を構えたことから三春町は城下町として発展した。今尚多くの「神社仏閣」や「蔵」などが町の中心市街地には点在しており風情のある町並みを作り出している。三春駅に降り立つと線路の奥の対抗側には数十本の桜が植栽されており、見事な桜景色が用意されており文字通り「桜駅」と化している。今春の桜の季節、三春町のメイン、シンボル、主役はなんと言っても樹齢1000年の「三春の滝桜」でその鑑賞&観光シーズンとなるととなると三週間弱でなんと30万人が訪れ三春町は様相は一変する。桜のメインは樹齢1000年の滝桜であるが、三春町全体では10000本の桜が公共施設、道路、駅、寺院、神社、公園、城址、川、ダム、山、林、個人のお家に植わっていて文字通り桜だらけの町となる。(2504)