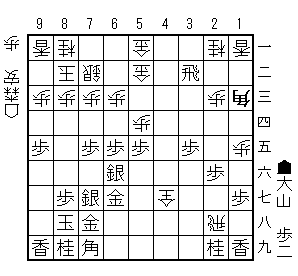
先手番大山先生の次の手は?
☆ 今日の棋譜
昭和54年8月、関根茂先生と第27回王座戦です。(今年2月に亡くなられたとか。)
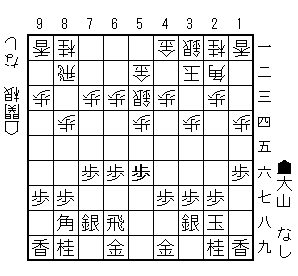
大山先生の四間飛車で、関根先生の53銀は持久戦を目指したものですが、これに56歩はちょっと珍しい手。13角は58飛で問題ないのですが、なんとなく違和感がありますね。中央位取りを防いだ(関根先生が得意そう)ということでしょう。
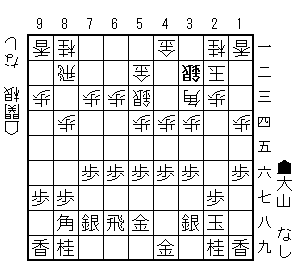
関根先生は位が取れないので左美濃に。

22玉の形の左美濃は角筋で攻められるのが嫌味。64歩としてそれをけん制して、角を転回します。
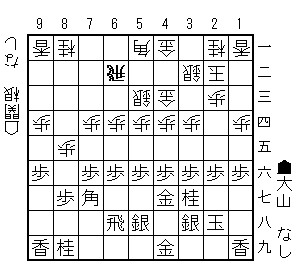
大山先生は軽く58銀で62飛を強要。
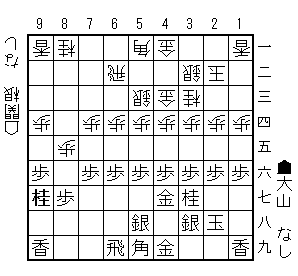
端桂です。関根先生は63飛としておくべきだったか。93桂は95歩があります。
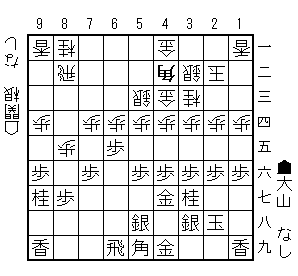
仕方なく耐える展開になりました。大山先生の作戦勝ちです。
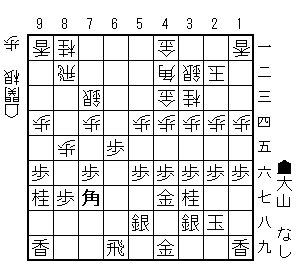
玉は堅いのですが、攻撃力が足りません。こういう時は動くよ、と見せかけて動いてもらうもの。77角で45歩を見せて

75歩から76歩を誘います。
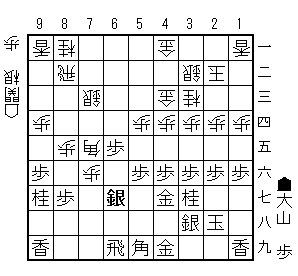
それから銀で76の歩を取りに行きます。関根先生としては角を引いて耐えるところ。

それを45歩から46歩で斬り合いに行ってしまいました。
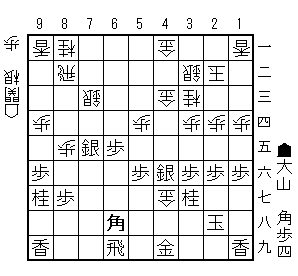
角金交換で金を打ってもたいした手がありません。

守りの金を攻めに使うことになり、流れが悪いです。
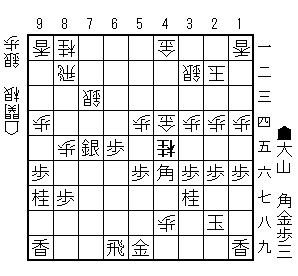
これで一応は攻めが続きます。ここまでは読んでの角金交換からの手順でしょうが、読んでも指さないほうが良いものです。
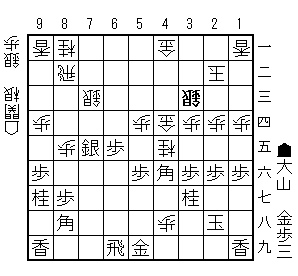
大山先生の88角が好手。つい74歩とか71角とか考えるのですが、この自陣角が急所です。33銀と受けさせて
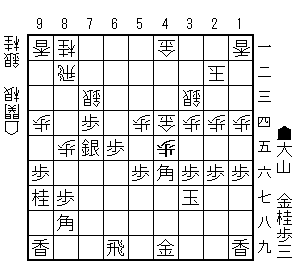
74歩。角を追われたら
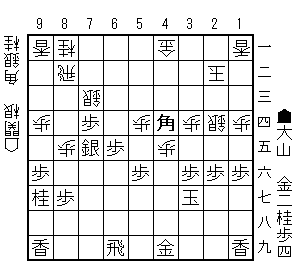
73歩成では怖いので、24角の方が安全そう。とにかく88角のラインを生かします。
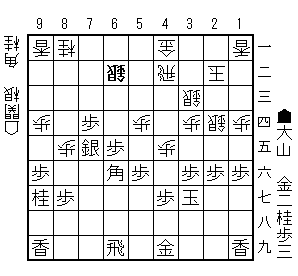
ここで一段落。大山先生が金銀交換プラス歩得でやや有利。普通は38金打とか、守っておくものですが

強く25歩から26桂。守らないで、玉を追われたら左に逃げようとしています。
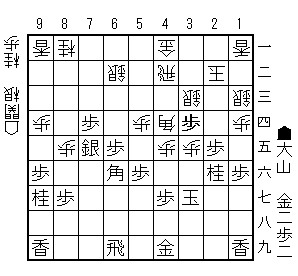
さらに35歩から攻めます。反動が怖いのですが広い玉なので気にしませんね。
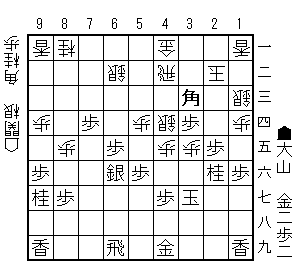
あとは駒を打ち込んで上から押さえていくだけ。
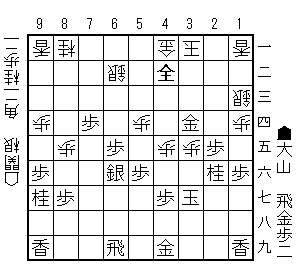
飛車を取り
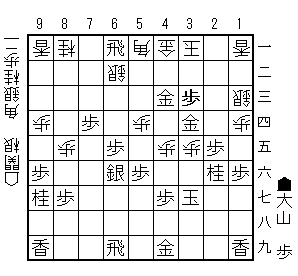
上から迫って投了図。
多分関根先生は居飛車党で鋭く深く読むタイプ。左美濃は向いていないというか、位取りのつもりが仕方なく、という選択で、やりにくい展開だったのでしょう。序盤の64歩と突いて角を移動する(84に持っていくつもり)というのが妥協した感じで、こういう指し方は作戦負けになりやすいのです。
大山先生は軽く動いて、無理に攻めさせて有利になりました。いろいろありそうなところで、77手目88角がとても働きました。
振り飛車党にとって、かなり勉強になる指し方だと思います。
#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS
# ---- Kifu for Windows V7 V7.30 棋譜ファイル ----
手合割:平手
先手:大山十五世名人
後手:関根茂8段
手数----指手--
1 7六歩(77)
2 8四歩(83)
3 7八銀(79)
4 3四歩(33)
5 6六歩(67)
6 6二銀(71)
7 6八飛(28)
8 4二玉(51)
9 4八玉(59)
10 3二玉(42)
11 3八玉(48)
12 5二金(61)
13 2八玉(38)
14 1四歩(13)
15 1六歩(17)
16 5四歩(53)
17 3八銀(39)
18 5三銀(62)
19 5六歩(57)
20 4四歩(43)
21 4六歩(47)
22 3三角(22)
23 3六歩(37)
24 2二玉(32)
25 5八金(69)
26 3二銀(31)
27 4七金(58)
28 4三金(52)
29 6七銀(78)
30 8五歩(84)
31 7七角(88)
32 7四歩(73)
33 3七桂(29)
34 6四歩(63)
35 2六歩(27)
36 9四歩(93)
37 9六歩(97)
38 5一角(33)
39 5八銀(67)
40 6二飛(82)
41 6九飛(68)
42 3三桂(21)
43 5九角(77)
44 2四歩(23)
45 9七桂(89)
46 8二飛(62)
47 6五歩(66)
48 4二角(51)
49 6四歩(65)
50 同 銀(53)
51 6五歩打
52 7三銀(64)
53 7七角(59)
54 7五歩(74)
55 同 歩(76)
56 7六歩打
57 5九角(77)
58 7五角(42)
59 6七銀(58)
60 4五歩(44)
61 7六銀(67)
62 4六歩(45)
63 7五銀(76)
64 4七歩成(46)
65 同 銀(38)
66 4六歩打
67 同 銀(47)
68 4七金打
69 6八角(59)
70 4八歩打
71 5九金(49)
72 4四金(43)
73 4五歩打
74 4六金(47)
75 同 角(68)
76 4五桂(33)
77 8八角打
78 3三銀(32)
79 7四歩打
80 3七桂成(45)
81 同 玉(28)
82 4九歩成(48)
83 同 金(59)
84 4五歩打
85 2四角(46)
86 同 銀(33)
87 4四角(88)
88 3三銀打
89 6六角(44)
90 4二飛(82)
91 4七歩打
92 6二銀(73)
93 2五歩(26)
94 1三銀(24)
95 2六桂打
96 4四角打
97 3五歩(36)
98 同 歩(34)
99 3四歩打
100 6六角(44)
101 同 銀(75)
102 4四銀(33)
103 3三角打
104 同 銀(44)
105 同 歩成(34)
106 同 玉(22)
107 3四金打
108 2二玉(33)
109 3三銀打
110 3一玉(22)
111 4二銀成(33)
112 同 玉(31)
113 6一飛打
114 5一角打
115 4三金打
116 3一玉(42)
117 3三歩打
118 投了
まで117手で先手の勝ち
















































