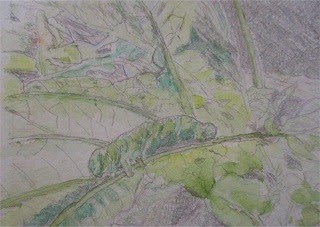一か月以上前に、朝からイソヒヨドリの鳴き声がうるさいとブログに書いて
東京電力に苦情をいれましたが、先日野鳥の対策の工事をしてくれました。
なんせイソヒヨドリは、同じ個体が朝の4時前から夜の7時過ぎまで電柱の先端で鳴いて
います。
人間もこれくらい熱意があったら、どんな相手でも嫁っこに来てくれそうですが、、、。

クレーン車が2台と補助の車が1台の3台で工事を行います。
朝8時30分から午後3時頃までかかりました。
一番上の電線が6600V 真ん中が200Vと100V 一番下がネットやその他です。
電線が多いので作業も大変そうでした。
電線の鳥よけは要望しなかったのですが、6600vと200vの電線に取りつけていました。
が、付近の電線の先端に付ける鳥よけは、なぜか一本付いていません。
作業者に聞いたら、その電柱には先端の鳥よけの要望は無いと言われました。
すぐに東京電力の担当者に連絡して、後日取り付ける事になりました。
イソヒヨドリの一番のお立ち台ですので、鳥よけを付けない訳にはゆきません。

季節の野鳥を観察していますが、電柱の先端を使うのはイソヒヨドリだけかな。
ま、来年の4月に間に合えば問題は無いと思われますが、相手は野鳥です。
まだなんかありそうです。
このところ夕方になると、ヒヨドリの鳴き声が賑やかです。
なんだろうと外を見ると、家のブロック塀に幼鳥がうずくまっています。
しばらく見ていると、親のヒヨドリが近くでその様子をうかがっています。
ヒヨドリの巣立ちのようです。

ヒヨドリの子供は、陽が落ちて暗くなる前にどこかへ飛び立って行きました。
野鳥が親になれるのは20%以下なので、頑張って親にな~れ。
ヒヨドリの季節が終わると、ムクドリの季節になります。
一番大群になるのがムクドリ。
さ~て、今年はどんなムクドリが来るのかな。