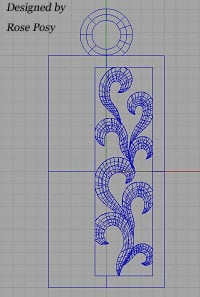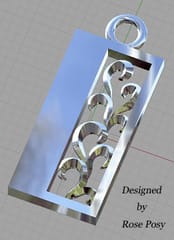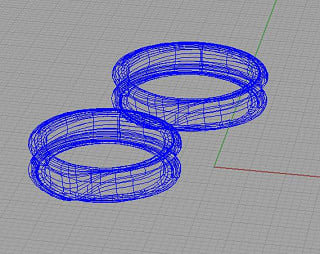先日ご紹介しました、花火柄ペンダントのおそろいリングです。

かなりボリュームがありますが、裏抜きもしっかりしてあり、透かしなのでとても軽い装着感です。私は、こういうコロンとしたフォルムのリングが大好きなのです。
このリング、意外にも浴衣姿にもぴったりなんですよ。

では、珠ペンダントの大柄バージョンや小柄バージョンとのコーディネート例を見てみましょうか。


定番ボールチェーン。

ケシパールとトルコ石で作ったチョーカー

メタリックホワイトの皮紐のチョーカー
次はピアスかな。たぶん完成したころには、花火シーズンが終わってるでしょうな。来年まで温めておくとしますか。

かなりボリュームがありますが、裏抜きもしっかりしてあり、透かしなのでとても軽い装着感です。私は、こういうコロンとしたフォルムのリングが大好きなのです。
このリング、意外にも浴衣姿にもぴったりなんですよ。


では、珠ペンダントの大柄バージョンや小柄バージョンとのコーディネート例を見てみましょうか。

まずは小柄版と。ボールチェーンで涼しげに。
以下は大柄版の着せ替えごっこです。
以下は大柄版の着せ替えごっこです。

定番ボールチェーン。

ケシパールとトルコ石で作ったチョーカー

メタリックホワイトの皮紐のチョーカー
次はピアスかな。たぶん完成したころには、花火シーズンが終わってるでしょうな。来年まで温めておくとしますか。



















 ハート穴を作る段階で考慮すべき事柄でした。とほほ。
ハート穴を作る段階で考慮すべき事柄でした。とほほ。