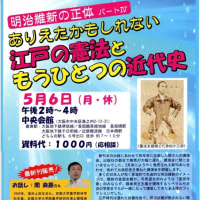自民党の中にあって稀有な脱原発派議員である河野太郎議員の最近のブログ記事はどれもすばらしい。3月31日には「再生可能エネルギー100%を目指す」宣言をした。心より拍手を送りたい。以下のサイト参照。
http://www.taro.org/2011/03/post-970.php
河野議員の提案の要点は以下の通り。
(1)政治的決断で原発の新規立地をすべて中止。
(2)既存原発の寿命を考え、2050年までかけて全原発を段階的に廃炉にする。
(3)段階的廃炉にする分は省エネと天然ガスと再生可能エネルギーで補っていく。
(4)最終的には再生可能エネルギー100%を目指す。
河野議員は同記事で次のように言う。「日本の外では、再生可能エネルギーが驚くべき勢いで伸びている。原発タリバンによる反再生可能エネルギープロパガンダから日本を解き放たなければならない」と。
経済産業省や経団連がまさに「原発タリバン」である。この間の彼らによるTPP推進プロパガンダもひどかったが、基本的に戦前の軍部のプロパガンダと一緒であり、信じてついていけば破滅しかないといえる。
タリバンとは言わずとも「脱原発は非現実。自然エネルギーでは原発の代替にはなり得ない。日本は原子力政策を推進していくしかない」と信じている人々は多い。もちろん日本の全原発をいますぐ廃炉になどできるわけではない。しかし「2050年までに全原発廃止」という長期目標を掲げるのを「非現実」というなら、それこそ「思考停止」というべきだ。現在の技術水準を固定的に考え、40年後の未来の代替技術も信じられないような人々はやはり「原理主義者」の一味である。
そもそも原子力エネルギーの原理であるウランの核分裂連鎖反応が発見されたのが1938年。それから20年もかからずに原子力発電が実用化されている。1930年代初頭には原子力発電など夢想もできなかったのだ。技術の普及はいざ始まれば、それほど速い。
岩波の『世界』の今年の1月号の特集は、原子力ルネッサンスの危険な動きに警鐘を鳴らす「原子力復興という危険な夢」であった。このたびその特集号の主な論文がネット上で無料公開された。下記サイト
http://www.iwanami.co.jp/sekai/
その中のマイケル・シュナイダー「原子力のたそがれ」という論文では、再生可能エネルギーの発電コストが、技術革新による「技術学習効果」によって劇的に低下してきているのに対し、原子力は逆に「負の技術学習効果」とでも呼び得る現象によって近年に新設された原発ほど発電コストが劇的に高まっていることを実証している。アメリカでは、すでに再生可能エネルギーの発電コストは原発よりも安くなりつつある。ぜひご参照を。
日本でも、原子力発電のコストなるものは、使用済み核燃料の再処理コストや放射性廃棄物の最終処分コストなどを一切勘案していないで計算されている。そうしたコストを含めれば原発などおよそ商業的には成立しない技術なのである。
http://www.taro.org/2011/03/post-970.php
河野議員の提案の要点は以下の通り。
(1)政治的決断で原発の新規立地をすべて中止。
(2)既存原発の寿命を考え、2050年までかけて全原発を段階的に廃炉にする。
(3)段階的廃炉にする分は省エネと天然ガスと再生可能エネルギーで補っていく。
(4)最終的には再生可能エネルギー100%を目指す。
河野議員は同記事で次のように言う。「日本の外では、再生可能エネルギーが驚くべき勢いで伸びている。原発タリバンによる反再生可能エネルギープロパガンダから日本を解き放たなければならない」と。
経済産業省や経団連がまさに「原発タリバン」である。この間の彼らによるTPP推進プロパガンダもひどかったが、基本的に戦前の軍部のプロパガンダと一緒であり、信じてついていけば破滅しかないといえる。
タリバンとは言わずとも「脱原発は非現実。自然エネルギーでは原発の代替にはなり得ない。日本は原子力政策を推進していくしかない」と信じている人々は多い。もちろん日本の全原発をいますぐ廃炉になどできるわけではない。しかし「2050年までに全原発廃止」という長期目標を掲げるのを「非現実」というなら、それこそ「思考停止」というべきだ。現在の技術水準を固定的に考え、40年後の未来の代替技術も信じられないような人々はやはり「原理主義者」の一味である。
そもそも原子力エネルギーの原理であるウランの核分裂連鎖反応が発見されたのが1938年。それから20年もかからずに原子力発電が実用化されている。1930年代初頭には原子力発電など夢想もできなかったのだ。技術の普及はいざ始まれば、それほど速い。
岩波の『世界』の今年の1月号の特集は、原子力ルネッサンスの危険な動きに警鐘を鳴らす「原子力復興という危険な夢」であった。このたびその特集号の主な論文がネット上で無料公開された。下記サイト
http://www.iwanami.co.jp/sekai/
その中のマイケル・シュナイダー「原子力のたそがれ」という論文では、再生可能エネルギーの発電コストが、技術革新による「技術学習効果」によって劇的に低下してきているのに対し、原子力は逆に「負の技術学習効果」とでも呼び得る現象によって近年に新設された原発ほど発電コストが劇的に高まっていることを実証している。アメリカでは、すでに再生可能エネルギーの発電コストは原発よりも安くなりつつある。ぜひご参照を。
日本でも、原子力発電のコストなるものは、使用済み核燃料の再処理コストや放射性廃棄物の最終処分コストなどを一切勘案していないで計算されている。そうしたコストを含めれば原発などおよそ商業的には成立しない技術なのである。