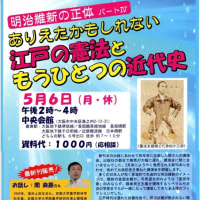昨日、日本学術会議の河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会の第4回会議が開かれ、私も外部からのヒアリングの場で意見を述べる機会を与えられました。
分科会のウェブサイトは下記にあります。追って私が提出した資料・意見書もアップされると思いますのでご参照ください。
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bunya/doboku/giji-kihontakamizu.html
報告の内容はテクニカルな点ばかりを述ただけのものですが、提出された要望書の最後に原発問題と絡めて以下のように付言しました。紹介させていただきます。
官・業・学によって形成された「閉鎖的村社会」の中で、外部からの異論を一切遮断して全体主義的に推進されてきたという点で、原発事業とダム事業は同質な構造を持つといえるのではないでしょうか。
***私が日本学術会議に提出した要望書より引用*********
未曾有の震災の折、可能な限り多くの予算を被災者救援、震災復興、さらに原発被害に対する補償などに振り向ければならない。今回の大震災では、福島県の藤沼ダムの決壊による水害によって5名が死亡、3名が行方不明という痛ましい惨事が発生した。巨額の予算が必要な割に防災の観点からも疑問の多いダム予算などは率先して震災復興に転用すべきという世論は高まっている。
福島第一原発事故の教訓でも明らかになりつつあるが、政・官・財界が一致して事業を推進し、事業を検証するための研究者などからなる組織が、前三者との癒着関係から本来あるべき客観的で科学的なチェック機能を喪失したとき、外部からの警告が一切届かない硬直した翼賛体制が出来上がり、今回のような悲劇的な事態に至ることにもなる。ダム事業においても、原発事業と同様の翼賛構造があったとはいえないだろうか。
「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の場では、飽和雨量48mmが現実的ではないとの意見を発表した鈴木雅一委員に対して一部の専門家が、「緑のダムっていうのはないんです」「緑のダムなんていうのは、幻のダムだと思います」(同会議の2月28日第4回会議の議事録より)など、事実関係に基づかない反論によって議論を打ち切ってしまっている。これは科学的態度からほど遠い、ダム建設を推進しようとする行政の側に肩入れした政治的発言といえるであろう。
この際、利根川のみならず、過大に算出されている可能性の高い全国の河川すべての基本高水を見直し、森林保水力の現状などを正しく組み込んだ上で再計算を実施すべきであろう。その上で、不要になったダム予算は震災復興に転用すべきと思われる。
*****引用終わり***********
この分科会は、昨年10月の衆院予算委員会で自民党の河野太郎議員の国会質問を契機に、八ッ場ダム建設の前提となる利根川洪水の流量計算の誤りが明らかになったことから、馬淵澄夫前国交大臣からの依頼によって、公正な立場の第三者の手による検証をする目的で設置されたものです。
ちなみに河野太郎議員は、原発問題においても、六ヶ所村の核燃サイクル工場や上関原発建設に反対するなど、自民党の国会議員の中にあって原発抑制論の立場を貫いてきました。この間の、熱狂的な原発推進世論の嵐の中にあっても、河野議員は首尾一貫してその態度を変えませんでした。心から敬服するとともに、今後ますます頑張っていただきたいと思います。
事業の推進者から独立した公正な第三者機関による科学的な検証が可能か否かが、全体主義か民主主義かの一つの試金石といえるでしょう。原子力安全委員会も、原子力安全・保安院も、全体主義に組み込まれた翼賛機構の一つにすぎなかったのです。
現在行われている、ダム建設事業者である国交省から独立した第三者による基本高水検証の場は、少なくとも、私のような立場の人間すらも呼ばれ、しかも要望の中の5点の内容に関しては、「いずれの点もしっかりと検討します」と約束してくださいました。公正に検証しようとしている方向性はうかがえました。日本学術会議が、本来のチェック機能を果たせるかどうか、今後も見守っていきたいと思います。
分科会のウェブサイトは下記にあります。追って私が提出した資料・意見書もアップされると思いますのでご参照ください。
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/bunya/doboku/giji-kihontakamizu.html
報告の内容はテクニカルな点ばかりを述ただけのものですが、提出された要望書の最後に原発問題と絡めて以下のように付言しました。紹介させていただきます。
官・業・学によって形成された「閉鎖的村社会」の中で、外部からの異論を一切遮断して全体主義的に推進されてきたという点で、原発事業とダム事業は同質な構造を持つといえるのではないでしょうか。
***私が日本学術会議に提出した要望書より引用*********
未曾有の震災の折、可能な限り多くの予算を被災者救援、震災復興、さらに原発被害に対する補償などに振り向ければならない。今回の大震災では、福島県の藤沼ダムの決壊による水害によって5名が死亡、3名が行方不明という痛ましい惨事が発生した。巨額の予算が必要な割に防災の観点からも疑問の多いダム予算などは率先して震災復興に転用すべきという世論は高まっている。
福島第一原発事故の教訓でも明らかになりつつあるが、政・官・財界が一致して事業を推進し、事業を検証するための研究者などからなる組織が、前三者との癒着関係から本来あるべき客観的で科学的なチェック機能を喪失したとき、外部からの警告が一切届かない硬直した翼賛体制が出来上がり、今回のような悲劇的な事態に至ることにもなる。ダム事業においても、原発事業と同様の翼賛構造があったとはいえないだろうか。
「今後の治水のあり方を考える有識者会議」の場では、飽和雨量48mmが現実的ではないとの意見を発表した鈴木雅一委員に対して一部の専門家が、「緑のダムっていうのはないんです」「緑のダムなんていうのは、幻のダムだと思います」(同会議の2月28日第4回会議の議事録より)など、事実関係に基づかない反論によって議論を打ち切ってしまっている。これは科学的態度からほど遠い、ダム建設を推進しようとする行政の側に肩入れした政治的発言といえるであろう。
この際、利根川のみならず、過大に算出されている可能性の高い全国の河川すべての基本高水を見直し、森林保水力の現状などを正しく組み込んだ上で再計算を実施すべきであろう。その上で、不要になったダム予算は震災復興に転用すべきと思われる。
*****引用終わり***********
この分科会は、昨年10月の衆院予算委員会で自民党の河野太郎議員の国会質問を契機に、八ッ場ダム建設の前提となる利根川洪水の流量計算の誤りが明らかになったことから、馬淵澄夫前国交大臣からの依頼によって、公正な立場の第三者の手による検証をする目的で設置されたものです。
ちなみに河野太郎議員は、原発問題においても、六ヶ所村の核燃サイクル工場や上関原発建設に反対するなど、自民党の国会議員の中にあって原発抑制論の立場を貫いてきました。この間の、熱狂的な原発推進世論の嵐の中にあっても、河野議員は首尾一貫してその態度を変えませんでした。心から敬服するとともに、今後ますます頑張っていただきたいと思います。
事業の推進者から独立した公正な第三者機関による科学的な検証が可能か否かが、全体主義か民主主義かの一つの試金石といえるでしょう。原子力安全委員会も、原子力安全・保安院も、全体主義に組み込まれた翼賛機構の一つにすぎなかったのです。
現在行われている、ダム建設事業者である国交省から独立した第三者による基本高水検証の場は、少なくとも、私のような立場の人間すらも呼ばれ、しかも要望の中の5点の内容に関しては、「いずれの点もしっかりと検討します」と約束してくださいました。公正に検証しようとしている方向性はうかがえました。日本学術会議が、本来のチェック機能を果たせるかどうか、今後も見守っていきたいと思います。