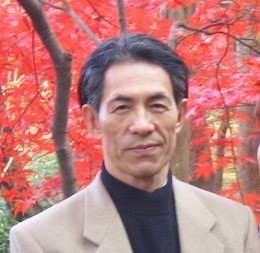写真は、戸建の確認会で撮ったものです。右側のコンクリートブロック塀は隣りの家のもので、こちらの新築の家の塀は、ネットフェンスとなっています。ブロック塀は8段積んでいますので、それだけで1.6m、基礎部分、そして、塀の一番上の笠木部分も入れると約2mあります。
写真は、戸建の確認会で撮ったものです。右側のコンクリートブロック塀は隣りの家のもので、こちらの新築の家の塀は、ネットフェンスとなっています。ブロック塀は8段積んでいますので、それだけで1.6m、基礎部分、そして、塀の一番上の笠木部分も入れると約2mあります。
ここでご覧頂きたいのは、塀の部分の矢印です。下の白い矢印は内覧会時点でのフェンスの高さ、上の緑の矢印は確認会の時点でのフェンスの高さです。内覧会では、地震で揺らされた時のブロック塀が心配なので、フェンスをもっと高くしてくれ、という要望を出しました。売主はその要望を受け入れ、フェンスを高くしたので、写真のようになっています。
フェンスを高くしてくれ、という要望を出したのは、古いブロック塀の安全性に不安があるからです。ブロック塀の場合、段数によっては鉄筋を入れますが、重量があること、重心が上にあること、接合部はモルタルであること等から、地震には弱く倒れやすいと言えます。地震で倒れれば、家も傷つきますし、人が近くにいれば大きな事故になります。
写真の場合、ブロック塀は隣りの家のものですし、既存ですから、何とかしてくれ、とは言いにくいものです。そのような場合には、自分で守るしかないでしょう。そのために、フェンスを上に伸ばし、ブロック塀を覆ってしまいました。こうしても、地震に対し、全く、心配がないわけではありませんが、スチールフェンスですから相当の補強にはなると思います。また、このような設計の変更は、出来れば、内覧会の時ではなく、契約時にしておいた方が良いと言えます。(08)
 一戸建て住宅の基礎は、ベタ基礎か布基礎、この2種類です。自分で家を建てる場合に、どちらの基礎の方が良いのでしょうか?私は、ベタ基礎をお奨め致します。理由は、ベタ基礎の方が除湿そして構造的な見地からも優れていると思われるからです。
一戸建て住宅の基礎は、ベタ基礎か布基礎、この2種類です。自分で家を建てる場合に、どちらの基礎の方が良いのでしょうか?私は、ベタ基礎をお奨め致します。理由は、ベタ基礎の方が除湿そして構造的な見地からも優れていると思われるからです。
布基礎とは、柱の下の土台に沿って、布のように部分的に鉄筋コンクリートで施工する基礎です。部分的ですから、1階の床下は、地面の部分とコンクリートの部分とがあります。布基礎の場合、地面が床下に面しますので、地面の湿気の影響を受けます。一方、ベタ基礎とは、文字通り、床下全体をベターと鉄筋コンクリートで施工する方法です。ですので、床下には、地面が見えるところはなくなります。
写真は、新築戸建の1階の点検口を開けて見たところです。この基礎は布基礎です。従い、部分的に地面が見えます。地面は、雨や地下水の影響でほとんど濡れた状態になっています。その湿気を防ぐため、地面の上には、除湿シートを敷いてあるのですが、写真のように、めくれたり、端が充分でなかったり、図面通りにはいきません。買主の目が行きにくいところでもあります。
床下は、換気が不十分になりがちなところですので、特に湿気が問題になります。基礎はコンクリートですから、多少の湿気は問題ないですが、土台から上は木材ですので、湿気は困ります。こういうことを考えますと、布基礎よりベタ基礎の方が基礎の工法として優れていると思います。また、地震などで不同沈下した場合も、ベタ基礎の方が不同沈下を修正しやすいと言えます。(03)
 写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、階段にある手すりです。感心したのは、上下2重に手すりを取り付けたことです。上は大人用、下は子供用ですが、安心感があります。子供の目線にも合わせた気遣いと思います。このような上下の手すりは駅の階段などでも見受けられます。
写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、階段にある手すりです。感心したのは、上下2重に手すりを取り付けたことです。上は大人用、下は子供用ですが、安心感があります。子供の目線にも合わせた気遣いと思います。このような上下の手すりは駅の階段などでも見受けられます。
「なるほど、これはいい!」と思いますが、意外とこのようにしている家は少ないです。やはり、どうしても、大人の目線になってしまうからでしょうか?家の中で、最も事故が多いのが階段とお風呂です。特に、階段の場合は、大きな事故につながりやすいです。こうしたところには、家族全員の安全を考える、大事なことだと気付かされました。(22)
 写真は戸建の建築中のもので、写っているのは1階の天井裏です。ご覧頂きたいのは↑部分の断熱材を天井裏に敷きこんだ部分です。手前の天井裏には、断熱材は入っていませんが、これから敷きこんでいきます。
写真は戸建の建築中のもので、写っているのは1階の天井裏です。ご覧頂きたいのは↑部分の断熱材を天井裏に敷きこんだ部分です。手前の天井裏には、断熱材は入っていませんが、これから敷きこんでいきます。
一般に、屋根裏、外壁、床下には断熱材を敷きこみますが、写真のような1階の天井裏や部屋の間仕切り壁の中には、入れ込まない場合が多いです。この住宅の設計も、元々は1階の天井裏には断熱材を敷きこまないことになっていました。そこを途中で変更して、1階の天井裏にも、厚さ55㎜のロックウール断熱材(グラスウール断熱材でも良い)を敷きこむように指示をしました。
戸建住宅の設計で最も注意が必要となるのが断熱と遮音だと思います。外からの断熱と遮音だけでなく、家の中でも独立性を高めたいものです。例えば、1階の天井裏、部屋と部屋の間仕切壁、水周りの壁、このようなところの断熱性と遮音性を高めることは大事なことでしょう。断熱材は遮音材としても使えますので、断熱材を入れ込むことは、遮音性も高まります。また、断熱材は建築基準法上は不燃材料ですから、火事の際など、1階から2階への延焼時間が少し長くなることも考えられます。
1階の天井裏、間仕切壁の中、このようなところに断熱材を入れるように設計変更しても、金額は僅かのアップで済みます。断熱材を並べたり、入れたりするだけですから、材料費と工事費込みで、4~5千円/坪程度です。但し、天井や壁を張ってしまった後では、厄介なので、契約時、上棟時など、壁や天井を張る張る前に、なるべく早い段階で要望しなければなりません。(64)
 写真は一戸建て(建売り)の内覧会で撮りました。写したところは洗面所で、ご覧頂きたいのは、タオル掛けと書いてあるところです。ここに掛けたタオルで手や顔を拭くのは、腰を曲げねばならず面倒だし、濡れた手のしずくが床に落ちるでしょう。洗面所のタオル掛けを付ける理想的な位置は、洗面台の左側の壁です。ここであれば、腰も曲げないし、しずくが垂れても、洗面台の上ですから問題ありません。
写真は一戸建て(建売り)の内覧会で撮りました。写したところは洗面所で、ご覧頂きたいのは、タオル掛けと書いてあるところです。ここに掛けたタオルで手や顔を拭くのは、腰を曲げねばならず面倒だし、濡れた手のしずくが床に落ちるでしょう。洗面所のタオル掛けを付ける理想的な位置は、洗面台の左側の壁です。ここであれば、腰も曲げないし、しずくが垂れても、洗面台の上ですから問題ありません。
建売りの場合、このようにタオルハンガーが壁に付いていないケースが非常に多いです。それでは、自分で左側の壁に付ければ良いでしょう、ということになりますが、壁の下地がないとしっかりと付けることはできません。建売りをお買いになる場合には、タオルハンガーが付いているかも確認して下さい。付いていない場合には、壁のどこに下地が入っているかを売主に確認し、その位置に付ければ良いでしょう。(64)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは玄関前のタイル部分です。ご覧頂きたいのは、玄関のタイル部分の端とブロック塀の隙間で、白い矢印で示したところです。この部分は構造的に異なるので、縁を切らないと地震などの影響によりお互いに損傷を与えてしまいます。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。写したところは玄関前のタイル部分です。ご覧頂きたいのは、玄関のタイル部分の端とブロック塀の隙間で、白い矢印で示したところです。この部分は構造的に異なるので、縁を切らないと地震などの影響によりお互いに損傷を与えてしまいます。
ここで良いな、と思ったのは、この隙間にエラスタイトという弾力性のある目地材を入れ込んであることです。タイルとブロック塀の隙間は15㎜ほどあります。この目地材を入れなければ、隙間が出来てしまうことになります。隙間が出来るとカギやお金が万が一落ち込んでしまうと、取り出すのが厄介になりますし、ゴミが入れば掃除も困難です。一戸建ての内覧会では、このような点も確認してみて下さい。もし、ここに隙間が出来ている場合には、売主に言って、何かで塞ぐように言って下さい。(511)
 写真は一戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、屋根の裏側に現場発泡の断熱材を吹き付けた部分です。この家は、建売りですが、このような吹き付けが採用されていました。建売りの場合、一般的な屋根裏断熱は、グラスウールマットを敷き並べることが多いので、このような吹き付けは珍しいです。屋根裏の断熱方法の主なものとして、以下の3種類があります。
写真は一戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、屋根の裏側に現場発泡の断熱材を吹き付けた部分です。この家は、建売りですが、このような吹き付けが採用されていました。建売りの場合、一般的な屋根裏断熱は、グラスウールマットを敷き並べることが多いので、このような吹き付けは珍しいです。屋根裏の断熱方法の主なものとして、以下の3種類があります。
➀断熱マット(グラスウールもしくはロックウール)を天井裏に敷き並べる。最も一般的。
➁現場で発泡断熱材を屋根裏に吹き付ける(写真のケース)。
➂ブローイングと言って、断熱材をチップ化したものを天井裏に雪のように空気で撒く。
この3種類の中で、総合的な判断は別にして、断熱性能に限り性能を比べると、最も優れているのは、➁の現場で発泡する方法と思います。理由は、隙間なく、断熱材が屋根の下側を覆いつくしてしまうからです。内覧会の時には、結構、長い時間、この家にいましたが、断熱効果は高いな、と感じました。(44)
 写真は注文住宅の内覧会で撮りました。出来上がったマイホームを眺めながら、ここのご主人が、一言、「玄関の上に庇(ひさし)が欲しかった・・・」とつぶやきました。写真では分かりにくいのですが、右下の黒い部分が玄関となっています。玄関の奥行きは半間(90cm)となっています。一般的に、玄関は奥に引っ込めて、2階部分で庇とする場合が多いです。この家もそうなっています。この庇部分の奥行きは90cmが多いです。建物の基本寸法は1間(1.8m)ですから、その半分を庇とするわけです。
写真は注文住宅の内覧会で撮りました。出来上がったマイホームを眺めながら、ここのご主人が、一言、「玄関の上に庇(ひさし)が欲しかった・・・」とつぶやきました。写真では分かりにくいのですが、右下の黒い部分が玄関となっています。玄関の奥行きは半間(90cm)となっています。一般的に、玄関は奥に引っ込めて、2階部分で庇とする場合が多いです。この家もそうなっています。この庇部分の奥行きは90cmが多いです。建物の基本寸法は1間(1.8m)ですから、その半分を庇とするわけです。
その玄関に付けられるドアの幅は80cm前後です。庇の奥行きが90cmとなると、玄関ドアを開けたときに、ドアの先端は庇の外側辺りまできます。そうなると、雨が降っている時には、傘を差しながら玄関を開けたり閉めたり、となる可能性があります。また、風雨が強い時には、玄関ドアまで雨が降りかかってきます。
そんなことを考えますと、玄関の庇の先から玄関ドアまでの距離は、出来れば1.2mは欲しいところです。1.5mあれば、相当にゆったり感が出てきますし、自転車を置いても雨は直接あたりません。玄関の中も広くしたい、外もゆったり感が欲しいと悩むところではあります。家を購入される際には、この玄関の庇の出具合も確認してみて下さい。(79)
 写真は、一戸建ての内覧会で、玄関周りを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、玄関ポーチとフェンスブロック塀との隙間です(赤の矢印部分)。塀とポーチを一体に作ることは出来ませんので、このような隙間があるわけです。
写真は、一戸建ての内覧会で、玄関周りを撮ったものです。ご覧頂きたいのは、玄関ポーチとフェンスブロック塀との隙間です(赤の矢印部分)。塀とポーチを一体に作ることは出来ませんので、このような隙間があるわけです。
ここで気になるのは、この隙間に何かを落し込んでしまった場合です。玄関ですからカギを出します。その時にカギやお金がすべって、この隙間に転がりこんでしまうこともあるでしょう。また子供の遊び道具や枯葉やゴミなども入るでしょう。そういう時に、この隙間には手が入りませんので、拾い上げたり、掃除するのが厄介になります。
それでは、どうすれば良いのでしょうか?玄関ポーチが出来上がる前であれば、目地モルタルなどを隙間に打ち込んでもらえば良いでしょう。出来上がってしまった後では、目地モルタルなどを打ち込むのは難しいでしょうから、隙間の寸法に合ったゴム系の板などを詰め込むのが良いと思います。(755)
 写真は戸建の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、床下収納の位置です。この位置が気に入りました。床下収納の位置が、キッチンの奥の端にあれば、その分、その上を歩くことは少なくなります。床下収納とは、床下を利用して、中に収納ボックスを置いて、その上にカバーを掛けます。カバーですから、収まりが結構難しくて、上を歩くと、カタカタしてしまうケースが多いです。また、カバーの取っ手も付きますから、少し引っ掛ったり、冷たかったり、気になる場合もあるでしょう。
写真は戸建の内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、床下収納の位置です。この位置が気に入りました。床下収納の位置が、キッチンの奥の端にあれば、その分、その上を歩くことは少なくなります。床下収納とは、床下を利用して、中に収納ボックスを置いて、その上にカバーを掛けます。カバーですから、収まりが結構難しくて、上を歩くと、カタカタしてしまうケースが多いです。また、カバーの取っ手も付きますから、少し引っ掛ったり、冷たかったり、気になる場合もあるでしょう。
床下収納を設置しようとお考えの際は、その位置は、少しでも、上にいる時間が短い方が良いと思います。そう考えると、写真のように、キッチンのなるべく奥の方が良いでしょう。また、収納ボックスの下に、砂袋を置いてある場合もあります。これは、重くなりすぎて、ボックスの底が抜けるのを防ぐためです。もし砂袋がなくて、重くて底が抜けるのが心配であれば、ビニール袋に砂を入れて、収納ボックスの下に置く事もできます。(03)
 写真は一戸建ての中間検査で撮りました。骨組みと外装工事が終わり、内装工事に入ってきます。この家は、屋根と外壁の断熱仕様が発泡ウレタンの吹き付けとなっています。写真は、外壁に吹き付け工事を実施しているところです。
写真は一戸建ての中間検査で撮りました。骨組みと外装工事が終わり、内装工事に入ってきます。この家は、屋根と外壁の断熱仕様が発泡ウレタンの吹き付けとなっています。写真は、外壁に吹き付け工事を実施しているところです。
この方法は、一般的なグラスウールなどのマットを敷き並べる方法に比べ、現場で吹き付けしますので、隙間が出来にくく、断熱性能は高いと言えます。ただ、工事費がグラスウールに比べ、やや高いことから、一戸建ての工事の主流にはなっていません。私は一戸建ての完成検査等で、いろんな種類の家の中に入りますが、特に夏の場合には、吹き付け断熱かグラスウールか、確認するまでもなく体感で分かります。(7325)
 写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。家がある程度出来上がって、買主の方は、これでは玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。
写真は、注文戸建の内覧会で撮りました。家がある程度出来上がって、買主の方は、これでは玄関ドアの開く向きが逆では?と疑問に思い始めました。確かに、写真のような状態では、玄関への階段が右側(矢印部分)ですから、外へ出る時にもドアが邪魔して通路が狭くなるし、引越しの際も不便です。写真のような反時計回りではなく、時計回りにすべきだったです。
これでは、という事で、売主に何でこういう設計にしたのか?と尋ねたところ、「時計回りだとお客さんが来た時に階段部分で待つことになる」と返事をしてきました。これを聞いて、呆れてしまいました。ここにお住まいになる買主の使い勝手が最優先で、いつ来るか分からないお客の都合なんか二の次と思います。こういう売主では困ります。売主は家の設計及び建設のプロですから、家としての常識は最低限確保しなければならないと思います。
結局、写真のケースでは、これから長く使う上で不便なので、ドアの開く向きを逆にする工事を行いました。この場合、結構なお金と時間がかかります。注文住宅の場合、設計の段階で特に注意が必要となります。売主は設計のプロですから、買主が満足するような家を建てなくてはなりません。家について、設計、構造、法律、設備、品質等について、買主はよく分からない場合が多いです。売主は誠実さと良識を持って対応せねばなりません。でも、後々、住んで困るのは買主ですので、部屋の位置と広さだけでなく、全体的な設計についても隅々までチェックすること、なるべく売主任せにしないことも大事となります。(103)

 写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。
写真は、戸建の内覧会で撮ったものです。ここで、ご覧頂きたいのは、青い付箋が貼ってあるガスメーターの位置です。ガスメーターが家の側面、駐車場側に取り付けられています。ここで心配になることは、駐車する際に、間違って、車をガスメーターにぶつけてしまうことです。この写真の例では、車を止めますと、ガスメーターからは10㎝ぐらいしか空きがありません。大きな車に変えた場合は、車との空きが更に少なくなってしまいます。運転に気をつければ、ガスメーターにぶつけることはないでしょう。でも、ウッカリ、ということもありえます。ウッカリでも、相手はガスですから、ぶつけたら大惨事になります。
そこで、内覧会の時に、このガスメーターの位置では車をぶつける可能性があるので、家の正面側に移設して欲しい、という要望を出しました。移設工事は大変なので、最初は業者も渋っていましたが、どうにか説得して、最終的には、無償で移設することを了解してくれました。 移設することを無償で了解してくれましたが、このような設計上の問題は、計画の段階でチェックしておく方が手間がかかりません。ガスメーターは月に一度は検針に来ます。ですから、人が入れない位置に置くことは出来ません。検針も問題なく出来て、危険性もないところ、設計の段階で吟味して、適切な位置に置かれるべきです。(76)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。いくつかの家が並んで建てられています。ここでご覧頂きたいのは、左の家と右の家との境界線からの距離ですが、それぞれ同じ50㎝となっています。ただ、境界のフェンスは右側の家に入っています。フェンスは境界線上に設置する場合もありますし、写真のように、どちらかの家に入れてしまう場合もあります。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。いくつかの家が並んで建てられています。ここでご覧頂きたいのは、左の家と右の家との境界線からの距離ですが、それぞれ同じ50㎝となっています。ただ、境界のフェンスは右側の家に入っています。フェンスは境界線上に設置する場合もありますし、写真のように、どちらかの家に入れてしまう場合もあります。
ここで問題となるのが、エアコンの室外機の置場です。左側の家の室外機は既に設置されていて、どうにか収まっています。内法幅が50㎝あれば、室外機を置くには問題ありません。ところが、右側の家は、フェンスがありますので、内法幅は40㎝程になってしまいます。こうなると室外機を置くには問題が出てきます。写真の右側の家のケースでは、売主と相談の上、フェンスを撤去することとしました。都内など、地価の高い所では、どうしても、境界線と外壁との距離は狭くなりがちです。エアコンの室外機の設置を考えますと、内法で最低でも50㎝は確保したいものです。(8211)
 写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井裏にあるグルニエ、屋根裏収納です。建築面積算入の関係から、グルニエの場合、天井高さは1.4m以下となる場合が多いです。勾配天井であれば、平均の天井高が1.4m以下となります。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井裏にあるグルニエ、屋根裏収納です。建築面積算入の関係から、グルニエの場合、天井高さは1.4m以下となる場合が多いです。勾配天井であれば、平均の天井高が1.4m以下となります。
ここでご覧頂きたいのは、矢印部分の段差がある所です。グルニエに上がるステップの開口の周りには枠があって、その枠はグルニエの床から1.3㎝上がっています。僅かですが、枠と床とで段差があるわけです。この段差が良いな、と思いました。理由は、グルニエに物を置いて、動かしている時に、間違って下に落としてしまうことが少なくなるからです。
一般には、グルニエの床は、全体的にフラットの場合が多いです。フラットですと、誤って物を落としてしまう危険性があります。また、このように僅かでも、段差があれば、グルニエへのステップを上がって行く場合でも、手を引っ掛けることができます。細かいことですが、気をつかっています。(1821)