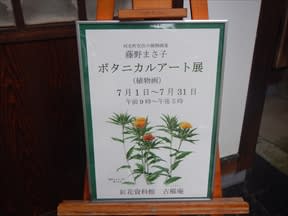JT跡地だったところを落札し、2008年(平成20年)2月に開業したホテルです。仙台駅から5分とかからず、便利な地です。ただ外観以上に部屋は古く感じました。TVは全室40型、Wi-Fiにも対応してましたが、エアコンのコントロールパネルと温水洗浄便座の古さはどうしたんでしょうか。とても7年前のものとは思われません。ホテル仕様の安価なのを中古で買ったんでしょうか。すぐに温水が出ないのですよ。ボタンを押すと温水を作ってからみたいになって、その後に出るものだから最初ちょっと冷たいんです。その違和感がケツにしばらく留まることになります。便座暖房も付いてませんので、冬は大変でしょうね。ベッドはセミダブルサイズでよかったんですが、枕のシミが枕カバーに浮き出てて気になりました。たぶんベッドメーキングした方も気付いてると思います。クレーマーのような記述になってしまってますが、そういう気になる点をつぶしていくのがユーザー評価を上げることに繋がるんではないかと思います。
カードキーの仕組みは未だによく分かりませんが、どうやらカードを引っこ抜いても冷蔵庫やエアコンの予約は効いてるようでした。空の冷蔵庫が冷やされてるのはありがたかったです。外で呑んできて24時に帰ってるのに、1Fのファミマで氷結やらビールを購入。これは習性なので買わないと落ち着きません。今回500mlの氷結はストロングしかなく、アルコール度数が9%。25時までやってる大浴場へいってる間に冷蔵庫で冷やし、呑んで寝たのは2時半。歯は磨いた記憶がありますが、朝起きたらビール半分残してました。当然もったいないから6時に起きてすぐ飲みましたよww


朝食会場は2Fの彩旬。この日行動を共にする3人とは店の前で待ち合わせてましたが、10分前に着きましたので彼此30分の待ち。キレてるのを隠しつつメールを打つのが難しかったです。朝食ビュッフェは50種類あり結構取ったつもりでしたが、画像を見るとそうでもないですね。ずんだ餅甘すぎ。


左上;値段は確認しなかったんですが、結構売れてるっぽい「アパ社長カレー」 右上;鳥の巣の卵のような照明。






天然温泉玄要の湯へは3回入りましたが、朝ヒゲを剃っててモミアゲも剃る際誤って耳に当たってしまい流血。従いまして朝は浴槽に入らずじまい。フロントの対応はとてもよかったです。カットバンの他消毒液も貸してくれました。その天然温泉は、敷地内の地下800mから湧出したph6.7泉温42.4度のナトリウム-塩化物泉(高張性中性高温泉)。加水、加温、塩素消毒ありの循環ですが、メタケイ、メタホウ酸も含まれてます。新幹線の高架下の露天というのは、ある意味貴重かも。