 かずさんは平成25年に他界し、今はプロジェクトチームがその遺志を引き継いでいます。本書はブログに書かれたものをまとめたものです。ほとんど在日と韓国について書かれたものですが、時々中国が出てきます。1991年にスービック海軍基地がフィリピンへ返還されたことが、中国の南沙進出につながったのは明らかです。なにしろシーレーンの最重要基地ですからね。近年韓国が中国へ傾倒したわけは、米国が見限ったためです。米韓相互防衛条約は2012年廃棄されるはずでしたが、北朝鮮情勢悪化で2020年まで延期されました。でも韓国駐留米軍はほとんど引き揚げたようです。通貨スワップの延長も停止、今後援助も予定されてません。UAE原発建設問題などもあり韓国輸出入銀行が、みずほから5億ドルを借入。政府系金融が日本の民間から借りることなど普通はありえません。政治、経済、軍事すべてにおいて、三橋貴明氏も言ってるように危険な段階だと思います。原発どころかロケットを飛ばす技術もないので、北とやることになったら負けるかもしれないですね。もちろん日本とだったら話になりません。現状では原潜とICBM以外はアメリカから注文をつけられてませんので、名前は空母じゃなくてもモドキまで持ってます。
かずさんは平成25年に他界し、今はプロジェクトチームがその遺志を引き継いでいます。本書はブログに書かれたものをまとめたものです。ほとんど在日と韓国について書かれたものですが、時々中国が出てきます。1991年にスービック海軍基地がフィリピンへ返還されたことが、中国の南沙進出につながったのは明らかです。なにしろシーレーンの最重要基地ですからね。近年韓国が中国へ傾倒したわけは、米国が見限ったためです。米韓相互防衛条約は2012年廃棄されるはずでしたが、北朝鮮情勢悪化で2020年まで延期されました。でも韓国駐留米軍はほとんど引き揚げたようです。通貨スワップの延長も停止、今後援助も予定されてません。UAE原発建設問題などもあり韓国輸出入銀行が、みずほから5億ドルを借入。政府系金融が日本の民間から借りることなど普通はありえません。政治、経済、軍事すべてにおいて、三橋貴明氏も言ってるように危険な段階だと思います。原発どころかロケットを飛ばす技術もないので、北とやることになったら負けるかもしれないですね。もちろん日本とだったら話になりません。現状では原潜とICBM以外はアメリカから注文をつけられてませんので、名前は空母じゃなくてもモドキまで持ってます。「試し腹」
「トンスル酒(コリアン・プー・ワイン)」
で検索すると相当やばい国だとわかるでしょう。
ODAについては、1966年~1998年までで
贈与無償資金協力・・・233.84億円
技術協力・・・・・・・913.72億円
政府貸与・・・・・・3,601.54億円
※1965年の日韓基本条約にて日本から韓国へ支払った5億ドルは除く。
現代の価値に換算すると総額は2~3兆円。70~80兆円と書いてる人もいますが、全くのでたらめと言っていいでしょう。それどころか、在日にかかってるお金はそんなもんじゃないです。日本人の5倍の受給率だという生活保護は必要ないでしょ。約3割は不正受給みたいですし。特別永住者、出入国特別法、指紋押捺免除など在日特権もいらなくないですか。その他帰化に関する問題、二重国籍、パチンコの不正送金、ヤク、柔道整復師の不正請求など枚挙にいとまがありません。しかし米軍基地からの銃器横流しなんかホントにあるんですかねー。重機の間違いであってほしいです。どれだけお金使っても感謝の言葉がないばかりか、歴史認識を繰り返すばかり。あまり遜ってるとシリア難民を押し付けられることになります。はっきり言って文化、宗教観の違いが大きすぎますので、あちらの国の人が入ってくると日本は崩壊してしまいます。韓国からの留学生は減少傾向にありますが、「留学生30万人計画」なんて日本政府は何考えてるんでしょうね。本書に書いてある通り、少子化で大学を減らさなきゃならないのに、留学生で成り立つ大学が増えたら問題ですよ。
昨年施行されたテロ資産凍結法とマイナンバー制度が徐々に効いてくることを期待するとして、あとはスパイ防止法の早期成立でしょうね。トランプ氏がメキシコとの国境に万里の長城を築くと言ってましが、国の足を引っ張る人々は排除する方向に向かってるんじゃないでしょうか。既存の政治に満足しない人々の人気をかってますが、パレスチナとイスラエルの中東和平交渉を『半年でまとめる』と豪語してるそうですし、やらせてみたら面白いんじゃないでしょうか。日本は費用負担が増えること必至ですけど。もしがあるかどうかトランプ占いしてみましょうか。










 江戸時代の扇野藩(架空の藩)が舞台で人物相関図はそれほど複雑ではありません。息もつかせぬ展開で、珍しく一気読みしてしまいました。主人公の伊也は、藩の勘定奉行を務める父有川将左衛門から、代々伝わる日置流雪荷派の弓術を教えられます。跡取りのため嫁に行けず、縁談は妹の初音が先でした。ところがその相手は、弓術の流派を異にする大和流の樋口清四郎。しかし弓で対決するうちに、妹の許婚に惹かれてしまいます。
江戸時代の扇野藩(架空の藩)が舞台で人物相関図はそれほど複雑ではありません。息もつかせぬ展開で、珍しく一気読みしてしまいました。主人公の伊也は、藩の勘定奉行を務める父有川将左衛門から、代々伝わる日置流雪荷派の弓術を教えられます。跡取りのため嫁に行けず、縁談は妹の初音が先でした。ところがその相手は、弓術の流派を異にする大和流の樋口清四郎。しかし弓で対決するうちに、妹の許婚に惹かれてしまいます。 吉田松陰が1856年(安政3年)に開いた松下村塾に高杉晋作(諱は春風)は通います。ここで久坂玄瑞らと人脈を築け、思想形成されたことが後々活かされてます。その前に神道無念流練兵館で桂小五郎、斎藤新太郎らと交流してはいましたけど。
吉田松陰が1856年(安政3年)に開いた松下村塾に高杉晋作(諱は春風)は通います。ここで久坂玄瑞らと人脈を築け、思想形成されたことが後々活かされてます。その前に神道無念流練兵館で桂小五郎、斎藤新太郎らと交流してはいましたけど。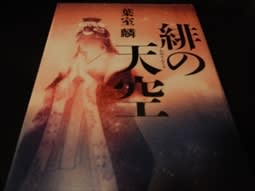 飛鳥時代から奈良時代にかけての物語です。主人公は、藤原不比等(藤原鎌足の次男)の娘安宿媛(あすかべひめ)で後の光明子。不比等に対抗するは長屋王(ながやのおおきみ)で、結局は藤原氏と蘇我氏の争いということになり、長屋王は藤原一族の専横を抑えるべく東奔西走します。長屋王にとっては大化の改新以来の恨みということになります。長屋王の手下の唐鬼はホント悪いヤツですね。蠱毒(こどく)を仕掛けてみたり、和同開珎のにせ金(私鋳銭)を造ったりと。そんな親同士の敵対を尻目に、長屋王の息子膳夫(かしわで)は安宿媛に“蘇”を馳走します。“蘇”とは古代の珍味チーズのことで、クックパッドにもレシピが載ってますので興味ある方はご覧ください。
飛鳥時代から奈良時代にかけての物語です。主人公は、藤原不比等(藤原鎌足の次男)の娘安宿媛(あすかべひめ)で後の光明子。不比等に対抗するは長屋王(ながやのおおきみ)で、結局は藤原氏と蘇我氏の争いということになり、長屋王は藤原一族の専横を抑えるべく東奔西走します。長屋王にとっては大化の改新以来の恨みということになります。長屋王の手下の唐鬼はホント悪いヤツですね。蠱毒(こどく)を仕掛けてみたり、和同開珎のにせ金(私鋳銭)を造ったりと。そんな親同士の敵対を尻目に、長屋王の息子膳夫(かしわで)は安宿媛に“蘇”を馳走します。“蘇”とは古代の珍味チーズのことで、クックパッドにもレシピが載ってますので興味ある方はご覧ください。 本書は『潮鳴り』の続編といっていいかもしれません。羽根(うね)藩の設定も一緒ですし、落魄(らくはく)した播磨屋とか借財の返済に苦しむ藩の台所事情など。序盤で、藩主の三浦兼定が質素倹約の緊縮財政を行った、と書かれていて心改め吉原遊びをやめたのかなと思いきや、終盤で「質素倹約は国許のみであり、江戸屋敷では贅沢や遊興費がかさんでいた」との記述がありましたので『潮鳴り』と状況はほとんど変わってません。そんな状況下で主人公の多門隼人は、御勝手方総元締として借財の返済業務を担うことに。人食い七右衛門に大蛇の臥雲、鬼隼人の嫌われ者三人がタッグを組み、黒菱沼の干拓という難工事に挑みます。
本書は『潮鳴り』の続編といっていいかもしれません。羽根(うね)藩の設定も一緒ですし、落魄(らくはく)した播磨屋とか借財の返済に苦しむ藩の台所事情など。序盤で、藩主の三浦兼定が質素倹約の緊縮財政を行った、と書かれていて心改め吉原遊びをやめたのかなと思いきや、終盤で「質素倹約は国許のみであり、江戸屋敷では贅沢や遊興費がかさんでいた」との記述がありましたので『潮鳴り』と状況はほとんど変わってません。そんな状況下で主人公の多門隼人は、御勝手方総元締として借財の返済業務を担うことに。人食い七右衛門に大蛇の臥雲、鬼隼人の嫌われ者三人がタッグを組み、黒菱沼の干拓という難工事に挑みます。