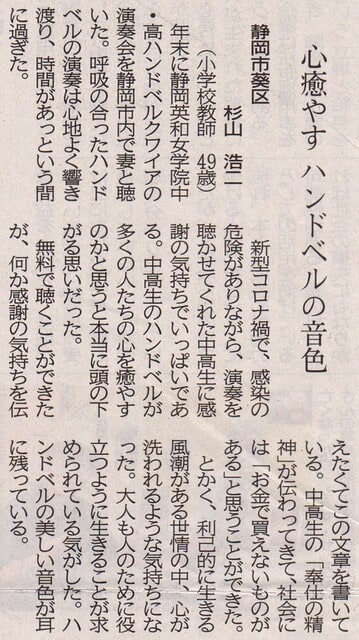2023年4月2日礼拝説教
『パウロと共に人間の側から神様の側へ』
【ルカ19:37~44】
はじめに
きょうは棕櫚の聖日、パーム・サンデーです。この日、イエス様はロバの子に乗って、エルサレムに近づき、人々は熱狂的にイエス様を歓迎しました。その後、イエス様はエルサレムを見て泣きました。エルサレムはこの時からおよそ40年後にローマ軍の攻撃によって滅んで廃墟になってしまいます。神の御子であるイエス様には、その未来の様子が見えていました。また、エルサレムは紀元前600年頃にもバビロン軍の攻撃によって滅亡して、廃墟になっていました。ですからユダヤ人たちは、またしても同じ悲劇を繰り返そうとしていました。それは、イエス様にとって涙を流すほどに悲しいことでした。
きょうの礼拝では、このイエス様の悲しみを皆さんと共に、分かち合いたいと思います。きょうの聖句は週報p.2の上に記したように、ルカ19章41節とヨハネ11章35節です。
そして、次の三つのパートで話を進めて行きます。
①背景:パウロと共に神様の側に移った福音書記者のマルコとルカ
②本題:a) 紀元70年に滅亡したエルサレムを見て泣いたイエス
b) 警告を聞かずに滅びたエルサレムを見て涙したイエス
c) 人間の側から見た神は怒っているが、実は泣いている
③適用:平和は皆がパウロと共に神様の側に移ることでつくられる
(いつも神様の側には居られないが、ディボーションの時は可能)
①背景:パウロと共に神様の側に移った福音書記者のマルコとルカ
先週ご一緒に読んだピレモンへの手紙の最後の方の24節で、パウロは次のように書きました(週報p.2)。
パウロはローマの自宅で軟禁生活を送っていましたが、そこには福音書記者のマルコとルカもいたのですね。これは私にとって新しい発見でした。ピレモンへの手紙は、聖書通読では何度も読んでいましたが、この手紙について思いを巡らしたことは、実はありませんでした。軟禁生活をしていたパウロと共にマルコとルカがいた、だからマルコとルカはイエス様の姿をリアルに書くことができるほどにまでに、イエス様に近づくことができていたのですね。そのことに初めて気付かされました。
先週、そして先々週も言いましたが、ローマで獄中書簡と呼ばれるエペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書を書いた時のパウロは、コリントでローマ人への手紙を書いた時のパウロよりも、きよめにおいて何ランクも昇格していて、別次元のきよめられ方をしていることを感じます。コリントにいた時のパウロはまだ人間の側にいると感じますが、ローマで軟禁生活を送っていたパウロは神様の側に移っていることを獄中書簡を読むと感じます。そして、ルカは使徒の働きの最後を、このローマの軟禁生活のパウロで締めくくっています。パウロの生涯は、この後も、なおしばらく続くのですが、ルカがそれを描かずにここで終わらせたのは、ルカがこの最高にきよめられたパウロの姿で使徒の働きを終わらせたかったからではないか、先週はそんな話をしました。
軟禁生活から解放されたパウロは、もちろんきよめられたままであったことでしょう。しかし、家の外に出て世間と交わるようになれば、どうしても人間の側に引き戻されることになります。BTC、聖宣神学院の神学生も似たようなことを経験します。神学生の寮生活は、世間とはなるべく隔絶された環境の中で、神様に近い生活を送ります。そうして、霊性が養われて行きます。しかし、卒業して神学院を離れると、寮生活をしていた頃よりも、どうしても人間の側に引き戻されます。BTCの寮生活は、神様に近い所で生活できた貴重な機会だったのだなと改めて感じます。
週報のp.3の下に載せている『岩から出る蜜』の連載が、今日で43回目になりました。この『岩から出る蜜』は、教団の初代総理の蔦田二雄先生が、聖宣神学院の院長だった時に神学生に向けて語ったメッセージを366日のディボーション用にまとめたものです。43回目ということは、約10ヶ月間、この連載を続けて来た、ということですね。調べてみたら、連載の第1回は、昨年の6月5日のペンテコステ礼拝の日でした。この連載を始めるのにふさわしい日だったのだなと思います。この連載を読んでいただいていた方には分かっていただいたと思いますが、聖宣神学院は、霊性を養うことをとても大切にしている神学校です。きょうの43回目でも触れられていますが、心霊的な経験を積むことを、とても大切にしています。もう少し分かりやすく言うなら、神様との霊的な出会いを経験して、神様と共に日々を過ごすことを、とても大切にしています。神学院では、この神様に近い生活をする環境が整えられていました。しかし、神学院を卒業すると、どうしても人間の側に引き戻されます。パウロも、軟禁生活から解放された後は、多少人間の側に引き戻されることがあったんだろうな、と今回そのように思いました。ルカはそうなる前のパウロ、神様に最も近い所にいた時のパウロの姿を書いて、使徒の働きを閉じたかったのではないか、そんな気がします。
その最高にきよめられたパウロと共にいたのが、福音書の記者のマルコとルカでした。マルコとルカが福音書のような霊的な書を書けたのは、マルコとルカが人間の側から神様の側に移っていたからであり、それはパウロと共にいたからこそ、それが可能になったのでしょう。
②本題:a) 紀元70年に滅亡したエルサレムを見て泣いたイエス
そうしてルカは、エルサレムを見て泣いたイエス様を描きました。本題のa) です。聖書をお読みします。ルカ19章41節から44節、
イエス様はこのように、約40年後にローマ軍の攻撃によって滅びるエルサレムの姿を霊的な目で見て泣きました。忘れてならないのは、イエス様はこの5日後の金曜日に十字架に掛かって死に、三日目によみがえるということです。このイエス様の十字架と復活によって人は罪から解放されて、イエス様を信じるなら聖霊を受けて神の子どもとされる特権を得ることができるようになりました。
しかし、これは霊的な世界のことです。聖霊を受けて聖霊に満たされた者はこの素晴らしい恵みに与ることができるようになりました。しかし、多くの者は、霊的に目覚めることなく、相変わらず罪の奴隷になっていました。イエス様は、この5日後には、十字架の苦しみを受けなければなりません。この十字架によって、たとえば1年以内にすべての人が悔い改めて神様の方を向き、救いの恵みに与って聖霊に満たされるようになるなら、イエス様は喜んで十字架に付いたことでしょう。「喜んで」というと言い過ぎかもしれませんが、十字架によって直ちに全人類が救われるなら、迷うことなく十字架に向かって行くことができたでしょう。しかし、イエス様は十字架を目前にして、エルサレムを見て涙を流して泣き、最後の晩餐の後では悶え苦しみました。マルコは福音書に、「アバ、父よ」(マルコ14:36)と父に祈るゲッセマネのイエス様を描きました。イエス様が苦しんだのは、この十字架を経てもなお、多くの人が神様から離れたままでいてエルサレムがまたしても滅んでしまうこと、さらに言うなら、二千年経った21世紀も変わらずにその不信仰が続くことをご存知だったから、ではないでしょうか。十字架で死ぬほどの苦しみを受けても、なお多くの人々が神様に背を向け続け、そればかりでなく、戦争を繰り返して多くの都市が破壊されて廃墟になっています。私たちはこの1年、ウクライナの悲惨な街の様子を、嫌というほど見せられました。
エルサレムを含むパレスチナの地域一帯も、紀元前のバビロン軍による攻撃、紀元70年のローマ軍の攻撃だけでなく、有名なところでは十字軍の時代に、そして第二次世界大戦後のイスラエルの建国後も戦争の悲劇が繰り返されています。このことをイエス様がどれほど悲しまれているか、私たちはもっとイエス様に近づいて、この悲しみを共有する必要があるでしょう。イエス様の悲しみを霊的に感じるようになるなら、少なくとも今よりはもう少しは、平和な世になるのではないでしょうか。
b) 警告を聞かずに滅びたエルサレムを見て涙したイエス
きょうはルカの福音書に加えて、ヨハネの福音書も味わいたいと思います。ヨハネもまた、人間の側から神様の側に移ることができた一人であり、神様のすぐ近くにいました。その神様との交わりに私たちも入るようにと、ヨハネは招いています。ヨハネの手紙第一1:3です(週報p.2)。
ディボーションの時に心を整えてヨハネの福音書と向き合う時、この福音書がとても霊的な書であることを感じて厳粛な気持ちになります。ヨハネの福音書からは、文字が印刷されている紙の表面よりも、さらに深い所から霊的な悲しみや怒りが匂い立って来ることを感じます。これは霊的な匂いですから、鼻で感じるものではなく、霊、或いは魂で感じるものです。
たとえるなら、広島の平和公園で感じる霊的な怒りや悲しみの匂いと同じ性質のものでしょう。広島の平和公園を訪ねたことがある方には、共感していただけると思いますが、ここを訪れると、とても厳粛な気持ちになります。そして、公園の土の下から霊的な悲しみが湧き立って来るのを感じます。平和公園は、見た目には、とてもきれいに整備された広大な公園です。しかし、ここに原爆が投下される前は、ここは多くの民家や商店が密集していた地域でした。それが、たった一発の原子爆弾によって焼け野原にされてしまいました。広島の平和公園は、その焼け野原の上に造成された公園です。ですから、そこを掘り返せば、無数の焼けただれた屋根瓦が出て来ます。木造の建物の壁や柱はすべて灰になってしまいましたが、屋根瓦は焼けずに残っているのですね。そして、原爆投下の直後は多くの骨も残されていました。それらは供養のためにできる限り拾われたそうですが、屋根瓦はそのまま残されて、今も平和公園の土の下にあります。その土の下から、悲しみが湧き立って来ることを霊的に感じます。
そして、ヨハネの福音書とは、そういう霊的な喜怒哀楽を感じる書です。表面に見える文字よりももっと深い所から、神様の悲しみや怒り、失望感が湧き上がっています。読者はそれを感じることで霊性を養うことができる、そういう書物です。たとえば、ヨハネ10章1節(週報p.2)、
この文字の下からは、エルサレムの街に門から入らずに、城壁を乗り越えて侵入して、王宮の財宝などを略奪した外国人の略奪隊の光景が霊的に湧き上がっていることを感じます。たとえば列王記第二24章1節は、このように記しています(週報p.2)。
カルデア人とはバビロニア帝国を建国した民族です。そのカルデア人などの略奪隊がエルサレムの城壁を乗り越えて街の中に侵入して王宮の財宝などが略奪されました。そうして、エルサレムの人々はバビロンに捕囚として引かれて行き、エルサレムは滅亡してしまいました。この略奪隊が城壁を乗り越える前、主イエス様は、エレミヤなどの預言者たちを通して、不信仰な南王国の人々に何度も繰り返して警告していました。不信仰を改めなければ滅びることになる、そういう警告です。しかし、人々は警告に耳を傾けず、主に背を向けていたので、ついに主の堪忍袋の緒が切れて、主は略奪隊をエルサレムに遣わして、滅ぼしました。
何度も何度も繰り返し警告を発したのに、南王国の人々が耳を傾けないために、主は仕方なくエルサレムを滅ぼすことにしました。これくらいの荒療治をしなければ、不信仰が改まらないということでしょう。このことがイエス様にとってはとても悲しいことでした。それで、イエス様は涙を流しました。きょうのもう一つの聖句のヨハネ11章35節です。
広島の平和公園の土の下から被爆者の、そしてイエス様の悲しみが湧き上がるのを霊的に感じるように、私たちはヨハネ11章35節の「イエスは涙を流された」から、人々の不信仰が改まらないことへのイエス様の深い悲しみを感じ取りたいと思います[*注(文末に記載)]
c) 人間の側から見た神は怒っているが、実は泣いている
聖宣神学院で聖書の学びを深める前の私にとって、旧約聖書に記されている神様は怒ってばかりいるというイメージがありました。神学院に入るには聖書を何度か通読している必要がありましたから、旧約聖書も何度も読みました。そして旧約聖書に記されている神様は怒ってばかりいる、そう感じていました。
しかし、神様は怒っているというより、実は悲しんでいたのですね。その神様の深い悲しみを、私たちはもっと感じることができるようになりたいと思います。パウロもマルコもルカも最初はそんなに霊的な人ではありませんでした。しかし、様々な経験を経て、霊性が養われました。私たちもそうありたいと思います。
今年の1月からのパウロの生涯のシリーズで見て来たように、パウロは気性が非常に激しい面がありました。それが、ローマで軟禁生活を送りながら、エペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書を書いた頃には、最高にきよめられていて、神様の側にいました。そして、マルコとルカは、そのパウロと共にいたからこそ、神様の側に移ることができて福音書のイエス様を描くことができました。人は誰もが罪人ですから、誰も最初はきよめられてはいません。それでも、イエス様を信じて御霊が与えられるなら、御霊の実が与えられてきよめられていきます。
そして、私たちの時代には、聖書を手軽に手に入れることができます。そうして旧約聖書を読み、また新約聖書の福音書、使徒の働き、パウロたちの手紙、そして黙示録を読むことで、神様のことを深く知ることができます。今年の私たちの教会の年頭聖句であるエペソ人への手紙1章17節をお読みします(週報p.2)。
こうして神様を知ることによって、私たちは神様に近づいて行くことができます。ですからパウロやマルコやルカやヨハネのように、人間の側から神様の側に移ることは決して不可能ではないでしょう。そのことを、パウロ・マルコ・ルカ・ヨハネは証人として証していますから、私たちも少しでも神様に近づく者たちでありたいと思います。
③適用:平和は皆がパウロと共に神様の側に移ることでつくられる
(いつも神様の側には居られないが、ディボーションの時は可能)
今まで何度か話して来たように、ヨハネの福音書は20章で一旦閉じられます。このヨハネの福音書が閉じられる前の20章の最後の方でヨハネは、イエス様の次のことばを記しています。ヨハネ20章21節から23節です。
このヨハネ20章でイエス様は「平安があなたがたにあるように」と三度も言っています。ヨハネの福音書が一旦閉じられる最後の章の20章の終わりの方でイエス様が三度も「平安があなたがたにあるように」と言っている、ということは、この「平安があなたがたにあるように」が、ヨハネの福音書の最大のメッセージの一つであるということです。
新改訳聖書は、この箇所で使われているギリシャ語の「エイレーネー」を「平安」と訳しています。しかし、新共同訳と新しいバージョンの聖書協会共同訳は「平和」と訳しています。聖書には「個人の救い」と「世界の救い」の両方のことが記されていますが、ここの訳し方を見ると、新改訳聖書はどちらかと言えば「個人の救い」寄りで、新共同訳と聖書協会共同訳はどちらかと言えば「世界の救い」寄りなのかなという気が何となくします。そして、皆さんがよくご存知のように、私自身は「世界の救い」寄りです。その「世界の救い」の観点からここを読むなら、21節の「平和があなたがたにあるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わします」は、イエス様は平和をつくるために私たちを世に遣わしている、と読み取れると感じます。
ウクライナの戦争が1年を越えてもなお終わらない、このような現代の21世紀において、私たちは平和をつくるために遣わされていることを感じます。そのために聖霊を受けて、御霊の実を結んできよめられて、互いに赦し合うことで平和をつくって行かなければならないのだと思います。
きよめられて人間の側から神様の側に移ることは難しいことですが、パウロやマルコやルカ、そしてヨハネがそれが可能であることを証ししています。もちろん、いつも神様の側にいることは不可能です。しかし、ディボーションの時には、それが可能です。心を静めて聖書に向き合うなら、御霊が働いて、私たちを人間の側から神様の側に移して下さいます。
パウロがエペソ1:17で書いたように、私たちは、知恵と啓示の御霊を受けて、もっと神様のことを知り、神様に近づきたいと思います。そのことに思いを巡らしながら、しばらくご一緒にお祈りしましょう。
*注:旧約聖書とヨハネの福音書との重なりについては、「平和への道をあきらめない」をご参照下さい
『パウロと共に人間の側から神様の側へ』
【ルカ19:37~44】
はじめに
きょうは棕櫚の聖日、パーム・サンデーです。この日、イエス様はロバの子に乗って、エルサレムに近づき、人々は熱狂的にイエス様を歓迎しました。その後、イエス様はエルサレムを見て泣きました。エルサレムはこの時からおよそ40年後にローマ軍の攻撃によって滅んで廃墟になってしまいます。神の御子であるイエス様には、その未来の様子が見えていました。また、エルサレムは紀元前600年頃にもバビロン軍の攻撃によって滅亡して、廃墟になっていました。ですからユダヤ人たちは、またしても同じ悲劇を繰り返そうとしていました。それは、イエス様にとって涙を流すほどに悲しいことでした。
きょうの礼拝では、このイエス様の悲しみを皆さんと共に、分かち合いたいと思います。きょうの聖句は週報p.2の上に記したように、ルカ19章41節とヨハネ11章35節です。
ルカ19:41 エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて、言われた。
ヨハネ11:35 イエスは涙を流された。
ヨハネ11:35 イエスは涙を流された。
そして、次の三つのパートで話を進めて行きます。
①背景:パウロと共に神様の側に移った福音書記者のマルコとルカ
②本題:a) 紀元70年に滅亡したエルサレムを見て泣いたイエス
b) 警告を聞かずに滅びたエルサレムを見て涙したイエス
c) 人間の側から見た神は怒っているが、実は泣いている
③適用:平和は皆がパウロと共に神様の側に移ることでつくられる
(いつも神様の側には居られないが、ディボーションの時は可能)
①背景:パウロと共に神様の側に移った福音書記者のマルコとルカ
先週ご一緒に読んだピレモンへの手紙の最後の方の24節で、パウロは次のように書きました(週報p.2)。
ピレモン24 私の同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。
パウロはローマの自宅で軟禁生活を送っていましたが、そこには福音書記者のマルコとルカもいたのですね。これは私にとって新しい発見でした。ピレモンへの手紙は、聖書通読では何度も読んでいましたが、この手紙について思いを巡らしたことは、実はありませんでした。軟禁生活をしていたパウロと共にマルコとルカがいた、だからマルコとルカはイエス様の姿をリアルに書くことができるほどにまでに、イエス様に近づくことができていたのですね。そのことに初めて気付かされました。
先週、そして先々週も言いましたが、ローマで獄中書簡と呼ばれるエペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書を書いた時のパウロは、コリントでローマ人への手紙を書いた時のパウロよりも、きよめにおいて何ランクも昇格していて、別次元のきよめられ方をしていることを感じます。コリントにいた時のパウロはまだ人間の側にいると感じますが、ローマで軟禁生活を送っていたパウロは神様の側に移っていることを獄中書簡を読むと感じます。そして、ルカは使徒の働きの最後を、このローマの軟禁生活のパウロで締めくくっています。パウロの生涯は、この後も、なおしばらく続くのですが、ルカがそれを描かずにここで終わらせたのは、ルカがこの最高にきよめられたパウロの姿で使徒の働きを終わらせたかったからではないか、先週はそんな話をしました。
軟禁生活から解放されたパウロは、もちろんきよめられたままであったことでしょう。しかし、家の外に出て世間と交わるようになれば、どうしても人間の側に引き戻されることになります。BTC、聖宣神学院の神学生も似たようなことを経験します。神学生の寮生活は、世間とはなるべく隔絶された環境の中で、神様に近い生活を送ります。そうして、霊性が養われて行きます。しかし、卒業して神学院を離れると、寮生活をしていた頃よりも、どうしても人間の側に引き戻されます。BTCの寮生活は、神様に近い所で生活できた貴重な機会だったのだなと改めて感じます。
週報のp.3の下に載せている『岩から出る蜜』の連載が、今日で43回目になりました。この『岩から出る蜜』は、教団の初代総理の蔦田二雄先生が、聖宣神学院の院長だった時に神学生に向けて語ったメッセージを366日のディボーション用にまとめたものです。43回目ということは、約10ヶ月間、この連載を続けて来た、ということですね。調べてみたら、連載の第1回は、昨年の6月5日のペンテコステ礼拝の日でした。この連載を始めるのにふさわしい日だったのだなと思います。この連載を読んでいただいていた方には分かっていただいたと思いますが、聖宣神学院は、霊性を養うことをとても大切にしている神学校です。きょうの43回目でも触れられていますが、心霊的な経験を積むことを、とても大切にしています。もう少し分かりやすく言うなら、神様との霊的な出会いを経験して、神様と共に日々を過ごすことを、とても大切にしています。神学院では、この神様に近い生活をする環境が整えられていました。しかし、神学院を卒業すると、どうしても人間の側に引き戻されます。パウロも、軟禁生活から解放された後は、多少人間の側に引き戻されることがあったんだろうな、と今回そのように思いました。ルカはそうなる前のパウロ、神様に最も近い所にいた時のパウロの姿を書いて、使徒の働きを閉じたかったのではないか、そんな気がします。
その最高にきよめられたパウロと共にいたのが、福音書の記者のマルコとルカでした。マルコとルカが福音書のような霊的な書を書けたのは、マルコとルカが人間の側から神様の側に移っていたからであり、それはパウロと共にいたからこそ、それが可能になったのでしょう。
②本題:a) 紀元70年に滅亡したエルサレムを見て泣いたイエス
そうしてルカは、エルサレムを見て泣いたイエス様を描きました。本題のa) です。聖書をお読みします。ルカ19章41節から44節、
ルカ19:41 エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて、言われた。
42 「もし、平和に向かう道を、この日おまえも知っていたら──。しかし今、それはおまえの目から隠されている。
43 やがて次のような時代がおまえに来る。敵はおまえに対して塁を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、
44 そしておまえと、中にいるおまえの子どもたちを地にたたきつける。彼らはおまえの中で、一つの石も、ほかの石の上に積まれたまま残してはおかない。それは、神の訪れの時を、おまえが知らなかったからだ。」
42 「もし、平和に向かう道を、この日おまえも知っていたら──。しかし今、それはおまえの目から隠されている。
43 やがて次のような時代がおまえに来る。敵はおまえに対して塁を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、
44 そしておまえと、中にいるおまえの子どもたちを地にたたきつける。彼らはおまえの中で、一つの石も、ほかの石の上に積まれたまま残してはおかない。それは、神の訪れの時を、おまえが知らなかったからだ。」
イエス様はこのように、約40年後にローマ軍の攻撃によって滅びるエルサレムの姿を霊的な目で見て泣きました。忘れてならないのは、イエス様はこの5日後の金曜日に十字架に掛かって死に、三日目によみがえるということです。このイエス様の十字架と復活によって人は罪から解放されて、イエス様を信じるなら聖霊を受けて神の子どもとされる特権を得ることができるようになりました。
しかし、これは霊的な世界のことです。聖霊を受けて聖霊に満たされた者はこの素晴らしい恵みに与ることができるようになりました。しかし、多くの者は、霊的に目覚めることなく、相変わらず罪の奴隷になっていました。イエス様は、この5日後には、十字架の苦しみを受けなければなりません。この十字架によって、たとえば1年以内にすべての人が悔い改めて神様の方を向き、救いの恵みに与って聖霊に満たされるようになるなら、イエス様は喜んで十字架に付いたことでしょう。「喜んで」というと言い過ぎかもしれませんが、十字架によって直ちに全人類が救われるなら、迷うことなく十字架に向かって行くことができたでしょう。しかし、イエス様は十字架を目前にして、エルサレムを見て涙を流して泣き、最後の晩餐の後では悶え苦しみました。マルコは福音書に、「アバ、父よ」(マルコ14:36)と父に祈るゲッセマネのイエス様を描きました。イエス様が苦しんだのは、この十字架を経てもなお、多くの人が神様から離れたままでいてエルサレムがまたしても滅んでしまうこと、さらに言うなら、二千年経った21世紀も変わらずにその不信仰が続くことをご存知だったから、ではないでしょうか。十字架で死ぬほどの苦しみを受けても、なお多くの人々が神様に背を向け続け、そればかりでなく、戦争を繰り返して多くの都市が破壊されて廃墟になっています。私たちはこの1年、ウクライナの悲惨な街の様子を、嫌というほど見せられました。
エルサレムを含むパレスチナの地域一帯も、紀元前のバビロン軍による攻撃、紀元70年のローマ軍の攻撃だけでなく、有名なところでは十字軍の時代に、そして第二次世界大戦後のイスラエルの建国後も戦争の悲劇が繰り返されています。このことをイエス様がどれほど悲しまれているか、私たちはもっとイエス様に近づいて、この悲しみを共有する必要があるでしょう。イエス様の悲しみを霊的に感じるようになるなら、少なくとも今よりはもう少しは、平和な世になるのではないでしょうか。
b) 警告を聞かずに滅びたエルサレムを見て涙したイエス
きょうはルカの福音書に加えて、ヨハネの福音書も味わいたいと思います。ヨハネもまた、人間の側から神様の側に移ることができた一人であり、神様のすぐ近くにいました。その神様との交わりに私たちも入るようにと、ヨハネは招いています。ヨハネの手紙第一1:3です(週報p.2)。
Ⅰヨハネ1:3 私たちが見たこと、聞いたことを、あなたがたにも伝えます。あなたがたも私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。
ディボーションの時に心を整えてヨハネの福音書と向き合う時、この福音書がとても霊的な書であることを感じて厳粛な気持ちになります。ヨハネの福音書からは、文字が印刷されている紙の表面よりも、さらに深い所から霊的な悲しみや怒りが匂い立って来ることを感じます。これは霊的な匂いですから、鼻で感じるものではなく、霊、或いは魂で感じるものです。
たとえるなら、広島の平和公園で感じる霊的な怒りや悲しみの匂いと同じ性質のものでしょう。広島の平和公園を訪ねたことがある方には、共感していただけると思いますが、ここを訪れると、とても厳粛な気持ちになります。そして、公園の土の下から霊的な悲しみが湧き立って来るのを感じます。平和公園は、見た目には、とてもきれいに整備された広大な公園です。しかし、ここに原爆が投下される前は、ここは多くの民家や商店が密集していた地域でした。それが、たった一発の原子爆弾によって焼け野原にされてしまいました。広島の平和公園は、その焼け野原の上に造成された公園です。ですから、そこを掘り返せば、無数の焼けただれた屋根瓦が出て来ます。木造の建物の壁や柱はすべて灰になってしまいましたが、屋根瓦は焼けずに残っているのですね。そして、原爆投下の直後は多くの骨も残されていました。それらは供養のためにできる限り拾われたそうですが、屋根瓦はそのまま残されて、今も平和公園の土の下にあります。その土の下から、悲しみが湧き立って来ることを霊的に感じます。
そして、ヨハネの福音書とは、そういう霊的な喜怒哀楽を感じる書です。表面に見える文字よりももっと深い所から、神様の悲しみや怒り、失望感が湧き上がっています。読者はそれを感じることで霊性を養うことができる、そういう書物です。たとえば、ヨハネ10章1節(週報p.2)、
ヨハネ10:1 「まことに、まことに、あなたがたに言います。羊たちの囲いに、門から入らず、ほかのところを乗り越えて来る者は、盗人であり強盗です。」
この文字の下からは、エルサレムの街に門から入らずに、城壁を乗り越えて侵入して、王宮の財宝などを略奪した外国人の略奪隊の光景が霊的に湧き上がっていることを感じます。たとえば列王記第二24章1節は、このように記しています(週報p.2)。
Ⅱ列王24:2 主は、カルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アンモン人の略奪隊を遣わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めて滅ぼすために彼らを遣わされたのである。主がそのしもべである預言者たちによって告げられたことばのとおりであった。
カルデア人とはバビロニア帝国を建国した民族です。そのカルデア人などの略奪隊がエルサレムの城壁を乗り越えて街の中に侵入して王宮の財宝などが略奪されました。そうして、エルサレムの人々はバビロンに捕囚として引かれて行き、エルサレムは滅亡してしまいました。この略奪隊が城壁を乗り越える前、主イエス様は、エレミヤなどの預言者たちを通して、不信仰な南王国の人々に何度も繰り返して警告していました。不信仰を改めなければ滅びることになる、そういう警告です。しかし、人々は警告に耳を傾けず、主に背を向けていたので、ついに主の堪忍袋の緒が切れて、主は略奪隊をエルサレムに遣わして、滅ぼしました。
何度も何度も繰り返し警告を発したのに、南王国の人々が耳を傾けないために、主は仕方なくエルサレムを滅ぼすことにしました。これくらいの荒療治をしなければ、不信仰が改まらないということでしょう。このことがイエス様にとってはとても悲しいことでした。それで、イエス様は涙を流しました。きょうのもう一つの聖句のヨハネ11章35節です。
ヨハネ11:35 イエスは涙を流された。
広島の平和公園の土の下から被爆者の、そしてイエス様の悲しみが湧き上がるのを霊的に感じるように、私たちはヨハネ11章35節の「イエスは涙を流された」から、人々の不信仰が改まらないことへのイエス様の深い悲しみを感じ取りたいと思います[*注(文末に記載)]
c) 人間の側から見た神は怒っているが、実は泣いている
聖宣神学院で聖書の学びを深める前の私にとって、旧約聖書に記されている神様は怒ってばかりいるというイメージがありました。神学院に入るには聖書を何度か通読している必要がありましたから、旧約聖書も何度も読みました。そして旧約聖書に記されている神様は怒ってばかりいる、そう感じていました。
しかし、神様は怒っているというより、実は悲しんでいたのですね。その神様の深い悲しみを、私たちはもっと感じることができるようになりたいと思います。パウロもマルコもルカも最初はそんなに霊的な人ではありませんでした。しかし、様々な経験を経て、霊性が養われました。私たちもそうありたいと思います。
今年の1月からのパウロの生涯のシリーズで見て来たように、パウロは気性が非常に激しい面がありました。それが、ローマで軟禁生活を送りながら、エペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書を書いた頃には、最高にきよめられていて、神様の側にいました。そして、マルコとルカは、そのパウロと共にいたからこそ、神様の側に移ることができて福音書のイエス様を描くことができました。人は誰もが罪人ですから、誰も最初はきよめられてはいません。それでも、イエス様を信じて御霊が与えられるなら、御霊の実が与えられてきよめられていきます。
そして、私たちの時代には、聖書を手軽に手に入れることができます。そうして旧約聖書を読み、また新約聖書の福音書、使徒の働き、パウロたちの手紙、そして黙示録を読むことで、神様のことを深く知ることができます。今年の私たちの教会の年頭聖句であるエペソ人への手紙1章17節をお読みします(週報p.2)。
エペソ1:17 どうか、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなたがたに与えてくださいますように。
こうして神様を知ることによって、私たちは神様に近づいて行くことができます。ですからパウロやマルコやルカやヨハネのように、人間の側から神様の側に移ることは決して不可能ではないでしょう。そのことを、パウロ・マルコ・ルカ・ヨハネは証人として証していますから、私たちも少しでも神様に近づく者たちでありたいと思います。
③適用:平和は皆がパウロと共に神様の側に移ることでつくられる
(いつも神様の側には居られないが、ディボーションの時は可能)
今まで何度か話して来たように、ヨハネの福音書は20章で一旦閉じられます。このヨハネの福音書が閉じられる前の20章の最後の方でヨハネは、イエス様の次のことばを記しています。ヨハネ20章21節から23節です。
イエス20:21 イエスは再び彼らに言われた。「平安があなたがたにあるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わします。」
22 こう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。
23 あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦されます。赦さずに残すなら、そのまま残ります。」
22 こう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。
23 あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦されます。赦さずに残すなら、そのまま残ります。」
このヨハネ20章でイエス様は「平安があなたがたにあるように」と三度も言っています。ヨハネの福音書が一旦閉じられる最後の章の20章の終わりの方でイエス様が三度も「平安があなたがたにあるように」と言っている、ということは、この「平安があなたがたにあるように」が、ヨハネの福音書の最大のメッセージの一つであるということです。
新改訳聖書は、この箇所で使われているギリシャ語の「エイレーネー」を「平安」と訳しています。しかし、新共同訳と新しいバージョンの聖書協会共同訳は「平和」と訳しています。聖書には「個人の救い」と「世界の救い」の両方のことが記されていますが、ここの訳し方を見ると、新改訳聖書はどちらかと言えば「個人の救い」寄りで、新共同訳と聖書協会共同訳はどちらかと言えば「世界の救い」寄りなのかなという気が何となくします。そして、皆さんがよくご存知のように、私自身は「世界の救い」寄りです。その「世界の救い」の観点からここを読むなら、21節の「平和があなたがたにあるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わします」は、イエス様は平和をつくるために私たちを世に遣わしている、と読み取れると感じます。
ウクライナの戦争が1年を越えてもなお終わらない、このような現代の21世紀において、私たちは平和をつくるために遣わされていることを感じます。そのために聖霊を受けて、御霊の実を結んできよめられて、互いに赦し合うことで平和をつくって行かなければならないのだと思います。
きよめられて人間の側から神様の側に移ることは難しいことですが、パウロやマルコやルカ、そしてヨハネがそれが可能であることを証ししています。もちろん、いつも神様の側にいることは不可能です。しかし、ディボーションの時には、それが可能です。心を静めて聖書に向き合うなら、御霊が働いて、私たちを人間の側から神様の側に移して下さいます。
パウロがエペソ1:17で書いたように、私たちは、知恵と啓示の御霊を受けて、もっと神様のことを知り、神様に近づきたいと思います。そのことに思いを巡らしながら、しばらくご一緒にお祈りしましょう。
*注:旧約聖書とヨハネの福音書との重なりについては、「平和への道をあきらめない」をご参照下さい