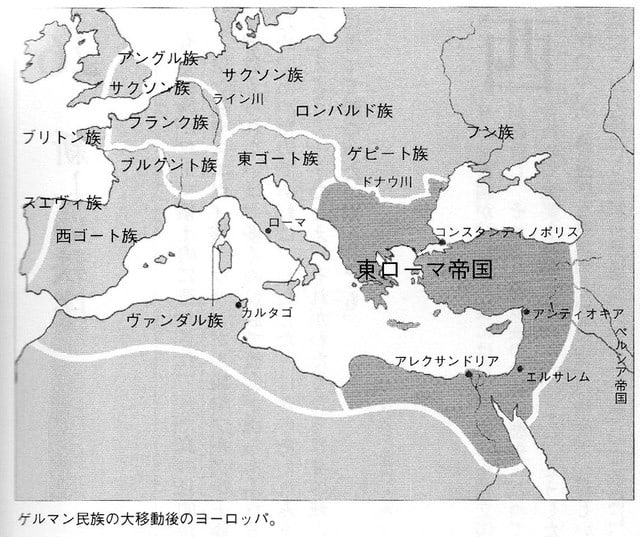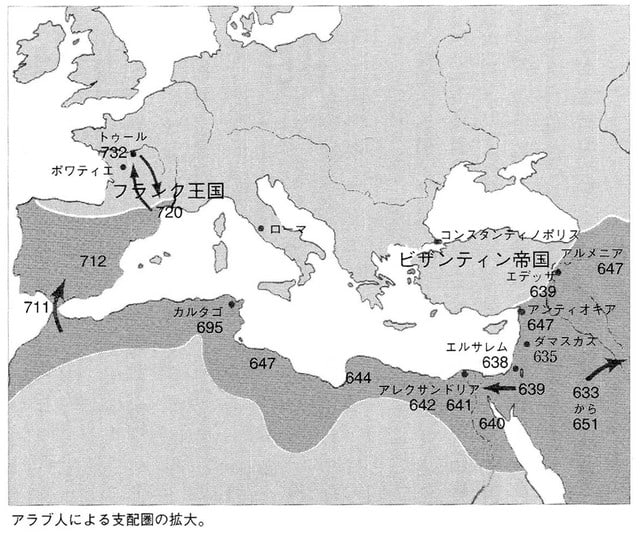2018年11月21日祈り会資料
『法を守ることで守られる信仰生活』
【ルツ1:15~17、2:1~4、4:1~12、18~22】
私たちは宗教法人法に沿って教会活動を行なっている。宗教法人法は素人的な目で見ると、煩雑で面倒なことが書いてある法律のようにも見えるが、実は私たちの信仰生活を守ってくれている。このことを、ルツ記を共に読むことで分かち合いたい。なぜならルツたちの信仰生活は律法によって守られていたからである。
聖書通読の初心者時代には、多くの者が出エジプト記の後半から申命記に至る律法の記述の「~しなければならない」の連続に困惑し、読み通すことに困難を覚えたであろう。しかし、これらの律法はイスラエルの民の信仰生活を守ってくれるものであった。
☆交読 ルツ2:1~4
1 さて、ナオミには、夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。
2 モアブの女ルツはナオミに言った。「畑に行かせてください。そして、親切にしてくれる人のうしろで落ち穂を拾い集めさせてください。」ナオミは「娘よ、行っておいで」と言った。
3 ルツは出かけて行って、刈り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは、はからずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。
4 ちょうどそのとき、ボアズがベツレヘムからやって来て、刈る人たちに言った。「【主】があなたがたとともにおられますように。」彼らは、「【主】があなたを祝福されますように」と答えた。
4節からはボアズが信心深い人物で彼らが模範的な信仰生活を送っていたことが伺える。またルツ1:15~17からは、ルツも信心深い女性であったことが伺える。
☆交読 ルツ1:15~17
15 ナオミは言った。「ご覧なさい。あなたの弟嫁は、自分の民とその神々のところに帰って行きました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。」
16 ルツは言った。「お母様を捨て、別れて帰るように、仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。
17 あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし、死によってでも、私があなたから離れるようなことがあったら、【主】が幾重にも私を罰してくださるように。」
2章の2~3節でルツは落ち穂拾いに出ることをナオミに申し出て出掛けて行った。この落ち穂拾いに関する規定が律法にはある。
☆レビ23:22 「あなたがたの土地の収穫を刈り入れるときは、刈るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者(在留異国人)のために、それらを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。」
ルツとナオミは律法に守られてベツレヘムでの生活を始めた。そして、ボアズはナオミの夫エリメレクの畑を買い戻し、ルツを妻に迎えた。これも律法に則って行なわれた。
☆レビ25:25 もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
☆交読 ルツ4:1~12
1 一方、ボアズは門のところへ上って行って、そこに座った。すると、ちょうど、ボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。「どうぞこちらに来て、ここにお座りください。」彼はそこに来て座った。
2 ボアズは町の長老十人を招いて、「ここにお座りください」と言ったので、彼らも座った。
3 ボアズは、その買い戻しの権利のある親類に言った。「モアブの野から帰って来たナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。
4 私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前で、それを買ってくださいと言おうと思ったのです。もし、あなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。けれども、もし、それを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。」彼は言った。「私が買い戻しましょう。」
5 ボアズは言った。「あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に存続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりません。」
6 するとその買い戻しの権利のある親類は言った。「私には、その土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから。私に代わって、あなたが買い戻してください。私は買い戻すことができません。」
7 昔イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取り引きを有効にするために、一方が自分の履き物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける認証の方法であった。
8 それで、この買い戻しの権利のある親類はボアズに、「あなたがお買いなさい」と言って、自分の履き物を脱いだ。
9 ボアズは、長老たちとすべての民に言った。「あなたがたは、今日、私がナオミの手から、エリメレクのものすべて、キルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの証人です。
10 また、死んだ人の名を相続地に存続させるために、私は、マフロンの妻であったモアブの女ルツも買って、私の妻としました。死んだ人の名を、その身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日、あなたがたはその証人です。」
11 門にいたすべての民と長老たちは言った。「私たちは証人です。どうか、【主】が、あなたの家に嫁ぐ人を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。また、あなたがエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。
12 どうか、【主】がこの娘を通してあなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のように、あなたの家がなりますように。」
2節のボアズが町の長老を招いたことや、7節の取引きを有効にするために自分の履き物を脱いだことなども律法に沿って行なわれたことである(脚注の引照)。こうして律法に守られてナオミとルツは困窮から救い出されて信仰生活を続けることができた。そして、ボアズの血筋からダビデが生まれてイスラエルの王となり、イエス・キリストへとつながって行った。ヨセフとマリアが住民登録でベツレヘムへ上って行き、そこでイエスが誕生したことも、この血筋による。さらに遡るとボアズはユダの息子ペレツの家系である。
☆交読 ルツ4:18~22
18 これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを生み、
19 ヘツロンはラムを生み、ラムはアミナダブを生み、
20 アミナダブはナフションを生み、ナフションはサルマを生み、
21 サルマはボアズを生み、ボアズはオベデを生み、
22 オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生んだ。
(以上)
『法を守ることで守られる信仰生活』
【ルツ1:15~17、2:1~4、4:1~12、18~22】
私たちは宗教法人法に沿って教会活動を行なっている。宗教法人法は素人的な目で見ると、煩雑で面倒なことが書いてある法律のようにも見えるが、実は私たちの信仰生活を守ってくれている。このことを、ルツ記を共に読むことで分かち合いたい。なぜならルツたちの信仰生活は律法によって守られていたからである。
聖書通読の初心者時代には、多くの者が出エジプト記の後半から申命記に至る律法の記述の「~しなければならない」の連続に困惑し、読み通すことに困難を覚えたであろう。しかし、これらの律法はイスラエルの民の信仰生活を守ってくれるものであった。
☆交読 ルツ2:1~4
1 さて、ナオミには、夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。
2 モアブの女ルツはナオミに言った。「畑に行かせてください。そして、親切にしてくれる人のうしろで落ち穂を拾い集めさせてください。」ナオミは「娘よ、行っておいで」と言った。
3 ルツは出かけて行って、刈り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは、はからずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。
4 ちょうどそのとき、ボアズがベツレヘムからやって来て、刈る人たちに言った。「【主】があなたがたとともにおられますように。」彼らは、「【主】があなたを祝福されますように」と答えた。
4節からはボアズが信心深い人物で彼らが模範的な信仰生活を送っていたことが伺える。またルツ1:15~17からは、ルツも信心深い女性であったことが伺える。
☆交読 ルツ1:15~17
15 ナオミは言った。「ご覧なさい。あなたの弟嫁は、自分の民とその神々のところに帰って行きました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。」
16 ルツは言った。「お母様を捨て、別れて帰るように、仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。
17 あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし、死によってでも、私があなたから離れるようなことがあったら、【主】が幾重にも私を罰してくださるように。」
2章の2~3節でルツは落ち穂拾いに出ることをナオミに申し出て出掛けて行った。この落ち穂拾いに関する規定が律法にはある。
☆レビ23:22 「あなたがたの土地の収穫を刈り入れるときは、刈るときに畑の隅まで刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と寄留者(在留異国人)のために、それらを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。」
ルツとナオミは律法に守られてベツレヘムでの生活を始めた。そして、ボアズはナオミの夫エリメレクの畑を買い戻し、ルツを妻に迎えた。これも律法に則って行なわれた。
☆レビ25:25 もしあなたの兄弟が落ちぶれて、その所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
☆交読 ルツ4:1~12
1 一方、ボアズは門のところへ上って行って、そこに座った。すると、ちょうど、ボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。「どうぞこちらに来て、ここにお座りください。」彼はそこに来て座った。
2 ボアズは町の長老十人を招いて、「ここにお座りください」と言ったので、彼らも座った。
3 ボアズは、その買い戻しの権利のある親類に言った。「モアブの野から帰って来たナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。
4 私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前で、それを買ってくださいと言おうと思ったのです。もし、あなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。けれども、もし、それを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。」彼は言った。「私が買い戻しましょう。」
5 ボアズは言った。「あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に存続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりません。」
6 するとその買い戻しの権利のある親類は言った。「私には、その土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから。私に代わって、あなたが買い戻してください。私は買い戻すことができません。」
7 昔イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取り引きを有効にするために、一方が自分の履き物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける認証の方法であった。
8 それで、この買い戻しの権利のある親類はボアズに、「あなたがお買いなさい」と言って、自分の履き物を脱いだ。
9 ボアズは、長老たちとすべての民に言った。「あなたがたは、今日、私がナオミの手から、エリメレクのものすべて、キルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの証人です。
10 また、死んだ人の名を相続地に存続させるために、私は、マフロンの妻であったモアブの女ルツも買って、私の妻としました。死んだ人の名を、その身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日、あなたがたはその証人です。」
11 門にいたすべての民と長老たちは言った。「私たちは証人です。どうか、【主】が、あなたの家に嫁ぐ人を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。また、あなたがエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。
12 どうか、【主】がこの娘を通してあなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のように、あなたの家がなりますように。」
2節のボアズが町の長老を招いたことや、7節の取引きを有効にするために自分の履き物を脱いだことなども律法に沿って行なわれたことである(脚注の引照)。こうして律法に守られてナオミとルツは困窮から救い出されて信仰生活を続けることができた。そして、ボアズの血筋からダビデが生まれてイスラエルの王となり、イエス・キリストへとつながって行った。ヨセフとマリアが住民登録でベツレヘムへ上って行き、そこでイエスが誕生したことも、この血筋による。さらに遡るとボアズはユダの息子ペレツの家系である。
☆交読 ルツ4:18~22
18 これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを生み、
19 ヘツロンはラムを生み、ラムはアミナダブを生み、
20 アミナダブはナフションを生み、ナフションはサルマを生み、
21 サルマはボアズを生み、ボアズはオベデを生み、
22 オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生んだ。
(以上)