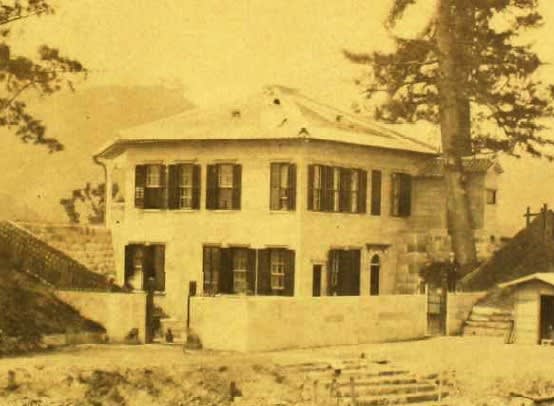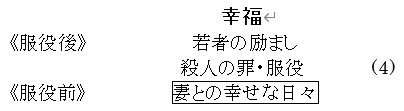2022年12月18日アドベント第4礼拝メッセージ
『恐れなく主に仕えるようにしていただく』
【ルカ1:67~80】
はじめに
今年のアドベントはルカの福音書を開いています。先週のアドベント第3礼拝ではマリアの賛歌と呼ばれる箇所を開きました。そして、きょうはザカリヤの賛歌と呼ばれる箇所をご一緒に見ることにしています。
きょうの中心聖句はルカ1章74節です
そして次の三つのステップで話を進めて行きます。
①全体的な背景:男の子を産んだザカリヤの妻のエリサベツ
②今日の聖書箇所:敵はあらゆる手を使って信仰を破壊する
③自分への適用:恐れなく目に見えない全能の神を信じる
①全体的な背景:男の子を産んだザカリヤの妻のエリサベツ
先週はマリアがザカリヤとエリサベツが住む家を訪ねた箇所をご一緒に見ました。その時、エリサベツは妊娠してから6ヶ月目に入っていました(26節)。そして、マリアはエリサベツのもとに3ヶ月ほどとどまってからナザレの自分の家に戻りました。ですから、マリアがナザレに戻った時、エリサベツは妊娠9ヶ月目で、まさに月が満ちようとしていました。そうして、57節にあるように月が満ちてエリサベツは男の子を生みました。
さて、夫のザカリヤはこの時まで、ずっと口がきけない状態にありましたが、それが解かれました。それは63節にあるように、「その子の名はヨハネ」と書いた時でした。ザカリヤの口がきけなくなったのは彼が御使いのことばを信じなかったからです。それゆえなのでしょう。御使いが言った通りの「ヨハネ」と名付けるべきことを人々に伝えた時、ザカリヤの口は開かれました。そうして、神をほめたたえました。
ここにも正しい人であるザカリヤの信仰が現れていると思います。私だったら、口がきけるようになった途端、「ああ、ひどい目に遭った」などと、つい言ってしまうかもしれません。しかし、正しい人であったザカリヤは開口一番、神をほめたたえました。きっと口がきけないでいる間、御使いのことばを信じなかったことを悔いていたのでしょう。それとともに、妻のエリサベツのお腹が大きくなっていく様子を、喜びを持って見ていたのでしょう。この3ヶ月は若いマリアも共にいてエリサベツも明るく過ごしていたことと思いますから、ザカリヤもまた明るく過ごしていたのでしょう。そうしてザカリヤは神をほめたたえました。それが今日の聖書箇所のザカリヤの賛歌です。
②今日の聖書箇所:敵はあらゆる手を使って信仰を破壊する
きょうの聖書箇所を見ましょう。68節から79節までを眺めると、75節までは主の救いについてザカリヤはほめたたえ、76節から79節までは、生まれた幼子が主の救いに備える者であることをザカリヤは賛美しています。まず主の救いの道を備える者についての76節から79節までを、先に見たいと思います。
バプテスマのヨハネが具体的に何をしたかは、マルコの福音書が簡潔にまとめていますから、マルコ1章の4節と5節をお読みします(週報p.2)。
罪を赦す権威があるのは神様だけです。神の御子であるイエス様には、その権威がありましたが、バプテスマのヨハネにはその権威は与えられていません。しかし、罪の赦しに導くための悔い改めのバプテスマを授けることはできました。それがバプテスマのヨハネに与えられた役割でした。神様に背いている罪を認めて悔い改める、この悔い改めがされているなら、イエス様による罪の赦しにすぐに導いて行くことができます。そして、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は「みな」、ヨハネのもとにやって来て、自分の罪を告白し、バプテスマを受けたとマルコの福音書は記しています。
ルカの福音書に戻ります。
これは神様の深いあわれみによるものです。神様に背くことは、本来は決して赦されない重大な罪です。この罪を、神様は深いあわれみによって赦して下さいます。神の怒りにふれて赦されていない間は、暗闇と死の陰に住んでいます。そんな私たちに神様は光りを与えて下さり、救って下さいます。バプテスマのヨハネはその救いへの道を整えて備えるために遣わされました。
では、主の救いをほめたたえるザカリヤの賛歌の前半の部分を見たいと思います。68節から71節、
71節に、この救いは私たちの敵からの救いであるとザカリヤは賛美しました。この場合の敵とは何でしょうか?目に見える形での敵としては、それは北王国を滅ぼしたアッシリアであり、南王国を滅ぼしたバビロニアでしょう。さらに言えば、このザカリヤの時代のユダヤを支配していたローマ帝国も敵と言えるでしょう。しかし、北王国と南王国が滅ぼされたのは、彼らの不信仰のゆえでした。預言者たちは再三にわたって王と民に、主に立ち返るように警告しました。しかし、それに聴き従わなかったために、不信仰の罪によって主の怒りにふれて滅ぼされてしまいました。
それゆえ、敵とはアッシリアやバビロニアなどのような外側の敵というよりは、不信仰という内側の敵でしょう。そして、その不信仰をあおっているのが悪魔です。敵である悪魔はあらゆる手を使って私たちの信仰を破壊しようとします。この敵からの救いは、74節でもう一度語られます。
主は私たちを敵である悪魔の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださいます。
③自分への適用:恐れなく目に見えない全能の神を信じる
この敵である悪魔の攻撃がいかに強力であるか、最後の3番目のステップに進んで、パウロのエペソ人への手紙を見ることで分かち合いたいと思います。少し長いですが、エペソ6章のその部分を、週報のp.2にも載せておきました。お読みします。
とにかく悪魔はあらゆる手を使って私たちの信仰を破壊しようとしますから、神のすべての武具を取って神様に守っていただかなければなりません。
悪魔の代表的な手口は、人の霊性を弱めて神の霊を感じる霊的な能力を奪うことでしょう。先週ご一緒に見たマリアの賛歌でマリアは1章46節と47節のように賛美しました。
マリアは「私は主をあがめ」ではなく、「私のたましいは主をあがめ」と言って主をあがめました。「私は私の救い主である神をたたえます」ではなく、「私の霊は私の救い主である神をたたえます」と言って、神をたたえました。
この霊性が悪魔によって弱められると、目に見えない神ではなくて、目に見える形あるものを頼るようになり、偶像を礼拝するようになります。或いは形式を重んじる律法主義に陥ります。イエス様の時代のパリサイ人たちは、まさに形式的な律法主義に陥っていました。安息日に働かずに主に心を向けることは大切なことですが、だからと言って安息日に病人を癒したイエス様を批判したパリサイ人はあまりに形式にこだわっていました。隣人を愛し、病人を癒すことは主の御心に適うことです。それゆえイエス様は安息日でも病人を癒しました。
目に見えない神様は変幻自在のお方です。形式主義に陥ると、この変幻自在の神様が見えなくなります。クリスマスによく語られる「くつ屋のマルチン」の話は、イエス様がまさに変幻自在のお方であることを示していますね。
くつ屋のマルチンは、ある晩、聖書を読んでいる時にうたた寝をしてしまいます。その夢の中でイエス様が現れて、「マルチン、明日あなたの所に行きます」とおっしゃいました。翌日、マルチンはイエス様とお会いするのを楽しみにしながら、いつ来て下さるだろうとずっと窓の外を気にしていました。すると、窓の外で雪かきをしていたおじいさんが寒さで凍えている様子が見えたので、家の中に招き入れて、熱いお茶をごちそうしました。
その次には上着もなく薄着で赤ちゃんを抱えていた若い母親の姿が見えたので、先ほどと同じようにその母親を家の中に招き入れました。彼女はここ何日も満足に食事をしておらず、お乳も出なくなっていたということで、マルチンは彼女に食事を与えました。そうして上着も着させて送り出しました。
イエス様はなかなか現れませんでしたが、マルチンはイエス様を待ち続けて、くつ屋の仕事をしながら窓の外を見ていました。すると今度は、売り物のりんごを盗んだ少年をつかまえてお仕置きしようとしているおばあさんの姿が目に入ったので、マルチンは外に出て行き、りんごの代金を払って少年を赦してあげるように説得しました。人を赦すことはとても難しいことですが、おばあさんはそうしようと思いました。少年も赦されたことで、優しい気持ちになり、おばあさんの荷物を持ってあげました。
そうして、日が暮れました。マルチンはイエス様が来なかったことにガッカリしていました。その時、「マルチン、マルチン」とおっしゃるイエス様の声がして、おじいさんが現れました。そのおじいさんはイエス様の声で「わたしですよ」と言いました。次に若い母親が現れて、イエス様の声で「わたしですよ」とおっしゃいました。おばあさんと少年も現れて「わたしですよ」とおっしゃいました。
このように、イエス様は変幻自在に現れるお方です。11月の子供祝福礼拝では、「しんせつなサマリア人」という絵本を使って、ルカの福音書の「善きサマリア人のたとえ」の話をしました。強盗に襲われて大ケガをした人もまたイエス様でしょう。祭司とレビ人は、神殿での儀式という形式を重んじていたためでしょう、大ケガをした人を見て見ぬふりをして通り過ぎました。でも親切なサマリア人はケガ人を介抱しました。
おわりに
悪魔の策略によって霊性が弱められると、形式主義に陥って変幻自在の神様の姿が見えなくなります。すると、天地万物をお造りになった全知全能の神様も見えにくくなります。神様が全地全能のお方であると信じるなら、私たちはマリアが告白したように、はしため(女奴隷)もしくは僕(しもべ、奴隷)に過ぎません。それゆえ、マリアのように「あなたのおことばどおり、この身になりますように」としか言えない者であることが分かります。でも悪魔の策略によって目に見えない神様が見えづらくなると、自分の力で何とかしようと悪あがきをするようになります。そうして、主にお仕えすることができなくなってしまいます。
しかし、ザカリヤがほめたたえたように、「主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる」お方です。ですから、私たちは恐れなく主にお仕えして、マリアのように、「ご覧ください。私は主のはしためです。あなたのおことばどおり、この身になりますように」と信仰告白できるお互いであらせていただきたいと思います。
このことに思いを巡らしながら、しばらくご一緒にお祈りしましょう。
『恐れなく主に仕えるようにしていただく』
【ルカ1:67~80】
はじめに
今年のアドベントはルカの福音書を開いています。先週のアドベント第3礼拝ではマリアの賛歌と呼ばれる箇所を開きました。そして、きょうはザカリヤの賛歌と呼ばれる箇所をご一緒に見ることにしています。
きょうの中心聖句はルカ1章74節です
ルカ1:74 主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。
そして次の三つのステップで話を進めて行きます。
①全体的な背景:男の子を産んだザカリヤの妻のエリサベツ
②今日の聖書箇所:敵はあらゆる手を使って信仰を破壊する
③自分への適用:恐れなく目に見えない全能の神を信じる
①全体的な背景:男の子を産んだザカリヤの妻のエリサベツ
先週はマリアがザカリヤとエリサベツが住む家を訪ねた箇所をご一緒に見ました。その時、エリサベツは妊娠してから6ヶ月目に入っていました(26節)。そして、マリアはエリサベツのもとに3ヶ月ほどとどまってからナザレの自分の家に戻りました。ですから、マリアがナザレに戻った時、エリサベツは妊娠9ヶ月目で、まさに月が満ちようとしていました。そうして、57節にあるように月が満ちてエリサベツは男の子を生みました。
さて、夫のザカリヤはこの時まで、ずっと口がきけない状態にありましたが、それが解かれました。それは63節にあるように、「その子の名はヨハネ」と書いた時でした。ザカリヤの口がきけなくなったのは彼が御使いのことばを信じなかったからです。それゆえなのでしょう。御使いが言った通りの「ヨハネ」と名付けるべきことを人々に伝えた時、ザカリヤの口は開かれました。そうして、神をほめたたえました。
ここにも正しい人であるザカリヤの信仰が現れていると思います。私だったら、口がきけるようになった途端、「ああ、ひどい目に遭った」などと、つい言ってしまうかもしれません。しかし、正しい人であったザカリヤは開口一番、神をほめたたえました。きっと口がきけないでいる間、御使いのことばを信じなかったことを悔いていたのでしょう。それとともに、妻のエリサベツのお腹が大きくなっていく様子を、喜びを持って見ていたのでしょう。この3ヶ月は若いマリアも共にいてエリサベツも明るく過ごしていたことと思いますから、ザカリヤもまた明るく過ごしていたのでしょう。そうしてザカリヤは神をほめたたえました。それが今日の聖書箇所のザカリヤの賛歌です。
②今日の聖書箇所:敵はあらゆる手を使って信仰を破壊する
きょうの聖書箇所を見ましょう。68節から79節までを眺めると、75節までは主の救いについてザカリヤはほめたたえ、76節から79節までは、生まれた幼子が主の救いに備える者であることをザカリヤは賛美しています。まず主の救いの道を備える者についての76節から79節までを、先に見たいと思います。
ルカ1:76 幼子よ、あなたこそいと高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、
77 罪の赦しによる救いについて、神の民に、知識を与えるからである。
77 罪の赦しによる救いについて、神の民に、知識を与えるからである。
バプテスマのヨハネが具体的に何をしたかは、マルコの福音書が簡潔にまとめていますから、マルコ1章の4節と5節をお読みします(週報p.2)。
マルコ1:4 バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の赦しに導く悔い改めのバプテスマを宣べ伝えた。
5 ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民はみな、ヨハネのもとにやって来て、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
5 ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民はみな、ヨハネのもとにやって来て、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
罪を赦す権威があるのは神様だけです。神の御子であるイエス様には、その権威がありましたが、バプテスマのヨハネにはその権威は与えられていません。しかし、罪の赦しに導くための悔い改めのバプテスマを授けることはできました。それがバプテスマのヨハネに与えられた役割でした。神様に背いている罪を認めて悔い改める、この悔い改めがされているなら、イエス様による罪の赦しにすぐに導いて行くことができます。そして、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は「みな」、ヨハネのもとにやって来て、自分の罪を告白し、バプテスマを受けたとマルコの福音書は記しています。
ルカの福音書に戻ります。
78 これは私たちの神の深いあわれみによる。そのあわれみにより、曙の光が、いと高き所から私たちに訪れ、
79 暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。」
79 暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。」
これは神様の深いあわれみによるものです。神様に背くことは、本来は決して赦されない重大な罪です。この罪を、神様は深いあわれみによって赦して下さいます。神の怒りにふれて赦されていない間は、暗闇と死の陰に住んでいます。そんな私たちに神様は光りを与えて下さり、救って下さいます。バプテスマのヨハネはその救いへの道を整えて備えるために遣わされました。
では、主の救いをほめたたえるザカリヤの賛歌の前半の部分を見たいと思います。68節から71節、
ルカ1:68 「ほむべきかな、イスラエルの神、主。主はその御民を顧みて、贖いをなし、
69 救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に立てられた。
70 古くから、その聖なる預言者たちの口を通して語られたとおりに。
71 この救いは、私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。
69 救いの角を私たちのために、しもべダビデの家に立てられた。
70 古くから、その聖なる預言者たちの口を通して語られたとおりに。
71 この救いは、私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。
71節に、この救いは私たちの敵からの救いであるとザカリヤは賛美しました。この場合の敵とは何でしょうか?目に見える形での敵としては、それは北王国を滅ぼしたアッシリアであり、南王国を滅ぼしたバビロニアでしょう。さらに言えば、このザカリヤの時代のユダヤを支配していたローマ帝国も敵と言えるでしょう。しかし、北王国と南王国が滅ぼされたのは、彼らの不信仰のゆえでした。預言者たちは再三にわたって王と民に、主に立ち返るように警告しました。しかし、それに聴き従わなかったために、不信仰の罪によって主の怒りにふれて滅ぼされてしまいました。
それゆえ、敵とはアッシリアやバビロニアなどのような外側の敵というよりは、不信仰という内側の敵でしょう。そして、その不信仰をあおっているのが悪魔です。敵である悪魔はあらゆる手を使って私たちの信仰を破壊しようとします。この敵からの救いは、74節でもう一度語られます。
72 主は私たちの父祖たちにあわれみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。
73 私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。
74 主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。
75 私たちのすべての日々において、 主の御前で、敬虔に、 正しく。
73 私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。
74 主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。
75 私たちのすべての日々において、 主の御前で、敬虔に、 正しく。
主は私たちを敵である悪魔の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださいます。
③自分への適用:恐れなく目に見えない全能の神を信じる
この敵である悪魔の攻撃がいかに強力であるか、最後の3番目のステップに進んで、パウロのエペソ人への手紙を見ることで分かち合いたいと思います。少し長いですが、エペソ6章のその部分を、週報のp.2にも載せておきました。お読みします。
エペソ6:10 終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。
11 悪魔の策略に対して堅く立つことができるように、神のすべての武具を身に着けなさい。
14 そして、堅く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを着け、
15 足には平和の福音の備えをはきなさい。
16 これらすべての上に、信仰の盾を取りなさい。それによって、悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。
17 救いのかぶとをかぶり、御霊の剣、すなわち神のことばを取りなさい。
18 あらゆる祈りと願いによって、どんなときにも御霊によって祈りなさい。
11 悪魔の策略に対して堅く立つことができるように、神のすべての武具を身に着けなさい。
14 そして、堅く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを着け、
15 足には平和の福音の備えをはきなさい。
16 これらすべての上に、信仰の盾を取りなさい。それによって、悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。
17 救いのかぶとをかぶり、御霊の剣、すなわち神のことばを取りなさい。
18 あらゆる祈りと願いによって、どんなときにも御霊によって祈りなさい。
とにかく悪魔はあらゆる手を使って私たちの信仰を破壊しようとしますから、神のすべての武具を取って神様に守っていただかなければなりません。
悪魔の代表的な手口は、人の霊性を弱めて神の霊を感じる霊的な能力を奪うことでしょう。先週ご一緒に見たマリアの賛歌でマリアは1章46節と47節のように賛美しました。
ルカ1:46 マリアは言った。「私のたましいは主をあがめ、
47 私の霊は私の救い主である神をたたえます。
47 私の霊は私の救い主である神をたたえます。
マリアは「私は主をあがめ」ではなく、「私のたましいは主をあがめ」と言って主をあがめました。「私は私の救い主である神をたたえます」ではなく、「私の霊は私の救い主である神をたたえます」と言って、神をたたえました。
この霊性が悪魔によって弱められると、目に見えない神ではなくて、目に見える形あるものを頼るようになり、偶像を礼拝するようになります。或いは形式を重んじる律法主義に陥ります。イエス様の時代のパリサイ人たちは、まさに形式的な律法主義に陥っていました。安息日に働かずに主に心を向けることは大切なことですが、だからと言って安息日に病人を癒したイエス様を批判したパリサイ人はあまりに形式にこだわっていました。隣人を愛し、病人を癒すことは主の御心に適うことです。それゆえイエス様は安息日でも病人を癒しました。
目に見えない神様は変幻自在のお方です。形式主義に陥ると、この変幻自在の神様が見えなくなります。クリスマスによく語られる「くつ屋のマルチン」の話は、イエス様がまさに変幻自在のお方であることを示していますね。
くつ屋のマルチンは、ある晩、聖書を読んでいる時にうたた寝をしてしまいます。その夢の中でイエス様が現れて、「マルチン、明日あなたの所に行きます」とおっしゃいました。翌日、マルチンはイエス様とお会いするのを楽しみにしながら、いつ来て下さるだろうとずっと窓の外を気にしていました。すると、窓の外で雪かきをしていたおじいさんが寒さで凍えている様子が見えたので、家の中に招き入れて、熱いお茶をごちそうしました。
その次には上着もなく薄着で赤ちゃんを抱えていた若い母親の姿が見えたので、先ほどと同じようにその母親を家の中に招き入れました。彼女はここ何日も満足に食事をしておらず、お乳も出なくなっていたということで、マルチンは彼女に食事を与えました。そうして上着も着させて送り出しました。
イエス様はなかなか現れませんでしたが、マルチンはイエス様を待ち続けて、くつ屋の仕事をしながら窓の外を見ていました。すると今度は、売り物のりんごを盗んだ少年をつかまえてお仕置きしようとしているおばあさんの姿が目に入ったので、マルチンは外に出て行き、りんごの代金を払って少年を赦してあげるように説得しました。人を赦すことはとても難しいことですが、おばあさんはそうしようと思いました。少年も赦されたことで、優しい気持ちになり、おばあさんの荷物を持ってあげました。
そうして、日が暮れました。マルチンはイエス様が来なかったことにガッカリしていました。その時、「マルチン、マルチン」とおっしゃるイエス様の声がして、おじいさんが現れました。そのおじいさんはイエス様の声で「わたしですよ」と言いました。次に若い母親が現れて、イエス様の声で「わたしですよ」とおっしゃいました。おばあさんと少年も現れて「わたしですよ」とおっしゃいました。
このように、イエス様は変幻自在に現れるお方です。11月の子供祝福礼拝では、「しんせつなサマリア人」という絵本を使って、ルカの福音書の「善きサマリア人のたとえ」の話をしました。強盗に襲われて大ケガをした人もまたイエス様でしょう。祭司とレビ人は、神殿での儀式という形式を重んじていたためでしょう、大ケガをした人を見て見ぬふりをして通り過ぎました。でも親切なサマリア人はケガ人を介抱しました。
おわりに
悪魔の策略によって霊性が弱められると、形式主義に陥って変幻自在の神様の姿が見えなくなります。すると、天地万物をお造りになった全知全能の神様も見えにくくなります。神様が全地全能のお方であると信じるなら、私たちはマリアが告白したように、はしため(女奴隷)もしくは僕(しもべ、奴隷)に過ぎません。それゆえ、マリアのように「あなたのおことばどおり、この身になりますように」としか言えない者であることが分かります。でも悪魔の策略によって目に見えない神様が見えづらくなると、自分の力で何とかしようと悪あがきをするようになります。そうして、主にお仕えすることができなくなってしまいます。
しかし、ザカリヤがほめたたえたように、「主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる」お方です。ですから、私たちは恐れなく主にお仕えして、マリアのように、「ご覧ください。私は主のはしためです。あなたのおことばどおり、この身になりますように」と信仰告白できるお互いであらせていただきたいと思います。
このことに思いを巡らしながら、しばらくご一緒にお祈りしましょう。
ルカ1:74 主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。