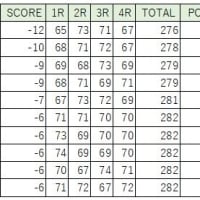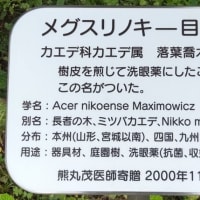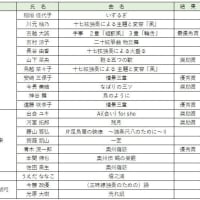幕末から明治時代にかけて活躍した生人形師・松本喜三郎の手による谷汲観音と聖観世音菩薩。谷汲観音は熊本市高平の淨国寺、聖観世音菩薩は熊本市春日の来迎院にそれぞれ納められている。この二つの観音像には奇しき縁があった。
明治11年、喜三郎は浅草での興業を最後に東京を離れ、各地を巡業しながら熊本に帰って来る。彼の最高傑作との評価が高い谷汲観音はこの時点では浅草寺伝法院の所蔵となっていたが、喜三郎は松本家の菩提寺である淨国寺に奉納したいと願っていた。その願いをかなえるため奔走したのが喜三郎の興業を世話していた永野弥七という人。実はこの人、来迎院のご住職・永野隆光上人の親戚にあたる。上人は前々から谷汲観音を来迎院へと願っていた。事情を察した喜三郎が、その替わりとして新たに制作したのが聖観世音菩薩なのである。生人形の興業用として作られた谷汲観音に対し、聖観世音は最初から観音像として作られた。
ちなみに観音像が身に纏う衣装は経年劣化するので、何年おきかに修復するのだそうだが、数年前に修復を手掛けたのが博多織屋次平さん。二つの観音像の修復に約2年の歳月を要したそうだ。
▼左が谷汲観音、右が聖観世音菩薩


明治11年、喜三郎は浅草での興業を最後に東京を離れ、各地を巡業しながら熊本に帰って来る。彼の最高傑作との評価が高い谷汲観音はこの時点では浅草寺伝法院の所蔵となっていたが、喜三郎は松本家の菩提寺である淨国寺に奉納したいと願っていた。その願いをかなえるため奔走したのが喜三郎の興業を世話していた永野弥七という人。実はこの人、来迎院のご住職・永野隆光上人の親戚にあたる。上人は前々から谷汲観音を来迎院へと願っていた。事情を察した喜三郎が、その替わりとして新たに制作したのが聖観世音菩薩なのである。生人形の興業用として作られた谷汲観音に対し、聖観世音は最初から観音像として作られた。
ちなみに観音像が身に纏う衣装は経年劣化するので、何年おきかに修復するのだそうだが、数年前に修復を手掛けたのが博多織屋次平さん。二つの観音像の修復に約2年の歳月を要したそうだ。
▼左が谷汲観音、右が聖観世音菩薩