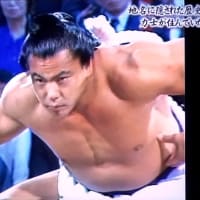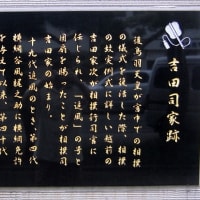今日はわが町壺川校区の正月恒例「どんどや」が京陵中学校のグラウンドで行われた。今年で51回目だそうである。消防団の皆さんが青竹で組み上げた櫓の前で、加藤神社宮司による神事の後、櫓に火が入るとたちまち紅蓮の炎が駆け昇る。門松や注連飾りが燃える炎とともにお迎えした歳神が真っ青な空へと還って行く。毎年繰り返される感動の瞬間だ。


【どんどやの由来】
どんどやの歴史は古く、今から約1000年前(平安時代)の記録に、三毬杖(さぎちょう)、左義長として知られ、これは宮中に於ける正月の年中行事で、三本の竹や木を組んで三脚にし、その上で、かがり火のように火を燃やした。
後年、宮中では正月十五日に清涼殿の東庭で天皇の吉書を焼き、それに扇子や短冊などを添えて焼いたが、その間、童が棒を振ったり、大鼓、鉦鼓を打って歌い囃して舞った。
また、この火祭りの行事は、日本中の極めて広い村や部落でも行われ、その呼び名も所によって、ドンド焼、サギチョウ等と様々であるが、人々はこの火を神聖視し、大きな力をみとめて次のような風習が信じられてきた。
1.年の初めに迎えた“年の神”を門松や注連飾りを燃やして、天へ送り返す。
2.この火で暖まると、子供達は益々元気に、老人は益々若返る。
3.この火に書初めを燃やし、その燃えさしが天高く揚がると手の上がるしるしとして喜んだ。
4.この火で餅や団子を焼いて食べると年中病気しない。



【どんどやの由来】
どんどやの歴史は古く、今から約1000年前(平安時代)の記録に、三毬杖(さぎちょう)、左義長として知られ、これは宮中に於ける正月の年中行事で、三本の竹や木を組んで三脚にし、その上で、かがり火のように火を燃やした。
後年、宮中では正月十五日に清涼殿の東庭で天皇の吉書を焼き、それに扇子や短冊などを添えて焼いたが、その間、童が棒を振ったり、大鼓、鉦鼓を打って歌い囃して舞った。
また、この火祭りの行事は、日本中の極めて広い村や部落でも行われ、その呼び名も所によって、ドンド焼、サギチョウ等と様々であるが、人々はこの火を神聖視し、大きな力をみとめて次のような風習が信じられてきた。
1.年の初めに迎えた“年の神”を門松や注連飾りを燃やして、天へ送り返す。
2.この火で暖まると、子供達は益々元気に、老人は益々若返る。
3.この火に書初めを燃やし、その燃えさしが天高く揚がると手の上がるしるしとして喜んだ。
4.この火で餅や団子を焼いて食べると年中病気しない。
以上
今年で壺川校区の「どんどや大会」は51回目になりますが、この日本古来の伝承的火祭りの行事を末永く、子供達に伝え、青少年が心身共に健全に育成され、豊かな人間になることを願っております。(壷川校区どんどや実行委員会)
♪ 童謡「左義長(さぎちょう)」北原白秋(赤い鳥 大正14年1月号)
(※歌詞は13番まであります)