大先輩のFさんから宿題を与えられている。それはかつて古式泳法の水連場として使われていた白川の淵のことである。以前、僕自身興味があったので、天神淵、八幡淵、傘淵については現地にも行ってこのブログ上にリポートした。今回、Fさんはそれ以外に「小淵」というのがあったと聞いていると仰る。「小淵」は初耳だったが、たしかにその名が見える文献もあるようだ。ネット検索や図書館に出向いて調べてみたが全然手がかりが見出せない。さらには国土省の白川出張所や熊本市の歴史文書資料室にも問い合わせてみたが、いずれも「小淵」についての資料が見つからないという返事だった。
今日ふと思いついて、以前、天神淵を調べに訪れたことのある渡鹿の菅原神社に行ってみた。間がいいことに宮司さんの奥様が境内におられたのでおたずねしてみた。奥様も聞いたことがないと仰る。しばらく淵談義に話が弾んだが、奥様が突然思い出したように「渡鹿堰の大井手取水口辺りが深みになっていたのでは…」と仰った。大井手取水口は現在、コンクリートの構築物になっているが、昔はおそらく全然違う姿だったと思われる。今日は確認するまでには至らなかったが、何となく答えが見えてきたような満足感で帰路についた。

渡鹿菅原神社・水分(みくまり)神社

天神淵があった辺り

渡鹿堰と大井手取水口
今日ふと思いついて、以前、天神淵を調べに訪れたことのある渡鹿の菅原神社に行ってみた。間がいいことに宮司さんの奥様が境内におられたのでおたずねしてみた。奥様も聞いたことがないと仰る。しばらく淵談義に話が弾んだが、奥様が突然思い出したように「渡鹿堰の大井手取水口辺りが深みになっていたのでは…」と仰った。大井手取水口は現在、コンクリートの構築物になっているが、昔はおそらく全然違う姿だったと思われる。今日は確認するまでには至らなかったが、何となく答えが見えてきたような満足感で帰路についた。

渡鹿菅原神社・水分(みくまり)神社

天神淵があった辺り

渡鹿堰と大井手取水口











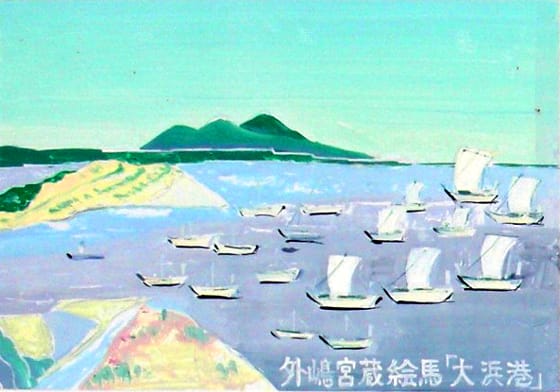



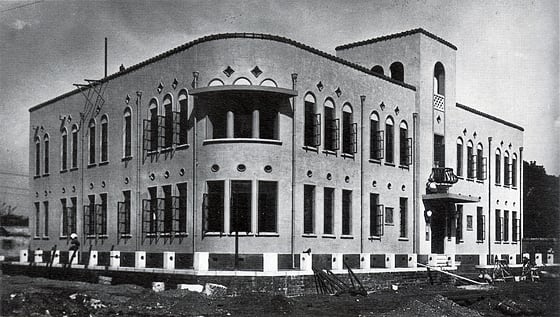









 江戸時代初期に書かれた史書「当代記」によれば、慶長12年(1607)の2月20日に、お国かぶきは江戸に招かれ、江戸城本丸・西の丸で勧進かぶきを行なった。慶長8年(1603)、京の都で、出雲の巫女であった国と名のる女芸能者により始まったかぶき踊りは大評判となり、その4年後、ついに能・狂言に次ぐ位の芸能として認知されたのである。この1週間前の2月13日からは、同じ場所で観世・金春の勧進能が行われており、お国は能役者とほとんど同格の扱いを受けたという。
江戸時代初期に書かれた史書「当代記」によれば、慶長12年(1607)の2月20日に、お国かぶきは江戸に招かれ、江戸城本丸・西の丸で勧進かぶきを行なった。慶長8年(1603)、京の都で、出雲の巫女であった国と名のる女芸能者により始まったかぶき踊りは大評判となり、その4年後、ついに能・狂言に次ぐ位の芸能として認知されたのである。この1週間前の2月13日からは、同じ場所で観世・金春の勧進能が行われており、お国は能役者とほとんど同格の扱いを受けたという。





 大河ドラマ「べらぼう」の物語の舞台は吉原遊郭。苦界に身を沈めた遊女たちにとって心の拠りどころとなっていたのが、廓内にあった四つの神社、九郎助稲荷、開運稲荷、榎本稲荷、明石稲荷だったといわれる。明治維新後、これらの神社は合祀され現在は吉原神社となっている。とりわけ崇敬を集めていたのが九郎助稲荷だったそうだ。「べらぼう」には九郎助稲荷の神使であるおキツネ様の化身として花魁姿の綾瀬はるかが登場する。彼女はナレーションも担当しているので「狂言回し」的な役がらなのだろう。
大河ドラマ「べらぼう」の物語の舞台は吉原遊郭。苦界に身を沈めた遊女たちにとって心の拠りどころとなっていたのが、廓内にあった四つの神社、九郎助稲荷、開運稲荷、榎本稲荷、明石稲荷だったといわれる。明治維新後、これらの神社は合祀され現在は吉原神社となっている。とりわけ崇敬を集めていたのが九郎助稲荷だったそうだ。「べらぼう」には九郎助稲荷の神使であるおキツネ様の化身として花魁姿の綾瀬はるかが登場する。彼女はナレーションも担当しているので「狂言回し」的な役がらなのだろう。 この塔は室町時代にはすでに著名であったという。この塔のまわりを取り囲む玉垣の寄進者名が塔の門柱に刻まれている。この玉垣は昭和10年に熊本市の水前寺北郊で開催された「新興熊本大博覧会」の際に造られたものらしい。そしてその寄進者名には二本木遊郭の妓楼名がずらりと並んでいる。なぜ、二本木遊郭がこぞって寄進したかというと、檜垣が遊女たちの守り神として崇敬されていたからである。歌人として知られる檜垣は若い頃、都の白拍子(しらびょうし)だったと伝えられる(諸説あり)。白拍子というのは高貴な人たちを相手に歌舞を行なう遊女だったといわれる。二本木遊郭の遊女たちは、ほど近い蓮台寺に祀られた檜垣を心の拠りどころとして生きていたのである。
この塔は室町時代にはすでに著名であったという。この塔のまわりを取り囲む玉垣の寄進者名が塔の門柱に刻まれている。この玉垣は昭和10年に熊本市の水前寺北郊で開催された「新興熊本大博覧会」の際に造られたものらしい。そしてその寄進者名には二本木遊郭の妓楼名がずらりと並んでいる。なぜ、二本木遊郭がこぞって寄進したかというと、檜垣が遊女たちの守り神として崇敬されていたからである。歌人として知られる檜垣は若い頃、都の白拍子(しらびょうし)だったと伝えられる(諸説あり)。白拍子というのは高貴な人たちを相手に歌舞を行なう遊女だったといわれる。二本木遊郭の遊女たちは、ほど近い蓮台寺に祀られた檜垣を心の拠りどころとして生きていたのである。 今日は磐根橋を渡った先から坪井の方へ降りる道を散歩した。曲がりくねった坂を下りながら、3年前、熊本博物館学芸員の中原幹彦先生からお誘いいただき、考古学講座の皆さんと熊本県伝統工芸館の裏にかつてあった坪井川船着場の現地調査に参加させていただいた時のことを思い出した。旧坪井川の船着場跡のほか棒庵坂から下る「あずき坂」や旧坪井川に架かる「折栴檀橋」の痕跡をと思ったのだが、残念ながら生い茂った草木で前に進めず断念した。
今日は磐根橋を渡った先から坪井の方へ降りる道を散歩した。曲がりくねった坂を下りながら、3年前、熊本博物館学芸員の中原幹彦先生からお誘いいただき、考古学講座の皆さんと熊本県伝統工芸館の裏にかつてあった坪井川船着場の現地調査に参加させていただいた時のことを思い出した。旧坪井川の船着場跡のほか棒庵坂から下る「あずき坂」や旧坪井川に架かる「折栴檀橋」の痕跡をと思ったのだが、残念ながら生い茂った草木で前に進めず断念した。








