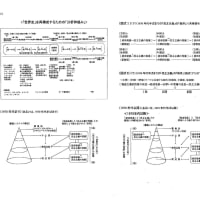なぜ今『21世紀の孫子の兵法』を語る必要があるのだろうかー私の「システム論」から紀元前5百年頃の『孫子の兵法』と21世紀のそれとの「違い」について考えるとき
ごく簡単に言えば、『孫子の兵法』は、「一国枠」で語られる「敵」と「己」に関する戦い方の話であるのに対して、21世紀のそれは「関係枠」を基にした戦い方に関する物語であるということになるだろう。21世紀における「敵」は、それこそ複雑な関係の中でつくられており、「己」と「敵」の境界が見えないのだ。もっと大胆に言えば、「敵」の中に「己」が組み込まれており、戦うこと自体が、最初から難しい話とならざるを得ないのである。
ところが、メディアの世界では、不思議なほどに、今なお『孫子の兵法』の時代を彷彿とさせる論議が、これでもかと思うほど行われているのだ。たとえば、中国がどうした、米国がそれにどのように反応したかとか、また韓国と北朝鮮の敵対関係がどのような展開を見せるのか、また世界遺産登録を巡る軍艦島などの「歴史問題」が、どういうわけなのか韓国対日本の二項対立の構図で、もっぱら語られるのだから、何をかいわんやなのである。
そんな話はおかしいし、そもそも違うだろうが。「敵」と「己」の関係は、それこそ開国以降の日本と日本を取り巻く欧米列強の関係をみても、またそこに組み込まれた朝鮮半島を始めとしたアジア諸地域との関係をみても、とても「一国枠」では語れない代物ではあるまいか。ここで補足しておくと、「一国枠」とは、「単一の」主権国家、国民国家の存在を指している。
私たちの日本という国家の建設の歩みを考えてみても分かるように、日本という主権国家は日本一国だけでは建設できなかったのだ。同時にまた、「日本人」だけの力で国家建設ができたわけではない。すべてが、「敵」と「己」ではなく、「敵と己」との「相互関係」の中でつくり出されてきたことに注意すべきなのである。無論この話は、日本だけに限定されるものではない。すべての主権国家、国民国家と呼ばれる国家建設にも該当する話である。
ところがなのだ。21世紀のこの時点においても、マスコミにおける「国際政治」の話は、ほとんどすべてが一国枠の話から一歩も出るものではない。「国際関係」を語る論者も、言葉の正確な意味における「関係」を語っていないのである。たとえば、自由、民主主義、人権の話をする場合にも、中国と香港との関係の中で、それは如実に示されることとなる。
「自由民主主義」の歴史を語る際、見事なほどに一国枠で語られることから、たとえば、今の香港問題において、中国の政治体制を批判して、中国も自由民主主義体制の国とならなければならない、と強い口調で中国の香港に対する抑圧姿勢を非難する論者は、その中国がそれこそ、1840年代以降の欧米列強の軍事介入とそれに伴う中国の植民地化政策(イギリスへの香港割譲はその一つの例である)を、当のイギリスや米国やフランスに代表される当時の自由民主主義国の歩みを批判したり、そうした歴史の背後に存在した理由を考察することはない。
せいぜいのところが、21世紀の今日においても、イギリスは確かに大英帝国を建設して、帝国主義国家の歩みを示したが、それにもかかわらず、イギリスがつくり出した自由や民主主義、法の精神といった普遍的価値は、「国際公共財」としての重要な遺産として、評価することを忘れてはならない云々の議論に終始するばかりである。
どういうわけなのか、そうした国際公共財としての普遍的価値を世界に提示したはずのイギリスなのに、そのイギリスが、そうした価値の実現をアジアやアフリカ諸国には許さないで、植民地や従属地としたのかに関する考察は、深められることなく、放置されたままなのである。つまり、自由民主主義国の建設の歩みと帝国主義の歩みとがどのように関係しているかに関する議論はほとんど手つかずのままなのである。
それにもかかわらず、先の中国の香港に対する、自由や民主主義の実現要求を抑圧する姿勢に対しては、ことのほか中国批判・非難はエスカレートする一方なのだ。おかしな話ではあるまいか。自由民主主義国家の建設に邁進していた先のイギリスや米国やフランスは、アヘン戦争から中華人民共和国の建設に至る感において、中国が要求する主権回復や関税自主権の求めに応じないままに、中国大陸での彼らの利権確保と対日戦争を有利にするために、中国の二つの勢力を甘言を弄しながら利用していたこと(勿論、そこには国民党や共産党もそうした諸国を利用していたことは言うまでもないこと)に対して、目を向けないのは何故なのだろうか。付言すれば、こうした諸国間の対立敵対関係は、一国枠を前提とする「敵」と「己」の二項対立図式からは理解できない話であるのは、間違いないだろう。
私たち日本と日本人の歴史を振り返るとき、未だに開国以降の関係の枠の中で生き続けていることを忘れてはならない。そして我々に開国を迫った欧米列強は、既にそうした関係枠から成る国際関係をつくり出してきたことに留意するならば、私たちは開国以前に欧米列強がつくり出した「近代の潮流」と向き合い、その全体像を描くことを試みる必要があるだろう。
結論を先取りして言えば、私はそれを「システム」とその「関係の歩み」(以下、「システム」と略す。)として描いてきたのである。何度も指摘したように、その全体像は、拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」-「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」セカイ・世界とそこでのセンソウ・戦争』(晃洋書房 2014年)所収の88-91頁の図式のモデルとして提示しているので、ぜひ参照いただきたい。
私のモデルを基にして、先の韓国と日本の間における「過去の歴史」問題を考えるとき、そしてそれは決して過去の問題などではなく、未だに続いている私たちの開国以降の関係の歴史それ自体に他ならないのだが、韓国との関係に対して、そしてこれから起こるに違いない北朝鮮との関係に対して、そして今後もますます歴史問題をカードとして利用する可能性の高い中国との関係に対して、日本外交が、私がここで開陳してきた開国以降の近代化の歴史に見る関係を、それこそ一国枠としての日本の国益にとらわれるのではなくて、日本という「己」が組み込まれてきた「敵」としての関係の歩みに配慮して、かつての日本の「侵略」戦争とその歴史問題を捉え直すならば、今以上に、韓国や北朝鮮、中国との距離は近くなるかもしれない。
ただし、そのためには、従来のような米国一辺倒の、またことさらに中国を敵として位置付ける日本外交の姿勢を改めなければならない。勿論、これはそれほどたやすいことではないし、一歩誤れば、相当に危うい状況に追い込まれるかもしれない。だからこそなのだ。
私たちがいま求められているのは、世界に向かって、私たちの国際関係の歴史を、そして日本の場合は、その中の日本の歴史を、日本と日本人の国益を守るために、『孫子の兵法』に依拠して、一国枠の世界観に立脚した「敵」と「己」の関係から、己を主張するのはやめるべきである。と言うのも、「国益」自体が、「関係」を前提としているからに他ならない。
そうではなくて、むしろ『21世紀の孫子の兵法』が語る関係枠を前提とした、日本も韓国も、北朝鮮も中国も、そして米国やイギリスやその他の国々が、「敵と己」としての相互に関係する「システム」を構成する要素であるとの観点から、「己」を捉え直すことの意義と意味を世界に発信することではなかろうか。それこそが、今なお「敵国条項」にある「敵」として、いつ攻撃されてもかまわないとされている、私たち日本と日本人のこれからの重要な責務となるだろう。
その意味でも、従来の欧米主導の中でつくられてきた一国枠、一地域枠の普遍的価値とそれに依拠した国際関係の歩みの実現に替えて、関係枠を前提とする新たなる普遍的価値の創造と、それに依拠した国際関係の歩みの実現を模索することが、今後ますます必要不可欠な仕事となるだろう。私は切に願うのである。先ずは手始めに、こうした地点から、過去の戦争とそれに伴う歴史問題の解決に向き合ってみたらどうか、と。
これらの問題解決のためには、どうしても次期覇権国となるだろう中国と中国人の力を借りなければならない。そのためにも、中国と中国人に対するこれまでの日本と日本人の厚顔無恥なる態度を改め、もっと謙虚な姿勢で中国の指導を仰ぐことが、何よりも肝要だと私は考えるのである。
そのためには、これまで当然とされてきた私たちの「知」そのものを、別の「知」へと変えていく必要があるだろう。それは、すなわち「一国枠」から「関係枠」の「知」へに、と言うことである。ここでも私は読者に望みたい。「一国枠」の「民主主義」論に替わる「関係枠」の「民主主義」論を、私たちの手にしてみてはどうか、と。
ごく簡単に言えば、『孫子の兵法』は、「一国枠」で語られる「敵」と「己」に関する戦い方の話であるのに対して、21世紀のそれは「関係枠」を基にした戦い方に関する物語であるということになるだろう。21世紀における「敵」は、それこそ複雑な関係の中でつくられており、「己」と「敵」の境界が見えないのだ。もっと大胆に言えば、「敵」の中に「己」が組み込まれており、戦うこと自体が、最初から難しい話とならざるを得ないのである。
ところが、メディアの世界では、不思議なほどに、今なお『孫子の兵法』の時代を彷彿とさせる論議が、これでもかと思うほど行われているのだ。たとえば、中国がどうした、米国がそれにどのように反応したかとか、また韓国と北朝鮮の敵対関係がどのような展開を見せるのか、また世界遺産登録を巡る軍艦島などの「歴史問題」が、どういうわけなのか韓国対日本の二項対立の構図で、もっぱら語られるのだから、何をかいわんやなのである。
そんな話はおかしいし、そもそも違うだろうが。「敵」と「己」の関係は、それこそ開国以降の日本と日本を取り巻く欧米列強の関係をみても、またそこに組み込まれた朝鮮半島を始めとしたアジア諸地域との関係をみても、とても「一国枠」では語れない代物ではあるまいか。ここで補足しておくと、「一国枠」とは、「単一の」主権国家、国民国家の存在を指している。
私たちの日本という国家の建設の歩みを考えてみても分かるように、日本という主権国家は日本一国だけでは建設できなかったのだ。同時にまた、「日本人」だけの力で国家建設ができたわけではない。すべてが、「敵」と「己」ではなく、「敵と己」との「相互関係」の中でつくり出されてきたことに注意すべきなのである。無論この話は、日本だけに限定されるものではない。すべての主権国家、国民国家と呼ばれる国家建設にも該当する話である。
ところがなのだ。21世紀のこの時点においても、マスコミにおける「国際政治」の話は、ほとんどすべてが一国枠の話から一歩も出るものではない。「国際関係」を語る論者も、言葉の正確な意味における「関係」を語っていないのである。たとえば、自由、民主主義、人権の話をする場合にも、中国と香港との関係の中で、それは如実に示されることとなる。
「自由民主主義」の歴史を語る際、見事なほどに一国枠で語られることから、たとえば、今の香港問題において、中国の政治体制を批判して、中国も自由民主主義体制の国とならなければならない、と強い口調で中国の香港に対する抑圧姿勢を非難する論者は、その中国がそれこそ、1840年代以降の欧米列強の軍事介入とそれに伴う中国の植民地化政策(イギリスへの香港割譲はその一つの例である)を、当のイギリスや米国やフランスに代表される当時の自由民主主義国の歩みを批判したり、そうした歴史の背後に存在した理由を考察することはない。
せいぜいのところが、21世紀の今日においても、イギリスは確かに大英帝国を建設して、帝国主義国家の歩みを示したが、それにもかかわらず、イギリスがつくり出した自由や民主主義、法の精神といった普遍的価値は、「国際公共財」としての重要な遺産として、評価することを忘れてはならない云々の議論に終始するばかりである。
どういうわけなのか、そうした国際公共財としての普遍的価値を世界に提示したはずのイギリスなのに、そのイギリスが、そうした価値の実現をアジアやアフリカ諸国には許さないで、植民地や従属地としたのかに関する考察は、深められることなく、放置されたままなのである。つまり、自由民主主義国の建設の歩みと帝国主義の歩みとがどのように関係しているかに関する議論はほとんど手つかずのままなのである。
それにもかかわらず、先の中国の香港に対する、自由や民主主義の実現要求を抑圧する姿勢に対しては、ことのほか中国批判・非難はエスカレートする一方なのだ。おかしな話ではあるまいか。自由民主主義国家の建設に邁進していた先のイギリスや米国やフランスは、アヘン戦争から中華人民共和国の建設に至る感において、中国が要求する主権回復や関税自主権の求めに応じないままに、中国大陸での彼らの利権確保と対日戦争を有利にするために、中国の二つの勢力を甘言を弄しながら利用していたこと(勿論、そこには国民党や共産党もそうした諸国を利用していたことは言うまでもないこと)に対して、目を向けないのは何故なのだろうか。付言すれば、こうした諸国間の対立敵対関係は、一国枠を前提とする「敵」と「己」の二項対立図式からは理解できない話であるのは、間違いないだろう。
私たち日本と日本人の歴史を振り返るとき、未だに開国以降の関係の枠の中で生き続けていることを忘れてはならない。そして我々に開国を迫った欧米列強は、既にそうした関係枠から成る国際関係をつくり出してきたことに留意するならば、私たちは開国以前に欧米列強がつくり出した「近代の潮流」と向き合い、その全体像を描くことを試みる必要があるだろう。
結論を先取りして言えば、私はそれを「システム」とその「関係の歩み」(以下、「システム」と略す。)として描いてきたのである。何度も指摘したように、その全体像は、拙著『21世紀の「日本」と「日本人」と「普遍主義」-「平和な民主主義」社会の実現のために「勝ち続けなきゃならない」セカイ・世界とそこでのセンソウ・戦争』(晃洋書房 2014年)所収の88-91頁の図式のモデルとして提示しているので、ぜひ参照いただきたい。
私のモデルを基にして、先の韓国と日本の間における「過去の歴史」問題を考えるとき、そしてそれは決して過去の問題などではなく、未だに続いている私たちの開国以降の関係の歴史それ自体に他ならないのだが、韓国との関係に対して、そしてこれから起こるに違いない北朝鮮との関係に対して、そして今後もますます歴史問題をカードとして利用する可能性の高い中国との関係に対して、日本外交が、私がここで開陳してきた開国以降の近代化の歴史に見る関係を、それこそ一国枠としての日本の国益にとらわれるのではなくて、日本という「己」が組み込まれてきた「敵」としての関係の歩みに配慮して、かつての日本の「侵略」戦争とその歴史問題を捉え直すならば、今以上に、韓国や北朝鮮、中国との距離は近くなるかもしれない。
ただし、そのためには、従来のような米国一辺倒の、またことさらに中国を敵として位置付ける日本外交の姿勢を改めなければならない。勿論、これはそれほどたやすいことではないし、一歩誤れば、相当に危うい状況に追い込まれるかもしれない。だからこそなのだ。
私たちがいま求められているのは、世界に向かって、私たちの国際関係の歴史を、そして日本の場合は、その中の日本の歴史を、日本と日本人の国益を守るために、『孫子の兵法』に依拠して、一国枠の世界観に立脚した「敵」と「己」の関係から、己を主張するのはやめるべきである。と言うのも、「国益」自体が、「関係」を前提としているからに他ならない。
そうではなくて、むしろ『21世紀の孫子の兵法』が語る関係枠を前提とした、日本も韓国も、北朝鮮も中国も、そして米国やイギリスやその他の国々が、「敵と己」としての相互に関係する「システム」を構成する要素であるとの観点から、「己」を捉え直すことの意義と意味を世界に発信することではなかろうか。それこそが、今なお「敵国条項」にある「敵」として、いつ攻撃されてもかまわないとされている、私たち日本と日本人のこれからの重要な責務となるだろう。
その意味でも、従来の欧米主導の中でつくられてきた一国枠、一地域枠の普遍的価値とそれに依拠した国際関係の歩みの実現に替えて、関係枠を前提とする新たなる普遍的価値の創造と、それに依拠した国際関係の歩みの実現を模索することが、今後ますます必要不可欠な仕事となるだろう。私は切に願うのである。先ずは手始めに、こうした地点から、過去の戦争とそれに伴う歴史問題の解決に向き合ってみたらどうか、と。
これらの問題解決のためには、どうしても次期覇権国となるだろう中国と中国人の力を借りなければならない。そのためにも、中国と中国人に対するこれまでの日本と日本人の厚顔無恥なる態度を改め、もっと謙虚な姿勢で中国の指導を仰ぐことが、何よりも肝要だと私は考えるのである。
そのためには、これまで当然とされてきた私たちの「知」そのものを、別の「知」へと変えていく必要があるだろう。それは、すなわち「一国枠」から「関係枠」の「知」へに、と言うことである。ここでも私は読者に望みたい。「一国枠」の「民主主義」論に替わる「関係枠」の「民主主義」論を、私たちの手にしてみてはどうか、と。