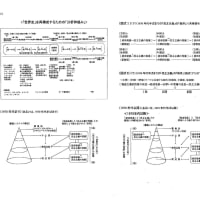「在沖米軍基地」移転の賛否を問う「沖縄県民投票」を巡るマスコミ報道から零(こぼ)れ落ちた「問題」を、「システム」とその関係の歩みから考えるとき
今回も前回からの記事の続きを書くつもりでいたが、そうした記事を紹介する前に、やはり沖縄米軍基地の普天間から辺野古への基地移転の是非を巡る「沖縄県民投票」に関して、システムの自己完結モデルに依拠しながら、少し言及しておきたい。
最初に断っておくが、沖縄の県民投票を受けて、日本政府や日本国民がどのような関わり方をするべきか、あるいは沖縄の民主主義を黙殺してはならない、日本の民主主義の真価が今こそ問われているのだ、沖縄の抱える問題に背を向けてはならない云々の議論に直接ここでは向き合わない。正直に言えば、向き合えないのだ。私には日本政府や米国政府と刺し違えても最後まで取り組むとの覚悟がない。上述の議論は巡り巡ってそこまで、私たちを導くだろう。つまり日本政府とその後ろに控えている米国政府との「戦争」を覚悟しなければならなくなるからだ。
しかしながら、急いで付言すれば、そうした戦争は、果たして日本政府や米国政府だけに限られたものなのか。米軍を追い出しても(もっとも、それさえもはるかに実現困難なことだが)、次にまた別の国の軍隊が日本や沖縄を占拠、占領する可能性を、今の時点でもって、すべて否定しさるのはできないだろう。先の「民主主義」に関わる議論には、初めからこうした覇権システム内における「力」と「力」のぶつかり合いを前提とした「親分ー子分」関係に見る帝国主義にともなう基本的問題が組み込まれていないのだが、それは一体どうしてなのか。そこには、民主主義と帝国主義の親和的な相矛盾しない相互に補完する関係とそれが抱えてきた問題を、議論の最初から視野の外においている、おこうとしている、そうした態度それ自体にも気づかないのは、誠に残念としか言いようがないのである。
こうした議論の在り方と同様に、以下に紹介する議論についても、ここでは関われないことを断っておく。すなわち、在沖米軍基地のある沖縄は地政学的観点からも軍事的要衝であり、いわゆる「冷戦の終焉」以降の世界情勢も、世界の平和と安定において、いまだに予断を許さない一触触発の緊迫した局面にある。朝鮮半島の情勢も、韓国と北朝鮮の両国間には緊張と緩和の流れが交互に継続しており、そこに今の日韓関係の悪化や北朝鮮による日本人拉致問題や核開発疑惑問題が重なる中で、さらには中国の軍事力の増強、増大と東シナ海の尖閣諸島の領有権問題を巡る中国側からのあからさまの、力づくの対応を見るにつけ、これまで同様に、いやそれ以上に、米軍による日本プレゼンスは、アジアの平和と安定の確保において、また「日本」と「日本人」の安全保障の実現において、無くてはならない存在なのだ。それゆえ、日米安保体制の存続とその同盟強化は日米関係において必要不可欠であることから、日本国内はもとより、在沖米軍基地の重要性も論を待たない。ただし、沖縄に集中する基地問題を解決するためにも、まずは普天間辺野古への基地移転は避けられないものとなってくる。沖縄の「民意」を逆なでするのではない。日本の防衛問題と沖縄における基地負担の軽減問題を共に視野の内に入れながら、今後も日本政府は米国政府との協力関係を維持発展させていく云々の議論である。
この議論の前提がそもそも怪しいのだ。今後も米国の軍事力が中国のそれを牽制、制御できるかのような前提に立っている。何よりも、歴代の覇権国の興亡史を的確に分析、整理した作業が何ら提示されていない。もし米国と中国の間に、米中安保同盟が締結されたならば、これまで何十年も当然のこととしてきた基地容認論者にみる先の議論とその前提が一瞬にして崩れ去ってしまうだろう。驚くべきは、「日本」と「日本人」を取り巻く国際関係におけるこうした未来図を、日本政府とその関係者が今後起こりうる重大事態の一つとして、何ら考慮しないままに、真面目に日本外交を論じてきたことである。これほど笑止千万な話はあるまい。
こうした点を踏まえながら、以下に私の持論を展開していこう。これもまた拙著や拙稿で論及してきた内容ではあるが、今一度ここで論じ直しておきたい。
1970年代までのシステムの歩み
①{[A]→(×)[B]→×[C]}
(このモデルは何度も断っているように、省略形の共時的モデルである。)
この時期の在沖米軍基地の存在目的は、上記のA、B、Cのシステムとその関係の歩みを擁護するためである。とくにシステムの高度化を実現する上で、覇権システムの維持と安定は不可欠の前提となる。その意味では、日本や米国を、また沖縄を守るためではないことをまずは確認しておきたい。在沖米軍基地の存在は、それ自体が覇権システムを強化し、強固にするのに与っている。そしてそのことが70年代以前のシステムの高度化の実現に導くと同時に、70年代以降のシステムとその関係の歩みを準備しながら、その形成と発展を促すのである。
1970年代以降のモデル
②{[B]→(×)[C]→×[A]]
(このモデルは何度も断っているように、省略形の共時的モデルである。)
この時期の在沖米軍基地の存続目的は、70年代以前のそれとは異なり、70年代以降のB、C、Aの関係から構成されるシステムとその関係の歩みを防衛するためである。ここでも日本や米国を守るためのものではないし、ましてや沖縄でもない。こうした点をまずは確認しておかねばならない。70年代以前の時期と同様に、ここでも付言すれば、在沖米軍基地の存在は、それ自体が覇権システムを強化し、強固にするのに与っている。
それゆえ、70年代以降のシステムとその関係の歩みを防衛するということは、何よりもBグループの先頭に位置する中国を防衛しているということだ。次期覇権国として台頭する中国を念頭に置けば、もはや在沖米軍基地の役割も、あと数十年年で、少なくとも朝鮮半島の統一の実現が確実になるころには、米軍の存在意義はかなり低下するであろう。今後は在沖中国軍基地化の様相を帯びてくる可能性が高くなるのではあるまいか。その関連で言えば、覇権システムにおいて、第9条では国民を守れないのは確かであり、それは単なるお飾りでしかないことを踏まえて、あえて言うならば、次期覇権国として台頭する国のすぐ横で、9条を見直して改憲すべきだとか、米国の力の存在をあてにした集団的自衛権の行使を高らかに叫ぶよりは、たとえどうすることもできない第9条をお飾りとして掲げる方が、日本の安全を考える際に、まだ少しはましな方策ではないか、と自虐的に私は見ている。とにかく、どちらの選択肢も満足のいくものではないのは確かなことだ。
それでは、もう一度ここで覇権システムに関する重要な問題を述べておきたい。モデルで描く外側の{ }の記号は覇権システムを表している。このモデルからわかることは、覇権システムの力でもって、A、B、Cにおける、あるいはB、C、Aにおける軍事力の衝突を介した力の暴発・暴走を抑え込んでいるのである。換言すれば、その暴発あるいは暴走が覇権システムの抑止・制御する力を凌駕した時に、覇権システムはその存在意義を失うこととなり、その瞬間に、システムとその関係の歩みは瓦解・頓挫せざるを得なくなる。
しかしながら、これまでの覇権システムの歴史を見る限り、いまだにそうした事態は生じたことがない。たとえA、B、C内で、軍事的爆発、暴走が生起したとしても、例えば世界大戦における場合を引き合いに出してみても分かるように、これまでの歴史が物語るのは、覇権システムの抑圧、抑止する力が結局のところは、優越、優位してきたことである。そこには、歴代の覇権国間において、覇権のバトンの引き渡し、引き継ぎにおいて現覇権国と次期覇権国との間にある種の「了解事項」が存在している、と私はこれまでの拙論で紹介してきた。
こうした観点から、70年代以前の在沖米軍基地と70年代以降の、とくに2030年前後以降の在沖中軍基地の可能性を推察するのである。もっともその「基地(化)」の在り様は米国のそれとは異なるであろう。最初は、中国軍艦や空母、潜水艦の寄港地としての基地提供から始まるだろう。
こうした「最悪の事態」を避けるためにも、だから在沖米軍基地は、日米安保体制は必要だとの声が聞こえてきそうだが、果たしてそうだろうか。日本は20世紀初頭に、日英同盟を結んでいた。その当時の英国は覇権国としての地位を失いかけてはいたが、なおそれでも覇権国として君臨していた。ところが1923年になると、次期覇権国として台頭し始めた米国からの「要請」で、日英同盟は破棄される(失効する)に至った。私には、こうした日英と英米間の関係が、今また日米と米中間で展開されているかのように思われるのだ。すぐ上で「最悪の事態」と述べたが、正確には、その始まりに過ぎない。
日英同盟の破棄によって、米国は日本と戦争しやすいチャンスを手に入れることができた。紆余曲折はあったものの、日米は衝突し、日本の敗北を見た。その敗北は、70年代以前までのシステムとその関係の歩みを強化し、システムの高度化に寄与した。同じように、今また、日米安保体制という日米同盟が破棄されたならば、中国は日本と戦争しやすいチャンスを得ることとなる。仮に日本が敗北して中国の勝利となれば、それは70年代以降のシステムとその関係の歩みを強化し、システムの高度化に寄与するであろう。中国は日本とのこの先の戦争を自覚し、その準備を着々と進めている。
そのために、東シナ海での尖閣諸島をめぐる「攻防」で日本の出方をうかがっているのは確かだろう。そこから、日米同盟が破棄された場合には、中国はあの手この手で日本に対して揺さぶりをかけてくるだろうが、その一つが先の寄港地を日本に呑ませる動きに出るのではあるまいか。今の日韓問題をめぐる日本政府や日本人の対応を見る限りでは、日本と中国の関係も相当にぎくしゃくしたものとなるのは必至であろう。そこを中国は、そして米国も狙ってくるに違いない。おそらく朝鮮半島の統一を巡る動きが加速するにつれて、「日本」と「日本人」はますます危うい局面に立たされることになる。システムの高度化にはやはり戦争が必要不可欠となることから、米中覇権連合を推進する勢力はその好機を狙っている。
こうした脈略からもう少し言及するならば、在沖米軍基地から米軍の撤退にともなう「力の空白」状況・状態が生まれることが予想される。その際、米中覇権連合の推進勢力は、したたかな計算のもとで、そうした空白状況・状態を引き起こすに違いない。その勢力の中には、第二次世界大戦中の日米戦争時に見られたように、「日本人」の協力者が必ず存在しているだろう。戦後の米国占領期から以降、GHQや米国政府に協力した「日本人」は戦時期の日本側における協力者であったが、今後予想される日中戦争後の「日本」と「日本人」を指導する中国政府への日本人協力者も、そうした戦時期の日本側における協力者であろう。その時になって、本来の意味における「売国奴」の正体がわかるだろう。その多くは現在の安倍政権や日米同盟に反対する人々である可能性が高い、と私は見ている。しかし、もうその時には、売国奴云々の議論もできなくなっているに違いない。
いずれにせよ、「日本」と「日本人」には、面白くも可笑しくもない話ではあるが、私はすぐ上で述べたシナリオ実現の蓋然性の高いことを予期している。もし私の見通したように事態が進行していくならば、もうその時にはなすすべもないこととなるのは必至である。私たちは、在沖米軍基地問題を、もっぱら沖縄の民主主義とか日本の民主主義という次元から、また対米国問題といった次元を念頭に置いて論じているように、決して「三つ」の下位システム、すなわち、覇権システム、世界資本主義システム、世界民主主義システムから成る「一つ」のシステムとその関係の歩みにおける転換、変容といった次元を視野の内に含んだ論議を行ってこなかったのではあるまいか。システムとその関係の歩みからすれば、「日本」と「日本人」のあまりにも米国一辺倒に、また日本の沖縄の民主主義問題に傾斜した論の流れは、言うまでもなく好都合なのだ。私たちの議論はほとんどが「内向き」のそれであり、日本を取り巻く、外からの、外側に位置した相手側に立った議論とはなっていないのだ。あまりにもお人好しな、独りよがりな話に終始してきただけだと述べるのは、言い過ぎなのであろうか。
逆に言えば、普通の日本人には厄介極まりない深刻な事態となる。そうした事態を少しも想像していないかのような、先の「沖縄の県民投票とその結果」報道の中で、私たちは今一番、肝心な問題に向き合わないままでいるのだが、暗愚な首相を擁く愚鈍な国民だからではとても済まされないことである、と私は言わざるを得ないのだ。
それではどうしてこのような「内向き」の議論に終始するのか。そうした背景を探りながらさらに以下に論を進めていきたい。この問題の考察は、前回までのブログ記事の内容と密接に関連してくるのである。
今回も前回からの記事の続きを書くつもりでいたが、そうした記事を紹介する前に、やはり沖縄米軍基地の普天間から辺野古への基地移転の是非を巡る「沖縄県民投票」に関して、システムの自己完結モデルに依拠しながら、少し言及しておきたい。
最初に断っておくが、沖縄の県民投票を受けて、日本政府や日本国民がどのような関わり方をするべきか、あるいは沖縄の民主主義を黙殺してはならない、日本の民主主義の真価が今こそ問われているのだ、沖縄の抱える問題に背を向けてはならない云々の議論に直接ここでは向き合わない。正直に言えば、向き合えないのだ。私には日本政府や米国政府と刺し違えても最後まで取り組むとの覚悟がない。上述の議論は巡り巡ってそこまで、私たちを導くだろう。つまり日本政府とその後ろに控えている米国政府との「戦争」を覚悟しなければならなくなるからだ。
しかしながら、急いで付言すれば、そうした戦争は、果たして日本政府や米国政府だけに限られたものなのか。米軍を追い出しても(もっとも、それさえもはるかに実現困難なことだが)、次にまた別の国の軍隊が日本や沖縄を占拠、占領する可能性を、今の時点でもって、すべて否定しさるのはできないだろう。先の「民主主義」に関わる議論には、初めからこうした覇権システム内における「力」と「力」のぶつかり合いを前提とした「親分ー子分」関係に見る帝国主義にともなう基本的問題が組み込まれていないのだが、それは一体どうしてなのか。そこには、民主主義と帝国主義の親和的な相矛盾しない相互に補完する関係とそれが抱えてきた問題を、議論の最初から視野の外においている、おこうとしている、そうした態度それ自体にも気づかないのは、誠に残念としか言いようがないのである。
こうした議論の在り方と同様に、以下に紹介する議論についても、ここでは関われないことを断っておく。すなわち、在沖米軍基地のある沖縄は地政学的観点からも軍事的要衝であり、いわゆる「冷戦の終焉」以降の世界情勢も、世界の平和と安定において、いまだに予断を許さない一触触発の緊迫した局面にある。朝鮮半島の情勢も、韓国と北朝鮮の両国間には緊張と緩和の流れが交互に継続しており、そこに今の日韓関係の悪化や北朝鮮による日本人拉致問題や核開発疑惑問題が重なる中で、さらには中国の軍事力の増強、増大と東シナ海の尖閣諸島の領有権問題を巡る中国側からのあからさまの、力づくの対応を見るにつけ、これまで同様に、いやそれ以上に、米軍による日本プレゼンスは、アジアの平和と安定の確保において、また「日本」と「日本人」の安全保障の実現において、無くてはならない存在なのだ。それゆえ、日米安保体制の存続とその同盟強化は日米関係において必要不可欠であることから、日本国内はもとより、在沖米軍基地の重要性も論を待たない。ただし、沖縄に集中する基地問題を解決するためにも、まずは普天間辺野古への基地移転は避けられないものとなってくる。沖縄の「民意」を逆なでするのではない。日本の防衛問題と沖縄における基地負担の軽減問題を共に視野の内に入れながら、今後も日本政府は米国政府との協力関係を維持発展させていく云々の議論である。
この議論の前提がそもそも怪しいのだ。今後も米国の軍事力が中国のそれを牽制、制御できるかのような前提に立っている。何よりも、歴代の覇権国の興亡史を的確に分析、整理した作業が何ら提示されていない。もし米国と中国の間に、米中安保同盟が締結されたならば、これまで何十年も当然のこととしてきた基地容認論者にみる先の議論とその前提が一瞬にして崩れ去ってしまうだろう。驚くべきは、「日本」と「日本人」を取り巻く国際関係におけるこうした未来図を、日本政府とその関係者が今後起こりうる重大事態の一つとして、何ら考慮しないままに、真面目に日本外交を論じてきたことである。これほど笑止千万な話はあるまい。
こうした点を踏まえながら、以下に私の持論を展開していこう。これもまた拙著や拙稿で論及してきた内容ではあるが、今一度ここで論じ直しておきたい。
1970年代までのシステムの歩み
①{[A]→(×)[B]→×[C]}
(このモデルは何度も断っているように、省略形の共時的モデルである。)
この時期の在沖米軍基地の存在目的は、上記のA、B、Cのシステムとその関係の歩みを擁護するためである。とくにシステムの高度化を実現する上で、覇権システムの維持と安定は不可欠の前提となる。その意味では、日本や米国を、また沖縄を守るためではないことをまずは確認しておきたい。在沖米軍基地の存在は、それ自体が覇権システムを強化し、強固にするのに与っている。そしてそのことが70年代以前のシステムの高度化の実現に導くと同時に、70年代以降のシステムとその関係の歩みを準備しながら、その形成と発展を促すのである。
1970年代以降のモデル
②{[B]→(×)[C]→×[A]]
(このモデルは何度も断っているように、省略形の共時的モデルである。)
この時期の在沖米軍基地の存続目的は、70年代以前のそれとは異なり、70年代以降のB、C、Aの関係から構成されるシステムとその関係の歩みを防衛するためである。ここでも日本や米国を守るためのものではないし、ましてや沖縄でもない。こうした点をまずは確認しておかねばならない。70年代以前の時期と同様に、ここでも付言すれば、在沖米軍基地の存在は、それ自体が覇権システムを強化し、強固にするのに与っている。
それゆえ、70年代以降のシステムとその関係の歩みを防衛するということは、何よりもBグループの先頭に位置する中国を防衛しているということだ。次期覇権国として台頭する中国を念頭に置けば、もはや在沖米軍基地の役割も、あと数十年年で、少なくとも朝鮮半島の統一の実現が確実になるころには、米軍の存在意義はかなり低下するであろう。今後は在沖中国軍基地化の様相を帯びてくる可能性が高くなるのではあるまいか。その関連で言えば、覇権システムにおいて、第9条では国民を守れないのは確かであり、それは単なるお飾りでしかないことを踏まえて、あえて言うならば、次期覇権国として台頭する国のすぐ横で、9条を見直して改憲すべきだとか、米国の力の存在をあてにした集団的自衛権の行使を高らかに叫ぶよりは、たとえどうすることもできない第9条をお飾りとして掲げる方が、日本の安全を考える際に、まだ少しはましな方策ではないか、と自虐的に私は見ている。とにかく、どちらの選択肢も満足のいくものではないのは確かなことだ。
それでは、もう一度ここで覇権システムに関する重要な問題を述べておきたい。モデルで描く外側の{ }の記号は覇権システムを表している。このモデルからわかることは、覇権システムの力でもって、A、B、Cにおける、あるいはB、C、Aにおける軍事力の衝突を介した力の暴発・暴走を抑え込んでいるのである。換言すれば、その暴発あるいは暴走が覇権システムの抑止・制御する力を凌駕した時に、覇権システムはその存在意義を失うこととなり、その瞬間に、システムとその関係の歩みは瓦解・頓挫せざるを得なくなる。
しかしながら、これまでの覇権システムの歴史を見る限り、いまだにそうした事態は生じたことがない。たとえA、B、C内で、軍事的爆発、暴走が生起したとしても、例えば世界大戦における場合を引き合いに出してみても分かるように、これまでの歴史が物語るのは、覇権システムの抑圧、抑止する力が結局のところは、優越、優位してきたことである。そこには、歴代の覇権国間において、覇権のバトンの引き渡し、引き継ぎにおいて現覇権国と次期覇権国との間にある種の「了解事項」が存在している、と私はこれまでの拙論で紹介してきた。
こうした観点から、70年代以前の在沖米軍基地と70年代以降の、とくに2030年前後以降の在沖中軍基地の可能性を推察するのである。もっともその「基地(化)」の在り様は米国のそれとは異なるであろう。最初は、中国軍艦や空母、潜水艦の寄港地としての基地提供から始まるだろう。
こうした「最悪の事態」を避けるためにも、だから在沖米軍基地は、日米安保体制は必要だとの声が聞こえてきそうだが、果たしてそうだろうか。日本は20世紀初頭に、日英同盟を結んでいた。その当時の英国は覇権国としての地位を失いかけてはいたが、なおそれでも覇権国として君臨していた。ところが1923年になると、次期覇権国として台頭し始めた米国からの「要請」で、日英同盟は破棄される(失効する)に至った。私には、こうした日英と英米間の関係が、今また日米と米中間で展開されているかのように思われるのだ。すぐ上で「最悪の事態」と述べたが、正確には、その始まりに過ぎない。
日英同盟の破棄によって、米国は日本と戦争しやすいチャンスを手に入れることができた。紆余曲折はあったものの、日米は衝突し、日本の敗北を見た。その敗北は、70年代以前までのシステムとその関係の歩みを強化し、システムの高度化に寄与した。同じように、今また、日米安保体制という日米同盟が破棄されたならば、中国は日本と戦争しやすいチャンスを得ることとなる。仮に日本が敗北して中国の勝利となれば、それは70年代以降のシステムとその関係の歩みを強化し、システムの高度化に寄与するであろう。中国は日本とのこの先の戦争を自覚し、その準備を着々と進めている。
そのために、東シナ海での尖閣諸島をめぐる「攻防」で日本の出方をうかがっているのは確かだろう。そこから、日米同盟が破棄された場合には、中国はあの手この手で日本に対して揺さぶりをかけてくるだろうが、その一つが先の寄港地を日本に呑ませる動きに出るのではあるまいか。今の日韓問題をめぐる日本政府や日本人の対応を見る限りでは、日本と中国の関係も相当にぎくしゃくしたものとなるのは必至であろう。そこを中国は、そして米国も狙ってくるに違いない。おそらく朝鮮半島の統一を巡る動きが加速するにつれて、「日本」と「日本人」はますます危うい局面に立たされることになる。システムの高度化にはやはり戦争が必要不可欠となることから、米中覇権連合を推進する勢力はその好機を狙っている。
こうした脈略からもう少し言及するならば、在沖米軍基地から米軍の撤退にともなう「力の空白」状況・状態が生まれることが予想される。その際、米中覇権連合の推進勢力は、したたかな計算のもとで、そうした空白状況・状態を引き起こすに違いない。その勢力の中には、第二次世界大戦中の日米戦争時に見られたように、「日本人」の協力者が必ず存在しているだろう。戦後の米国占領期から以降、GHQや米国政府に協力した「日本人」は戦時期の日本側における協力者であったが、今後予想される日中戦争後の「日本」と「日本人」を指導する中国政府への日本人協力者も、そうした戦時期の日本側における協力者であろう。その時になって、本来の意味における「売国奴」の正体がわかるだろう。その多くは現在の安倍政権や日米同盟に反対する人々である可能性が高い、と私は見ている。しかし、もうその時には、売国奴云々の議論もできなくなっているに違いない。
いずれにせよ、「日本」と「日本人」には、面白くも可笑しくもない話ではあるが、私はすぐ上で述べたシナリオ実現の蓋然性の高いことを予期している。もし私の見通したように事態が進行していくならば、もうその時にはなすすべもないこととなるのは必至である。私たちは、在沖米軍基地問題を、もっぱら沖縄の民主主義とか日本の民主主義という次元から、また対米国問題といった次元を念頭に置いて論じているように、決して「三つ」の下位システム、すなわち、覇権システム、世界資本主義システム、世界民主主義システムから成る「一つ」のシステムとその関係の歩みにおける転換、変容といった次元を視野の内に含んだ論議を行ってこなかったのではあるまいか。システムとその関係の歩みからすれば、「日本」と「日本人」のあまりにも米国一辺倒に、また日本の沖縄の民主主義問題に傾斜した論の流れは、言うまでもなく好都合なのだ。私たちの議論はほとんどが「内向き」のそれであり、日本を取り巻く、外からの、外側に位置した相手側に立った議論とはなっていないのだ。あまりにもお人好しな、独りよがりな話に終始してきただけだと述べるのは、言い過ぎなのであろうか。
逆に言えば、普通の日本人には厄介極まりない深刻な事態となる。そうした事態を少しも想像していないかのような、先の「沖縄の県民投票とその結果」報道の中で、私たちは今一番、肝心な問題に向き合わないままでいるのだが、暗愚な首相を擁く愚鈍な国民だからではとても済まされないことである、と私は言わざるを得ないのだ。
それではどうしてこのような「内向き」の議論に終始するのか。そうした背景を探りながらさらに以下に論を進めていきたい。この問題の考察は、前回までのブログ記事の内容と密接に関連してくるのである。