今発売中の月刊ホビージャパン6月号に、M1A1マインプラウ(タミヤ 1/35)の作例が掲載されました
こちらが表紙。HJ誌は600号目なんですね。記念の付録として、「ホビージャパン600号のあゆみ」が付いてます。全号の表紙や毎年の2-5冊の内容を丁寧に解説するなどして、同誌の歴史を紹介。これ、とてもいいです。昔の表紙を見てると、ほんと懐かしくなりますね。
本誌の誌面は、平成最後の号ということでエヴァンゲリオン、ガンダム、ガメラなど、あちこちで平成がらみの企画が載ってます。私のは、平成の最初のころに起こった湾岸戦争をテーマに、小澤京介氏のT72M1の作例と共に紹介されてます。
湾岸戦争も約30年も前なんですねえ、、。ついこの間のように思ってしまいますけどね。この後に、土居雅博氏が「戦車模型塗装の30年史」と題して、1Pの解説ページを書かれてます。30年を俯瞰して眺める内容に「なるほどなあ!」と。
というわけで、よろしければ誌面をご覧下さい。マインプラウ、カッコいいですね。それにしても現用戦車って、反則気味にカッコいいので困ってしまいますね(?)
で、私は結構長い間同誌で模型のお仕事をさせてもらってるんですけど(こないだ調べたら、ちょうど10年目でした。そんなにやってたんだ?とびっくり)、よくよく考えたらタミヤMMシリーズの作例は初めてでした。そもそも、MM以外でもタミヤ製品自体の作例をしたことがないです。要するに、私はそういうポジションなんですね(?)
先月の中四国AFVの会では、ゲストトークのテーマは「タミヤMM50周年」でした。その流れもあってか、会場や酒席でもMMの話題が多かったような。そんなこんなで、このところMMについてあれこれ思い出したりする機会がなんだかんだとあったので、今回はその辺を書いてみたいと思います。最初に断っておきますが、メチャメチャ長いです。阪急梅田から北千里に着くまでに読めないかもしれないくらい長いです(分かりにくいし、そんなには長くはない!っって、この突っ込みも分かりにくい!)。
さて、私はもちろん、MMは大好きです。確か、最初に買ったのは7歳くらいでした。ここでクイズです。そのアイテムはなんでしょう?まあ、当てられないでしょうね(考える人なんておるか!)。答えはこの後すぐ!(笑)
しかし、「大好き」といいながら今持ってるのはこんだけです。しかも、このうち2個(ブレンガンキャリアーとバリケードセット)は人にもらったものです。なはは。その節はありがとうございました!
もちろん、欲しいのは無数にあるんすけどね。けど、買っても作れないのでセーブしているのであります。まあ、もちろんお金もないんすけどね(笑えない)。
えー、それではクイズの答えです。私の初MMは「M21モーターキャリア」です。まー、これは誰も当たらんかったでしょうね(だから、どーでもいいって)。人生初のMMくらいは持っとこう、と思って何年か前に現行品を買いました。でも張り箱の昔のやつ、欲しいなあ、、。
7歳くらいの頃は、ボンネットトラックやバスが大好きで、その流れでボンネット式の車両に魅かれてたんですね。しかも、後ろがキャタピラなのがたまらんかったような記憶があります。今は枢軸派の私ですが、当時はそれほどでもなく(?)、パッと見いいやつは何でも買ってました。ハーフトラックつながりでは、これと同じ頃に8トンハーフを買ってます。でも8トンはシングルなので、MMじゃなくて「戦車シリーズ」ですね。「戦車シリーズ」はモーターで走らせることができるシリーズで、ディスプレイオンリーのMMとは別のものです。
で、その8トンが、最初に色を塗った模型でした。模型屋に行ったとき、連れてってくれた父親にドキドキしながら「色塗りたいから塗料買っていい?」と聞いたことを覚えてます。わけ分からんまま、グンゼのラッカーを買って、変な3色迷彩にしたような。でもシンナーを買わず(そんなのがあるなんて知らない)、筆を洗えなくてガビガビになったような、、、っって、ほんと他人からするとどーでもいい話だよなあ、と思っちゃうんですけど、それを言いだすと、今回はほぼ全てどーでもいい話なので、以下もどんどんどーでもいい話をしていきます。すいません。
MMの凄いところは、いちいち書いてられないほど、たくさんありますね。その一つが、何十年も前とほぼ同じものが今でも手に入る、という点。例えばハセガワの飛行機もキット自体は昔と同じでも、パッケなどが変わっています。タミヤのはほぼ同じです。これは凄い!以前作ったキットなら「パッ!」と当時のことを思い出したりします。
モーターキャリアだと、当時じいさんの部屋で箱を開けて、インストの幌の作り方を見て「こ、これはおいらにゃー、無理だあ!!」と思ったのを覚えてます。それにしても、これ、今でも難易度高スギ(笑)
そういえば、この幌は「タミヤインストブック2」(大日本絵画)のコラム「みんな自作できたのかな、、」でも紹介されてたので、そういう人、多いかもですね。このキットはそのうち作ろうと思ってるので、その際は頑張って幌も作って、昔日の雪辱を果たしたいです(笑)。あ、あと後部の床を前後逆に間違えて接着しちゃって、迫撃砲が逆向きになったんですよ。それも込みでキチンと作りたいです。で、そういう楽しみ方(?)ができるのもMMのいいところですね。ただ、こういう楽しさがあるのは、こんな風な「あとひと工夫」を紹介している、とても読み応えのあるインストや、カッコいい箱絵など、キット以外にもお楽しみの要素がたくさんあるからなんですね。ここはMMのキモといっていいポイントでしょう。
それにしても「何十年も前と同じものが今でも手に入る」っていう商品は模型以外でもなかなかないですよ。ちょっと思いつかないです。例えば、本でも「坊ちゃん」や「シャーロック・ホームズ」でも、内容は今も昔も同じですが、出版社や装丁、翻訳が変わると、また別の感じになってしまいますものね。
さて、次はMM企画あるある「マイベストMM」のコーナー!!一人でやってるとバカみたいだぞ!!(笑)
「ベストキット」はもうダントツで「日本陸軍歩兵セット」ですね!そして「ベストパッケージ&箱絵」は「オートバイセット」です。
日本兵セットはほんと凄いです。チハも凄いんですけど(もちろんベスト2です)、日本兵セットはなんというか、箱絵からキットのレベル(服の皺など、彫刻が狂気の沙汰です)から、なんかもう全体的に変なオーラがでてますね(笑)。気合の入り方が半端じゃない、というのがビシバシ伝わってきます。でも、雑誌のベストで選ばれてるのを見たことがないような、、。ほんと、凄いと思うんですけどね、これ。
チハもそうですが、今ランナーを見てると「これを40年以上前に作ったの?ウソだろ?」とゾッとします(いやほんと)。箱絵も素晴らしすぎです。これ、頑張って模写したなあ、、。昔のタミヤニュースで、中西立太氏がこのキットを開発する際の裏話を書かれてましたね。開発時に、軍服と装備を中西氏がタミヤに持って行き、社員の杉本・田村両氏に着てもらったときの思い出でした(今探したら、ありました。200号の記念特集でした)。「軍服には、その国民の骨肉的な表情がある。なので日本人には日本軍の服が似合う」といった趣旨でした。当時フムフムと興味深く読んだ記憶があります。
「オートバイセット」の箱絵はほんと素敵ですね。真横からのバイクの絵を、上下に置いて、間に文字を挟む、というレイアウトが実に斬新でカッコよすぎです。この箱は、部屋に見えるように飾ってます。上下の兵士のポーズがちょっと違うのもにくいです。これは鳥山明さんが「Dr.スランプ」の扉絵にしてましたね。確か、ツェンダップにセンベエさんが乗ってたような。「Dr.スランプ」はあちこちに模型やモデルガンの要素がちらほらと出てて、子供ながらに「鳥山センセ、あんたも好きねえー」と思ってましたね(笑)。そんな、漫画以外の「知ってるやつは知ってる」というディテールも大好きでした。
日本陸軍歩兵セットは、長年唯一の日本兵キットだったということもあり、かつヘッドの日本人顔は今でも1級品なので、なんだかんだでずっと買ってます。ファインモールドの日本兵が充実するまでは、胴体はドラゴンとの混合、ヘッドはこのキット、という必殺技(笑)でしのいでました。というわけで、今11箱目(笑)。
あと一箱で綺麗に四角になりますね(笑)。頑張るぞ!(目的ズレてんぞー)。
日本兵セットに限らず、キャラメル箱のシリーズはとても好きです。箱全面に、果てはベロにまで情報がびっしり詰まっているゴージャスな感じもこれまたMMならではですね。それにしても、箱絵がカッコよすぎる、、。サイドの装備品の絵も含めて、他に比べてなんか気合が違うような気がしますが、どんなもんでしょう。一度原画を見てみたいものです、、。
さて、このキット、子供の頃は350円でした(今は700円)。キャラメル箱のシリーズは、安いので小さいし戦車キットのゴージャス感には及びませんが、それとはまた別の「なんかいいものを買った!」という満足感を得られましたね。
個人的には、MMの人気を支えた大きな理由のひとつがこのキャラメル箱シリーズだったんじゃないかと思ってます。私を含め、友達の平均的な小遣いは月500円とか1000円くらいでした。それだと、一つ1000円とか850円の戦車はなかなか買えないです。ましてや、他にハセガワの飛行機キットとか銀玉鉄砲とか発泡スチロールのグライダー(ありましたよね)とかお菓子とかを買わないといけないので(笑)、なおさらです。
そういう子供にとって、キャラメル箱は安く買えて、しかもかなり満足できるシリーズだったんですね。フィギュア以外にも、このオートバイとか75ミリ砲とかバリケードとか、アイテムに幅があったのもよかったです。75ミリ砲、これも当時350円でしたからねえ。ちょっと安すぎですね。
で、小遣いの少ない子でも、これらを買ったら「お、ええやん、見せて」とその時は仲間の主役になれるし、「あいつはアレを買った」と個人のコレクションとして十分認められるわけです。こういうのって、子供からすると結構大きいです。その頃の年上のお兄さんたちの世界がどうだったのかは分からないのですが、子供だった私の周りはそんな感じでした。
そして、そういう小物でも集めていくと、もんの凄いこと(笑)になるのは皆さんよくご存知かと。バリケードや土嚢を置いて、75ミリ砲を置いて、機関銃チームを置いて、、、と、地面を作らなくても、例えばコタツの上に一つの「世界」が出来上がるっていうのはたまらない魅力がありました。しかも、全部自分が作ったもの、という。その満足感はかなりのものでした。これも、ちょっと他のプラモにはない要素です。
それにしても、キャラメル箱の側面の箱絵もいいですよねえ。購買意欲をそそる、といいますか(笑)。タミヤの箱って積んでもカッコいいんですよね、なんか。そういえば、プラモの箱は作った後も捨てずにとっておいて、目立つところに積んで悦に入ってましたねえ、、。
ちなみに、この75ミリ砲とイギリス歩兵セットは、今回のブログの下調べをしてるときにオークションで見かけてつい買ってしまったものです(笑)。箱が焼けたりで安かったのですが、届いてみたらかなり前の小鹿版(値段を見ると最初期のですね)でした。ラッキーでしたね。でも75ミリ砲は作るつもりで買ったのに、作れなくなってしまいました(笑)。仕方ない、現行版、買うか(コラ)
あと、MMではないのですが、戦車シリーズ(リモコンとかシングルのモーターライズのやつ)の存在も、子供には大きな魅力でした。これは、これまた7歳くらいのときに初めて買ったM10。

何年か前に、状態のいいのが出てたので買いました。タミヤのリモコンは、今でも高値取引ですね。それは、希少価値もあるんでしょうけど、やっぱり全体的なゴージャス感が今でも生きているからでしょう。箱を開けたこの感じがなんとも、、。正直、これもちょっと高かった(笑)ですが、私みたいなノスタルジーおっさんがいる以上、ずっと高値取引でしょうねえ。Ⅲ号戦車のリモコン、メッチャ欲しいんですけどまあ手が出ません。誰か下さい(アホか)。
このM10は当時モーターを買うことができなくて、ディスプレイになってしまいました。前に何かで書きましたけど、モーターはお店のレジの奥の棚にあって、それを入手するには、必要なモーターの種類を確認した上でお店の人に申告しなくてはならず、ビビリな子供の私には非常に困難な手続きだったのであります。もちろん、お金も無かったし(笑)
その後、もう少し大きくなった10-11歳頃になると、MMと並行してリモコンもよく買ってました。今はMMと戦車シリーズはなんか分けられて語られてますが、当時はもちろんそういう意識なんてなくて、いっしょくたにして楽しんでましたね。友達とリモコンで相撲をとったり、庭にコースを作ったりとか。この辺は、リモコン経験者は皆さん同じかと思います。
リモコンは、お年玉とか誕生日のお小遣い(じーさんばーさんが奮発してくれてたのです)が入ったら、欠かさず買ってましたね。最初からモーターが付いてる1500円のやつも「よっしゃよっしゃ」って感じでした(笑)。ちなみに、モーターなしのが1200円でした。1500円のは140モーターで、車格がちょっと大きいアイテム(タイガーとかパンサーとか)で、1200円のは130モーター別売りで、ちょっと小さいやつ(Ⅲ号やマチルダなど)でした。今も、ギアボックスの一部はとってあります。
左がパンサーのですね(分かりにくいけどPAと刻印がある)。他はT34のです。下の小さいのはⅢ突の130モーター用のです。Ⅲ突のは、モーター固定用の板がないのが残念。
さて、その頃(1985-6年ごろ)は、すでにMMでは生産休止になっていたアイテムも、リモコンではまだありました。例えばⅢ突とT34の42年型はリモコンでしか知りませんでした。MMのリモコン版は、アクセサリーパーツがオミットされてるのですが、そもそもMMのキットを見たことがないので、そんなことはもちろん知りません。T34なんかは「あっさりしたキットだなあ」と思ってました。しかし、その後スポットでMM版が出たとき、アクセサリーパーツのランナーに驚愕したという(笑)。
今でも不思議なのですが、MM版を生産休止にしても、リモコンは生産を続けてたんでしょうか? でも、リモコンでもⅢ号やマチルダ、KVなどは当時見たこともありません。T34とかは単に問屋さんに在庫が残ってただけなのかもしれませんね。この辺は地域によって違ってたのかも。そういえば、リモコンはありましたけど、シングルはどのアイテムもほとんど見たことがないです。作ったことがあるのはⅡ号戦車とロンメルだけでしたね。今でも、シングルの箱絵って初めて見るものばかりです。
MMの特集はあれこれありますけど、戦車シリーズに焦点を当てた特集とか見てみたいですね。M10などMM入りできなくてそのままというキットもありますし、箱絵もシングル・リモコンともども特有のものなので、面白いと思うんですけどね。先に書いたように、生産時期のことも知りたいです。
先にちょっと書きましたが、私がMMを始めとするプラモに一番はまってた年代は小学3-4年生から中学1-2年生くらいの1984-88年ごろです。要するに、いわゆる「冬の時代」のど真ん中だったんですね。なんちゅうか、一番ヒドイ時期に最前線だったわけです。スターリングラードにいきなり送られた新兵、みたいな(笑)。
当時から、なんとなくマイナー気味なアイテムに惹かれてたのですが、その頃はそれらはことごとくカタログ落ちしてました。例えばⅢ号戦車、Ⅲ突、ロシアフィールドカー、マチルダ、KVⅠ・Ⅱ、セモベンテ、一式砲などなど、どれも店頭で見た記憶がありません。ちょっと年上の方からすると「えっ!」と驚かれるかもですが、ほんとなんですよ。ひょっとすると小学1-2年生くらいの頃はあったかもですが。でも一番はまってた時期には、確かになかったです。
ではなぜ、店頭にないアイテムを知ってたかというと、現行品の箱の横の他のアイテム紹介を見たというのもありますが、何年か前のカタログが模型店で100円で売られてて、それで見てたというのも大きいです。最新のカタログはちょっと高くて(当時500円くらいだったかな?)買えなかったんですね。初めて買ったのが1980年版でした。これは、大人になってから買い直したもの。
この年の見開きのジオラマに、金子辰也氏の「PARADICE」が載ってて、それをはっきり覚えてたので1980年版だと特定できました。「PARADICE」のあの錆びたチハを見たときのドカーン!ときた感じは今もよく覚えてます。そういう人、多いんじゃないでしょうか。
で、古いカタログのすでに売ってないMMアイテムを見て「これ欲すぅいー!!」と悶絶していたという。今から考えたら、自分で自分を生殺しにしてたわけです。間抜けスギ(笑)。
それにしても、MMのこのページはたまらんですね。なんか、色合いがいいんですよね。見本の塗装仕上げの感じと背景の色の相性がいいのかな?
というわけで、私にとっての「冬の時代」の飢餓感は、新製品が出ないというだけじゃなくて、既存のアイテムも手に入らないし見た事もない、という2重の苦しみだったわけです。当時は、スケールモデル全体が低調で、模型雑誌でも新製品の作例というよりは、絶版モデルを元にした作例が多かったように思います。なのでなおさら飢餓感が募ってたという。そういえば、MG誌で松本州平氏が、寂れた模型店のショーケースで見つけた、埃を被ったⅢ号戦車の完成品を再生して、作例にしてましたよね。そんなこんなで思い出すと、今から考えるとちょっと信じられないくらいの感じだったんだな、と。
当時は「あれが欲しいこれが欲しい」が高じて、何度も夢にまで出てくるほどでした。知らない店に入ったら欲しいキットがあって「やった!!」という感じのやつ。漫画みたいですけど、ほんとなんですよ。アホですね(笑)
で、中学1-2年生くらいの頃から、MMの欠番がちょこちょこスポット生産されるようになりました。夢に出てきたⅢ号戦車とロシアフィールドカーはメチャクチャ嬉しかったですね。Ⅲ号とⅢ突が一緒に再販されて、Ⅲ号は2個欲しかったんですけど、一個しか買えなくて残念だった記憶があります。その代わりⅢ突は2個買いました。確か、ほぼ同時期にロシアフィールドカーが再生産されたのかな?KVⅠやSU85、T34・42年型など、ソ連物がまとめて再販されて、夢中で買いましたね。感無量でした。そう考えると、この頃はもうかなりお金に余裕があったんだなあ、と。
しかし、この頃の完成品は残念ながら処分してしまってないのですが、箱だけはとってます。ロシアフィールドカーも2個買って、一個が残ってます。でも、久しぶりに箱を開けたら部品が虫食い。そういやちょっと前に使ったんだった。もったいない、、。
Ⅲ号戦車は、土居雅博氏のMG誌のJ型のスクラッチに感激したこともあり、誌面を見ながら、頑張って改造しましたね。ほんと取っておいたらよかったです。子供のころの完成品は、進学で県外に出るとき、まとめて処分しちゃったんですよね。残念、、、。
空き箱も処分しましたけど、Ⅲ号のだけは取っておいたんですね。中は当時のジャンクボックスになってます。フィギュアはスクラッチの芯にするなど、今でも現役なんですね、実は。あと、森川由香里さんのカコナールのCMカードが入ってますね(笑)。プラ板代わりに使ってたんだと思います。
作りかけで放棄したフンクワーゲンは残骸のジオラマにするとかして、どーにか成仏させられんかな?とか考えてるんですけどね。
カタログに話を戻すと、M1A1マインプラウの作例の記事にも書きましたが、この頃のカタログの刷り込みが今でも尾を引いてます。M1はずーっと「MMの中でも新し目のアイテム」と思い込んでたんですけど、調べたら124番(マインプラウは158番)とかなりのベテランでした。なんのことはない、当時は全然新製品が出なかったので、何年もカタログの後ろの方にずーっとあったってことなんですね(笑)。
この辺の感覚って、世代ごとに違うと思うのですが、これもまたMMの魅力の一つですね。なんせ、50年も続いているシリーズなので、年代を超えて話ができるという。模型趣味自体、年齢とは関係なく初対面でもすぐ打ち解けられるいい趣味だと思うんですが、あるメーカーの特定のシリーズでここまで会話が成り立つのって、そうそうはないように思います。世代間のギャップですらも、ネタになるんですね。
ある飲み会で、模型仲間のO山氏が「新発売の告知を知って、発売を心待ちにした初めてのMMは?」とお題を出しました。各自の答えで大盛り上がりでした。古ければ「ええっ!お見それしやした!」となるし、新しいと「若い!その頃俺もう●歳だよ!」って感じになるんですね(笑)。その席での最古参はO野氏の「サイドカーセット」(これにはびっくり)、最若手が私の「新砲塔チハ」でした。O山氏曰く、このお題を出すと、酒席が盛り上がるんだそうです。確かに、そうですね。とても面白いし、話題のきっかけとしては申し分ないです。AFVモデラー限定のお題ですが、皆さんもよろしければ試してみて下さい(笑)
私の「新砲塔チハ」はさっき調べたら87年発売でした。さっきも書きましたが、私がかなりはまってたのは88年ごろまでで、それ以降はモデルガンとかエアガンの鉄砲の方に興味が移って、模型から徐々に離れていってしまいました。89年12月には例のタイガーⅠ後期型が発売され、それ以降少しずつ「雪解け」が始まります。でも、その頃にはもうほとんど模型を作らなくなってました。タイガーが発売された時のこともよく覚えてない(!)ほどなので、かなり離れちゃってたんですね。ほんのちょっと前までは、ドイツもののMM新製品を心待ちにしてたのに(私の中では、ドイツもののMM最新キットは今でもデマーグと休息セットのコンビです(笑))。今から考えても、ほんと間が悪いというか、勝手というかなんというか、、。
その後、高校を出て大学に進学して、県外で一人暮らしを始めると、お金的にもスペース的(模型を作るのは6畳一間じゃかなり難しい)にも模型はとても作れない感じになって、完全に私の模型趣味は途絶えてしまいました。子供のころはあんなにはまってたのに、不思議なものです。
よくよく考えると、それは一緒に楽しめる仲間がいなくなった、というのが大きかったのかもと思います。小学生の頃は、プラモは「男子のたしなみ」という感じで、やってないほうがおかしい、くらいでしたけど、中学生になると誰も作らなくなりましたからね。この辺の寂しさは、今でもよく覚えてます。でも、この寂しさも私の原点といえば原点、ですね。「誰もやってなくても、自分が好きなものは好き!でいいよな!それを自分なりにやっていこう!」と思ってたような。
模型は止めちゃいましたけど、ミリタリー自体への興味は学生時代もずっと変わらず、むしろ病気はどんどん悪化してて(笑)、本を読んだり、生活費を削ってモデルガンを買ったり(笑)で、そっちの趣味は続けていました。模型誌もたまーにチェックはしてましたが、立ち読みとかで気が済んでましたね。で、これも前にどこかで書きましたけど、卒業するころにアーマーモデリングが創刊されて「おおおお!なんか凄えことになっとる!!」と模型熱が再燃。就職して、お金とスペースに余裕ができると、親の仇を討つように(笑)模型を買い、作り、今に至る、というわけです。
正直、この時期にアーマーモデリングが創刊されなかったら、多分模型を再開してないですね。少し早くても、遅くても微妙だったかも。創刊時は学生で、誌面を見ても作りたくても作れなくて「就職したら、ガッツリやるぞ!」と1年くらいその気持ちをためまくり、パーンとはじけた、みたいな。なんか、ゲルリッヒ砲みたいな感じでした(笑)。ほんと、この場合は逆に間がよかったんですね。タイミングって、大事だし不思議ですね。
って、あれ、なんか気が付いたら「森男の模型半生記」みたいになってますね(笑)。でも、まあ、こうやって振り返ってみると、MMは私の模型の中でかなりコアな部分を形成したんだということがとてもよくわかりました。なので、これでいいのだ(笑)。
とはいえ、客観的に見ると、私がMM少年だった時期というのはかなり短いですね。多く見積もっても、せいぜい8年くらいです。ふーん、こんなもんだったのか、という。さっきから「MM大好き!」みたいな風に書いてますけど、全然ヌルイですね、私。なんかほんとすいません、って感じです。でも、好きなんですよ、ほんと。
で、どのくらいヌルイのかを証明するために、これまで作ったMMを列記してみます。2回以上作ったのは()で注記します。リモコンやシングルのも含みます。アイテム名は適当です。
ナンバー順に「6ポンド砲」「Ⅱ号戦車(2)」「キューベルワーゲン(2)」「アフリカ軍団歩兵セット」「Ⅲ号戦車」「ウィリスジープ」「88ミリ砲(2)」「ドイツ戦車兵セット」「Ⅲ突(2)」「ドイツサイドカー」「ハノマーク(2)」「ロシアフィールドカー(2)」「オートバイセット」「土嚢セット」「バリケードセット」「ロシア歩兵セット」「マチルダ」「ジェリカンセット」「レンガセット」「ドイツ歩兵突撃セット(2)」「37ミリ砲(2)」「M3リー」「カーロアルマート」「ドイツ機関銃チーム」「M3グラント」「75ミリ砲」「T34 42年型(3)」「M3スチュアート」「8トンハーフ4連高射砲」「ドイツ4輪装甲車222」「キングタイガー」「T34 43年型」「ホルヒ」「Ⅳ号H型(リモコン)」「タイガーⅠ(2)」「マーダーⅡ」「ドイツ歩兵進撃セット」「パンサー」「ロンメル(シングル)」「フンクワーゲン」「KVⅠ」「チハ(2)」「SU85」「モーターキャリアー」「日本陸軍歩兵セット(流用込みで10以上(笑))」「Ⅳ号戦車D型」「ホルヒと20ミリ対空砲」「20ミリ対空砲」「M8自走榴弾砲」「ドイツ小火器セット(3-4くらい? もう覚えてない)」「グライフ」「M4A3シャーマン」「動物セット」「チハ新砲塔」「M1A1マインプラウ(こないだの作例だ(笑))」「連合軍車両アクセサリーセット((2)日本軍戦車に鹵獲品設定でジェリカンとかバッグを乗せまくった)」「ドラゴンワゴン(本体のみ)」「ドイツ自転車セット(2)だけど、ちゃんと作ってない。全部日本の自転車に改造」「アメリカ現用車両装備品セット(これも作例)」「BT7」
とまあ、こんなもんです。計59アイテム。メッチャ少ないですね。ヌル過ぎですね。「あ、こいつ偉そうなこと書いてるのに、あれも、そしてこれも作ってない!!」とか思われる覚悟でさらしてみました(笑)。今の最新作が366のアキリーズなので、6分の1も作ってないわけです。リニューアルとかの重複を除いても、5分の1もいってないでしょう。
というわけで、ヌルイという自覚はありますので、今はたまにでもいいから、これまで作ったことがないMMで楽しみたいなあと思ってます。作ったことがないのって「逆貯金」みたいな感じがしませんかしないですかそうですか。パットンとかM113とか、ローバーの救急車とか、当時はあんまりピンと来なかったけど今はいいなあと思うようなアイテムはたくさんありますからね。もちろん、子供のころに作ったやつをもう一回、というのもいいですよね。75ミリ砲、やっぱ買うか!(笑)
昔のカタログを、今眺めながら「次はどれ作ろうかな?」って考えてたら、なんか子供のころに戻ったような気がして、ワクワクします。こういう楽しみ方も歴史の長いMMならではなんじゃないかなあ、と。これらはそういう気持ちで作ったものです。
古いMMは、変にあれこれいじるんじゃなくて、キットのよさを生かしてMMらしい作品にする、そしてちょっと遊ぶ、というようなスタイルが楽しいですね。完全なストレートで作った6ポンド砲はかなり楽しめました。マーダーⅡとか、MMはやっぱ2桁だよなあ、いや、3桁のシャーマンもぜんぜんいいな!(どっちやねん)とかとか、ほんと楽しめます。とはいえ、最近は全然作れてないので、これまた「言うだけ番長」になりかけてるんですけど(笑)
というわけでお終いです。いやー、今回は(も?)長かった!!どなたか最後まで読んでくれましたでしょうか(笑)。ゴールデンウイークはずっと予定がなかったこともあるんですけど、MMといえばあれも書きたい、これも書きたい、とかとかでメチャクチャ長くなってしまいました。すいません。でも、語り尽くそうと思っても語り尽くせない、それくらいの魅力があるシリーズであるということなんですよね。また、前半で予告したように、ほんとどーでもいい話ばかりでしたけど、これはこれで、1980年代後半の、いちMMファンの模型体験記、という意味では興味深い資料になる、、、ことはないか(笑)。ほんとすいません。
で、ここまで読んでくださった猛者の皆さん(ここまでに果たして一体何人が落伍しただろうか、、、)は、冒頭の話題はとっくに消し飛んでるかと思います(笑)。HJ誌最新号、よろしければぜひご覧下さい(思い出しましたか?)。それにしても、子供のころは、自分の作ったMMが模型雑誌に載るようになるとは思ってもなかったですね。なんともいえないです。感無量です。なので、今回の作例はそういうのも込みでしみじみとしてしまいましたね。
なんか、上手く元に戻って、大団円になったような気もしますが、気のせいですね(笑)
それでは。
※最後のMM作品は、過去に個別のエントリーで紹介しています。よろしければご覧ください。





















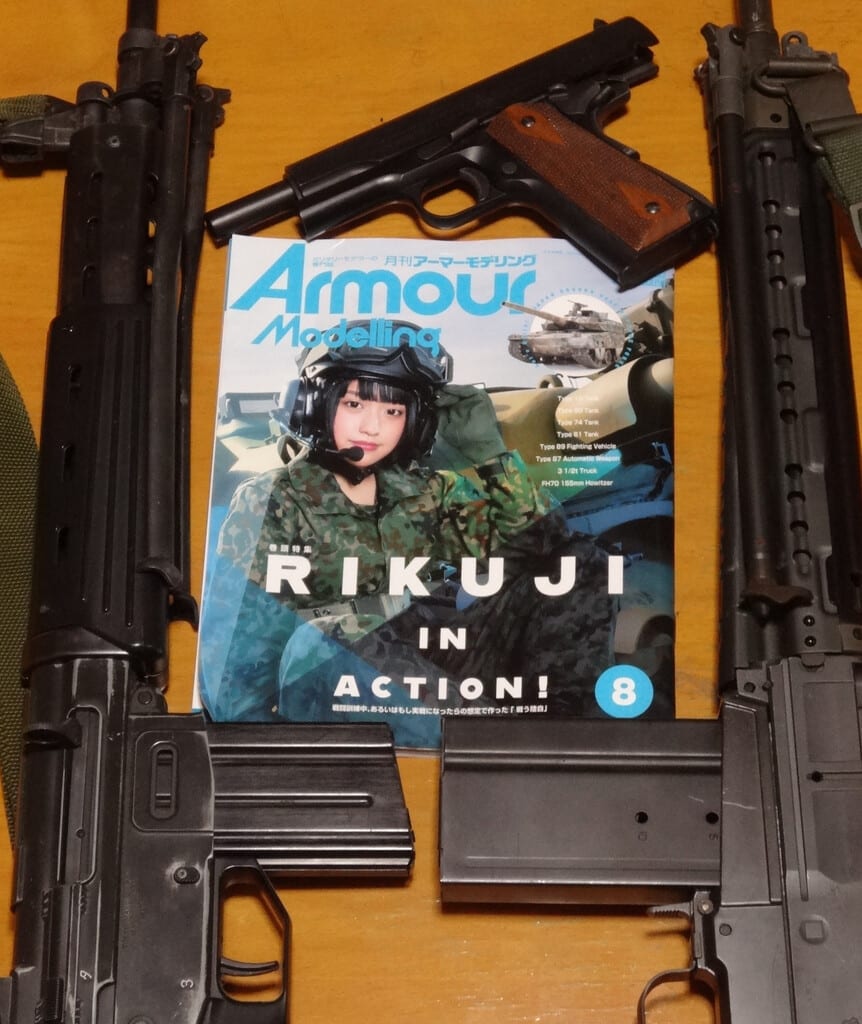

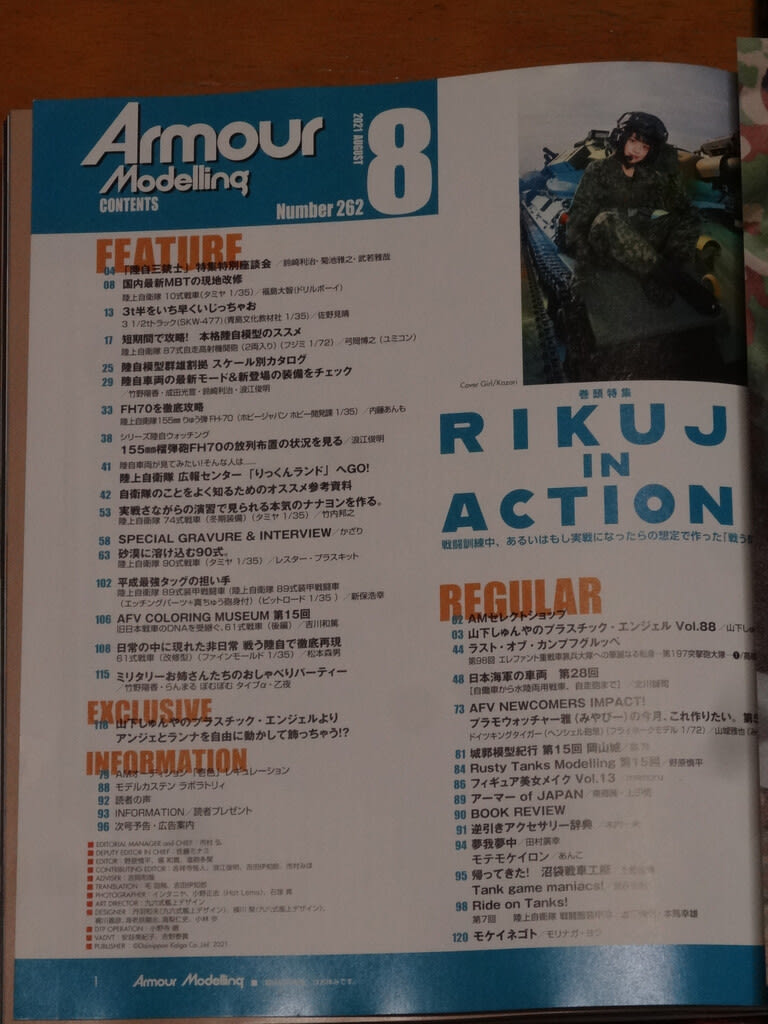



















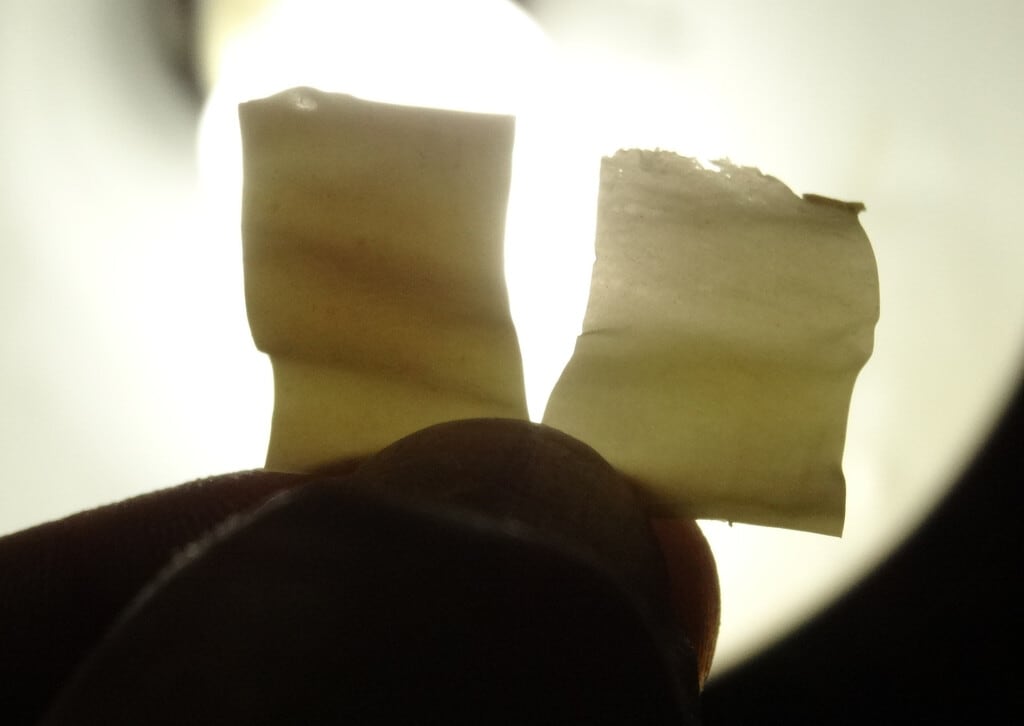


































 私はこれを見て「やっぱり売ってるんだ!」と確信してしまったのでした(笑)しかし、地元の模型店にないのは不可解です。それはなぜかといろいろ考えた結果「都会でしか売ってないからなんだろうなあ」という結論に(笑)
私はこれを見て「やっぱり売ってるんだ!」と確信してしまったのでした(笑)しかし、地元の模型店にないのは不可解です。それはなぜかといろいろ考えた結果「都会でしか売ってないからなんだろうなあ」という結論に(笑)








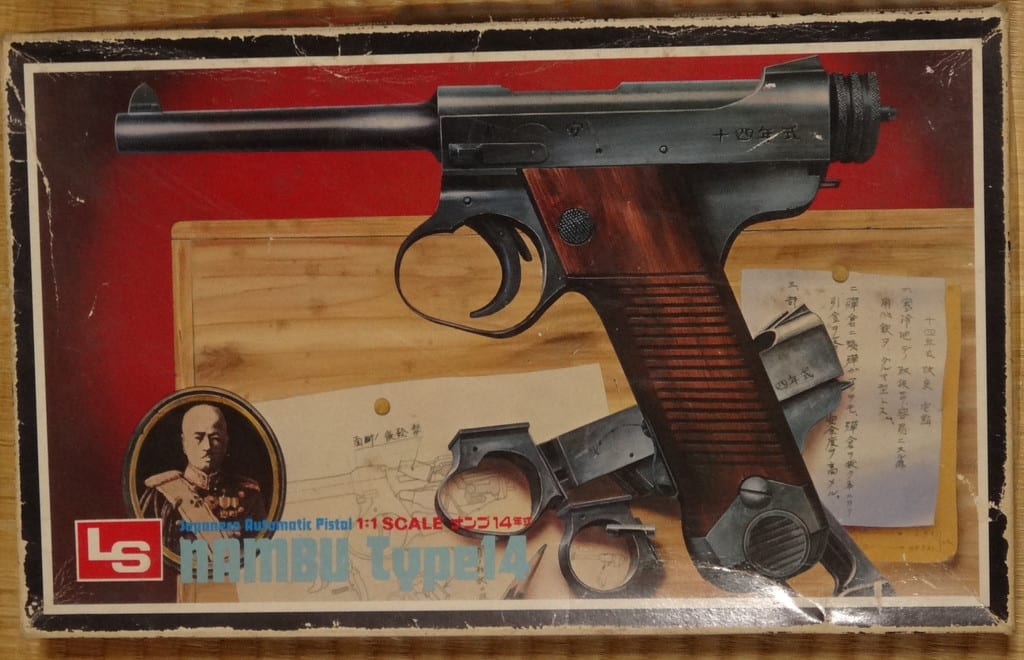






 マジで背筋がゾッとします。オーパーツですよこれ、、。そういえば、タミヤのチハもそうですね。なんか、ギアがグワッと入っちゃったんでしょうね、、。
マジで背筋がゾッとします。オーパーツですよこれ、、。そういえば、タミヤのチハもそうですね。なんか、ギアがグワッと入っちゃったんでしょうね、、。



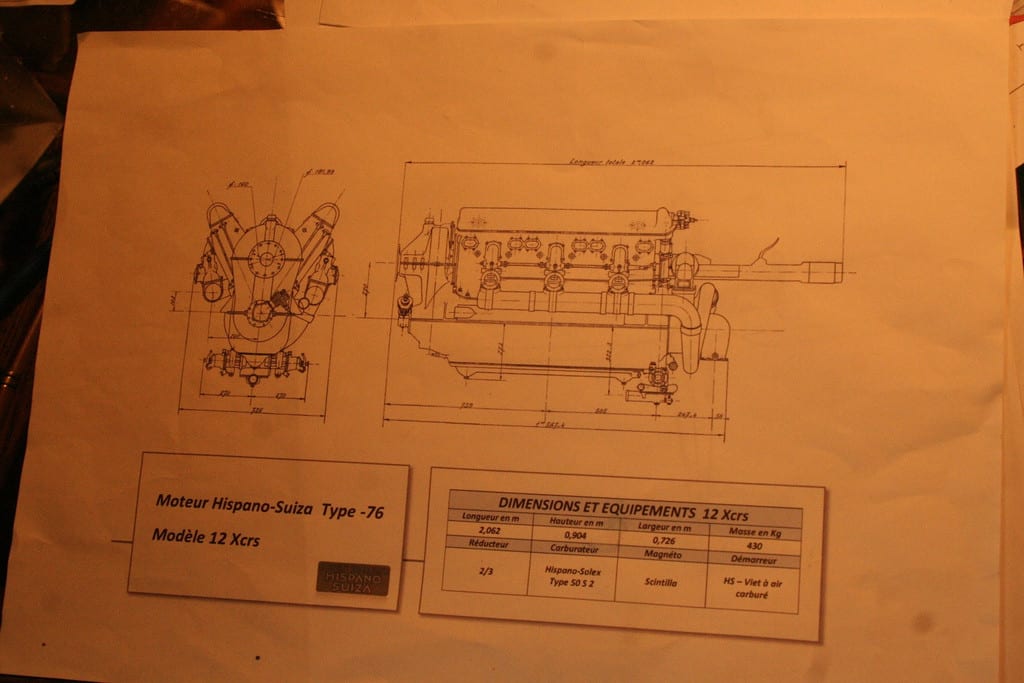
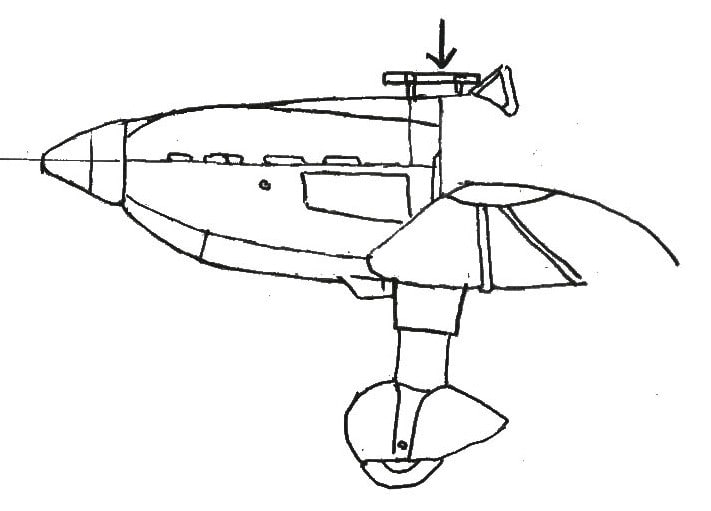




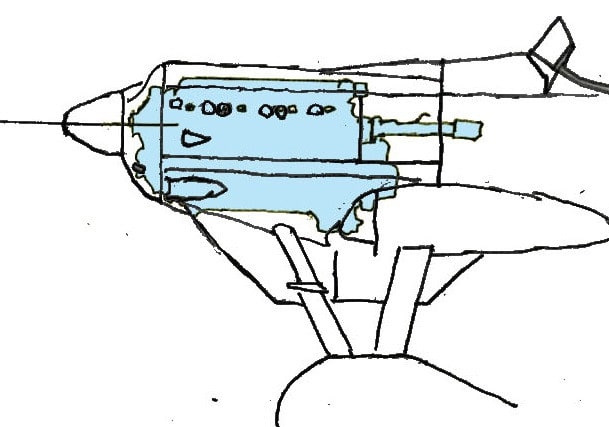

















































 ビールを飲み飲み、今日一日やって、なんとか目処がついたかな?ちゅー感じっす。飲んでなかったらもっと早くできるんですけどねー(笑)関係各位の皆様、今しばらくお待ち下さい。今日はもう、寝ようかな(コラ)
ビールを飲み飲み、今日一日やって、なんとか目処がついたかな?ちゅー感じっす。飲んでなかったらもっと早くできるんですけどねー(笑)関係各位の皆様、今しばらくお待ち下さい。今日はもう、寝ようかな(コラ)


