シンギュラリティ(Singularity)とは、技術特異点のことで、人工知能が人間の能力を超えることで起こる出来事です。
技術特異点人類が人工知能と融合し、生物学的な思考速度の限界を超越することで、現在の人類からして、人類の進化速度が無限大に到達したように見える瞬間に到達することをいいます。
実際に人類の進化速度が無限大になることはありませんが、進化速度が極めて速く、数学的な特異点と同様に見えるため、このように名付けられました。2010年代以降、一躍有名になったレイ・カーツワイルの予言の影響により、一般層を中心に2045年問題とも呼ばれています。
今朝のテレビ朝日の番組で、このことを取り上げていました。
情報科学、ナノテク、生命科学の専門家3人へのインタビューが放送されていましたが、本当にすごい進歩ですね。
医療分野に限っても、ナノテクロボットが人間の身体に入って糖尿病の治療をする、ゲノム編集技術の進展でがんの完治が5年以内に可能になる、10年以内に老化の防止が可能になる、というような驚くべき研究の最前線です。
技術は加速度的、指数関数的に進歩すると言われていますが、本当にその通りですね。
人類最初のコンピュータであるエニアックと同じ機能のコンピュータがスマホですから、すごい進歩です。
この先5年間でどのような進歩を遂げるのか、全く想像が尽きません。
楽しみでもあるし、恐ろしくもある。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
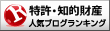
特許・知的財産 ブログランキングへ
 弁理士 ブログランキングへ
弁理士 ブログランキングへ
技術特異点人類が人工知能と融合し、生物学的な思考速度の限界を超越することで、現在の人類からして、人類の進化速度が無限大に到達したように見える瞬間に到達することをいいます。
実際に人類の進化速度が無限大になることはありませんが、進化速度が極めて速く、数学的な特異点と同様に見えるため、このように名付けられました。2010年代以降、一躍有名になったレイ・カーツワイルの予言の影響により、一般層を中心に2045年問題とも呼ばれています。
今朝のテレビ朝日の番組で、このことを取り上げていました。
情報科学、ナノテク、生命科学の専門家3人へのインタビューが放送されていましたが、本当にすごい進歩ですね。
医療分野に限っても、ナノテクロボットが人間の身体に入って糖尿病の治療をする、ゲノム編集技術の進展でがんの完治が5年以内に可能になる、10年以内に老化の防止が可能になる、というような驚くべき研究の最前線です。
技術は加速度的、指数関数的に進歩すると言われていますが、本当にその通りですね。
人類最初のコンピュータであるエニアックと同じ機能のコンピュータがスマホですから、すごい進歩です。
この先5年間でどのような進歩を遂げるのか、全く想像が尽きません。
楽しみでもあるし、恐ろしくもある。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ























