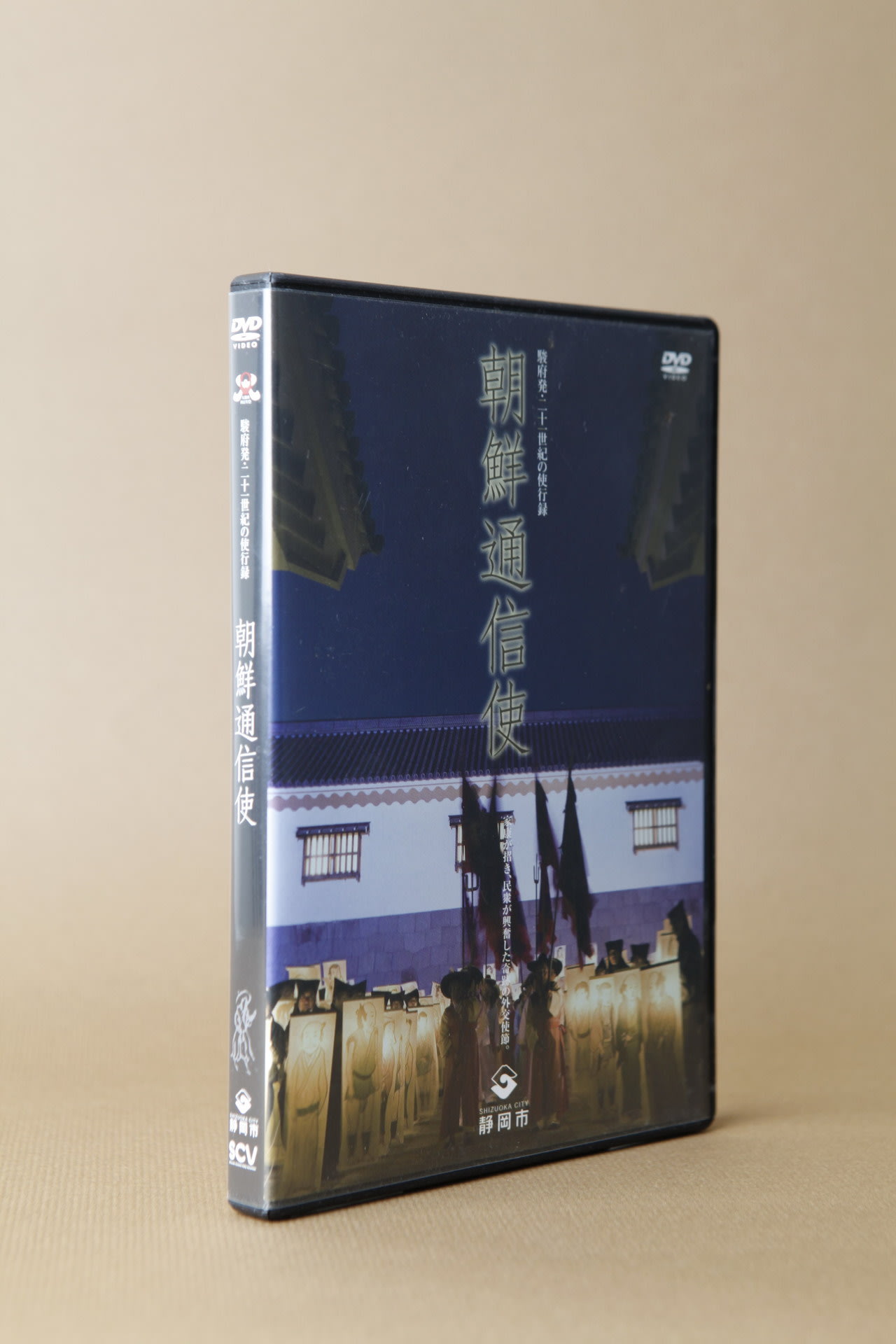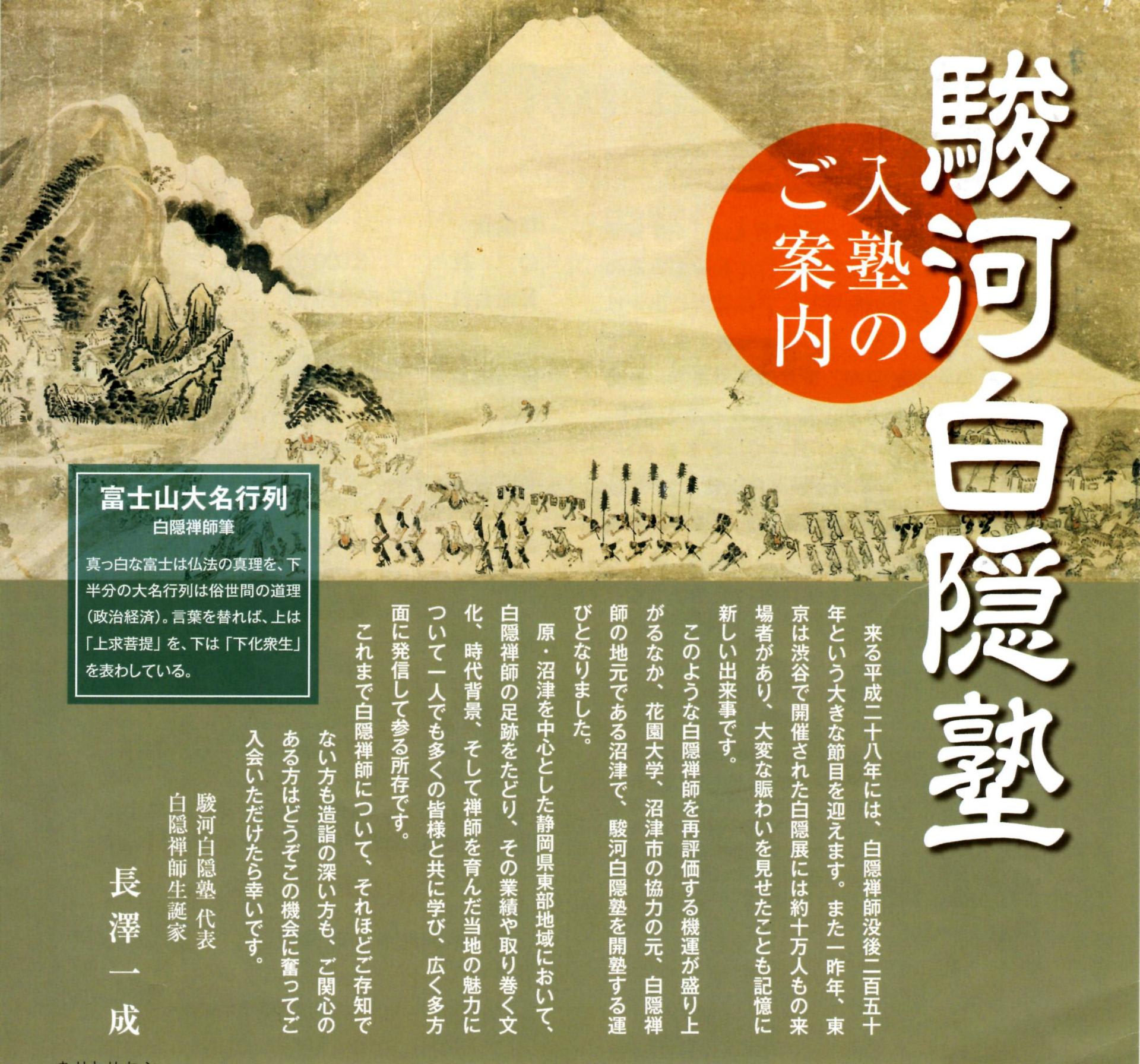今年は沼津で2回、7月と11月に開かれた白隠フォーラムに参加したことで、白隠さんと、白隠さんが終生暮らした沼津というまちをグッと身近に感じています。これまで沼津といえば、食や酒や観光の取材がほとんど。白隠さんを通してみた沼津には新鮮な驚きや発見がありました。今後、自分がこのまちとどう関わっていくのか、不思議な転換期になった感があります。
11月の白隠フォーラムでは、沼津で新たに【駿河白隠塾】という組織が立ち上がることが発表されました。白隠さんの生家・長澤家の現在の当主長澤一成さんが代表に、芳澤勝弘先生が塾長となって、フォーラムや縁地ツアー等を定期的に開催し、地元で白隠さんをきちんと学ぶ場にしていこうというもの。11月に参加した友人たちは、わりと軽く、「沼津市が白隠さんを担ぎ出して町おこしするんだ~」というとらえ方をしていましたが、私は自治体のシティプロモーションという枠ではとらえきれない深いものを感じていました。静岡市が2007年にシティプロモーション予算で映画【朝鮮通信使】を製作したときの“裏側”を経験し、誰もが知っている有名人や人気キャラクターではなく、一般に馴染みのない人物や片寄った見方をされがちなテーマでシティプロモーションするという作業はハンパな覚悟では出来ないと思っています。
長澤さんは現在、耕文社という印刷メディア企業を経営されており、芳澤先生は白隠学の世界的権威ですから、このお2人がヘッドとなれば、かなりのことは出来ると期待されますが、川上のほうで盛り上がるだけでは長続きしない、川下のほうからジワジワ熱を上げる導火線というか発火源みたいなものも必要ではないでしょうか。
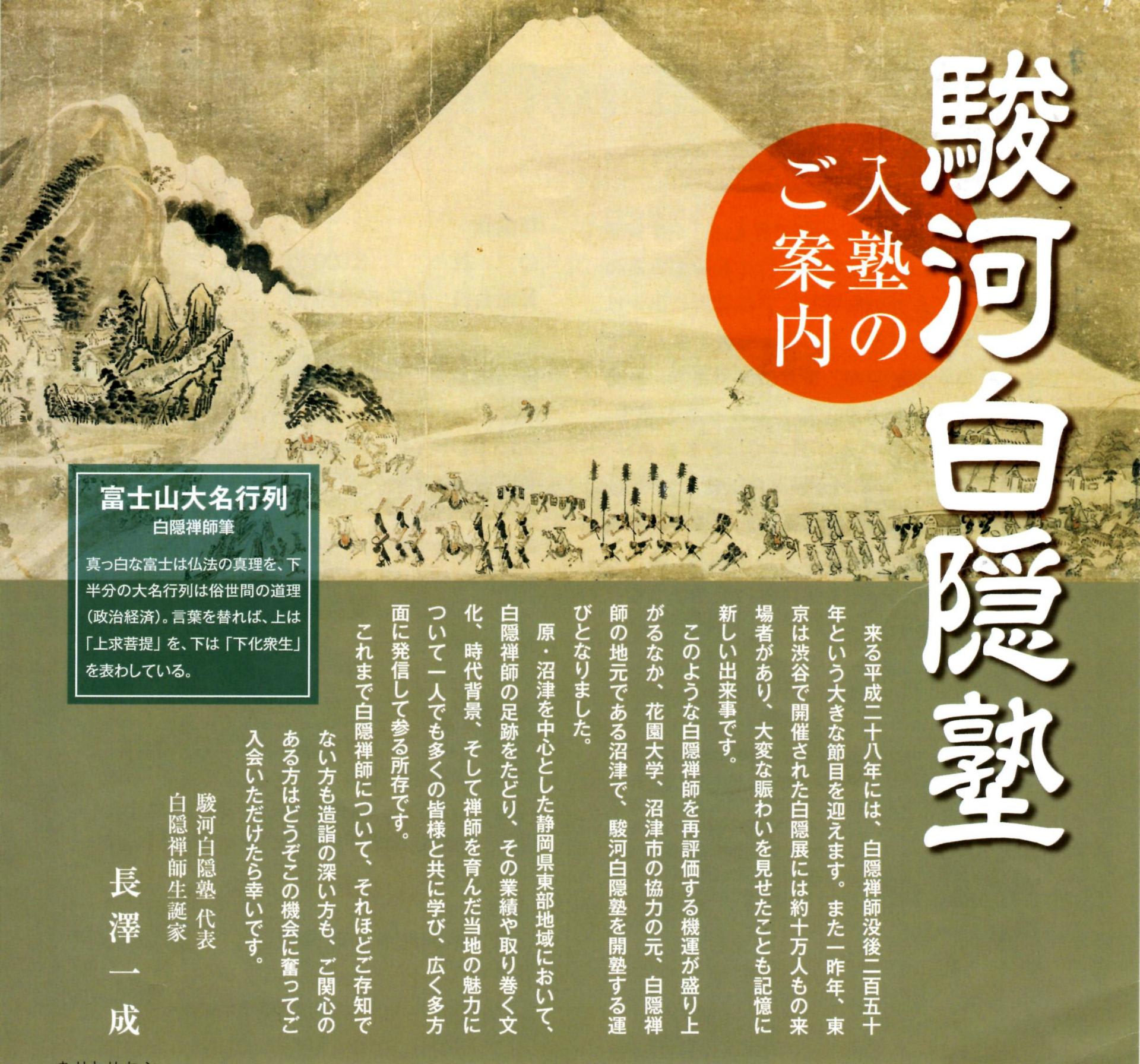
そんなこんなで駿河白隠塾の船出を川下のほうから見守るつもりでいたところ、思いがけず運営委員に、というお声かけをいただき、18日に開かれた顔合わせの会合に参加しました。代表と塾長のほか、理事5名、運営委員16名、事務局5名というしっかりした組織で、県や市や経営団体代表者や文化事業者など等、立派な肩書きの方々ばかり。静岡市民でフリーランスのライターで地酒研究会・・・なんて自分は場違い感アリアリで、挨拶では地酒「白隠正宗」の話と朝鮮通信使制作時の裏話ぐらいしか出来ず(苦笑)。もうちょっと沼津に貢献できそうな、マシな自己アピールができなかったかなーと帰宅後に反省し、過去、沼津について書いた原稿を精査してみたら、ありました!
以下は、スルガ銀行のシンクタンクから受注していた仕事で、沼津市の教育関係者の座談会(2009年11月開催)を記録したものです。その名も「夢ある人づくり塾」。改めて読み返してみたら、沼津には素晴らしい教育哲学があるんだと深く感じ入りました。○○塾というネーミングも、この頃から定番だったのかな。白隠さんの名前が出てくる部分を書き出してみます。
「白隠さんは世界のインテリの王道のように扱われていますが、白隠さんは地獄が怖くて仕方なくて、地獄から遠ざかるにはどうすればいいかが修行のきっかけだったという。そういうことは子どもたちにもあって、いじめに対する恐怖は共通して持っている。いじめられたくないから、いじめ側に入るわけでしょう。子どもたちには、ポジティブな夢ばかりでなく、ネガティブなものだって目標になるんだと教えてもいいのではないでしょうか?何でも夢にならないものはない、地獄ですら目標になるんだと。」
「白隠さんに関しては、私どもが中学高校のころはまったく触れられていなかったと思います。たまたま私は本を読んで知っていたのですが、たぶん今、白隠さんを市の教育で取り上げるとなると、宗教や個人崇拝云々の問題になるでしょう。社会全体、日本全体が夢を持っていないというのはそのとおりですが、地球規模の環境問題がクローズアップされている中、これをテーマに日本人が世界を救う、みたいなことをやろうじゃないかと考えています。」
「夢があっても挫折する場は多い。私の弟は東大の赤門を見て絶対ここに入ると宣言しながら入れなかった。私も入れませんでしたが、そんな挫折はしょっちゅうあっても何とかやっていくのが人間です。今、自殺が非常に多いのは、夢破れると簡単にあきらめてしまう。夢ある人は子どものことばかりでなく、生涯教育の面でも通じることだと思います。」
「教育委員会で小学校や中学校を訪れた時、先生の退職率が高いと聞きました。小学校や中学校が勉強の場ではなく、生活指導の場になってしまっていて、生活指導をしてくれない先生に親がクレームをつけるという。家庭教育が崩壊したため、躾から何からみんな学校に押し付け、先生は「こんなストレスの多い仕事はやってられない」と退職率が増えているというのです。家庭教育の崩壊をいかに食い止め、再生させるかを考えないと、いくら学校改革をやったところで何も解決しないと思います。」
「白隠禅師は子どものころ、地獄が怖くて夜も眠れず、大きくなるまで母親が懐にひしと抱きしめて眠らせたという。親というのは、学校の先生にどう文句を言おう、じゃなくて、子どもと正面から向き合い、ひしと抱きしめてほしい。手を上げるにしても、抱きしめた後で叩いたほうがいいんじゃないでしょうか。いきなりぶん殴られて、喧嘩にならないほうがおかしい。夢だって、親が釣りに夢中なところを見せてもいい。どんなつまらない魚だって夢中になって釣りをしている父親を見れば、一緒にやってみようと思うでしょう。そういう親子関係が基本ではないでしょうか。白隠さんのおっかさんのような理想が、故郷にあるじゃないですか。家庭におけるしつけも含めた教育のモデルが、わが故郷に在り、ですよ。」
「大事なところは本に親しむ、かかわる、読み書きを大切にするということですね。東北大学の先生が脳の血液の流れを調べたところ、読み書き計算をしているとき、脳の活性化に役立つということがわかりました。とくに小学校中学校の教育では大切ですね。もうひとつ、家族の構成が、家庭教育において非常に大きい。私が子どもの頃は、母親に叱られても祖父がなだめてくれたものです。家庭教育で互いに分担できるのが理想でしょうが・・・。」
「地獄を怖がっていたらひしと抱きしめてあげてくださいよ。地獄なんてテレビゲームでしか見たことないなんて親子は、お寺に行って地獄絵を見てきなさいといいたい。宗教教育は日本で徹底的に禁じられていますから、家庭で教えるしかない。南無妙法蓮華経を唱えようとしたら、次の選挙に影響するからなんて言われる。そんなの関係ないでしょう。日蓮さんが命をかけて伝えた教えです。山岡鉄舟は馬で龍譚寺(白隠が開いた禅道場)まで行って参禅して、また馬で江戸城まで帰って勤務についたという。それぐらい自己研さんに励んだ人です。そういう人を輩出したのが駿河静岡なんです。」
「人間の問題は、本質的に人間自身を深めていかないと解決しないように思います。個人と、社会的存在としての人間をどうするかを考えないと、根本は解決しないのでは。教育問題から離れてある種の哲学の問題になるのかもしれませんが、我々学生のころは哲学的なことを一生懸命考えたものですが、日本にそういうものがなくなってしまいましたね。」
「親や先生から「お前の夢は何だ」と聞かれること自体にストレスを感じる子どももいるようです。世の中には夢を持って邁進する人もいれば、夢を持った人を支え、協力して叶えようとする人もいます。よくイギリス人は「人間には『キャプテン』と『クルー』の2種類いて、全員キャプテンだったら船は動かない。キャプテンが指示する方向に櫂をこぐクルーがいて、初めて船は進む」という。だから子どもたちに夢を聞いた時、友だちにはっきりした夢を持ってリーダーシップを発揮できる子がいたら、自分にこれという夢がなくてもその人についていく―そういうことも大事だよと教えるべきだと思います。」
「日本の戦後教育は、みんなキャプテンになるよう教えたんですね。それは無理なんだよね。悪しき平等です。平等はあくまでも機会の平等です。もうひとつ、家庭は教育を目的じゃなく手段にしてしまっている。ようするに、いい大学に行くためにいい高校に行き、いい高校に行くためにいい中学に行くという。何になりたいのか、そのためにどの学校を選ぶかという発想がない。親が失敗したことを子どもにもしているように見えます。」
「地獄大菩薩の絵を見て潰れそうな会社を立て直した社長さんが実際にいたんですよ。地獄でさえ夢になるのです。言葉教育に力を注いでいる沼津なら、別に白隠さんや地獄大菩薩でなくてもいいので、基礎能力の慣用と道徳心を大切にしてほしい。お隣の小田原には二宮尊徳さんもいるでしょう。尊徳さんの素晴らしさは彼が残した文字や言葉から学んでほしい。大人も子供も精神の骨格は同じです。子どもは親の道具じゃないし、教師は学校の職務業績の指標として見てほしくはないのです。」
「我々の世代はキルケゴールやニーチェなどをかじり、神は存在するかどうかなんて思案したものですが、我々下の世代、つまり今の親の世代ではそういうことはしないでしょう?哲学は今の日本は非常に貧困です。大学自身がそうですね。今の学生はまず漫画でしょう。我々は文学やらいろんなものを読みましたが。」
「死と直面することで人は哲学になれるんですね。戦前の人が哲学的だったのは、いつ徴兵されるかわからない状況で生と死を考えざるを得なかった。そういう状態に戻すというのは平和に逆行するわけですが。結論は出なくてもいいのです。ある種、自分の在り方についてフレキシブルに考えるというのが大切です。」
「子どもは葬式にたくさん連れていくべきでしょうね。人の死をたくさん見せるべき。」
「言葉の教育は非常に大切です。言葉というのは、ようするに情報を伝えるだけでなく、自分自身が言葉を通してしっかり考えている。その意味で言葉の重要性を考えなければなりません。我々学生のころは、酒を飲みながらも議論をしたものですが、今の学生は議論しません。」
「今の臨床心理学や心理療法では、世界共通で「物語」になっていると相互理解が進むといわれています。物語という形になっていると、なぜ人と人が結ばれるかが理解できる。世界中で、言葉を使って物語にすることで、世界を解釈できるのです。これには子どものころから本を読み、物語が好きになることが大切です。」
「日本は言霊の国だったのです。日常の中で言葉を大切にしていた。沼津の理想は言葉教育先進シティです。」
白隠さんの物語をつむぐ、芳澤先生という素晴らしいキャプテンの指し示す新たな航路。一番下っ端クルーとして一所懸命漕ぎ続けていきたいと思います。なお駿河白隠塾では2015年2月27日(金)18時から、プラザヴェルデで第1回フォーラムを開催予定です。講師は芥川賞作家玄侑宗久さんと芳澤先生。チラシが入手出来次第、詳しくご案内しますのでご期待ください。