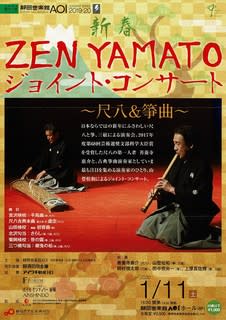ちょうど今、ある商品のネーミングで脳内格闘中。改めて、名前を付けるというのは本当に難しいし責任が重いと痛感しているところですが、2月16日に参加した北村欽哉先生の朝鮮通信使講座@静岡市長田生涯学習センターでは、地名のネーミングに秘められた光と影の存在を知りました。
講座のテーマは『朝鮮岩の謎に迫る~消えた朝鮮ヶ谷・起木梅伝説』。朝鮮岩というのは静岡市民ならご存知の方もいらっしゃると思いますが、静岡と焼津の境にあり、日本坂につながる満願峰(標高470メートル)ハイキングコースの眺望ポイントですが、なぜ朝鮮岩と呼ばれるのかハッキリした理由はわかっていないようです。

そもそも日本坂も、1834年に記された『駿河国新風土記』に〈日本坂という地名は神祖(=徳川家康)がこの地に遊行した折、この地を朝鮮ヶ谷と命名したという説もある〉と紹介されており、家康命名説は『なこりその記』(1842)、『駿国雑志』(1843)にも紹介されています。
また朝鮮岩から見た長田地域一帯を朝鮮ヶ鼻と記した記述が1806年の『東海道分間延絵図』に登場します。
今から12年前の2008年に静岡県朝鮮通信使研究会で同じテーマで先生が講演されたとき、日本坂一帯に朝鮮の地名が多く残る理由を「秀吉の朝鮮侵攻で拉致されてきた被虜人がこの一帯に住んでいたのかもしれない。彼らは奴隷売買されて各地に連れてこられたから」と推測されましたが、朝鮮岩に関しては今回、新たな説を披露されました。

郷土史家春田鉄雄氏がまとめた『おさだ留帳』(1989)によると、朝鮮というはもともとは晁川(ちょうせん)という表記が正しく、晁(ちょう)というのは天平の時代、阿倍仲麻呂が唐に渡ったときに使用していた姓。つまり晁川とは阿倍(安倍)川のことで、安倍川の西にある岩だから晁西岩(ちょうせいいわ)。それがなまって朝鮮岩になったというのです。親父ギャグみたいな話ですが、1808年に池田安平という人が書いた『日古登能不二』に「晁川(あべかわ)*ルビは本文のまま の辺に釣を垂れ、はやはすなどを得たり。彌勒のかたへ来たりて・・・」という記述があり、晁川が安倍川を指す証拠にもなっているんですね。
一方、日本坂を指す朝鮮ヶ谷や朝鮮ヶ鼻という表記は、今は残っていません。残っていないどころか、1861年の『駿河志料』には"日本坂は日本武尊が越えた坂" と書き換えられており、これが今に至るまでの定説になっています。
静岡には日本平もありますが、こちらも やまと平(日本武尊が平定した地)という意味付け。平凡社の『静岡県の地名』(2000)、角川書店の『静岡県地名大辞典』(1982)、静岡新聞社の『静岡大百科事典』(1978)など最新の調査結果に基づいたであろう地名関連書籍などでも、この説を採っています。つまり1861年の『駿河志料』以降の文献には、日本武尊のことしか載っていないのです。
唯一の例外は1956年に松尾書店から発行された『史話と伝説』。日本坂は徳川家康が狩りの時にここに来て、日本一の景色だと褒め称えたことから日本坂と言うようになったとありますが、〈朝鮮〉の二文字は見当たりません。
〈朝鮮〉の表記が消えた事例は、他にもあります。国道1号線の丸子から岡部・藤枝方面に向かう途中の赤目ヶ谷に長源寺という寺があり、境内に起樹天満宮という小さなお社があります。1843年の『駿国雑志』によると、神社の梅の木が街道側に傾いて、朝鮮通信使の行列の妨げになるので切り倒そうとしたところ、一夜にして梅の木は神社側に起き上ったという故事があるそう。
また延享4年(1747)の史料にも、“朝鮮通信使が通る道に支障があってはいけないと、並木や枝を整えるよう代官がこまかく指示をした”という記述があります。梅の木が一夜にして起き上ったという説は天満宮らしいファンタジーだと思いますが、実際のところは、旗鑓を高く掲げて行進する通信使一行の支障になるから梅の木を剪定したのだろうと想像できます。
ところが1861年の『駿河志料』では、建久元年(1190)に源頼朝が上洛するとき、社前の梅が駅路に横たわっていたので枝を切ることになったが、梅の木は一夜にして起き上ったとあり、それ以降の文献やガイドブックはこの頼朝説のみを採用しています。つまりここでも、何の脈略もなく突然、頼朝伝説が登場し、1861年の『駿河志料』以降、完全に塗り替えられたというわけです。
なぜ、日本坂や起樹天満宮の縁起が、日本武尊や頼朝伝承に書き換えられたのか、朝鮮通信使研究家たる北村先生が疑問に思わずにいられないのも無理からぬこと。『駿河志料』の筆者は、わずか27年前に書かれた『駿河国新風土記』にある日本坂=家康の朝鮮ヶ谷命名説を無視し、さらにわずか18年前に書かれた『駿国雑志』にある起樹梅=朝鮮通信使通行説を無視して、頼朝説を用いたのです。これを明治以降の研究家も踏襲した。古い文献を無視して『駿河志料』の説だけを採る理由を、北村先生は『駿河志料』が書かれた時代背景にあると指摘されました。
今、巷を賑わせる新型コロナウイルスじゃありませんが、駿河志料出版の3年前の1858年、江戸で約1万2千人が命を落とすコレラが大流行しました。当時の人はもちろんコレラ菌が原因だなんて判りませんから、狐憑きだと恐れ、キツネを退治してくれるオオカミを祀った神社のお札を買い漁ったのです。さしずめ今のマスクみたい?
このキツネはそもそも1853年に突如現れた黒船が海の向こうから連れてきたのだと噂になり、さらに1854~55年にかけて安政の大地震ー今で言う南海トラフ巨大地震と一連の地震が各地を壊滅させます。巨大地震と疫病が連鎖する歴史なんて、絶対に繰り返さないで欲しいと願わずにはいられませんが、とにかく、駿河志料が書かれた頃、目に見えない恐ろしい不可抗力に襲われ、人々は厭世観に陥ったに違いありません。
徳川政権が長く続き、社会に様々なひずみが生じていた18~19世紀にかけ、国内では徳川が信奉する儒学に対抗する意味で、国学論者の声が大きくなってきます。それがやがて尊王論=天皇を中心としたナショナリズムの萌芽につながっていきます。
ここ駿府の地でも、尊王論を説いて幕政批判し死罪になった山縣大弐の兄で野沢昌樹という国学者が、京を追われて丸子の長源寺に寓居します。彼の元に駿府の有力町人や武士が集まり、ちょっとした国学ブームが。本居宣長を熱心に学んだ彼らは清少納言の枕草子にある〈森は木枯らしの森〉の記述をもとに、安倍川と藁科川の合流点に木枯森碑を建てたのでした。
ちなみに野沢が寓居した長源寺は、前述の起樹天神宮のある寺。であれば、国粋主義者たちが起立梅について朝鮮の二文字を消し、さらには朝鮮ヶ谷の家康命名説をも消すよう働きかけたのではないかと想像してしまいますね。幕府がガタついていたとはいえ、まだ治世者だった徳川方の威光があれば、神君家康や家康の功績である朝鮮通信使のことを無きものにするとは考えにくい。となると『駿河志料』のような地方誌を書いた市井の物書きレベルにも、反徳川・国学至上主義が浸透していたと想像できるのです。
国学を熱心に学ぶことは日本人として正しいとは思いますが、「日本エライ」「日本スゴイ」が行き過ぎると排他的な思想に陥りがちだろうことは、その後の日本がたどった歴史からもわかります。
お寺好きな私にとって、明治政府の廃仏毀釈は本当に愚策。朝鮮とは何百年も戦争をせず平和友好関係を築いた世界史でも希有な隣国同士だったのに、それが徳川前政権の功績だからと全否定するのも浅はか。仏教や儒教は確かに外国産の宗教かもしれないけれど、島国日本の先人たちはそれを受容し、一千年以上かけて日本的にアレンジし定着させた。陸の国境を持たない海洋国家・日本は、万事そのようにして独自の国づくりをしてきたのに・・・。先生のお話を聞いているうちに、偏った国粋主義者たちへの怒りが湧いてくる一方、自分が駿河志料を書く立場だったらと想像し、時代の風に抗う難しさを痛感しました。
それにしても、なぜ朝鮮岩だけが、朝鮮の二文字を残すことができたのかは謎のままです。私にその謎解きができる能力があれば挑戦してみたいところですが、とりあえずは今直面するネーミングの仕事をなんとか完遂させなければ。

 (1996年10月22日静岡新聞夕刊)
(1996年10月22日静岡新聞夕刊)