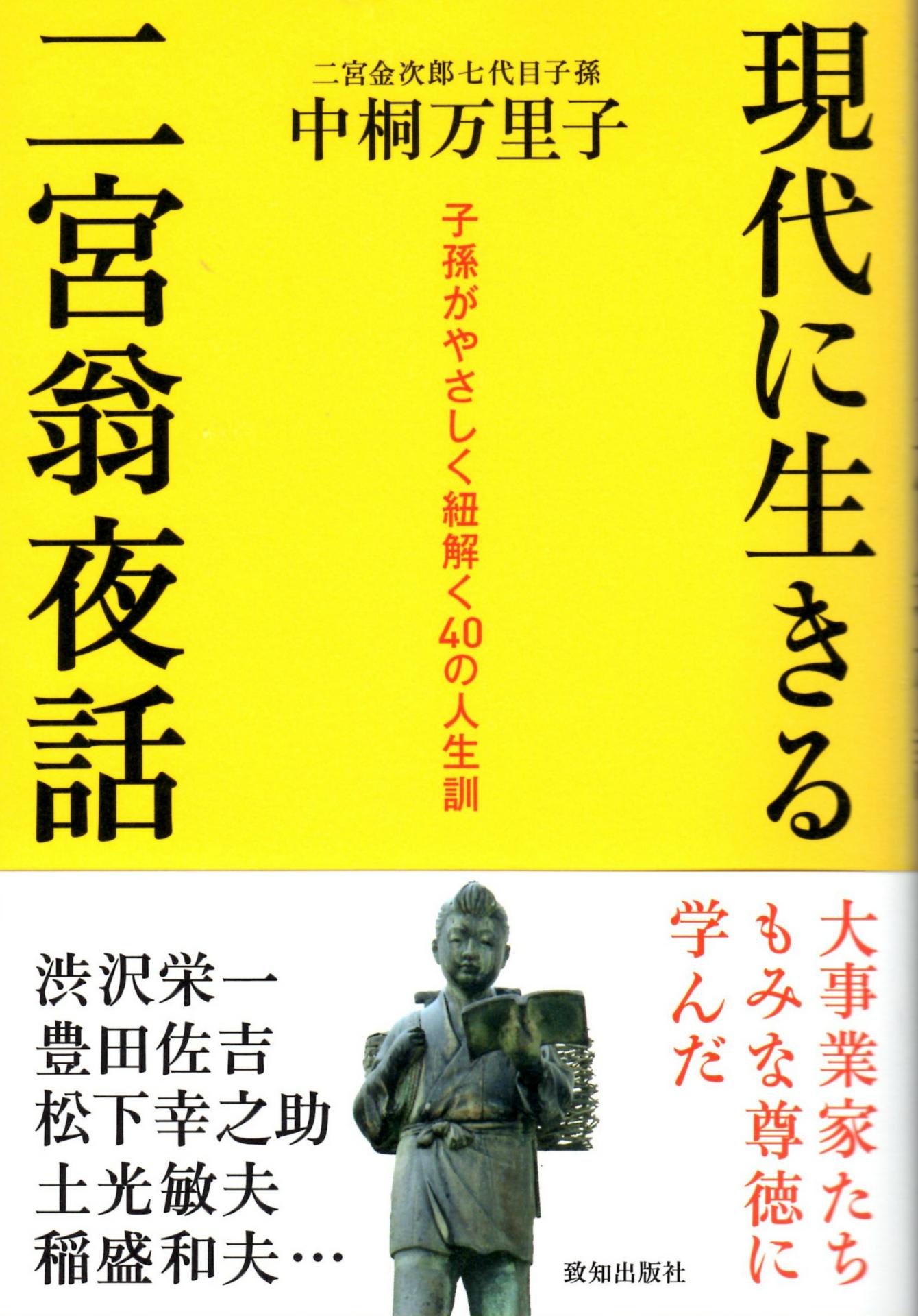2月23日は静岡県が条例で制定した『富士山の日』(その理由についてはこちらもぜひ)。各地でさまざまな行事が執り行われた中、私は【白隠正宗】の醸造元・高嶋酒造(沼津市原)で早朝から取引先酒販店や飲食店のみなさん70余名が集って行なった【富士山の日朝搾り】のラベル貼り&出荷作業を取材しました。23日未明から搾って瓶詰めしたての静岡県産米「誉富士」精米歩合60%純米生原酒おりがらみ。アルコール度数は16.9度。日本酒度+2、酸度1.2。この数値が示すように低酸でおだやかな、実に静岡酒らしい優麗な味わいでした。

西は名古屋、東は町田から集まった取引先のみなさんは、こういう作業に参加するということに大変なやりがいを感じていたようで、作業終了後に蔵元がふるまってくれた朝ごはんのかやくおにぎり&豚汁を美味しそうに頬張り、またこの日の夜、県内各地の飲食店で開催された「しずカパ(2月23日、誉富士の酒で18時30分に一斉に乾杯するイベント)」でもこの酒で大いに盛り上がったようです。私が平成8年(1996)にしずおか地酒研究会を発足したときに掲げた活動テーマ「造り手・売り手・飲み手の和」のカタチが、20年経てこんなに進化したのか・・・と、じんわり感動しちゃいました。もっとも私はこの日、富士~沼津地区で3軒取材をして疲労が重なり、熱を出して自宅でおとなしく寝てました(苦笑)。


現在、各蔵の上槽(搾り)作業を取材していますが、搾りのタイミングというのはもろみの醗酵状況によって実に慎重に計ります。何日の何時に搾るか直前にならないとわからないため、こちらも事前に予定が立てられず、運よくタイミングがあった蔵元にしか行けません。それだけに、2月23日朝に搾ると事前告知し、このタイミングに合わせて醗酵をきちんとコントロールした蔵元杜氏・高嶋一孝さんの手腕には惜しみない拍手を送りたいと思います。ちなみに3月22日は“逆さ富士の日”と銘打って、富士山の日朝搾りを加水火入れして限定発売するそうです。入手可能な取引先酒販店は高嶋酒造(こちら)へお問合せください。


ところで、私が注目したのは、富士山の日朝搾りのラベルです。初代歌川広重と三代歌川豊国が共同制作した『双筆五十三次・はら』という浮世絵。高嶋さんは所蔵先の国立国会図書館まで出向いて許可を取ったそうです。

ここに描かれた「富士の白酒」。おりがらみの誉富士純米生原酒のラベルに実にぴったりですが、「富士の白酒」自体は今現在、高嶋さんが造っておられる純米酒とは違うスペックのようです。
実は、昨年来、酒造史料の調査で県立図書館に日参しているうちに、偶然、平成8年(1996)7月に富士市立博物館で開催された企画展『郷土と酒』の図録を見つけて、ちょうどひと月ぐらい前、博物館へ直接出向いて図録を入手したばかりだったのです。私は当時、発足間もない地酒研活動に忙殺され、企画展を見逃してしまったため、図書館で図録を見つけたときは「あ~っも~っ」と声を上げるほど自分にガッカリ(苦笑)。その図録に「富士の白酒」のことが詳しく紹介されていました。

それによると、「富士の白酒」が文献や浮世絵に登場し始めたのは江戸後期。北斎の東海道五十三次・吉原(1803~10頃)では「白酒のもろみを石臼で磨く図」、駿河国新風土記(1840~43頃)には「富士酵、糯を焼酎に和して醸す、味美なり」、本市場村明細書上帳(1843)には「立場茶屋、名物白酒商売仕候」等などと紹介されています。本市場(現在の富士市本市場付近)は、江戸時代、吉原宿と蒲原宿の間にある東海道の間宿で、富士川流域の加島平野に位置していた。この地域は“加島五千石”とうたわれた穀倉地帯で、西北にあたる岩本村は1233石を誇り、幕藩体制下の村としては最大規模に近かったそうです。こういう土地で酒造りが活発になり、名物とうたわれるようになるのもナットクですね。
駿河国新風土記に「富士酵、糯を焼酎に和して醸す、味美なり」としか記述がないため、白酒がどのように醸造されていたのかは不明のようですが、白酒の一般的な醸造法を紹介した江戸時代の百科辞典・和漢三才図会によると、
「白酒は精米したもち米7升を1斗の酒の中に漬け、かたく封をする。これを春夏なら3日、秋冬なら5日たって口を開け、箸でその飯粒をとかす。なめてみて甘味が生じたのを見計らって、このもろみを(石臼)で磨く。白色は乳のようで甘い」
とあります。富士の白酒の場合、酒ではなく焼酎に漬けていたようです。いずれにせよ、造り酒屋が大々的に造って売り出したというよりも、本市場の農家が間宿で茶店を兼業し、店頭で旅人にふるまったささやかなおもてなし、だったようで、浮世絵でさかんに描かれたということは、さぞかし“味美”で評判だったのでしょう。
東街道覧図略には本市場の茶店にこんな狂歌が残っていたと紹介されています。
「風になひく雲にはあらての旅人のひつかけてゆく富士の白酒」
「白さけの看板に立つや雪の不二」
「何みても雪かと斗見せつきの女子の顔も富士の白さけ」
「年よりて又のむべき思ひきや銭のあるたけふじの白酒」
静岡県産米の誉富士と、静岡県で開発された静岡酵母で、実に静岡らしい純米酒を醸し、それを富士山の日の朝に搾り切り、取引先を集めてもてなした高嶋さんの心意気に感動するとともに、白隠禅師や富士の白酒というかけがえのない郷土の歴史を酒のラベルに載せて発信する姿勢に、酒の蔵元がなぜ地域に必要かを改めて考えさせられます。
東海道筋に多い静岡県の蔵元は、他県の蔵元が欲しくても得られない「歴史」という財産を持っています。今の若い売り手や飲み手には、すぐにはピンと来ないかもしれませんが、歴史、とりわけ街道という人やモノや情報が行き交う場所で育まれた歴史と、歴史が伝える「物語」は、国内のみならず、世界に誇れるオンリーワンのもの。物語のチカラを、これからの造り手・売り手・飲み手も上手に活かしていくべきでは、と思います。しずおか地酒研究会で歴史部会でも作ろうかな。