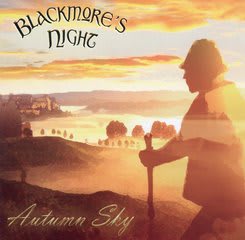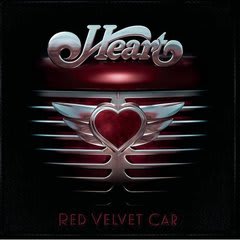ANGRAのあの名盤『Temple Of Shadows』をプロデュースしたDennis Wardが手掛けた
スタジオ・プロジェクト。
いや、本当はPINK CREAM69のベーシストなのだが、私にはその方がわかりやすい。
ボーカリストは、元HAREM SCAREMのHarry Hess。
そのため、HAREM SCAREMの1stである1993年発売の『Mood Swing』の感触を持つという。
私はちょうどその頃のヘア・メタルを聴き逃してしまっているので、比べようがない。
従って、聴いたままを書いてみる。
まず聴いてびっくりするのは、すべて爽やかなメロディック・ハードで、捨て曲がないことだ。
メロディラインの美しさ、キャッチーさ、感動的な度合い、どれを取っても素晴らしい。
サウンドがカラッとしてて、籠った感じがまるでなく、抜けている。
ハードでありながら、重低音がそれほどでもなく、ミドル・テンポが多い。
ヘア・メタルが出現する前のバンドとしては、REOスポードワゴンが近い。
時折入るギターソロは、テクニックはさて置き、華麗で派手めでよく合っている。
Harry Hessの甘さもあるハスキーな声がいい。
これにコーラスが合わさって、広がりと爽やかさが倍増している。
曲の展開は、胸がかきむしられるような切なさや懐かしさがたまらない。
HOUSE OF LORDSが楽曲提供しているのを知り、納得した。
1曲目の“This City”の華麗なギターで始まるオープニングからして、惹きつけられる。
一緒に歌いたくなる。
2曲目の“When You Believe”の高揚していく感は得難い。
明るめな曲もいいのだが、バラードが最高の出来だ。
3曲目の“Part Of Me”、4曲目の“Crazy”の、スローなマイナーコードから始まり、
途中からじわじわと盛り上がっていくのは、どう言われようと日本人好みだろう。
ダレそうな後半の10曲目に、ややヘヴィーな“Yesterday's Rain”を持ってくるのは、心憎い気配りだ。
さすがDennis Ward。
スタジオ・プロジェクト。
いや、本当はPINK CREAM69のベーシストなのだが、私にはその方がわかりやすい。
ボーカリストは、元HAREM SCAREMのHarry Hess。
そのため、HAREM SCAREMの1stである1993年発売の『Mood Swing』の感触を持つという。
私はちょうどその頃のヘア・メタルを聴き逃してしまっているので、比べようがない。
従って、聴いたままを書いてみる。
まず聴いてびっくりするのは、すべて爽やかなメロディック・ハードで、捨て曲がないことだ。
メロディラインの美しさ、キャッチーさ、感動的な度合い、どれを取っても素晴らしい。
サウンドがカラッとしてて、籠った感じがまるでなく、抜けている。
ハードでありながら、重低音がそれほどでもなく、ミドル・テンポが多い。
ヘア・メタルが出現する前のバンドとしては、REOスポードワゴンが近い。
時折入るギターソロは、テクニックはさて置き、華麗で派手めでよく合っている。
Harry Hessの甘さもあるハスキーな声がいい。
これにコーラスが合わさって、広がりと爽やかさが倍増している。
曲の展開は、胸がかきむしられるような切なさや懐かしさがたまらない。
HOUSE OF LORDSが楽曲提供しているのを知り、納得した。
1曲目の“This City”の華麗なギターで始まるオープニングからして、惹きつけられる。
一緒に歌いたくなる。
2曲目の“When You Believe”の高揚していく感は得難い。
明るめな曲もいいのだが、バラードが最高の出来だ。
3曲目の“Part Of Me”、4曲目の“Crazy”の、スローなマイナーコードから始まり、
途中からじわじわと盛り上がっていくのは、どう言われようと日本人好みだろう。
ダレそうな後半の10曲目に、ややヘヴィーな“Yesterday's Rain”を持ってくるのは、心憎い気配りだ。
さすがDennis Ward。