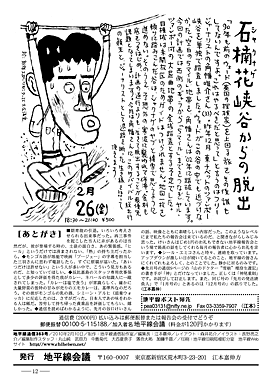今日は「千代田3331」というアートスペースのオープニングに行ってきました。
ここは廃校になった小学校の跡地を利用して、現代アートの作家がコミュニティーと関わりながら何かを発信していこうというスペース。
有名作家も参加したかなり面白いスペースになりそうです。
印象に残ったのは、八谷和彦さんというメディアアーティストの主催する「秋葉作ってみたラボ」。科学とアートの融合といった感じで驚きがあり楽しめました。
あと、秋田県大館市の若者たちがメインの「ゼロダテ アートプロジェクト」も可能性を感じさせる企画。
大館で売られている日用品をアートな感覚で販売するスペースもあったのですが、思わず竹で編まれた「ウナギ取り用の魚籠」を衝動買いしてしまいました。なんに使えばいいのか・・・。
オープニングでもいろいろな人と出会えて、何か新しいワクワクする事がはじまる予感があります。
http://www.3331.jp/
で、そんな予感を感じつつ、お昼は近所の秋葉原でランチ。
なんとメイド喫茶です。
まあ正確には「鉄道居酒屋 LittleTGV」というお店で、メイドじゃなくて女性駅員さんが迎えてくれるのですが、かなり面白い経験でした。
テレビとかでは見た事があったのですが、オムライスを頼むと、駅員さんが文字をケチャップで書いてくれます。
で僕がお願いしたのがこの文字。

かわいい駅員さんも「?」という表情でしたが、ちゃんと書いてくれました。
それにしても、駅員さんがとても楽しそうに接客するのが興味深かったです。
かなりディープなお客さんも来店していましたが、とても上手く応対していて、僕たちのような素人客にも積極的に話しかけてくれて盛り上げる演出力はなかなかのもの。かなり感心しました。

というわけで、さすがアキハバラ、アートもあるしメイドもいるカオスな土地です。
ここは廃校になった小学校の跡地を利用して、現代アートの作家がコミュニティーと関わりながら何かを発信していこうというスペース。
有名作家も参加したかなり面白いスペースになりそうです。
印象に残ったのは、八谷和彦さんというメディアアーティストの主催する「秋葉作ってみたラボ」。科学とアートの融合といった感じで驚きがあり楽しめました。
あと、秋田県大館市の若者たちがメインの「ゼロダテ アートプロジェクト」も可能性を感じさせる企画。
大館で売られている日用品をアートな感覚で販売するスペースもあったのですが、思わず竹で編まれた「ウナギ取り用の魚籠」を衝動買いしてしまいました。なんに使えばいいのか・・・。
オープニングでもいろいろな人と出会えて、何か新しいワクワクする事がはじまる予感があります。
http://www.3331.jp/
で、そんな予感を感じつつ、お昼は近所の秋葉原でランチ。
なんとメイド喫茶です。
まあ正確には「鉄道居酒屋 LittleTGV」というお店で、メイドじゃなくて女性駅員さんが迎えてくれるのですが、かなり面白い経験でした。
テレビとかでは見た事があったのですが、オムライスを頼むと、駅員さんが文字をケチャップで書いてくれます。
で僕がお願いしたのがこの文字。

かわいい駅員さんも「?」という表情でしたが、ちゃんと書いてくれました。
それにしても、駅員さんがとても楽しそうに接客するのが興味深かったです。
かなりディープなお客さんも来店していましたが、とても上手く応対していて、僕たちのような素人客にも積極的に話しかけてくれて盛り上げる演出力はなかなかのもの。かなり感心しました。

というわけで、さすがアキハバラ、アートもあるしメイドもいるカオスな土地です。