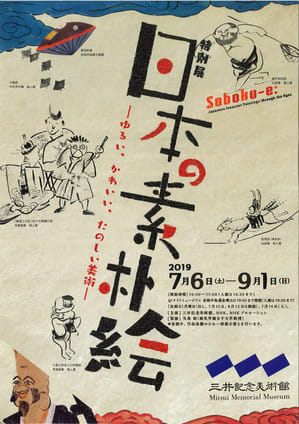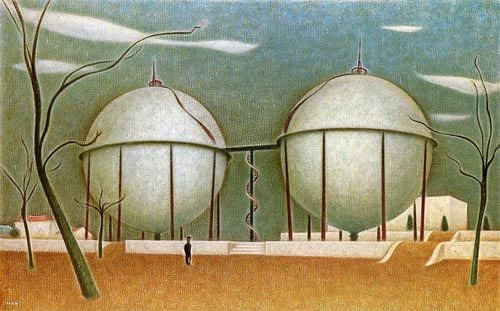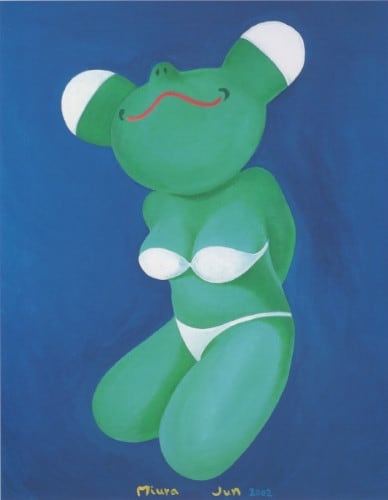昨日は、渡辺えりさん、小日向文世さん、そして、のんちゃん出演のオフィス3○○の舞台『私の恋人』@本多劇場

もちろん、のんちゃんの初舞台が目当てでした。
芸達者な二人の大先輩に混じり、のんちゃんも含め3人で30役をめまぐるしく演じるという展開。
ストーリーは時間も空間も錯綜し、展開も早く付いていくのがやっと、というか途中からよく分からなくなちゃった。
とは言え、決して退屈ではなく最後まで楽しく見ることができました。
その理由は、3人の安定した演技。
特に、のんちゃんは舞台上でも独特の存在感で光り輝いていました。
本当にすごい女優さんだな~。
最初の登場シーンから、髪を上げた少年役が可愛らしく、メガネを掛けたり、アボリジニになったり、セーラー服を着ていたりとほんと次から次への早着替え。
コメディエンヌ的な才能も感じたし、何より、のんちゃんが楽しそうに演じているのが何より。
本多劇場という箱もベストだし、満足でした。
次はもう少しじっくり見られるようなお芝居希望です。


もちろん、のんちゃんの初舞台が目当てでした。
芸達者な二人の大先輩に混じり、のんちゃんも含め3人で30役をめまぐるしく演じるという展開。
ストーリーは時間も空間も錯綜し、展開も早く付いていくのがやっと、というか途中からよく分からなくなちゃった。
とは言え、決して退屈ではなく最後まで楽しく見ることができました。
その理由は、3人の安定した演技。
特に、のんちゃんは舞台上でも独特の存在感で光り輝いていました。
本当にすごい女優さんだな~。
最初の登場シーンから、髪を上げた少年役が可愛らしく、メガネを掛けたり、アボリジニになったり、セーラー服を着ていたりとほんと次から次への早着替え。
コメディエンヌ的な才能も感じたし、何より、のんちゃんが楽しそうに演じているのが何より。
本多劇場という箱もベストだし、満足でした。
次はもう少しじっくり見られるようなお芝居希望です。