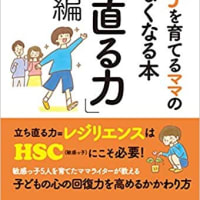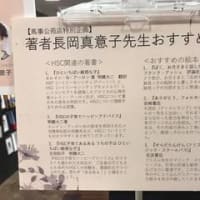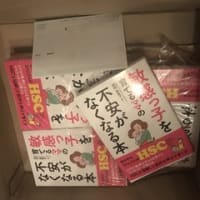ハイリーセンシティブな個性というのは、
ヒト以外の動物にも見られると分かっているそうです。
確かに、犬や猫や馬にも、個性がありますよね。
同じ状況に置かれても、反応が違ったりする。
そうした個性の中に、周りの刺激により敏感に反応する
「ハイリーセンシティブな個体」があるというんですね。
獣医と「間接炎」について話していたときに、
「犬によって痛みへの耐性が違うんですよ、
全然気にしない犬もいますし、
少しでもキャインとなる犬もいるんです」
と言っていたのを思い出します。
我が家の犬も、痛みや見知らぬ人などに対して、
センシティブなところがあるかも。(笑)
そこで、
「ハイリーセンシティブなサル」を扱った研究に興味深いものがあります。
(『Higly Sensitive Child』 by Elaine N Aronより)
「高反応なサル=ハイリーセンシティブなサル」の何頭かを、
1.穏やかで落ちついた母親ザル
2.ナーバスな母親ザル
に育てられるよう割り当て追跡してみたところ、
1の穏やかな母親ザルに育てられたサルは、
2のナーバスな母親サルに育てられたサルより
「レジリエンス」を培い、
群れのリーダーになる場合もあったとのこと。
一方で、「高反応のサル=ハイリーセンシティブなサル」は、
「低反応のサル」より、
母親から引き離されたことを、
大人になってもより引きずる場合がはるかに多かったとのこと。
著者のアーロン氏は、HSCというのは、
母親から引き離されるといった劇的な出来事だけでなく、
「世話してくれる人(caregiver)」の「心ここにあらず(mentally absent)」
だったりといった「心の状態」にもより影響を受けやすいとしています。
「心ここにあらず」とは、
いざと言うときに頼れなかったり、
うつやストレスを溜め込んでいたり、
過度に心配していたりといった状態とのこと。
例えば、ミネソタ大学の心理学者の研究でも、
「ハイリーセンシティブ」な乳児を30分間、
1.心のこもった(attentive)世話人
2.心ここにあらず(inattentive)の世話人
と共に過ごさせ様子をみたところ、
HSCの子の方が、世話する人の状態に、
より大きな影響を受けたといいます。
「HSCは、いざという時に頼れる人がそばにいるというだけでなく、
そばにいる人のサポートの度合いにも敏感なんです」
とアーロン氏は結論付けています。
HSCらしき子をもつ親としては、
ちょっとプレッシャーも高まりますが、
こうして縁あり親子となった以上、
まあたとえ完璧からは遠くても、
できることをしていく、それだけですよね。
ココロヲコメテ!とがちがちになる必要もなく、
5分でも3分でも、
ゆったりと子供と過ごすのを楽しむ時を、
心がけてみる。
それだけでも、随分と違ってきます。
肩の力を抜いて、お互い、できることをしていきましょう!