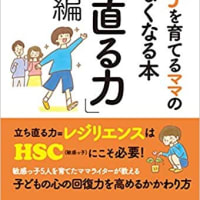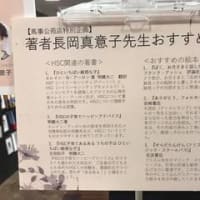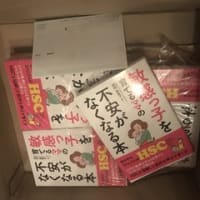「気質」について、
・子供&自分の気質を理解するために覚えておきたい「9つの要素」、一般&HSCの観点から
・「子供には『3つの気質類型』がある」という研究、養育者自らがその子に期待することを見直す大切さ
とみてきました。
ところで、
この「気質」研究を続けられてきた精神科医トーマス&チェス夫妻ですが、
ご自身の4人のお子さんについて、
「同じ家庭で同じような環境に育ちながらも、
どうしてひとりひとりこうも違うのだろう?」
という疑問を持ったことから、
これらの「気質」研究を始めたそうです。
私自身5人育てていて、よーく分かります。
それぞれホントに、違いますから。
その子その子に向き合いつつ、
向き合い方を見直していく大切さ、
身近な家庭から、日々実感しています。
では、異なる「気質」を理解しつつ、
目の前の子にどう向き合っていったらいいのか?
精神科医トーマス&チェス夫妻の研究を参考に、
1.外界に慣れにくい子、養育者にとって扱いにくい子(THE DIFFICULT CHILD):10%
2.外界にゆっくりと慣れる子、養育者にとって時間のかかる子(THE SLOW-TO-WARM-UP):15%
3.外界に慣れやすい子、養育者にとって扱いやすい子(THE EASY CHILD):40%
の順に、少し具体的にみていきましょう。
1.外界に慣れにくい子、養育者にとって扱いにくい子
就寝食事時間の不定期さ、家庭のルールに慣れるのに時間がかかるなど、「扱い方」の問題は初期から現れるといいます。そして、世話をする人が、「一貫せず、忍耐強くなく、懲罰的だったりすると、子供は他の子よりも一層ネガティブに反応する」とされています。
「子供の気質を完全に理解した際立った客観性、一貫した扱いのみが、その子が他者と容易に仲良くなり、適切な行為を学ぶことを可能にします。これには、長く時間がかかるかもしれません」とのこと。
これまで接した子の中にもまさしく!と思う子達がいましたが、「(家庭では)難しい子タイプ」が我が家にもいます。
とにかく、こうと決めたらこう!と「やり抜く力」や意志が強いです。「あ、オッケーな場合もあるんだ」と分かると、そこを突破口にどんどん境界を越えようとしますから、「一貫した姿勢」がより大切になってきます。大声で泣きわめいて癇癪を起したり、分かりやすい「強烈な反応」をすることも多く、こちらもつられてどっかーんと爆発してしまったり、いい聞かせても「やり抜こう」とするため、こちらも「怒りのボタン」を押されっぱなしだったり。
このタイプの子は本当に、養育者の忍耐を鍛えてくれます。罰を用いるとしても、より重いものへとエスカレートせざるをえなくなっていくだけですから、「予防」(環境を整える、いい時に話し合う、温もりのある信頼関係を築く)に力を注ぎ、できたときにはしっかりとこまめに認めてやります。
トーマス&チェス夫妻によるヒント:
・取り組んでいることを邪魔され気がそれるのを好まない「やり抜く力の強い子」は、呼ばれてすぐに走り寄ることを期待されるべきではありません。呼ばれる前にあと何分あるかを前もって知らせてやるんです。
順応性のある子は、コンセントにモノを突っ込んでいるのを見つけた際でも、いかに危険かを一度教えれば、二度とすることがないでしょう。それでも「やり抜く力の強い子」は、ほかの活動へと気をそらしたり、危険から物理的に引き離す必要があるかもしれません。
・”活動レベルの高い子は、例えば、8時間の自動車の旅にずっとじっと座っていることを求められるべきではないんです。頻繁にストップし、走り回り彼のエネルギーの通りをよくすることを許されるべきです。
また教室でも、鉛筆やほかのモノで遊んだり、隣の生徒との活動に巻き添えになったりと、絶え間なくごそごそする生徒は、明らかに特別な扱い方を必要とします。もし教師が、その子は学びたくないのだと決めつけ、そのように扱うのならば、その子は、自分を愚かで好かれないと結論付け、より問題のある行動さえ起すようになるでしょう。教師は、「迷惑」や「邪魔」といった感情的な表現をなるべく避け、彼のエネルギーを建設的な方向へと向ける術を提供してやるのが最もいいのです。雑用に走らせたり、黒板をふかせたりなどです。”
私自身もチャレンジングな子達に接しつつ何度も実感したことです:
ごそごそ動いた方が学習効果アップ!ADHD・ギフテッド・舞踏家タイプの子
・”「難しい子」は、すぐにマスターできない学習課題に対しての、教師の消極的で、放任&無干渉的な態度に、ネガティブに反応します。教師には、忍耐が必要です。ルールを学ぶことに向き合い続け、新しいタスクに親しむことで、自信をもって取り組むことを達成していくために、長くかかるかもしれないません。”
・”放任・無干渉な扱いは、「やり抜く力が弱く、すぐに気がそれるような子」にとってもうまくいきません。このような子は、ほとんど要求されず、ほとんど達成を期待されないとするなら、うまくいきません。彼の能力を生かすよう、要求する必要もあります。”
無干渉と過干渉の間で、本人が自主的にやる気になれるような関わり方をしてやりたいです。タスクを細かく分け、小さな達成を積み重ねるなどの工夫を身につけさせてやりたいですね。
2.外界にゆっくりと慣れる子、養育者にとって時間のかかる子
これらの子が「成功する発達のカギは、その子が自身のペースで環境に順応するのを許すこと」といいます。「親や教師がこれらの子に新しい環境にも早く行動するよう圧力をかけるならば、彼らの持つ強烈さが彼らの引きこもる自然な傾向をより強烈にします」と。また一方、「彼らは新しい物事を試すための励ましと機会を必要としています」とのこと。
例えば、ボビーという子の例があげられています:
”彼の両親は、ボビーが新しい物事に参加することを励ますことがありませんでした。ボビーが気に入らないものがあれば、単にひっこめることで対応したんです。乳児期には、ボビーは新しい食物を拒否し、口から吐き出しましたが、すると両親は、彼の食事からその食材を除去しました。10歳になるまでに、ボビーは、ハンバーガーと、アップルソースと、半熟卵だけを食べるようになっていました。そして社会面でも一人。新しい人々や新しい要求にさらされるどんな活動もボビーにとって不可能となりました。それでも、彼は彼自身のスピードで追及できるアクティビティーには喜びを見出し取り組みました。”
無理をさせ過ぎる圧力は、ネガティブに働きますが、無理させ過ぎない少しの無理をさせる励ましや機会やプッシュは必要なんですね。この「ややこしさ」、私自身もう何度もうなずきたくなるほど実感しています。
(今夏の水泳レッスンでの次男の様子や、プールサイドで出合ったさまざまな「気質」について、次の記事をまとめ中です)
また敏感な子の場合、親も子供の感情の動きに敏感だったりして、子供がネガティブな感情を示すことは避けたいとすぐに引っ込めてしまうこともあるだろうなと、私自身を振り返っても思います。
目の前のしかめつらや泣きべそも、「過程」だと捉えること。いつも笑ってハッピーでなくてもいいんですよね。ただ、笑ってハッピーであるといった状態が、「軸」にあってくれたら、その「軸」を築いていけたらな、私自身、そう思っています。
「無理過ぎないちょうどよい加減の少しの無理」、この加減が分かるのが、身近な親か、優れた教育者なのでしょうね。
トーマス&チェス夫妻によるヒント:
・”高い順応性のある子は、新しい食べ物を抵抗なく受け入れ、むしろ喜びさえすると期待されることもできます。一方、順応性に乏しく、(外&内に向かって)強烈な反応を示す子の場合、何日間かかけ、それぞれの食事で提供されることにより、慣れるようになっていくでしょう。もし子供に拒否された食材をひっこめ、それでも何週間後に再び試し、また抵抗にあい引っ込め、と繰り返すならば、子供は、単に十分だだをこねるなら、自分のやり方を貫けるのだと学ぶでしょう。”
・”学習面でも、「ゆっくり慣れる子」は、忍耐と、励ましと、繰り返し学習タスクにさらされることを必要とするかもしれません。慣れることにより、より快く取り組み達成することができるようになります。”
これは例えば我が家の場合、博物館や水族館などを訪ねつつ実感しています。初めて訪ねた時は、何かを学ぶというよりは、とにかくその場に圧倒されっぱなし。数度訪ねてから、少しずつ展示物の詳細に目がいくようになっていきます。
3.外界に慣れやすい子、養育者にとって扱いやすい子
極端に手を焼くというほどではないかもしれませんが、時に養育者にとって「難しいな」とか「困ったー」と感じる、その子の「~気質より」というものはあるでしょう。遊びを中断されると癇癪を起こす場合は、前もって残り時間を知らせるなどの工夫をしたり、「気がそれやすい」と感じる場合は、目標を小分けにしてみたり、必要なことに取り組むのを拒否する場合など、慣れるのにより時間をかけてやったりと、その子の示す「傾向」に合わせ、「難しい子」や「ゆっくり慣れる子」に接する際の注意点を適用していきたいです。
また「扱いやすい子」が、自主性や、自らの欲求や感情を引っ込め続けたまま「扱いやすく」なっていやしないかを見てやりたいです。敏感な子は、周りの要求も敏感に感じ取ります。本人が、どう思うか、どう感じているかなど、表現したり選択する機会を与えてやりたいです。
特に、「慣れにくい子」や「慣れるのに時間がかかる子」の場合、不可欠なのは、「通常以上にこの子の扱いには手がかかるだろうと自覚すること」といいます。周りの比較的大多数(40%)の「扱いやすい子」にうまくいくやり方でも、この子にはうまくいかないかもしれないと腹を据えてしまうこと。私自身、そう開き直ることで、随分と気持ちが楽になりました。
決まったことを決まった期間に皆で一斉にこなしていかなくてはならない学校などの集団の場合、子供のひとりひとりに注意を向けられなかったり、ひとりひとりのニーズに合わせたカリキュラムを組み込むスペースがないのが問題なんですよね。先生の仕事量も半端ではなく、物理的な時間や気持ち的余裕を持つのが難しいこともあるでしょう。
異なる気質を持つ子供たちのニーズが満たされる場が整えられていくことを願いつつ。
新居暮らし3日目。
あれやこれや詰めて閉めたダンボールを開け、
あれやこれや取り出し生活を整えつつ。
今日はこれから小中高の手続きに走り回ります!
皆さんよい日を!