
少数精鋭によって質の高さを誇るのは、誰にでもできます。
難しいのは、規模を拡大して、かつ、質的高さを維持することです。
企業は、単に質の高さを誇るのではなく、規模を拡大しながら、質の維持を図ることが大切です。
Being proud of quality is just an excuse of being unable to increase quantity.
Boasting a high quality by a small number of people, anyone can do it.
The difficult thing is to expand the scale and maintain qualitative height.
Companies are not simply boasting of high quality but it is important to maintain quality while expanding scale.










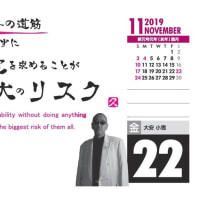
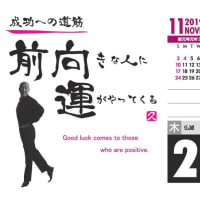
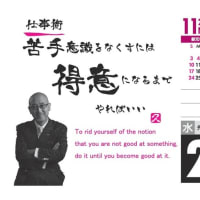
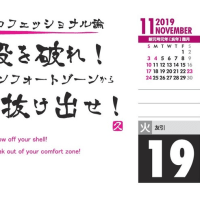
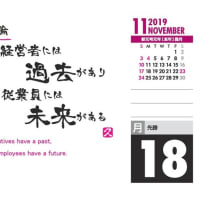
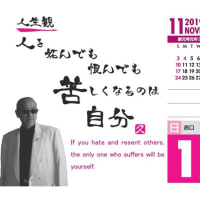
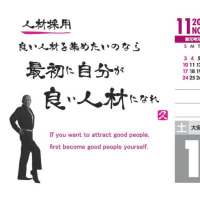
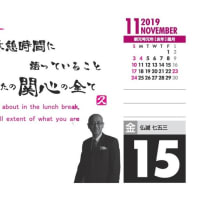
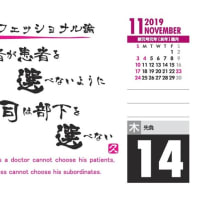
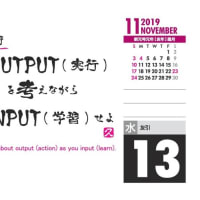
there is a mission to spread it.
そこで組織の標準化やシステム化が必要となる
ある程度の規模になるとそのような仕組みづくりをしていかなければクオリティを維持することができなくなってしまう
So be himself go with the aim of the next stage, we think that it may be for the sake of customers.
質の良いサービス、組織、仕組づくりができているのであれば、拡大に向け、進むことです。
小さくとどまっている必要はありません。
意見すると反する考え方ですが、両方を追求することが他社との差別化にもつながります。
orではなく、andの考えが大切です。
ただ、本当にそうでしょうか。
それは業務プロセスが確立されていない時期の発想です。拡大しても、業務プロセスを変えず忠実に業務を行えば、質は低下するのではなく向上します。人が多くなり、様々な視点が入ることで、質はでさらに向上していきます。
業務プロセスを守り、拡大するべきです。
自分の提供するものに価値を感じているのであれば質の維持を保ちながら、組織の拡大を図るべきだと思います。
経営者一人の力ではなく、
仕組みによって組織全体で成果を上げられるようにすることは、大変難しく根気のいることなのだと思います。
その苦労をしてまで、
より多くの価値を提供したいという強い気持ちがあるかどうかです。
It is important for us to ask for both quality and quantity however all most people are liable to lost either. When we drive the car, if we suddenly accelerate, we can not control it like bisons.
It's conclusion that we have to require the balance quality and quantity which we can control.
Keeping quality and increase quality is very important. Who has density of knowledge anything can do easily. Company is observing employee’s quality, but it is important to maintain quality by individual for every stage.
数あるうちの1社になるのか、業界や世の中全体をけん引する存在になるのか。
この志を他の誰でもなく自ら持とうとすることが重要なのだと思います。
質を上げれば、量を制約する。
業務の正確性の担保とスピードの維持。
廉価多売とブランド戦略。などなど。
こういうときはどちらかを取るという選択をするのではなく、どちらも達成するためにはどうするかを考えるべきだ。
or条件のどちらかを選択し、達成する目標設定よりかは、and条件でどちらも達成しようとする目標設定に限り、イノベーションは訪れる。
そもそも組織を作るのは、一人でできないことをみんなでやることで、質量ともに向上させていくことが目的です。どちらか一方に偏った時点で敗北なのだと思います。
二兎を得てうまくいく、
…
通常は、そんないい話無いよ、
と考えるのかもしれません。
しかし、
無いと誰が決めたのでしょうか。
本当にないのでしょうか。
世の中には
やる前からあきらめる言葉が沢山あふれています。
そして、出来ない理由を求めてしまいます。
大切なのは
どう乗り越えていくかです。
限界は自分で決めていることに
早く気付くことが成功の近道なのかもしれません。
量的な拡大に伴い必要となるのがリーダーです。組織の根幹にある方向性や価値を共有を伴わない量の拡大は組織としての質の低下になりかねません。
人材育成ができていないが故に特定の少数に頼らざるを得なず、量的な拡大が見込めないのだと思います。
品質が高いのに会社の規模を大きく出来ないなら、その会社は教育者が不足した会社です。
長期の存続は不可能です。
真の教育者がいる会社は品質を落とさずに規模を拡大出来る。それは単に良い社員を増やすだけでなく、第2第3の経営者を育て、第2第3の教育者を育てるからです。
しかし、真の教育者に頼りきりになってしまうと、次世代が育つ前にその教育者を欠いた時に組織は総崩れになってしまいます。
なので、特定の人に頼りきることの無い人材教育の仕組み作りが出来ているかが会社の寿命を決めます。
どちらを優先するかは、自由だが、拡大してから質をあげるのは非常にむずかしい。
急拡大しないように注意。
Though it is difficult things, but for existence of the company it is necessary to expand the scale and maintain qualitative height.
But when company expand his scale, that time it is difficult to maintain quality.
Those who are able to rise their quality and quantity similarly and
In the same time, they will exist in the present competitive market
両者は全国展開していながら、何百人といるスタッフの誰に当たっても、質の高いサービスを均一に受けることができ、そのレベルは顧客に感動を与えるレベルです。
徹底したマニュアル化と、研修制度、厳しい検定試験の存在によって、それが実現可能となっていると思いますが、つまり仕組化と共にすべきことは、いかに『真の教育者』の数を増やしていくかだと思います。
市場の変化や需要に対応しきてれはいない。
量的な面を拡大しつつ、質を高めることが誇れるべきことである。
なので自ら次のステージを目指していくことは、顧客のためにも良いことと思います。
注意したいことは、あまりにも急ぎすぎると土台から崩れてしまうので、計画を立て、報連相がしっかりできる関係づくりが大切です。
会社として、謙虚に規模と質を追求し続けること。そのプロセスこそが誇るべき対象なのだと考えています。
「うちの事務所は、税理士の資格者のみを採用している。
だから質が高い。顧客に満足してもらえる。」
「人数は少ないが、少数精鋭。
だから安心して我々に仕事を任せてください。」
そうやって見せれば、一定数の顧客層には響き顧客が増える。
そして、仕事量が一杯になり、人を増やそうと思うが
そんなに簡単には増やせない。
なので仕事量を調整する。顧客を絞る。
顧客を絞れば、当然拡大はしていかない。
拡大しなければ、やがて社員は新たな機会(チャンス)を
求めて、他へ旅立つか、自分で独立する。
新しい社員を雇おうにも、何で惹きつけるのか。
高い報酬なのか、新たな経験や機会なのか。
どんな組織でも、新たに人が雇えなければ、必ず
時間とともに衰退していく。
拡大がなければ、新たな機会を生み出していくことができない。
なので、将来ではなく、今あるものをどれだけ良く
見せるかを考える。
それでしか、生き残っていくことができない。
何をもって世の中に存在意義を打ち出すか。
目の前の顧客を助けるのか。より多くの企業を助けるのか。
ここに、経営トップの価値観が現れる。
あとは、それを完コピすればいい。
有能な何人もの人材を求めるから
うまくいかない。
それを拡げる使命がある。
ただし、自分以上の人材を雇いいれることができたとしたら、その限りではありません。
そんなミッションを持ったとき、少数精鋭では限界があります。
コンセプチュアルスキルで高い価値を創造し、ヒューマンスキルで人を巻き込み、テクニカルスキルで具体的な形を作っていく。
戦略づくりと人づくり。
この両方ができれば、少数精鋭という言い訳は出てこないはず。
そこで必要なのが仕組化だと思います。
同じ労力を投下しなくても実績を上げる仕組化です。
組織の拡大においても質を低下させない仕組み作りが必要ですし、コンサルティングファームにとって売り上げ(価値提供)の仕組化は最重要課題です。