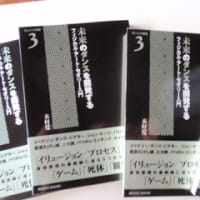若いダンサー(ソロ、グループ、演劇系も含む)8組が、20分の作品を披露、キュレイターは桜井圭介。STスポットが主催するこの「ラボ20」という企画は、以前から新しい魅力的なダンサーが生まれるコンテンポラリー・ダンスの登竜門的存在であり続けている。それだけに、不作の回や低調の回に出くわすと、単にこの企画がと言うよりもダンスの世界がもう行き詰まりを見せているのではと切ない気持ちにさせられてしまう。小さいが実際はかなり重要な意義を担っているラボ、今回は、ぼくとしてはずいぶん面白かった。へんちくりんなの(おかしな言葉だけどこうとしか言いようがないので)が見られたからだ。
「へんちくりん」というのは、企みとしてやろうとすればするほど「企み」の作為性がちらつき、作為する賢明さにおいて「普通」だと思わされてしまう。だからといって、天然の「へんちくりん」は希有だし舞台にあげられると途端におとなしくなりがちだ。「へんちくりん」を舞台にあげるには、だからすごく難しい。どこまで自分を意識しつつ無視するか、どこまで自分から自由になりつつなお自分にこだわるか、が重要になってくる。
全く未知数ではあるけれども、外山晴菜のパフォーマンス(「ハテノシノナイ」)はこの点でまことに「へんちくりん」だった。薄茶色のタンクトップの肩あたりに赤い布きれを巻き付ける妙なセンスから、そのことに早く気づけば良かった。淡泊なルックスでダンサー体型と言うよりは、普通の大学生の雰囲気。こちらからはまったくその必然性が理解できない頻繁に切り替わる曲とかもそうなんだけれど、ともかく次々と動いてしまう、それがどんな意味で置かれているのかなどこちらに察知させる前に次の何かが始まってしまう。だから一見中途半端に見えるし、実際動きの質は高くないからヘタとも言えるのだけれど、そうした基準でははかれない暴走のおかしさがいつまでもとぎれない。メルヘンチックともなんともとれないイメージがとぎれなく、多動症的にしかも殆ど反復なしに繰り出されていく。これは確信犯、いや単にビギナーズなんとか?世間は騒音おばさんとか片づけられないひととか「特異点」のひとについついひかれてしまうけれど、まさにそんな「へん」なパフォーマンス。でも、彼女の作品プロフィールには「みんなで楽しめる自分だけの世界」を目指すとある。確かにそうなっていた。こんなぐちゃぐちゃのぐにゃぐにゃをそのまま舞台に上げるダンサーに、批評性の欠如を指摘するむきもあるかもしれない、けれどもはやこれは批評以後のダンスなのかも知れないし、批評の形式自体が批評されていると思わされもするのだった。
外山のへんちくりんに比べれば、他の作品はみなおとなしく「へん」へと突き進む。「おとなしく」とは適度に頭をつかっているということ(外山さんが頭使ってないと言うことはないと思うんだけれど、っていうかそこがその難しいところで)。梶本はるか(「ひとまず、こしらえる」)は、冒頭吉野家の牛丼を一気に一杯食べ、そのたぷんとしたおなかで烈しくミニマルなダンスをし続ける。ぼくはなるべく余計なコトしないところに好感をもった。牛丼は受け狙いというより牛丼の入ったおなかによって踊るからだの存在を意識させる狙いだったろうし、その狙いはそこそこ成功したと思う。最後はあらためて牛丼を持ち込んで食べ始めたところで暗転、というやはりミニマルというか反復を意識させる終わりで、これも的確だった。ちょっと思ったのは、テンポのあるロックな曲をバックに烈しく踊るのは若さゆえのことではあろう、けれど、その「若さ」をこんなにシンプルに表現していいものか。その若さのイメージに抗ってもいいのでは。いや、若いからだが勝手にやってしまうことなのかも知れない、そうなのかな。
「若さ」ということだと、関かおり(「あたまにあ」)は、狂気に傾倒する系の「若さ」のダンスだった。小さく人型に切ったスイカの山盛りをミキサーにかけ、それを飲む、飲むと烈しく踊りだし、音がやむと放心し、最後に黒い液体を放尿する。踊りは烈しく、また痙攣のインパクトも強いし見応えがある。途中のがに股でひょこひょこ動くところなんかも、別の狂気の色が現れた感じでヒット。ただし、一連の流れは、実にベタだ。ドラッグをきめるとこんなになってしまいました、という感じ。このストーリーは、ミキサーが舞台前方に透明カップと共に置かれた瞬間に(少なくとも赤い皿を観客に披露した瞬間に)大体見えてしまう。だから問題は、この伝えてしまったストーリーをどう回避するか、迂回するか、反抗するか、あるいはそこに何かしらの新しい共犯関係を創り出すか、だ。と思っていると、案外素直にミキサーのボタンを押してしまうし、案外まじめに赤いジュースを飲んでしまう。「このジュースを飲むことは実にすごいことなんだ」というのが、ダンサーが観客に説得したい観念(イメージ)だろう、けれども、いわばそこで起きているのは演劇的な事態であって、それを実際にスゲーと思う前にそう思ってくれというダンサー側の説得の押しに、見る方の腰はむしろ引けてしまうのだ。ぼくは、ジュースを手にした時「飲むな!」と心で祈った。ミキサーにスイカが満タンになった時「スイッチ押すな!」と思った。飲むか飲まないか、押すか押さないか、の間にこそダンスがある。物語にのるかそるか、という境に。そこが案外あっさりだった、残念。
市川瑠璃子(「ラクリモサ」)は、冒頭、サングラスをかけた市川が正面を向いて立っているところからはじまる。なんとこう無邪気に客の正面に立ってしまうことか、と思いつつ、その他人をあまり気にしない感じっていまの大学生あたりに共通の風情だよなと納得しているとばたっと寝そべった。姿勢の悪い猫背な背中がだらしなくたおれる。かなりふくよかな体躯と相まって、サングラスをかけ、ギリシア風ないまどきのワンピ姿の一見お嬢様系ないでたちがほんとにそぐわないことにいらだちとおかしさを覚える。かっこつけているが実際はかっこわるいことに対してどのような自意識をもっているのかが判然としない。わざと「かっこつける=かっこわるい」風に見せようとしているのか、ただかっこつけているのか。ナルシスなのかクリティカルなのか、メタかベタか。まあ、そもそもふっくらしすぎなのだ。はみ出てしまうのだ。狙いがそっぽを向く体型なのだ。このいかにもいまどきの若い女の子らしいふっくらとしたからだが舞台でふらふらしていることに、ある種のリアリティを感じるってとこか。
佐藤想子(「ミントとウォルター」)は、メルヘンな女の子の部屋の適度な妄想のお時間。途中で30秒ほど踊った。それがなんともいえず独自な情緒から生まれている気がして、なんらテク的にもセンス的にもハイではないのだけれど、定型におさめようとしない等身大を感じた。大学のゼミで、学生が独り言のように自分の意見をぼそぼそ話す時のようだ。伝える力が足りなくて相手の手前で落ちる。けれども、それは伝わらないからダメなんじゃなくて、伝わらない距離を感じさせられる点でひとつの表現になりうる(その点では岡本真理子を想起させる)。あとは、そういうことに本人がどれだけ自覚的か、なのだが。
桑野由起子+中島由美子=(「消化ハーフ」)は、長いひもを用意して二人で大きなあやとりをする。ひもで互いを感じ合う、コンセプトはそういうことだろう、そこそこ面白い。ただ、コンセプトが重要なのではなくて、そこで起きる動作のいちいちであるはずで、そこが案外淡泊なのだった。
小指値(「i wanna be a machine, but...」)は五人組で演劇的な作品。つまり、ある女性の人生を代わる代わる語っていく。設定はそれで、語るというシンプルな所作の周りの空っぽの空間を、五人の大げさなポーズが埋めていく。言葉と体の関係のズレというか、無意味な並置が見所なのかも知れないが、あまり心動かされず。
ひろいようこ&橋本正彦(「状態系「ハイパーオセロー」」)を見るのは、ぼくは4回目。さすがに見慣れてしまったか、あるいはやっている側にも慣れがあったのか、ひとつひとつの所作がどんどん流れていってしまう。オセロをする男と女、男は寡黙ただ盤を見つめる。女は体がしだいに揺れはじめ、どんどん余計なことをしてしまう。バナナをちぎっては盤の上に置いたり、開脚してお尻を男に向けたり、スカートにあるチャックを激しく上下動させたり。
新しい感触を得た。この新しさは反感とか拒否をともなうものだろうし、拙さや未熟さを指摘されるものでもあると思う。でも、わがままに自分のやりたいことを見せている気がしたのだ。野放図な身体、ぶっきらぼうな身体のリアリティ。それがすべきことはし、すべきでないことはしないミニマルなパフォーマンス(であろうとしたこと、上記したようにかならずしも貫徹できたとは思えないけれど)によってあらわれた。このひとたちの次回作は見られるのだろうか。すべての人に対して次回作が見たいと思った。
「へんちくりん」というのは、企みとしてやろうとすればするほど「企み」の作為性がちらつき、作為する賢明さにおいて「普通」だと思わされてしまう。だからといって、天然の「へんちくりん」は希有だし舞台にあげられると途端におとなしくなりがちだ。「へんちくりん」を舞台にあげるには、だからすごく難しい。どこまで自分を意識しつつ無視するか、どこまで自分から自由になりつつなお自分にこだわるか、が重要になってくる。
全く未知数ではあるけれども、外山晴菜のパフォーマンス(「ハテノシノナイ」)はこの点でまことに「へんちくりん」だった。薄茶色のタンクトップの肩あたりに赤い布きれを巻き付ける妙なセンスから、そのことに早く気づけば良かった。淡泊なルックスでダンサー体型と言うよりは、普通の大学生の雰囲気。こちらからはまったくその必然性が理解できない頻繁に切り替わる曲とかもそうなんだけれど、ともかく次々と動いてしまう、それがどんな意味で置かれているのかなどこちらに察知させる前に次の何かが始まってしまう。だから一見中途半端に見えるし、実際動きの質は高くないからヘタとも言えるのだけれど、そうした基準でははかれない暴走のおかしさがいつまでもとぎれない。メルヘンチックともなんともとれないイメージがとぎれなく、多動症的にしかも殆ど反復なしに繰り出されていく。これは確信犯、いや単にビギナーズなんとか?世間は騒音おばさんとか片づけられないひととか「特異点」のひとについついひかれてしまうけれど、まさにそんな「へん」なパフォーマンス。でも、彼女の作品プロフィールには「みんなで楽しめる自分だけの世界」を目指すとある。確かにそうなっていた。こんなぐちゃぐちゃのぐにゃぐにゃをそのまま舞台に上げるダンサーに、批評性の欠如を指摘するむきもあるかもしれない、けれどもはやこれは批評以後のダンスなのかも知れないし、批評の形式自体が批評されていると思わされもするのだった。
外山のへんちくりんに比べれば、他の作品はみなおとなしく「へん」へと突き進む。「おとなしく」とは適度に頭をつかっているということ(外山さんが頭使ってないと言うことはないと思うんだけれど、っていうかそこがその難しいところで)。梶本はるか(「ひとまず、こしらえる」)は、冒頭吉野家の牛丼を一気に一杯食べ、そのたぷんとしたおなかで烈しくミニマルなダンスをし続ける。ぼくはなるべく余計なコトしないところに好感をもった。牛丼は受け狙いというより牛丼の入ったおなかによって踊るからだの存在を意識させる狙いだったろうし、その狙いはそこそこ成功したと思う。最後はあらためて牛丼を持ち込んで食べ始めたところで暗転、というやはりミニマルというか反復を意識させる終わりで、これも的確だった。ちょっと思ったのは、テンポのあるロックな曲をバックに烈しく踊るのは若さゆえのことではあろう、けれど、その「若さ」をこんなにシンプルに表現していいものか。その若さのイメージに抗ってもいいのでは。いや、若いからだが勝手にやってしまうことなのかも知れない、そうなのかな。
「若さ」ということだと、関かおり(「あたまにあ」)は、狂気に傾倒する系の「若さ」のダンスだった。小さく人型に切ったスイカの山盛りをミキサーにかけ、それを飲む、飲むと烈しく踊りだし、音がやむと放心し、最後に黒い液体を放尿する。踊りは烈しく、また痙攣のインパクトも強いし見応えがある。途中のがに股でひょこひょこ動くところなんかも、別の狂気の色が現れた感じでヒット。ただし、一連の流れは、実にベタだ。ドラッグをきめるとこんなになってしまいました、という感じ。このストーリーは、ミキサーが舞台前方に透明カップと共に置かれた瞬間に(少なくとも赤い皿を観客に披露した瞬間に)大体見えてしまう。だから問題は、この伝えてしまったストーリーをどう回避するか、迂回するか、反抗するか、あるいはそこに何かしらの新しい共犯関係を創り出すか、だ。と思っていると、案外素直にミキサーのボタンを押してしまうし、案外まじめに赤いジュースを飲んでしまう。「このジュースを飲むことは実にすごいことなんだ」というのが、ダンサーが観客に説得したい観念(イメージ)だろう、けれども、いわばそこで起きているのは演劇的な事態であって、それを実際にスゲーと思う前にそう思ってくれというダンサー側の説得の押しに、見る方の腰はむしろ引けてしまうのだ。ぼくは、ジュースを手にした時「飲むな!」と心で祈った。ミキサーにスイカが満タンになった時「スイッチ押すな!」と思った。飲むか飲まないか、押すか押さないか、の間にこそダンスがある。物語にのるかそるか、という境に。そこが案外あっさりだった、残念。
市川瑠璃子(「ラクリモサ」)は、冒頭、サングラスをかけた市川が正面を向いて立っているところからはじまる。なんとこう無邪気に客の正面に立ってしまうことか、と思いつつ、その他人をあまり気にしない感じっていまの大学生あたりに共通の風情だよなと納得しているとばたっと寝そべった。姿勢の悪い猫背な背中がだらしなくたおれる。かなりふくよかな体躯と相まって、サングラスをかけ、ギリシア風ないまどきのワンピ姿の一見お嬢様系ないでたちがほんとにそぐわないことにいらだちとおかしさを覚える。かっこつけているが実際はかっこわるいことに対してどのような自意識をもっているのかが判然としない。わざと「かっこつける=かっこわるい」風に見せようとしているのか、ただかっこつけているのか。ナルシスなのかクリティカルなのか、メタかベタか。まあ、そもそもふっくらしすぎなのだ。はみ出てしまうのだ。狙いがそっぽを向く体型なのだ。このいかにもいまどきの若い女の子らしいふっくらとしたからだが舞台でふらふらしていることに、ある種のリアリティを感じるってとこか。
佐藤想子(「ミントとウォルター」)は、メルヘンな女の子の部屋の適度な妄想のお時間。途中で30秒ほど踊った。それがなんともいえず独自な情緒から生まれている気がして、なんらテク的にもセンス的にもハイではないのだけれど、定型におさめようとしない等身大を感じた。大学のゼミで、学生が独り言のように自分の意見をぼそぼそ話す時のようだ。伝える力が足りなくて相手の手前で落ちる。けれども、それは伝わらないからダメなんじゃなくて、伝わらない距離を感じさせられる点でひとつの表現になりうる(その点では岡本真理子を想起させる)。あとは、そういうことに本人がどれだけ自覚的か、なのだが。
桑野由起子+中島由美子=(「消化ハーフ」)は、長いひもを用意して二人で大きなあやとりをする。ひもで互いを感じ合う、コンセプトはそういうことだろう、そこそこ面白い。ただ、コンセプトが重要なのではなくて、そこで起きる動作のいちいちであるはずで、そこが案外淡泊なのだった。
小指値(「i wanna be a machine, but...」)は五人組で演劇的な作品。つまり、ある女性の人生を代わる代わる語っていく。設定はそれで、語るというシンプルな所作の周りの空っぽの空間を、五人の大げさなポーズが埋めていく。言葉と体の関係のズレというか、無意味な並置が見所なのかも知れないが、あまり心動かされず。
ひろいようこ&橋本正彦(「状態系「ハイパーオセロー」」)を見るのは、ぼくは4回目。さすがに見慣れてしまったか、あるいはやっている側にも慣れがあったのか、ひとつひとつの所作がどんどん流れていってしまう。オセロをする男と女、男は寡黙ただ盤を見つめる。女は体がしだいに揺れはじめ、どんどん余計なことをしてしまう。バナナをちぎっては盤の上に置いたり、開脚してお尻を男に向けたり、スカートにあるチャックを激しく上下動させたり。
新しい感触を得た。この新しさは反感とか拒否をともなうものだろうし、拙さや未熟さを指摘されるものでもあると思う。でも、わがままに自分のやりたいことを見せている気がしたのだ。野放図な身体、ぶっきらぼうな身体のリアリティ。それがすべきことはし、すべきでないことはしないミニマルなパフォーマンス(であろうとしたこと、上記したようにかならずしも貫徹できたとは思えないけれど)によってあらわれた。このひとたちの次回作は見られるのだろうか。すべての人に対して次回作が見たいと思った。