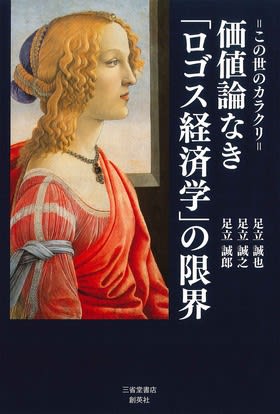
基本的な設問がある。
なぜ銀行業が衰退したのか? フィンテックに乗り遅れたから? いや、デジタル通貨への対応に手間取ったから? これらの答えはみな間違い。
なぜ中国は経済大国になれたか? 輸出ビジネスで世界の工場となったから? 人件費が安く、全体主義だから集中できたからか。いずれも誤答です。
この世にはカラクリ、とりわけ通貨の信用性への誤信という詐欺めいた仕掛けがあって、その謎がわかれば、新資本主義なるものの正体も解き明かせる。
著者は三兄弟。いずれも慶応大学に学び、ひとりは石油ビジネスで世界を駆けめぐり、ひとりは銀行マンとしてNY、北京、ジャカルタなどで経済実態を眺めてきた。もうひとりは商社マンとして世界を股にかけて飛び回った。
この三人の國際通が定年後、毎日曜に定期的に集まって、思う存分に討議し、結論を出した。それが本書に凝結された、ブレーンストーミングの結晶である。読んでみると表現は難しい箇所もあるが、世界経済の謎が展望台に立ったように見透けるのだから不思議である。
本書の要諦は以下の通りだろう。
「旧来の経済学はその前提を『価値と貨幣通貨を同一視すること』で成立してきた(中略)。ニクソンショックでドル兌換が廃止される頃から、その弊害が『肥大化』し、限界に陥った」。
すなわち「『貨幣通貨が価値を生むという価値創造機能貨幣説』の「価値」という概念を『天然価値』とすべきものを「人工価値」に「すり替える(同一視する)」ことから成り立っている」のである。(236p)
フェイスブック(その後『メタ』と改称)はデジタル通貨「リベラ」の発行準備を整えていたが、欧米諸国の中央銀行に反対されて、ついに頓挫、1月31日に正式に撤退を発表した。GAFAMのなかで、メタだけが株価を下げた。
デジタル通貨に対して主要各国の中央銀行が主権侵害を危惧したのも、中国が『世界の覇権を握るためにこの電子通貨体制をいちはやく構築しようとするだろうという警戒感・恐怖心』があったからだ。
「たとえばアメリカ国家にとっては、中国との基軸通貨の覇権争いのみならず、FB(フェイスブック)などのIT巨大企業や、ウォールストリートやロスチャイルド系の國際金融資本という民営銀行系とも覇権を争わねばならないという四つ巴の戦になる」(中略)「国際経済環境に地殻的変動をひきおこすことになる」
なぜか。
「アメリカの財政赤字も、融資という民間銀行の巨大な利権も消えてしまう」からだ。
したがって「国家が(通貨覇権競争で)優勢になるとすれば、この流れに並行して,MMT的経済構造を各国が採用するベクトルが強まる(中略)。MMTの構造自体が第一義的には国家単位で完結される構造になっていて平仄があうからです」(183−185p)
中国が強大になれたのは、ドルに手品師の如く便乗して肥ったからである。
「人民元を國際基軸通貨たるドルの『擬似ドル化(=同じにする。同一視させる)』させ、あたかもドルが中国の国内通貨であるように装うことで、ドルの有する価値を最大限利用してきました。この『擬似ドル=人民元』は潤沢に中国国内に行き渡り、天然価値を経由して人工価値を生み出した。つまり、中国共産党の裁量で実施できる人民元の増刷は、ドルの増刷を米国の許可無しで中国が実施しているようなもの」だからである。
人の土俵に上がり込んで餌を盗み取り、自分だけが肥る。それを相手が気がつかない。まさにシナ人の伝統、その「智嚢」ぶり!
カッコウは他人の巣に子供を産み、育てさせるという『特技』がある。カッコウの卵は仮親の卵より早くかえるので、カッコウのヒナは仮親の卵を落とし、育ての親が運んでくる餌を独り占めして成長する(中略)。ヒナが成長すると仮親より大きくなり、自分の姿とは違うのに仮親は献身的に餌を与え続ける」(196−197p)。
嗚呼、まさに日本の六兆円もの経済援助で中国はまるまる太り軍事大国となって日本を脅かしている。(カッコウは南方系の鳥で、日本の郭公はホトトギス。まったく違う)。
この手品を実現できたのは擬似ドルであり、アメリカがようやく気がついたのはトランプ前政権の時だった。
いやはや、カラクリが分かると、世界の奧底で蠢く国々や団体や個人の野心が見えてきた。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます