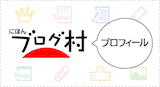朝の写真が日の出の時間に戻ってきた。
といっても、写真を撮る時間はほぼ同じで、夜明けが少し早まってきたわけで、私が生きて生活している地球と太陽との相対的な位置関係が変化した結果こうなっているというだけの話しだ。

自分のことを客観視するというのは難しい。
それはこうしてあれこれ考えていることからも明らかだ。
考えというのは、肉体が感じる快不快から始まって、頭で考える利益不利益などで、結局のところすべては自分の判断の範囲内。
今、こうして書いていることだって私という人間が思いついたことに過ぎない。
人間の行動はすべて主観的な思いから始まるのに、その結果が思い通りになることは滅多にない。
仮に、短期的な目標を立ててそれを達成したところで、その後アテが外れたなんてこともある。
がっかりしないためには、できる限り客観的に結末を予想しておくといいのだろうが、では、どこまで予想しておけばいいのかなど誰にもわからない。
客観的にみて一番はっきりしているのは、死ぬことだが、残念ながらそれがいつ来るのかよくわからないし、わかった時に自分が何をどう考えるかもわからない。
こうして考えてみると、父の死に様は見事だった。
仕事に打ち込み、多くの人の役に立っていたが、体調を少し崩したのち、最期は生きる気力を失って静かに旅立った。
犬のナイトもコロも、最期は生きようとする気力を失ってやすらかに旅立った。
人生で唯一明らかな結末は死ぬことだ。
自分というものが死にゆく存在であり、生きているのは死ぬためだと常に考えていられるようになれば落ち着いた毎日を送ることができるかもしれない。
生きることは怖いかもしれないが
応援よろしくお願いします