
日本橋三越劇場で、「寺垣武の発想」と題された、寺垣さんの製作した歴代プレーヤーの展示とトークショーが開催された。
午後と夜の部の二部構成で開かれ、私は夜の部に行った。
2,300人ほどの来場者の8割ほどが寺垣研究所を訪問したことがあると挙手していた。
世の中がデジタルに向かおうとした時代にアナログプレーヤーを作り始めた寺垣さん。
その動機は、レコードのカッティングマシンは針先に数百ワットのエネルギーを注ぎ込んで溝を掘っている、というたった一行の記事だった。
それほどのエネルギーを注ぎ込んで彫った100ミクロンほどの溝をトレースして音を再生するのに、どのレコードプレーヤーを見ても、とても再生できる構造はしていないと直感したのだ。
だったら作ってみようと。
レコードプレーヤーを作るのではない、レコードに刻まれた溝の微妙な凹凸を、正確に測定しようという表面粗さ計を作ろうとしたのだ。
とてつもない精密機械を作る挑戦が始まった。
しかしスピーカーによって音が違ってくることに気付き、原音を忠実に再生するスピーカを作る羽目になった。
その過程で物質波に思いが至った。
ヴァイオリンやチェロの音の出方、鈴虫やセミの音の出方は、今のスピーカーの音の出し方とは原理が違うことに気付き、物質波スピーカーも作った。
会場にいる人たちはみんな話は知っている。
寺垣節を心地よく聞いた。
写真は86歳の寺垣さんが注文生産を開始した帆型スピーカー。
50台ほど作る予定だそうだ。
午後と夜の部の二部構成で開かれ、私は夜の部に行った。
2,300人ほどの来場者の8割ほどが寺垣研究所を訪問したことがあると挙手していた。
世の中がデジタルに向かおうとした時代にアナログプレーヤーを作り始めた寺垣さん。
その動機は、レコードのカッティングマシンは針先に数百ワットのエネルギーを注ぎ込んで溝を掘っている、というたった一行の記事だった。
それほどのエネルギーを注ぎ込んで彫った100ミクロンほどの溝をトレースして音を再生するのに、どのレコードプレーヤーを見ても、とても再生できる構造はしていないと直感したのだ。
だったら作ってみようと。
レコードプレーヤーを作るのではない、レコードに刻まれた溝の微妙な凹凸を、正確に測定しようという表面粗さ計を作ろうとしたのだ。
とてつもない精密機械を作る挑戦が始まった。
しかしスピーカーによって音が違ってくることに気付き、原音を忠実に再生するスピーカを作る羽目になった。
その過程で物質波に思いが至った。
ヴァイオリンやチェロの音の出方、鈴虫やセミの音の出方は、今のスピーカーの音の出し方とは原理が違うことに気付き、物質波スピーカーも作った。
会場にいる人たちはみんな話は知っている。
寺垣節を心地よく聞いた。
写真は86歳の寺垣さんが注文生産を開始した帆型スピーカー。
50台ほど作る予定だそうだ。
















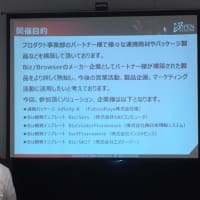



むしろ使ってくれたほうが喜びます。
そういう方です。
「人に向かわない技術は意味がない」が口癖です。人に向かう技術を考えるからどんどんまねして欲しいと言わんばかりです。
実際、寺垣さんはNEC、富士通、リコー、オーディオテクニカ、最近までキヤノンの生産技術顧問を歴任しています。
物造りのノウハウを伝授するのが本業でした。
たまたまレコードのカッティングに400Wのパワーを注ぎ込んでいるという記事を見たために、我々の知るところとなりましたが、そうでなければほんの一部の生産技術者だけが知るような人なのです。
私の早起きは歳のせいですね。
歳を取るというのはいいことです。
寝ている時間が少なくても苦になりません。
物理的には「弾性波」と思うのですが…
「弾性波」と説明する方がよいのではないでしょうか?
寺垣スピーカーの原理を応用すれば、薄型テレビの画面をスピーカーにする(二次元音源)とすることも可能と思います。(現在のスピーカーは0次元音源を組み合わせて2次元音場
を表現している)
これですね。
http://topicmaps.u-gakugei.ac.jp/phys/matsuura/lecture/general/presentation/ElasticWave/ElasticWave.files/frame.htm
これだと思います。
寺垣さんに伝えてみます。