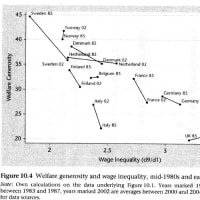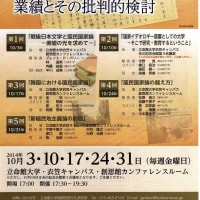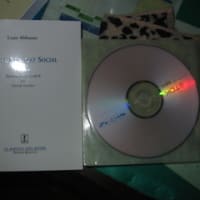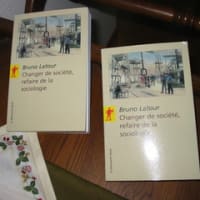現在ある必要があって、いわゆる百科全書のsociété、socialに関連した項目を読み直している。
18世紀の仏語なのだが、日本の辞典は総じて古い用語法の説明も網羅しているので、問題なく読める。
これと関連してだが、以下の本が日本語で読める。
日本における社会概念の変遷、また西欧のsocial概念の変遷を検討した著作であり、非常に参考になる。
ただ、発表媒体の問題もあると思うが、socialという語をそのまま日本の社会という語に置き換えてしまっているため、socialという語そのものの意味の変遷をあまり追っていないのが残念だが(などと偉そうなことを言える身では、私は全くないのだが……)
日本語で社会といった場合、現代的な意味でのsocial、societe概念を直接意味してしまう。これは、全体社会を前提とした概念であり、social概念の変遷を追うと、social概念、またsosiete概念が、かつては部分社会を意味していたことがわかる。
これは以前も書かせていただいたが(こちら)、ラテン語のsocietasは、現在の社会概念の語源とされているが、そこにはもろもろの変遷があった。societasは、当初、第一に同盟者によるassociationを指していた。ここでのsocietasという語は、現在で言うところの部分社会を指す概念であり、全体社会という観念自体(現在の社会概念はこれを指しているといえよう)が存在していなかった。
百科全書ではguerre socialeという項目がある。これはローマ時代の同盟市戦争のことで、guerre des alliesとも呼ばれている(ウィキペディアに同盟市戦争という項目があった。恐るべし)。ここでのsocialという語の用法などを考えると、social、societeという語が同盟者(allie)によるassociationに関連付けられていることがわかる。
私などは、近代的な意味での社会を指すときは日本語の「社会」を用い、必ずしも近代社会(主に全体社会)をいみするものではない時には、social,societe概念を用いれば、概念の変遷をかなり明確に記述できるのではないかと、考えてしまっている(安易な発想かもしれないが)。
ただ、欧米の言語でこれを表現しようとなると、骨が折れる作業になるだろうが……。
部分社会もsocietyだし、この用法は未だに現在にも残っている(societyという語は、学会、協会などを指す時にも用いられる)。と同時に、全体社会も同じsocietyという語で表される……。
18世紀の仏語なのだが、日本の辞典は総じて古い用語法の説明も網羅しているので、問題なく読める。
これと関連してだが、以下の本が日本語で読める。
 | 社会 (思考のフロンティア) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |
日本における社会概念の変遷、また西欧のsocial概念の変遷を検討した著作であり、非常に参考になる。
ただ、発表媒体の問題もあると思うが、socialという語をそのまま日本の社会という語に置き換えてしまっているため、socialという語そのものの意味の変遷をあまり追っていないのが残念だが(などと偉そうなことを言える身では、私は全くないのだが……)
日本語で社会といった場合、現代的な意味でのsocial、societe概念を直接意味してしまう。これは、全体社会を前提とした概念であり、social概念の変遷を追うと、social概念、またsosiete概念が、かつては部分社会を意味していたことがわかる。
これは以前も書かせていただいたが(こちら)、ラテン語のsocietasは、現在の社会概念の語源とされているが、そこにはもろもろの変遷があった。societasは、当初、第一に同盟者によるassociationを指していた。ここでのsocietasという語は、現在で言うところの部分社会を指す概念であり、全体社会という観念自体(現在の社会概念はこれを指しているといえよう)が存在していなかった。
百科全書ではguerre socialeという項目がある。これはローマ時代の同盟市戦争のことで、guerre des alliesとも呼ばれている(ウィキペディアに同盟市戦争という項目があった。恐るべし)。ここでのsocialという語の用法などを考えると、social、societeという語が同盟者(allie)によるassociationに関連付けられていることがわかる。
私などは、近代的な意味での社会を指すときは日本語の「社会」を用い、必ずしも近代社会(主に全体社会)をいみするものではない時には、social,societe概念を用いれば、概念の変遷をかなり明確に記述できるのではないかと、考えてしまっている(安易な発想かもしれないが)。
ただ、欧米の言語でこれを表現しようとなると、骨が折れる作業になるだろうが……。
部分社会もsocietyだし、この用法は未だに現在にも残っている(societyという語は、学会、協会などを指す時にも用いられる)。と同時に、全体社会も同じsocietyという語で表される……。