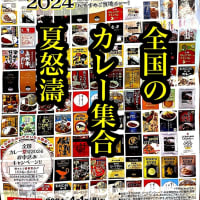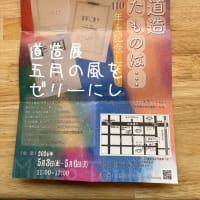「俳人風狂列伝」。角川選書。
この本を手に取ったのは、岡本癖三酔について取り上げられていたからである。
癖三酔は、大場白水郎の俳句の師である。白水郎についても若干の記述があるかもしれない。
大場白水郎に関する資料はいろいろ頂戴しているのに、その「研究」はちっとも進んでいない。
どこから手をつけようか。そんな気持ちもあった。
作者は、石川桂郎。石川桂郎は、杉田久女に入門して俳句を作り始め、石田波郷の「鶴」の同人である。
雑誌「俳句研究」の編集にも携わった。
ゆめにみる女はひとり星祭 桂郎
という句がある。
この本は、面識のある俳人を中心に、破滅型?の俳人のエピソードを描いたもので、読売文学賞を受賞している。
癖三酔は、慶応で、三田俳句会を組織し、そこから久保田万太郎や大場白水郎が育ったということである。
岡本癖三酔についての文の題は、「室咲きの葦」。
この題は、癖三酔が十五年もの間、神経衰弱と糖尿病のため自分の部屋から一歩も外に出なかったことに由来する。
昼間から雨戸を閉め切り、ルミナールを飲んで眠り、昼夜のない生活をしたと言う。好悪の感情が激しく、気に入ったものにはとことん惚れたらしい。
ある俳人の人物批評によると、癖三酔は「非常識的非常識」 に属するという。
ちなみに、癖三酔という名前に「酔」の字があるが、酒は一滴ものめなかったらしい。
エピソードはおもしろい。が興味のある人は直接この本を読むといい。
文中、白水郎の名前ができてきたのは1カ所だけだった。
癖三酔が溺愛した娘美津子が死んだとき、棺を追って白足袋のまま飛び出した癖三酔を羽交い締めにして止めた という部分である。癖三酔は、美津子のために小型トラック一杯の花を買い、墓を花で埋め尽くしたとある。
俳人にも奇人変人は多くいるものだ。
重症患者を装うため、他人の喀血を痰壺から飲み込む高橋鏡太郎、蟻の町に暮らした田尻得次郎。むろん尾崎放哉や山頭火にも筆が及んでいるが、前者のリアルさにはかなわない。
高橋鏡太郎の文の中に山岸外史が登場したのにはびっくりした。山岸は、一般には、評伝『人間太宰治』(昭和37年,筑摩書房)の著者として知られているひとであるが、四季派に連なる詩人でもあり、私も父小山正孝から幾度となくこの名前を聞いた。そして、中央公論社で正孝が最も親しくしていた佐野龍馬の奥さんが山岸の娘さんだということも聞いていた。なぜ、その山岸が俳人の高橋鏡太郎と縁があったのか。人間はどこでどうつながっているかわからないものだ。
俳句に関して、しなければならないことが多い。
中心は、日本学校俳句研究会の活動と学校俳句を極めること。第二は、自分の俳句を少しは見てくれのよいものにすること。三つ目が大場白水郎に関することだ。
今年もあと残すところ三百六十四日である。