先週、金・土の2日間、ジオパーク推進委員会と環境省の自然保護官事務所主催に依る勉強会が行われました。なかなか週末に時間を作る事ができない私は久々のフィールド参加です。
金曜日の夕方から開かれた講演会、始めに、ジオパーク推進委員でもある環境省の服部さんが“崩壊斜面のモニタリング調査”について
今までの経緯を解り易く解説してくれました。

調査目的や実際に設置されている観測機器の紹介の後、第1回~15回目までの植生の変化を画像で説明。
徐々に植物達が再生していく様子がとてもよく判り興味深かったです。
(この日の講演記録は撮っていません)
足場の悪い崩壊斜面に定期的に通い植物の変化や土壌の様子を事細かに記録していく
これは中々大変な事だなと思います。
しかし、この様な地道な活動によって様々な知見が積み重ねられ、次の災害にも役立つのですね。
何事も無く過ごせれば一番ですが、日本では地理的要因も有り必ず何処かで災害が起こります。
地震・噴火に台風・津波・土砂災害・・・被害が出なければただの自然の営みですが
そこで暮らしている以上、自然の仕組みを知る事は掛け替えのない命を守る為にとても大事です。
服部さんの仰っていた「地球活動の変化を学んで自然との共生を考える」まさにその通りだと思います。
続いて、東京農工大 大学院 石川先生のお話し

3年前に、予期せぬ台風26号による大雨で起きてしまった大災害ですが
出来るだけ速やかに安全を確保し、住民にとって不安の無い生活を取り戻さなければなりませんでした。
その為の取り組みに、色々アドバイスを頂いたのが石川先生との事です。
そんな先生からは、崩落斜面の新たな土砂流出を植生回復により防げる仕組み等をお話して頂きました。
傾斜地において、樹木の土壌安定に果たす役割はとても大きいそうです。
大島の土砂災害では、崩壊斜面を補強する為様々な工法を用いた大々的な土木工事も行われていますが、早い段階で植生の復活を促す為、皆さんご存知の様にヘリによる種子散布が行われました。
従来の植生が残っている場所、そして災害に依って一気に裸地と化してしまった場所。
何も無くなってしまった場所にプロットと呼ばれる囲いを作り、植生の変化と地面を流れる雨水や地中への浸透率などを調べ土壌侵食の軽減を目指しているとの事です。
続いて
ジオガイド養成講座でもお世話になっている上條先生のお話し

先生からお聞きする伊豆諸島の植物の話しは、ガイドの時にとても役立っています。
大島固有の植物やその変化に、興味を持つお客様が沢山いらっしゃるのです。
ツアー中の話題は火山や歴史等様々ですが、目に入る情報と結びつく植物に関してが最も多い様に思います。
今回も先生からは、島の植物達にどんな特徴があり、何故その様に変化してきたか?
島の固有種を守る為には、どの様な問題がありどんな対応が必要か等・・・
他の島々の状況なども交えながら貴重なお話しをして頂きました。
噴火によって大きな被害を受けた三宅島も泥流対策の緑化が推進されているとのですが、時間の関係で全てお聞きする事が出来なかったのが少し残念でした。
大島の崩壊斜面モニタリング調査からも様々な事が判り、植栽技術の開発や本来有る地域の植生を守りつつ回復に結び付けるシステムを考えていきたいとの事でした。
最後に京都大学の今西先生から“生物多様性とは何か?”“なぜ生物の多様化が望まれるのか?”についてお話しが有りました。この演目、実は環境省の服部さんからお願いされたとの事。
専門では無いと言いつつも、大変解り易く生物多様性とは何か?何故それが重要なのか等、説明して下さいました。

意外とこの言葉、言葉自体を知らない方や知っていてもその意味を答えられない方が多いのですね。
私自身も勝手に解釈していた部分が有り、改めてこの言葉の持つ意味をしっかり捉える事ができました。
ちなみに、先生自身は地域性を活かしそれを守りながら緑化する方法や、遺伝情報等から緑化植物の区分を調べる研究をなさっているそうです。
各項目の最後には疑問に答える時間が用意され、様々な質問が飛び出しました。
結局、予定されていた時間を40分余りオーバーしましたが、とても充実した講演会でした。
さて、楽しみにしていたフィールド“崩壊斜面モニタリング観察”の日。町役場が用意してくれたマイクロバスに乗り込み出発です。
参加人数は、定員27名との事でしたが完全にオーバーしている様です。
補助椅子も全部使い満席となったバス。 (画像は有りませんが・・・)
工事の為、ここ数日車両侵入禁止になっていたのですが、今回は特別にモニタリング現場までバスで行きます。

モニタリング現場は、A地点・B地点の2ケ所
設置されているのは、プロットと呼ばれる縦5m横約2mの枡(この中の植生の変化や泥の流出等を調べます)。
そして幾つかの雨量計と風向風速計・温湿度計・地温計・照度計等、様々の観測機器。

観測するシーズンに依っては、機器類が植物に埋もれてしまう様ですが、一昨日はまだ新芽の状態だったので、機器や植生の様子もよく判りました。
一通り機器類の説明が終わり、何やら実験が始まりました。
土中に刺した透明の筒の中に水を流し込み、浸透率(浸透時間)を確認する実験の様です。

1回目、見る見るうちに減っていく筒の中の水にビックリしましたがこれは単なる水漏れ・・・。

その後は、土中に浸透していく様子をしっかり確認できました。
さて、3ケ所目の実験準備を始めたところで、早朝ツアーに出ていた西谷から電話が・・・
ようやく参加できたフィールドでの勉強会、残りわずかだったのですが、戻らざるを得なくなりました。
山頂口まで車に乗せてくれたIさん、ありがとうございました。
植生の変化に興味のある方は、頂いた資料等有ると思いますのでご連絡ください。
By 柳場
追: (過去のモニタリング調査の様子は西谷がかなり詳しく報告しています。)
第二回植生回復調査
崩壊斜面モニタリング調査・報告その1
崩壊斜面モニタリング調査・報告その2
崩壊斜面モニタリング調査・報告その3
久しぶりの崩壊斜面モニタリング調査
(伊豆大島ジオパークHPに切り替わります)”第1回・崩壊斜面モニタリング調査
この他にも検索すると沢山出てきます。懐かしい顔ぶれも登場しますよ。
ご覧になっていない方は、是非チェックしてみて下さい。








































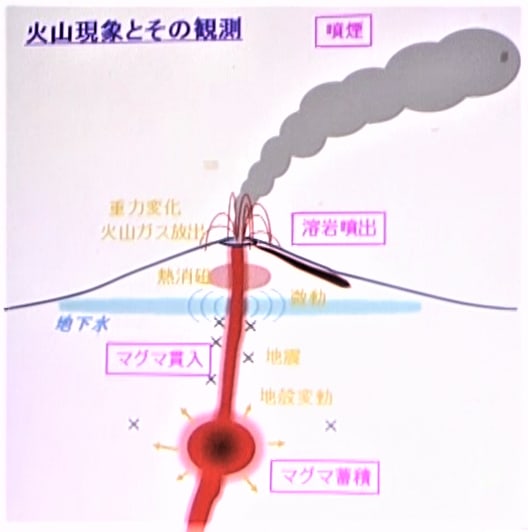
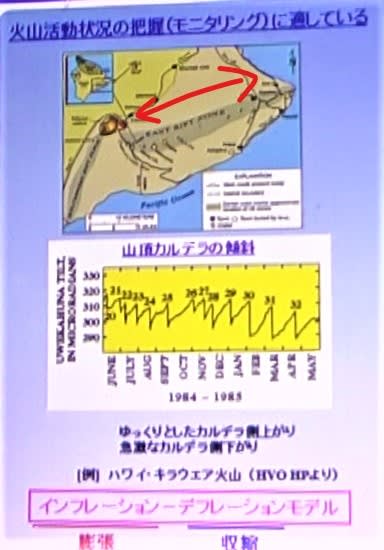




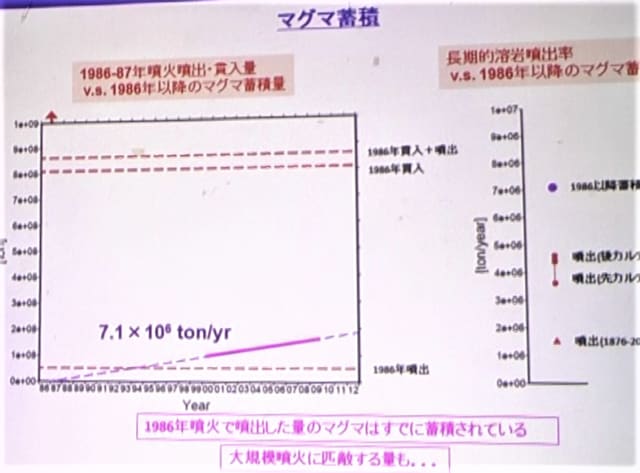






















































 、
、












































