
上海レポート、初回は上海蟹の紹介です。
上海蟹というのは淡水の湖にいる蟹で、写真のようにハサミに毛が密生しているのが特徴です。
中国語で「大閘蟹」(ダアジャアシエ)といいます。
陽澄湖という湖でとれるものが一番で、紐で縛って出荷される際に陽澄湖産のものはラベルがついているそうです。(ラベルの偽物が出回っているくらいのブランドだそうです)
関サバ、関アジのようなものでしょうか。
旬は雄のミソが乗っている11月中旬から12月上旬頃。
ちょうど今回は旬の最後のほうの駆け込みでした。
今回は初日の夕食、2日目の昼食と都合2杯いただきました。
写真は2日目に行った、地元でも上海蟹の名店と名高い「王宝和酒家」のものです。
王宝和酒家は上海蟹で稼いでもう一軒近くに「王宝和大酒店」という立派なホテルを構えてますが、そちらのレストランはちと高いということで、コストパフォーマンス優先で本店で昼に食べる事にしました。
シーズンの最後のほうなので、特大サイズのものはなかったのですが、さすが老舗、初日の店よりは大ぶりで、ミソもたっぷりのものが出ました。
ちなみに値段は上海蟹だけで1杯195元。
実はそれ以外の料理と酒(8皿と紹興酒2本)は5人で200元ととても安いです(1元=約150円)。
その他の食事については後日書こうと思いますが、食材を贅沢したり、豪華なお店を選ばなければ基本はとても安いです(逆に上海蟹ならビルが建つのもうなずけますねw)
さて、食べ方ですが
これが蒸す前の紐で縛った状態。ストロボをたかなかったので赤っぽく見えますが、実際は緑がかった色をしています。
そしてこれが茹で上がり
大きさは中の上でこのくらい(茹でたてはとても熱いのでつまんでます)
これをまずひっくり返します。
それで、股間のところ(雄の特徴です)をぺロッとめくります
そして、そのまま甲羅をベリベリッとはがします。
ミソが盛り上がっているのが見えますね(^^)
まずは甲羅の内側のミソと肉をこそげおとします。
甲羅に紹興酒を入れて飲むのもお勧めです。
(このへんから食べるのに集中して、ピンぼけの写真が多くなりますがご勘弁を・・・)
甲羅を仕上げたらいよいよ本体です。
両手で脚を持って、バキッと真中から2つに割ります。
そして、それにしゃぶりついてミソを食べます。
ここが上海蟹のハイライトといえましょう(^^)
つぎに、脚を2本持って根元から折ります。
そして、とり残したミソをしゃぶり尽くして、後の身は黒酢につけて食べます。
そのあと、脚を解体して身をいただきます。
ここまでくれば、あとは黙々と食べるだけです。
蟹が大きければ先のほうまでばらせますが、普通は胴体の次の節までが作業に見合う感じです。
小さいハサミは最初から出してくれるところもありますが、出してくれなければ頼んだほうがいいです。
蟹用のフォーク(もう片方が細長いスプーンになっている)は日本独自のもののようで(初日の店では出てきたのですが、裏に"Made in Japan"の刻印がありました)店にないときは、第一関節の先の尖った爪の部分を代用するといいです。
また、根元の第1節目は、箸でぎゅっと押し出すと、身が丸ごと抜けてとてもうれしいです^^
初日よりも2日目のほうが作業の熟練度が増し、達成感もひとしおでした。
王宝和酒家では、食べ終わった後に生姜入りのお茶がでました。
蟹は身体を冷やす「陰」の食べ物なので、身体を温めるものと一緒に食べるようにします。
また初日の店は黒酢に生姜が入っていましたし、蒸すときには身体を温める効果のあるシソの葉を一緒に入れたりするようです。
フィンガーボウルが用意されますが、脚の先まで念入りに食べると、指についた蟹の臭いが夜まで抜けないこと、請け合いです。
























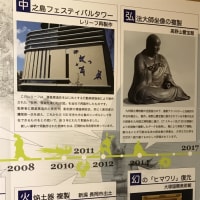
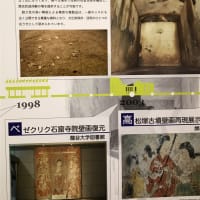








経済が発展し、日本以上の金持ちがゴロゴロいる今の上海。いい蟹も、いい料理も味わえます。
値段も一流になりましたが。
高額品ほど価格差がなくなっている感じがします。
逆にブランド品は日本より高いようですが、飛ぶように売れているようです。