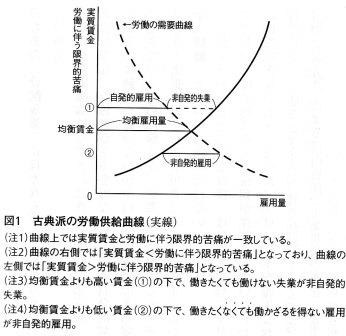少し前に公園のダビデ像「下着をはかせて」…町民が苦情 というニュースがありました。
そこで
本書は、駅前などにおかれている男性彫刻の股間表現はなぜ曖昧模糊(モッコリ?)としているのだろう、と疑問に思った著者が、男性彫刻とその歴史を遡った快作(怪作)。
もとは雑誌『芸術新潮』に「股間若衆-日本近現代彫刻の男性裸体表現の研究」として世に出た論文とその続編「新股間若衆-日本近現代写真の男性裸体表現の研究」に、書き下ろしである「股間漏洩集」を加えた三部仕立てになっています。
この、古典を引用しつつ硬軟両様の表現を使い分けるところが芸術表現と股間の一物の関係をあらわしており、明治以降の性表現への官憲の取り締まりへの対応の暗喩にもなっています。(もっとも「股間漏洩集」は前の2作とのつながりがないと「和漢朗詠集」でなく単なる失禁を連想してしまいますが...)
明治以降、裸体表現をめぐって美術界と警察の「風俗紊乱」取り締まりとのせめぎあいが続いてくる中で、特に男性の裸体は突起物がある分、股間の表現が難しく、そのために様々な工夫(中には珍妙なものや涙ぐましいものもあります)がこらされてきました。
そして、芸術の裸体表現は展示会だけでなくやがて出版物へ掲載されるようになると、それが美術界の中だけの問題にとどまらず、社会問題となります。
ついに朝倉文夫の女性裸体像「時の流れ」を写真掲載した愛知新聞が新聞紙法違反に問われた裁判で、画期的な大審院判例が出ます。
右夫人の局部に相当する部分には何物の之を隠蔽するものなき事原判決の如くなるも、之と同時に其部分は人の注視を促すに足るべき何物の描写せられたるものなきのみならず、右婦人の姿勢表情共に閲覧者をして羞恥厭悪の念を発起し道義上良心を攪乱せしむるに足るものあるを見ずして単に藝術美の表題を認識し得るに過ぎざるを以て、之を風俗を害する挿画なりと為すを得ず
(大審院 大正7年2月13日判決)
ここから「藝術製品の陰部にあたる部分は何も隠す必要はないが、特殊感情を集中させるような技巧をこらしてはならないという鉄則」が打ち立てられ、局部の表現の仕方、局部を構成するディテールが問題となり、しばらく前まで続いていた「陰毛の有無」基準ができたそうです(なんと今から95年前の基準なんですね)。
たとえ如何なる藝術品といへども局部に陰毛や陰裂を描いたものは、局部の一点に観る人の特別な好奇心を集中して淫汚な感覚を唆るから、総合的に見て、すべて、これを猥せつとすることになったのであって、この標準は今日迄一貫して維持されて変らないのである
(馬屋原成男『日本文藝発禁史』(注:著者は当時の東京高等検察庁の検事だそうです))
今では桜田門の警視庁の入り口に、朝倉文夫の「競技前」という男性裸像参照が置かれているのは歴史の皮肉です。 (これについては、雑誌『薔薇族』初代編集長伊藤文学が警視庁に出頭したときのエピソードでも触れられています(伊藤文学のひとりごと))
また本書は、わいせつ表現問題だけでなく、芸術作品としても男性の裸体はいかに女性の裸体表現に比べて日陰の存在であったかについて、彫刻と写真表現を中心にその歴史を振り返っています。
そして、戦後になり、彫刻は戦後復興のシンボルとして、多くの「股間若衆」が作成され駅前に置かれる一方で、写真の分野では、芸術写真自体戦前から女性ヌードに大きく遅れをとっていたうえに、戦後のアマチュア写真時代になると、男性のヌードは日陰の身になってしまうという対比は印象的です。
また、巻末におまけとしてある全国各地の小便小僧が、小さな一物を露出しながらも(することで?)市民に愛されているのを見ると(たとえば浜松町駅の小便小僧を参照)、禁忌の感覚の微妙さを一層感じます。
本書を読み終えたあなたは、街角に立つ股間若衆に温かい眼差しを送っている自分に気づくことでしょう。