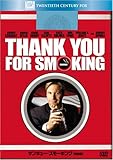やはり「2」というのは難しい。
今回はスミソニアン博物館も巻き込んでの騒動になりますが、主人公以外にも前回の登場人物(登場展示物?)もからめて連続性をだしたのはいいのですが、関係する登場人物(展示物)が多くなりすぎて、ちょっと散漫になったかも。
自然史博物館とスミソニアン博物館を1日で回ればそうなっても仕方ないですけど(笑)
それと、話が現代史になってくると、アメリカ人的なツボを理解できないので面白さが減ってしまっているのかもしれません。
カスター将軍の「英雄」の評価の見直しというのはどこかで聞いたことがあったのですが、今でもアメリカ的にはけっこうなネタなのでしょうか。
そのかわりナポレオンの身長コンプレックスとかイワン雷帝などの描き方がステレオタイプなのもアメリカっぽいです。
お茶の間健全娯楽としては面白いです、十分面白いですけど、第一作のようなカタルシスがないのは高望みしすぎなのでしょうか。
今回はスミソニアン博物館も巻き込んでの騒動になりますが、主人公以外にも前回の登場人物(登場展示物?)もからめて連続性をだしたのはいいのですが、関係する登場人物(展示物)が多くなりすぎて、ちょっと散漫になったかも。
自然史博物館とスミソニアン博物館を1日で回ればそうなっても仕方ないですけど(笑)
それと、話が現代史になってくると、アメリカ人的なツボを理解できないので面白さが減ってしまっているのかもしれません。
カスター将軍の「英雄」の評価の見直しというのはどこかで聞いたことがあったのですが、今でもアメリカ的にはけっこうなネタなのでしょうか。
そのかわりナポレオンの身長コンプレックスとかイワン雷帝などの描き方がステレオタイプなのもアメリカっぽいです。
お茶の間健全娯楽としては面白いです、十分面白いですけど、第一作のようなカタルシスがないのは高望みしすぎなのでしょうか。
 |