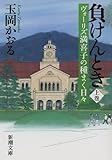直木賞受賞後第一作。もっとも注目される直木賞後の第一作の本作品に描かれている場所は大坂です。
そうですー、大坂なんですよっ!
※このブログを見てくださってる方には上方落語に耳馴染みがある方が多いと思っての呼びかけその1
10年ちょっと前には時代小説をまったく読まなかった私が今や上方落語を筆頭に浄瑠璃やら江戸時代の上方文化にどっぷりはまってるとはこれまた不思議。しかも、時代小説を読み始めたきっかけのお一人が朝井まかてさんでした。
大坂を舞台にした作品が少ない中、本屋で新刊のお知らせを見て小躍りしました。
主人公が西鶴!てことは、大坂が舞台やおまへんか?!
大坂を舞台とする時代小説に飢えている私は心躍らせレジに向かったのでした。
そして、読み始めると、
これが見事な大坂のことば。振り仮名も要チェックですよ、みなさん。
西鶴を盲人の娘からの視点で描き、またその人物像に迫っていきます。
時代の先頭に立ち、新しい文芸を築いた西鶴を娘から描くことによりドラマとしての情、そして、当時の大坂の風を感じる作品です。
史実をもとにした作品なので実在の人物もたくさん登場します。
なんといっても近松門左衛門!
※このブログを見てくださってる方には浄瑠璃に馴染みがある方が多いと思っての呼びかけその2
義太夫作家でもあった西鶴とからめてでてまいります。
それから、歌舞伎役者もでてきます。西鶴がひいきにしたという上村辰彌。今に続く上村の屋号の最初の頃の方です(二代目上村吉彌の弟)。なんだか、この時代を私も一緒に体験しているように思える絶妙の配置。
そして、忘れてはならないのが市井の名もなき庶民たち。
物語の最後の方にでてきます。この集まり、まさに落語的。
西鶴が感じ、筆にしたためた時代の空気は落語の中にまだ息づいているんだと胸が熱くなりました。
あ…文芸愛好家向きの感想じゃないなあ。お許しを。
いずれまた改めて感想書きます。たぶん。

学生時代のテキストをひっぱりだしてきました。実は論文に「日本永代蔵」を引用しておりまして、西鶴先生にはお世話になっていたんですよ、私も。