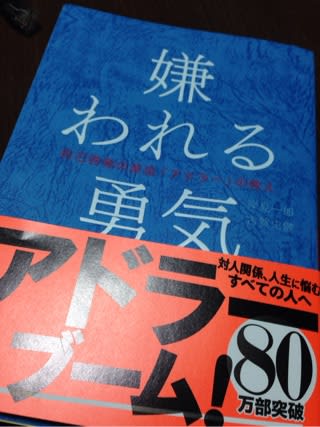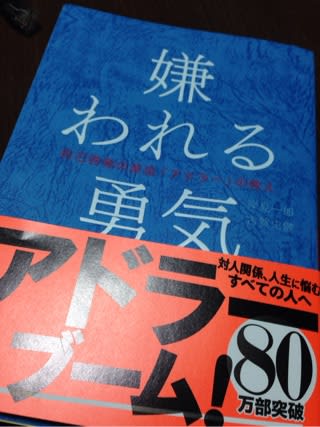
自己啓発本はあんまり読まない。カーネーギーも何冊かセットになったのを買ったにも関わらず読まずにブックオフに出してしまいまして。
ただ話題のアドラー心理学に興味を持ち、ベストセラーのこれを。対話形式で入門編て感じ。
アドラー心理学のなんたるかは置いといて、年末にちろりさんとお会いしたときに「あさいちに上沼恵美子さんがでたの見た?あの人すべての人に好かれそうと思ってないねんて」と目をキラキラさせて言うておられてたのでこの前動画サイトでその回を見ました。
痛快。さすがえみちゃん(笑)!
さて、私もかなり屈折していたり、意外と社交性なかったり(オンオフのボタンがある)していて、そんなにいい人間ではありません。し、それが悪いことだとも思ってないのよね~。
で、本著『嫌われる勇気』なんですが、物事の価値観を人に委ねないにまるっと同意。人からどう思わられてるかを気にするのはあやふやな他者にその価値を丸投げしてしまってることになってしまうし、それってしんどいやないか、と。
前からなんですが人からAという悩み事の相談を受けると別口で別の方から同じ内容の相談を続けて受けることがあります。
今回は他人に対して悪い事を考えてしまう、と悩んでいた人に対して
「あ?死ねとか思うってことでしょ、あるある~」
続いて別口でもそんな相談がありまして以下同文。
そりゃ不道徳かもしれないが実際行動起こしてる訳ではないし、そう思ったんだから仕方ないのでは。それで自分を責めたらどこまで傷つくのだろうと思ってしまいます。そう思うきっかけはあったんだから。
私も下衆な人間なんでベキゲスに何があったかは推測したりしてますが、テレビに抗議の電話をするほど行動する人って生きにくい世の中を生きてはるなあ~と思います。他人の生き方が違うと思ったら正さないと気が済まないのって大変よ!私は清廉潔白な人間ではないのでそんなこたあできません。
ま、そんなことが書いてある本ではありませんが、人に価値観を委ねないというところに共感しました。

てなことを書いてたら2月の100de名著はこちらでした。