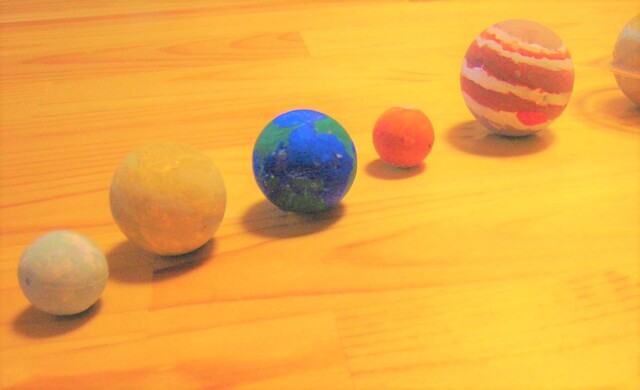ご覧いただきありがとうございます。
gooブログがサービス終了するため(2025年11月)
アメブロへお引越ししていますので、こちらもよろしくお願いいたします。
https://ameblo.jp/kodomonoie-aiai/
モンテッソーリ教育では、文化教育という分野があり、
その中には、宇宙、地球、地理、歴史…さまざまな内容が含まれます。
園によって、取り組み方が違うので、
文化教育まで取り入れていないところもあるようですが…
教師養成コースや先日のブラッシュアップセミナーで、
おすすめの絵本が、こちらです。
せいめいのれきし 改訂版
宇宙の始まりから、現在の人間の生活までを描いています。
彼女が亡くなる前に、8年間かけて完成させたのだそうです。
この作者の他の絵本は、こちら。
いたずらきかんしゃちゅうちゅう (世界傑作絵本シリーズ―アメリカの絵本)
ちいさいおうち (岩波の子どもの本)
マイク・マリガンとスチーム・ショベル
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー (世界傑作絵本シリーズ―アメリカの絵本)
どれも、息子が好きだった本ばかりです。
そして、この作者とモンテッソーリ教育との関係を聞き、
早速、図書館で借りて読んでみました。
ヴァージニア・リー・バートン―『ちいさいおうち』の作者の素顔
確かに書いてありました
p9
彼女が書いた自伝的文章には、
「…私の家の古い納屋は学校に早変わりして、
おそらくこの国で初めてのモンテッソリ(モンテッソーリ)教育が行われたのだと思います」
p99抜粋
この本(『メーベル』)も含めて、バートンの本の評判を高めているのは、
彼女の調査には信憑性があるということである。子供の本を作るにあたって、
どんなことが一番好きかと聞かれて、彼女は、
「主に調べることね。調べることはとても面白いから、私は大好きなの。
『メーベル』を納得いくまで十分描き終えた頃には、ケーブルカーを自分で
運転できると思ったくらいよ」と答えた。
彼女はかつて「子供たちは旺盛な知識欲を持っている。楽しい方法で教えられれば、
子供たちは学ぶことが大好きなのだ」とも言っている。
坂の街のケーブルカーのメイベルは、童話館ぶっくくらぶから、先月届きました。
すべてを理解できるのは、4年生くらいなのかもしれませんが、
もう少し早くても楽しめるとは思いました。
彼女の絵本は、子どもたちの知識欲に応えてあげられる絵本だと思います。
バージニア・リー・バートンの絵本が好きな方は、↓ぜひ、読んでみてくださいね。
ヴァージニア・リー・バートン―『ちいさいおうち』の作者の素顔
絵本が作られた背景を知ると、また新たな発見がありますよ。
日本にも来られたことがあり、日本を背景にした本を作りたいとも言っていたそうです。
残念ながら、それはかないませんでしたが…。
参考までに…
『メイベル』以外は、息子が年中~年長のときに、大好きでした。
息子に、このことを話すと驚いていましたが、
「どれも面白かったよねー」と、なつかしがっていました。
毎日毎日絵本を読んでいた時期が懐かしいと思うような年になってきました。
今、お子さんに読んであげられる方々、存分に楽しんでくださいね
 ぜひ、こちらもお読みください。
ぜひ、こちらもお読みください。
モンテッソーリ教育を初めて知る方へ
マリア・モンテッソーリ
モンテッソーリに関する書籍













 )
)