
コンビーフはCorned Beefと綴る。「塩漬けの肉」という意味で、トウモロコシのような粒の大きい岩塩を使用したことに由来する。保存用の食料として軍隊でも用いられた。日本では台形の缶詰となった製品が最も一般的である。食べてみると、ほぐされて筋状になった肉が複雑にからまっていることがわかる。

リヴァーブはRevaerbと綴る。Re+Verbということだ。Verbは「動詞」という意味で使われるが、ラテン語までさかのぼれば「言葉」という意味であったことがわかる。発した言葉が返ってくる「やまびこ」のような、噂話が様々な尾ひれをつけて発信元に戻ってくるというようなイメージがリヴァーブということか。
現在リヴァーブといえば、一般的に残響を意味する。部屋の中で音を聴くとき、聴いている者には直接音のほかに、壁や部屋にあるあれやこれやに反射して空間をへめぐった後に届く音も聴こえるのだが、そのわずかだけ遅れて届いた音を残響として認識するというわけである。それは下の図のようにあらわされる。

この図では音を線であらわしているのだが、当然のことながら、実際はこの線は無数にあるものとして考えなければならない。そして空間内を複雑にからみあって聴く者の耳に届いているのだ。それはまるで缶の中で複雑にからまりあっている筋状の肉のかたまり、つまりコンビーフのように見えてこないだろうか。
さて、ダンエレクトロはミニシリーズのリヴァーブペダルに「コンビーフ」と名前をつけた。上記はその理由を例によって類推してみたものである。
このペダルにはMIXとHI-CUTの二つのノブがある。MIXを右いっぱいに回し、HI-CUTをそれとは逆に左いっぱいに回した設定が、このペダルで最もリヴァーブが深くかかっている状態である。多くの人はこのサウンドをスラップバックエコーのようだと思うだろう。そうなると、前回紹介したBLTとどう違うのかということになってくるのだが、リヴァーブもしくはエコーとしてのみ考えるならばそれほどの違いはないと考えてよいのかもしれない。しかし、このペダルの使い道を他に探るとするなら、MIXを左方向に、HI-CUTを右方向にそれぞれ回していきながら、残響音はしないが、ギターの音は少し湿り気を帯びて光沢感が出てくるというような、そんなポイントをうまく活用するといった感じでどうだろう。


















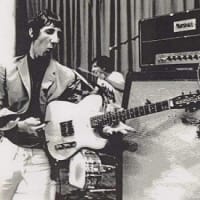
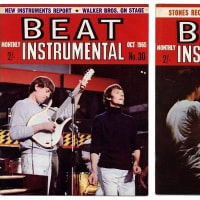






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます