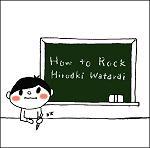ギターの歴史をたどれるような本が1冊くらいは欲しいな、と思って見つけたのがこれ。

ボストン美術館が出した「DANGEROUS CURVES THE ART OF THE GUITAR」は美術館が所蔵しているギターを通じて、バロック期から現代に至るギターの歴史を豊富な画像でたどる、というもの。
複弦5コースのものからリラやハープとかけあわされたミュータントなギターたち、そしてもちろん、現在までに多種多様なデザインが生み出されてきたエレクトリック・ギターたちも、夥しくその危ない曲線の魅力で私を誘惑するのだった。
この本を買ってから発見したのだが、実はボストン美術館のサイトにほぼ全容がアップされているのである。ということはつまり、この本を買わなくてもよかったんじゃないかという気にもなったりするわけで。
だのじゃん的にはもちろん、こうしたギターの歴史をたどる本の中で、ダンエレクトロのギターがどのように扱われているのかが気になるというのもあったのだが、しっかりとブロンズフィニッシュのショートホーン3012が掲載されていた。
ダンエレクトロのギターについてはそのデザインや使用する材についてのオリジナリティや廉価なギターを通販で販売したことで、多くの人にとっての「初めてのギター」になったことなど記されている。

ボストン美術館が出した「DANGEROUS CURVES THE ART OF THE GUITAR」は美術館が所蔵しているギターを通じて、バロック期から現代に至るギターの歴史を豊富な画像でたどる、というもの。
複弦5コースのものからリラやハープとかけあわされたミュータントなギターたち、そしてもちろん、現在までに多種多様なデザインが生み出されてきたエレクトリック・ギターたちも、夥しくその危ない曲線の魅力で私を誘惑するのだった。
この本を買ってから発見したのだが、実はボストン美術館のサイトにほぼ全容がアップされているのである。ということはつまり、この本を買わなくてもよかったんじゃないかという気にもなったりするわけで。
だのじゃん的にはもちろん、こうしたギターの歴史をたどる本の中で、ダンエレクトロのギターがどのように扱われているのかが気になるというのもあったのだが、しっかりとブロンズフィニッシュのショートホーン3012が掲載されていた。
ダンエレクトロのギターについてはそのデザインや使用する材についてのオリジナリティや廉価なギターを通販で販売したことで、多くの人にとっての「初めてのギター」になったことなど記されている。