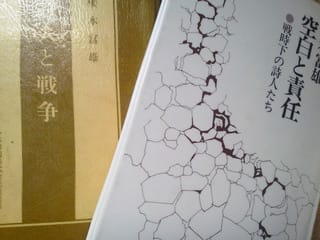
『死と滅亡のパンセ』(辺見 庸)を読み進めている中で、この著者の作品(とその一貫した姿勢)に触れていました。改めていくつかの作品を読みました。
題名にも明らかなように、かつての「大東亜戦争」(太平洋戦争)、筆者は具体的には昭和16(1941)年から昭和20(1946)年の期間を指していますが、日本が中国戦線から太平洋戦線へ拡大し、ついには国内外に計り知れないほどの多くの人命を失い(奪い)、遂には、「敗戦」を迎えます。その戦争に一億国民を導く(扇動する)担い手として文化人、文学者の多くが、戦争遂行に荷担していきます。特に当時は「小国民」としてあった筆者の痛切な反省と自戒の上に立って、戦争賛美の作品を発表していった詩人たちへの戦争責任を追及したのが、この二冊の書です。「詩人と戦争」は1977年10月の刊行、「空白と責任」は、1983年7月の刊行。基本的な作品構成、内容は、「詩人と戦争」が先行、ただし、奥書では限定300部となっていますので、広範の人の目には触れなかったようです。その後、一般向けの書として後者が発刊されたと思われます。
その矛先は、積極的に戦争を賛美した詩を次々と発表し、あげく、若者を戦場に勇躍して送り込ませ、死に至らしめた、そうした行為を厳しく自己批判した高村光太郎などに向けられたものではありません。
いっさいそうした自己批判もなく(口をぬぐい)、むしろ自らの戦争賛美の詩を後に改ざんし自らの所行を隠蔽していった草野心平、金子光晴の二人を取り上げて、戦後、いかに己の所行を隠蔽してきたかを厳しく追及していく。この二人は詩壇の押しも押されぬ重鎮中の重鎮。むしろ、戦争当時、我も我もと戦争賛美に傾いていった(別の見方では、息が詰まるような文壇、出版界の)中にあって、反戦、非戦を貫いてきた詩人として戦後高く評価されてくる人たち。そのために、吉本隆明、伊藤信吉などという著名な詩人、評論家を敵に回す作業でもあった。それにも臆せず、「戦い」を挑んでいきます。
それは、3・11とりわけ福島第一原発事故を受けて、それまでいかに多くの文化人・文学に関わる人間が「原発」推進に手を貸し、ひとたび事故が起こるや、それまでの自らの言動への自己批判もなく、我関せずを決め込む「輩」への辺見さんの鋭い追求姿勢と重なっています。辺見さんは、自らの依って立つ姿勢によって、先駆的な「評論」活動として櫻本さんの著作を評価するわけです。
改ざん、あるいは埋もれてしまった資料を明らかにし、改ざんされた詩と発表当時の詩を比較検討する、ある意味で、執念深く追求する姿勢は、筆者自身の自己否定・自己批判の姿勢と重なっていきます。こよなく詩を愛するが故の、詩人の発言です。
一方で、これらの書が出版されて、30年近く。一頃、詩人全集などが発刊されてもてはやされた時代からもずいぶんと時が経ちました。詩が人の心をうち、慰め、勇気を与え・・・、戦争当時のように鼓舞する、いい意味でも悪い意味でも、そうした勢い・インパクトに欠けている現在(と思われます)。詩自体が、詩壇という仲間意識、あるいはサロン化されて閉塞状態にもあるように感じます。
筆者たちが熱く論争した時代は、ある意味で詩のよき時代でもあったようです。さて、東日本大震災・福島原発事故以降の文芸界のあり方は果たして? 辺見さんやタカハシさんなどは積極的に打って出ていますが。
題名にも明らかなように、かつての「大東亜戦争」(太平洋戦争)、筆者は具体的には昭和16(1941)年から昭和20(1946)年の期間を指していますが、日本が中国戦線から太平洋戦線へ拡大し、ついには国内外に計り知れないほどの多くの人命を失い(奪い)、遂には、「敗戦」を迎えます。その戦争に一億国民を導く(扇動する)担い手として文化人、文学者の多くが、戦争遂行に荷担していきます。特に当時は「小国民」としてあった筆者の痛切な反省と自戒の上に立って、戦争賛美の作品を発表していった詩人たちへの戦争責任を追及したのが、この二冊の書です。「詩人と戦争」は1977年10月の刊行、「空白と責任」は、1983年7月の刊行。基本的な作品構成、内容は、「詩人と戦争」が先行、ただし、奥書では限定300部となっていますので、広範の人の目には触れなかったようです。その後、一般向けの書として後者が発刊されたと思われます。
その矛先は、積極的に戦争を賛美した詩を次々と発表し、あげく、若者を戦場に勇躍して送り込ませ、死に至らしめた、そうした行為を厳しく自己批判した高村光太郎などに向けられたものではありません。
いっさいそうした自己批判もなく(口をぬぐい)、むしろ自らの戦争賛美の詩を後に改ざんし自らの所行を隠蔽していった草野心平、金子光晴の二人を取り上げて、戦後、いかに己の所行を隠蔽してきたかを厳しく追及していく。この二人は詩壇の押しも押されぬ重鎮中の重鎮。むしろ、戦争当時、我も我もと戦争賛美に傾いていった(別の見方では、息が詰まるような文壇、出版界の)中にあって、反戦、非戦を貫いてきた詩人として戦後高く評価されてくる人たち。そのために、吉本隆明、伊藤信吉などという著名な詩人、評論家を敵に回す作業でもあった。それにも臆せず、「戦い」を挑んでいきます。
それは、3・11とりわけ福島第一原発事故を受けて、それまでいかに多くの文化人・文学に関わる人間が「原発」推進に手を貸し、ひとたび事故が起こるや、それまでの自らの言動への自己批判もなく、我関せずを決め込む「輩」への辺見さんの鋭い追求姿勢と重なっています。辺見さんは、自らの依って立つ姿勢によって、先駆的な「評論」活動として櫻本さんの著作を評価するわけです。
改ざん、あるいは埋もれてしまった資料を明らかにし、改ざんされた詩と発表当時の詩を比較検討する、ある意味で、執念深く追求する姿勢は、筆者自身の自己否定・自己批判の姿勢と重なっていきます。こよなく詩を愛するが故の、詩人の発言です。
一方で、これらの書が出版されて、30年近く。一頃、詩人全集などが発刊されてもてはやされた時代からもずいぶんと時が経ちました。詩が人の心をうち、慰め、勇気を与え・・・、戦争当時のように鼓舞する、いい意味でも悪い意味でも、そうした勢い・インパクトに欠けている現在(と思われます)。詩自体が、詩壇という仲間意識、あるいはサロン化されて閉塞状態にもあるように感じます。
筆者たちが熱く論争した時代は、ある意味で詩のよき時代でもあったようです。さて、東日本大震災・福島原発事故以降の文芸界のあり方は果たして? 辺見さんやタカハシさんなどは積極的に打って出ていますが。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます