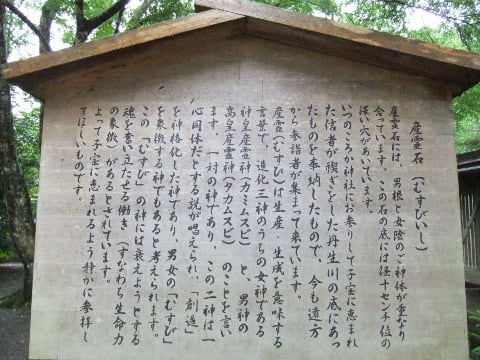帰路の途中、
大和七福八宝巡りの最後の寺である子嶋寺に行ってなかったので、
奈良県高市郡高取町にある子嶋寺へ。
宗派:高野山真言宗
御本尊:大日如来
創建年:1848年
開基:報恩大徳
このお寺は何気に凄い。
報恩法師の弟子である延鎮と征夷大将軍坂上田村麻呂が京都清水寺を建立し、
あの清水寺が小嶋寺の支坊だったそうです。
【山門】

もともとこの門は数十もあった高取城の二の門を移築したそうです。
後で寺の方に聞いた話ではこの山門を建てると、
2億円はかかると宮大工が言ったそうです。
そう聞くとありがたみを感じる今日この頃。(笑)
高取城は今は城跡だけが残っているのですが、
現存していたら日本最大の城だったそうで、
時の明治政府が武士の残党が城に篭城しないように取り潰した歴史があります。
本当に残念ですね。
まったく城を潰したり廃仏毀釈したりと明治政府は最悪ですね。
【境内】

今はとても小さなお寺ですが最盛期の子嶋寺は21の子院が立ち並び、
現在の高取町と明日香村にまたがる広大な境内地をもっていたそうで、
藤原道長の日記「御堂関白記」によれば、
寛弘4年(1007年)には道長がこの寺に参詣している由緒あるお寺です。
このお寺もまた廃仏毀釈で徹底的に破壊されたようです。
十三重石塔は一条天皇から下賜されたもの。
【本堂】


嘉永元年(1848年)建立。
拝観料300円を支払って本堂の中へ。
これが大正解。
もし中に入っていなければこの寺の凄さは分からなかっただろう。
特に見仏人は見ないと損しますよ。
まぁ、朱印さえ貰えればいい人はそれでいいんでしょうけど。
本堂内は残念ながら撮影禁止でした。

御本尊の大日如来像です。
(写真は寺の小冊子より。)
決して大きくないのですが細かく手の込んだ装飾で、
尚且つ気品のあるキリリとした表情が秀逸です。


堂内には御本尊様より目立つ物がある。
それが国宝に指定されている紺綾地金銀泥絵両界曼荼羅図である。
左が金剛界曼荼羅、右が胎蔵曼荼羅。(Wikipediaより)
弘法大師が唐より請来し時の嵯峨天皇に献上された品で、
京都・神護寺、東寺の曼荼羅図と共に日本三大曼荼羅図に数えられます。
子嶋寺中興の祖とされる真興が一条天皇の病気平癒祈願の功により
賜ったと伝わる。
何でも中国が返してくれと言ってきたり、
かのルーブル美術館が貸してくれと言ってくるほどの逸品です。
堂内にあるのはレプリカで本物は防火設備と保存に適した奈良国立博物館に寄託。

(写真は寺の小冊子より。)
子嶋寺は大和七福八宝巡りの大黒天を担っており、
室町時代作の大黒天が祀られています。
現在は足元以外はガラスケースで覆われていますが、
足を触ることが出来るので御利益があるように触っておきました。(^^
寺の方の説明によると以前はガラスケースは無かったのですが、
大黒天の一部を持って帰る不届き者がいたそうで、
ガラスケースが設置されたとのこと。
本当に罰当たりなことを平気でする人もいるんですね。(怒)

(写真は寺の小冊子より。)
征夷大将軍坂上田村麻呂の自作像と伝わる。
本堂にはその他に申請すれば国宝に指定されると言われる
飛鳥時代の仏頭や延鎮僧都の像など素晴らしい仏像の数々を堪能出来ます。


千寿院へ続く廊下には瓦や不動明王の石仏などが置かれていました。
しかもただの瓦ではありません。
職人に言わせるとあれほど細かい瓦を割らずに焼くなんて、
現代の技術でも無理だとのこと。
【十一面観音像】

千寿院に祀られている高取城主の念持仏。
以前は住職と高取城主しか堂内に入れなかったそうです。
手前にある袋に包まれた嶋投聖天は残念ながら秘仏です。
【御朱印】

【満願】

ようやく満願達成しました。(^^
この子嶋寺は正直余り期待しておりませんでしたが、
本堂の中が凄すぎた。
寺の方にいろいろ説明していただき勉強になったし、
沢山ウンチクのある話をしてとても堪能しました。
何度も訪れたいと思う数少ないお寺です。
大和七福八宝巡りの最後の寺である子嶋寺に行ってなかったので、
奈良県高市郡高取町にある子嶋寺へ。
宗派:高野山真言宗
御本尊:大日如来
創建年:1848年
開基:報恩大徳
このお寺は何気に凄い。
報恩法師の弟子である延鎮と征夷大将軍坂上田村麻呂が京都清水寺を建立し、
あの清水寺が小嶋寺の支坊だったそうです。
【山門】

もともとこの門は数十もあった高取城の二の門を移築したそうです。
後で寺の方に聞いた話ではこの山門を建てると、
2億円はかかると宮大工が言ったそうです。
そう聞くとありがたみを感じる今日この頃。(笑)
高取城は今は城跡だけが残っているのですが、
現存していたら日本最大の城だったそうで、
時の明治政府が武士の残党が城に篭城しないように取り潰した歴史があります。
本当に残念ですね。
まったく城を潰したり廃仏毀釈したりと明治政府は最悪ですね。
【境内】

今はとても小さなお寺ですが最盛期の子嶋寺は21の子院が立ち並び、
現在の高取町と明日香村にまたがる広大な境内地をもっていたそうで、
藤原道長の日記「御堂関白記」によれば、
寛弘4年(1007年)には道長がこの寺に参詣している由緒あるお寺です。
このお寺もまた廃仏毀釈で徹底的に破壊されたようです。
十三重石塔は一条天皇から下賜されたもの。
【本堂】


嘉永元年(1848年)建立。
拝観料300円を支払って本堂の中へ。
これが大正解。
もし中に入っていなければこの寺の凄さは分からなかっただろう。
特に見仏人は見ないと損しますよ。
まぁ、朱印さえ貰えればいい人はそれでいいんでしょうけど。
本堂内は残念ながら撮影禁止でした。

御本尊の大日如来像です。
(写真は寺の小冊子より。)
決して大きくないのですが細かく手の込んだ装飾で、
尚且つ気品のあるキリリとした表情が秀逸です。


堂内には御本尊様より目立つ物がある。
それが国宝に指定されている紺綾地金銀泥絵両界曼荼羅図である。
左が金剛界曼荼羅、右が胎蔵曼荼羅。(Wikipediaより)
弘法大師が唐より請来し時の嵯峨天皇に献上された品で、
京都・神護寺、東寺の曼荼羅図と共に日本三大曼荼羅図に数えられます。
子嶋寺中興の祖とされる真興が一条天皇の病気平癒祈願の功により
賜ったと伝わる。
何でも中国が返してくれと言ってきたり、
かのルーブル美術館が貸してくれと言ってくるほどの逸品です。
堂内にあるのはレプリカで本物は防火設備と保存に適した奈良国立博物館に寄託。

(写真は寺の小冊子より。)
子嶋寺は大和七福八宝巡りの大黒天を担っており、
室町時代作の大黒天が祀られています。
現在は足元以外はガラスケースで覆われていますが、
足を触ることが出来るので御利益があるように触っておきました。(^^
寺の方の説明によると以前はガラスケースは無かったのですが、
大黒天の一部を持って帰る不届き者がいたそうで、
ガラスケースが設置されたとのこと。
本当に罰当たりなことを平気でする人もいるんですね。(怒)

(写真は寺の小冊子より。)
征夷大将軍坂上田村麻呂の自作像と伝わる。
本堂にはその他に申請すれば国宝に指定されると言われる
飛鳥時代の仏頭や延鎮僧都の像など素晴らしい仏像の数々を堪能出来ます。


千寿院へ続く廊下には瓦や不動明王の石仏などが置かれていました。
しかもただの瓦ではありません。
職人に言わせるとあれほど細かい瓦を割らずに焼くなんて、
現代の技術でも無理だとのこと。
【十一面観音像】

千寿院に祀られている高取城主の念持仏。
以前は住職と高取城主しか堂内に入れなかったそうです。
手前にある袋に包まれた嶋投聖天は残念ながら秘仏です。
【御朱印】

【満願】

ようやく満願達成しました。(^^
この子嶋寺は正直余り期待しておりませんでしたが、
本堂の中が凄すぎた。
寺の方にいろいろ説明していただき勉強になったし、
沢山ウンチクのある話をしてとても堪能しました。
何度も訪れたいと思う数少ないお寺です。