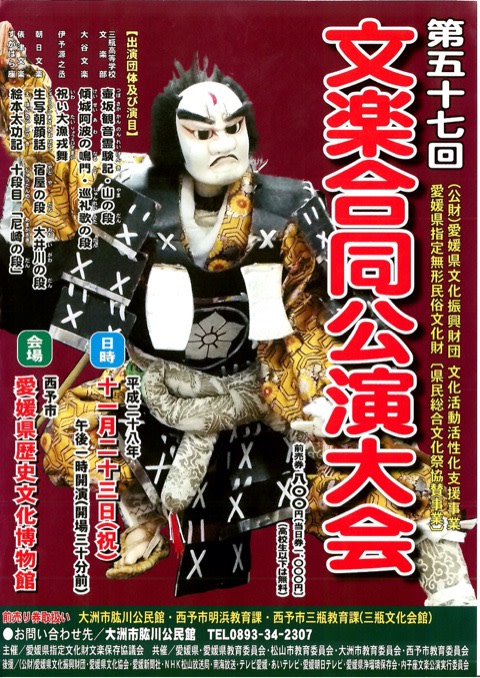八幡浜市民ギャラリーの「大空への挑戦」を見る。飛行機原理を発見したとされる二宮忠八の功績を出発点に、近代、現代、そして未来の人々の大空への夢、飛行機の歴史を端的に紹介した展示。
これまで、八幡浜で二宮忠八が取り上げられる際には、「ライト兄弟よりも前に飛行原理を発見して、模型飛行器を飛ばした偉人」と紹介され、「二宮忠八翁」と「翁」の尊称が付けられてきた。
ところがどっこい、二宮忠八が飛行原理を発見したとされるのは青年期であり、決して「翁」ではない。
「翁」とつけられるのは、なんでかというと、飛行機が世界各地で戦闘で用いられるようになった戦中に忠八が国定教科書に掲載されるなど、再評価がされる。この時期が「翁」だったことによる。
そして、この再評価も、シンプルに飛行科学による評価ではなく、戦争・戦闘=飛行機=日本での先駆者忠八、という戦中の時代のボトムアップもあってのものだった。
しかし、その時代のボトムアップは一般には意識もされず、地域の偉人としてのイメージが戦後も続いて、八幡浜では「翁」を付けて呼んできた。
ところが、今回の八幡浜市民ギャラリーの展示では、戦後から今にいたる飛行機開発の挑戦がきちっと紹介されている。(こんな展示、いままでなかった!)
「大空への挑戦」が戦中の戦闘飛行を背景としたものではなく、今、未来に続く飛行を意識した展示内容となっている。これは八幡浜における二宮忠八の新たな評価指標を提示している、と思ってしまう。
今回の展示で、戦前イメージを引きずる「二宮忠八翁」の脱皮ができたのではないか。この新たなステージによって、若き忠八のチャレンジをもっとピュアにシンプルに評価できるかもしれない。
そんなことを考えさせられる展示でした。
もう、二宮忠八「翁」って言わんでもええんやないん?飛行原理発見したとき、若かったんやけん。
そう考えると、タイトルの「大空への夢」って、まさにピッタリ。若き忠八の大空への挑戦!
はい、とにかく展示は明日11/20が最終日です!