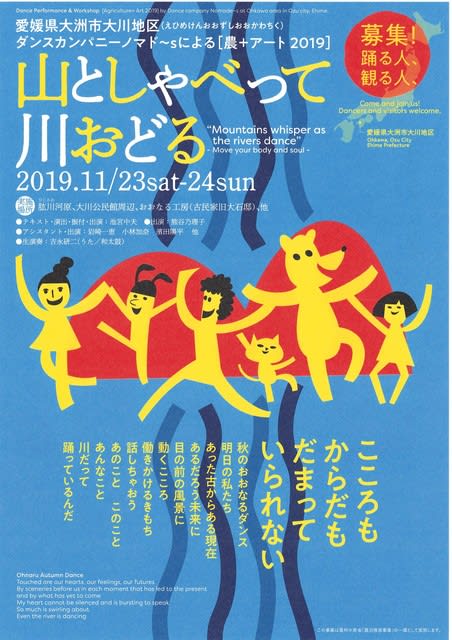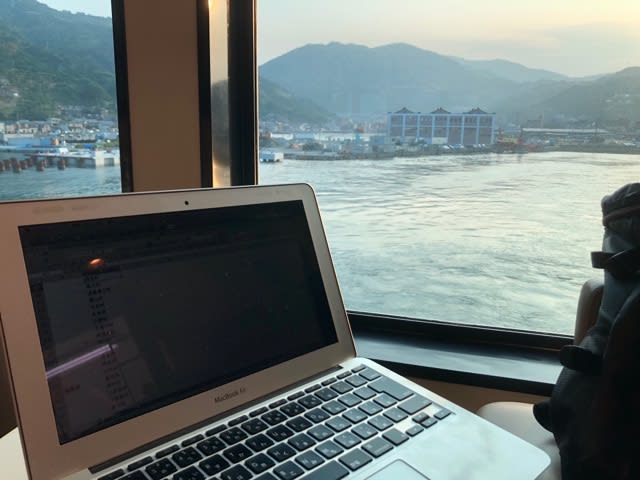愛媛新聞2019年9月24日よりメモ
「民事裁判記録廃棄 伊方1号機訴訟も 松山地裁 将来検証困難」
全国初の原発設置の是非を争った四国電力伊方原発1号機を巡る訴訟記録が廃棄。
「裁判が公正だったか、事実認定に誤りがないか。記録がなければ将来検証できない」。
松山地裁は「どんな判断で廃棄したか承知していないが、近年は公文書を含めて史料の歴史的価値や保存の必要性の認識が社会的に高まっており、変化を踏まえて適切に保存などを行なっていきたい」。
公文書管理法では対象が行政庁に限定されているが、欧米では司法、行政に関わらず公文書館が保存について指導、監督。
浅古弘氏(法制史)は「裁判所だけの問題ではなく、日本の公文書管理の仕組みが非常に脆弱。国全体でもう一度在り方を考え直す必要がある」。
以上、記事抜粋。
先月からかな。共同通信の記事以降、全国の裁判所で歴史的な民事裁判の記録が多数廃棄されていたことが記事になっている。今回の愛媛新聞の取材はその流れかなと。
判決文など結論文書は保存されているだろうけれど、審理の過程が全くわからなくなる。検証できなくなる。
裁判記録は、最高裁まで争われたものでも最高裁や高裁では保管されない。記録は地裁に戻されて保管されるのがルール。地裁で裁判記録が廃棄されれば、判決文以外、何も残らなくなる。
規定では判決文の保存期間は50年。民事裁判の記録は確定後に一審の裁判所が5年間保存し、その後に廃棄。
規定通りに適切に処理した、ということなのだろうが、重要な裁判記録が規定どおりに廃棄されることが常態化していたことに驚かされる。
重要な憲法判断や判例、社会的に注目された裁判は、「史料または参考資料となるべき記録」は「特別保存」として永年保存されることが義務づけているのではなかったのか。この特別保存はなかなか適用されず。適用の判断をする文書管理の専門職員がいない中では難しいのかも。
伊方訴訟の記録廃棄。そして愛媛には県の公文書館が設置されていないことも含めて、歴史的公文書の管理の現状への危機を感じてしまう。
裁判所で廃棄されているので、伊方訴訟では原告の住民側で保存している裁判記録が後世、非常に重要な歴史的資料になる。その整理、保存がこれからとても大事。伊方訴訟だけでなくて、今治織田が浜や長浜臨海工業開発や、宇和島市ごみ焼却場など、愛媛における住民訴訟は、それぞれ原告側の記録保管状況を確認しないといけない。時間が経って、世代が変わって原告側でも廃棄されてしまったら・・・。それを住民側に求めるのも酷。やはり、司法の公的責任として、住民運動に関する裁判は特別保存扱いで永年保存しないと・・・。
なお、伊方訴訟については資料集がクロスカルチャー出版から刊行されている。これが裁判記録の一部かもしれないし、刊行されたものの中で廃棄されたものもあるかもしれない。
『伊方原発設置反対運動裁判資料 全7巻』
http://kw.maruzen.co.jp/ln/set_series/64_crosscultureshuppan.pdf
【2019年9月25日追記】
裁判記録は廃棄とのことですが、地元住民側で残してきた記録については保存、整理の取り組み。昨日会合あって、今朝の新聞にも取り上げられていました。
以下、愛媛新聞 2019年9月25日より抜粋
「伊方原発反対軌跡を後世に 八西協故広野さんらの私信や日記2000点 神戸大大学院講師ら」「南海日日で論陣 近藤さん遺稿も 妻 次の運動につなげて」
四国電力伊方原発の建設当時から続く地元団体の反対運動について、神戸大大学院などが資料の保存を進めている。資料は日記、写真、裁判記録、チラシなど。吉川圭太特命講師が、24日、八幡浜市で中間報告し「これほど体系的に残された反原発運動の記録はまれ。多くの人が活用できるようデジタル化などを進めたい」 「学生運動やローカルメディアの動向、他地域との連携など、多様な情報が含まれている。住民の生活に根ざした人類史的に貴重な資料」と述べた。
資料は、地元住民らでつくる「伊方原発反対八西連絡協議会」の元会長で2005年に死去した広野房一さんらが残した2000点余り。
保存が進められている伊方原発反対運動資料には、地域紙「南海日日新聞」の記者として反原発の論陣を張り続け、2015年に死去した近藤誠さんが残した数百点も含まれている。