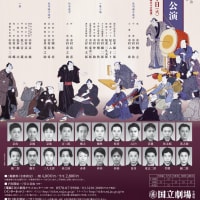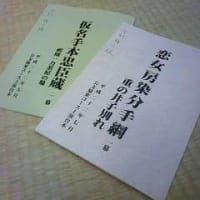『櫓のお七』の見せ場は、なんといってもお七の<人形振り>でございましょう。恋しい男への切ない気持ちを、あえて感情のない人形になり切ることで表現する。歌舞伎の巧みな演出の一つでございます。
このお七の演技を盛り上げるのが、舞台一面に降りしきる雪でございます。時に激しく、時にちらほらと、場面場面に合わせて降り方も変わります。
歌舞伎において、上から降ってくる雪は、天井に備え付けられた竹製の<雪カゴ>に詰めた紙製のものを、カゴに取り付けたロープを舞台袖で引くことで操作いたしますが、近年では、カゴにかわって西洋式の<ネット>を使うことも多いです。目の粗い網になるわけですが、こちらのほうが、舞台一面に、均一に降らせることができるようですね。
紙製の雪は、ごく薄い和紙を四角く切ったものを使用します。昔は三角に切っていたそうで、そのほうがより雪らしいチラチラ感が出たそうですが、戦後に作る手間の問題から四角になったそうでございまして、私は三角の雪は見たことがございません。
同じように空から降ってくるものに<散り花>がございます。桜の花吹雪ですね(梅、その他の花のこともある)。雪と同様、、舞台全面に降らせる場合にはカゴかネットを使い、操作は大道具さんが担当いたしますが、役者の演技や曲のキッカケを見ながら降らせる場合には、役者が担当することもございます。そういう時は、えてして舞台全面ではなく、局地的に降らせる場合が多いですし、役者自身が舞台の天井にのぼり、手作業で散らせる(花咲爺さんのように)のがもっぱらです。
私がいたしました雪や桜を思い出しますと、『化競丑満鐘』で、雪女が住む家の井戸の上にだけ雪を降らせたのと、『狐と笛吹き』で、主人公である楽士春方と、やがて恋仲となる、ともねというひと組の男女の踊りに合わせて、『将軍江戸を去る』では、主人公徳川慶喜のセリフをきっかけに、『元禄忠臣蔵・御浜御殿綱豊卿』では、赤穂浪士、富森助右衛門に狙われた徳川綱豊が、桜の木にぶつかるそのはずみ、と、シンの俳優さんの演技に合わせて、花を散らせる作業をいたしました。
『化競』や『狐と~』では、自ら舞台の天井に登って降らしましたし、『将軍~』では、天井に設置したごく小さいカゴを舞台袖で操作、『御浜御殿~』では、大道具の桜の立ち木に仕掛けられた<引き栓>を立ち木の裏で引っ張ることで、枝に隠された、花びらを乗せた受け皿が倒れ、こぼれるように花びらが散る、という仕掛け。このように、雪や花の降らせかたは様々です。
いずれにしましても、よく舞台を見て、キッカケ、合図を逃さにように、そして降らせる量、時間を間違わないようにするのがポイントですが、なにせ人力ということもあり、ときには仕掛けの不具合で、思うようにいかないときもございます。ひと月の間、試行錯誤で勤めております。
今月の『櫓のお七』では、大道具さんが降らせて下さっておりますが、小降りにしたりどか雪にしたり、あるいはピッタリ止ませなくてはならないところもありと、なかなか大変だと思います。雪の降らせかたと、登場人物のセリフ、あるいは浄瑠璃の歌詞が密接につながっているところもありますので、これからご覧になる方は、その辺りも、是非御注目下さいませ。
実は『櫓のお七』の幕切れで、セリフを言うときに雪を吸い込んでしまうときがあるのです。紙ですから大したことはないのですけど、一瞬「ウエッ」となってしまうので困ります。されど舞台は、そんな事情におかまいなく、ラストシーンを盛り上げるべく降りしきるわけで…。
このお七の演技を盛り上げるのが、舞台一面に降りしきる雪でございます。時に激しく、時にちらほらと、場面場面に合わせて降り方も変わります。
歌舞伎において、上から降ってくる雪は、天井に備え付けられた竹製の<雪カゴ>に詰めた紙製のものを、カゴに取り付けたロープを舞台袖で引くことで操作いたしますが、近年では、カゴにかわって西洋式の<ネット>を使うことも多いです。目の粗い網になるわけですが、こちらのほうが、舞台一面に、均一に降らせることができるようですね。
紙製の雪は、ごく薄い和紙を四角く切ったものを使用します。昔は三角に切っていたそうで、そのほうがより雪らしいチラチラ感が出たそうですが、戦後に作る手間の問題から四角になったそうでございまして、私は三角の雪は見たことがございません。
同じように空から降ってくるものに<散り花>がございます。桜の花吹雪ですね(梅、その他の花のこともある)。雪と同様、、舞台全面に降らせる場合にはカゴかネットを使い、操作は大道具さんが担当いたしますが、役者の演技や曲のキッカケを見ながら降らせる場合には、役者が担当することもございます。そういう時は、えてして舞台全面ではなく、局地的に降らせる場合が多いですし、役者自身が舞台の天井にのぼり、手作業で散らせる(花咲爺さんのように)のがもっぱらです。
私がいたしました雪や桜を思い出しますと、『化競丑満鐘』で、雪女が住む家の井戸の上にだけ雪を降らせたのと、『狐と笛吹き』で、主人公である楽士春方と、やがて恋仲となる、ともねというひと組の男女の踊りに合わせて、『将軍江戸を去る』では、主人公徳川慶喜のセリフをきっかけに、『元禄忠臣蔵・御浜御殿綱豊卿』では、赤穂浪士、富森助右衛門に狙われた徳川綱豊が、桜の木にぶつかるそのはずみ、と、シンの俳優さんの演技に合わせて、花を散らせる作業をいたしました。
『化競』や『狐と~』では、自ら舞台の天井に登って降らしましたし、『将軍~』では、天井に設置したごく小さいカゴを舞台袖で操作、『御浜御殿~』では、大道具の桜の立ち木に仕掛けられた<引き栓>を立ち木の裏で引っ張ることで、枝に隠された、花びらを乗せた受け皿が倒れ、こぼれるように花びらが散る、という仕掛け。このように、雪や花の降らせかたは様々です。
いずれにしましても、よく舞台を見て、キッカケ、合図を逃さにように、そして降らせる量、時間を間違わないようにするのがポイントですが、なにせ人力ということもあり、ときには仕掛けの不具合で、思うようにいかないときもございます。ひと月の間、試行錯誤で勤めております。
今月の『櫓のお七』では、大道具さんが降らせて下さっておりますが、小降りにしたりどか雪にしたり、あるいはピッタリ止ませなくてはならないところもありと、なかなか大変だと思います。雪の降らせかたと、登場人物のセリフ、あるいは浄瑠璃の歌詞が密接につながっているところもありますので、これからご覧になる方は、その辺りも、是非御注目下さいませ。
実は『櫓のお七』の幕切れで、セリフを言うときに雪を吸い込んでしまうときがあるのです。紙ですから大したことはないのですけど、一瞬「ウエッ」となってしまうので困ります。されど舞台は、そんな事情におかまいなく、ラストシーンを盛り上げるべく降りしきるわけで…。